“ものが見えるようになるためには訓練が必要”ということは、訓練の度合いとその成果のあり方によって、“見えていること”の内容が異なっているということになります。
そこには個人差ということがあり、したがって、同じ場所で同じ時刻に同じものを見ていても、何を見ているかは人それぞれだということになるわけです。
つまり外見上は同じものを見ているはずが、見ているものは人によって違っているということです。
事実は一つということが当然のごとく言われますが、実はそうではなく、事実は人の数だけあるということです。
自分が見えていると思っているものが他者と共有していると思ったら大間違いです。
見るということはどこまでも孤独な作業なのですね。
では、コミュニケーションということはどうなるのでしょうか?
人と人の間に、厳密な意味でのコミュニケーションは成り立たないのだ、というのも一つの考え方かもしれません。
厳密にはコミュニケーションは成立しないと前提するところから、人と人の関係をどう考えていくか、というのは一つの方向であると思います。
しかし私自身は、「事実は人の数だけある」という命題は、むしろコミュニケーションということが成り立つための前提であると考えたいと思っています。
人はそれぞれみな違うものを見ているのだから、それを報告し合うことでコミュニケーションということが成立すると、それが文化というものだと考えているのです(詳しく書くのは、またの機会ということにします)。
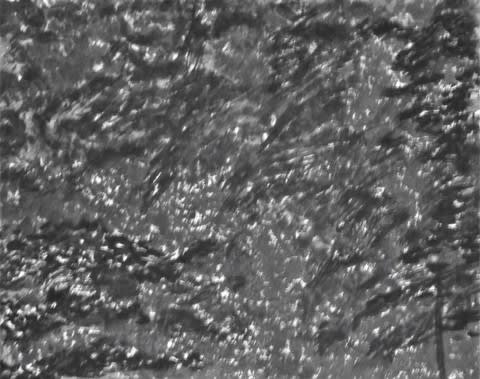
話は変わりますが、今私の手元に、たまたまですが、上島鬼貫(うえじまおにつら)という俳人の句集があります。
鬼貫は江戸時代の人で、芭蕉より一世代ぐらい後、京都に在住して、東の芭蕉、西の鬼貫と言われた人です。
代表作に「おもしろさ急には見えぬ薄(すすき)かな」という句がありますが、これなども、“ものが見えるようになるためには訓練が必要”ということを詠っていると言ってよいかと思います。
鬼貫が書いた『独(り)ごと』という俳論書があって、その中で薄について次のように書いています。
「薄は、色々の花もてる草の中にひとり立ちて、かたちつくろはず、かしこがらず、心なき人には風情を隠し、心あらん人には風情を顕はす。只その人の程ほどに身ゆるなるべし」
また、こんなことも書いてます。
「花の句は花のみをいひ、月の句は月のみいひて、しかも意味深きをよしとす」
見ることは孤独な作業であるゆえに、何を見ているかは自分にしかわかりません。
自分には何が見えているのか、何を見ようとしているのか、すべて自分で探り当てていくほかありません。
鬼貫は、作句は生涯をかけての「まこと」を求めていく事業であると言ってますが、それは「何を見ているか」を自分で探り当てていく道であり、
その行き着くところは「花の句は花のみをいひ、月の句は月のみいひて、しかも意味深き」というところであるようです。
最後に、薄を詠んだ代表的な句をいくつか、歳時記などから拾って紹介しておきましょう。
同じ鬼貫の作から始めます。
茫々と取りみだしたるすすきかな 鬼貫
折りとりてはらりとおもき芒かな 飯田蛇笏
薄を詠った句として代表的と見なされています。
薄活けて一と間に風の湧くごとし 佐野美智
薄の日本的楽しみ方ですね。
まん中を刈りてさみしき芒かな 永田耕衣
耕衣は私の好きな俳人の一人。
この際なので拙作の最近作も。
「風立ちて天穹を掃くすすきかな」



















