この伊奈町立「郷土資料館」は、リーフレットを要約すると次のように記されている。
江戸末期(文政年間と伝えられる)に建てられ、一部に改造(馬屋撤去等)がみられるが、ほぼ原型に近く、建物自体が伊奈町の貴重な文化資産であり、長く保存するとともに、これに、時間及び生活様式の変化にともない消滅してゆく町の民俗・歴史資料を収集、保存。衣・食・住から娯楽関係まで、年間をとおして日常生活の全体がわかるように資料を展示している。
・開館昭和58年11月3日
・建物構造茅葺木造平屋
・建築面積179平方メートル(約54坪)
 伊奈町立「郷土資料館」のホームページ(休館日、開館時間等はこちらをご覧下さい)
伊奈町立「郷土資料館」のホームページ(休館日、開館時間等はこちらをご覧下さい) 駐車場:有(無料)
駐車場:有(無料)  入館料:無料
入館料:無料

長屋門 土蔵の内扉を利用して作成された「郷土資料館の修復 覚」


郷土資料館の構内に展示されている高札や田舟


郷土資料館内土間に展示されている農耕具やかまど等々


田の字づくりの座敷


座敷内に展示されている民具や衣類等
伊奈町立「郷土資料館」 地図(「地図」もしくは「ユーザ地図」をクリックすると大きい地図にジャンプします)
























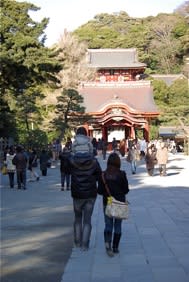










 「願掛け寶袋尊」の案内板(画像をクリックしますと拡大します)
「願掛け寶袋尊」の案内板(画像をクリックしますと拡大します)



















