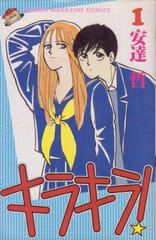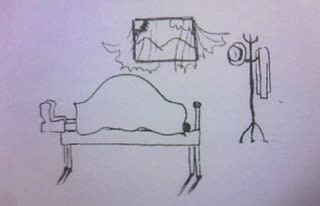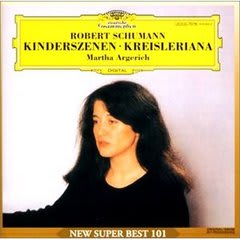からっ風の吹きぬける「神」の最終戦争予定地・ハルマゲドン (上図)
ハルマゲドンという言葉をはじめて耳にしたのは、いつだったでせうか---?
それは、まったく耳慣れぬコトバであり響きでした。僕ら、一般のニッポン人庶民の生活圏からはるか離れた生活圏の、珍しい耳ざわりの、遠い言葉。最初、僕、これのことなんかの丼だと思いましたもん。
永井豪の劇画「デビルマン」で見かけたのが最初だったのかな? それとも、平井和正の「幻魔大戦」を石森章太郎が慢画化したのを読んだときに見たほうが早かったっけ?
うーむ…はっきりと限定はできませんが、そのうちのどちらかにまちがいなかったような気がします。
僕が少年時代をすごした1970年代はいまとちがってのんびり牧歌的な空気が日本各所のあちこちにまだ残っていまして、情報の拡散なんてぜんぜん起こってもいませんでした。
当時は、ハルマゲドンという言葉に、まったく知名度も市民権もなかったように思います。
それが多少なりとも知られるようになったのは、僕の小6とときに出た、五島勉さんの「ノストラダムスの大予言」の爆発的ヒットが契機だったんじゃないですかね?
それがSFファンやら漫画ファンやらの層に少しづつ結びついて、ハルマゲドン認識者の層の裾野をじんわりゆっくり広げていったような気がします。
しかし、オームやなんたらの影響でいくらかオカルト・タッチで語られることの多いこのコトバなんですけど、元はといえばこれ、「聖書」に出てくる言葉なんですよね。
ええ、出所は「聖書」---新約聖書のほうの「ヨハネの黙示録」の16章16節です。
もともとはヘブライ語らしいんですが、いま多く使われているハルマゲドンの語源は、どうもギリシァ語の `Aρμαγεδων のようですね。
意味は、ヘブライ語の「ハル Har」が山や丘陵、「メギド Megiddo」が地名で、「メギドの山、丘陵」の意。
なお、「ハルマゲドン」というこの単語、「聖書」のなかでここ一箇所だけしか出てきません。
実際に使われている部分をちょっと書きぬいてみませうか。
----第六の者が、その鉢を大ユウフラテ川に傾けた。すると、その水は、日の出る方から来る王たちに対し道を備えるために、かれてしまった。また見ると、龍の口から、獣の口から、にせ預言者の口から、かえるのような三つの汚れた霊が出てきた。これらは、しるしを行う悪霊の霊であって、全世界の王たちのところに行き、彼らを招集したが、それは、全能なる神の大いなる日に、戦いをするためであった。(見よ、わたしは盗人のように来る。裸のままで歩かないように、また、裸の恥を見られないように、目をさまし着物を身に着けている者は、さいわいである。)三つの霊は、ヘブル語でハルマゲドンという所に、王たちを招集した。(「ヨハネの黙示録第16章12節-16節」新約聖書・日本聖書協会より)
なるほど、ここが、ハルマゲドン関連情報の凡ての源泉だったのか。
なんでも、現在のメギドはイスラエルの国立公園に指定されていて、この国立公園の入口看板には「聖書の預言では、この地で人類最終戦争が起きることになっている」と書かれているとか。
さらに追加情報としてつけくわえますと、こちら、かのナポレオンがエジプト遠征でこの地に赴いた際、「世界中の軍隊がここで大演習できる」と感心したと伝えられているほど、軍事的に絶好の場所でもあるそうです。
ま、いずれにしましても、こちらが多くの人々から「将来、人類の世界最終戦争が起きる場所」として認識されている、という事実は重要でせう。
なぜなら、僕ら日本人は、一般的に「なに、予言? マジでっか、それ?(なぜか関西弁のイントネーションで)」なんてついからかいのまなざしを投げちゃうような、現実的な凡俗体質をわりかし持っちゃってますから。「ハルマゲドン」なんていわれても、その妙な語感に対してギャグで返しを入れたくなる、多神教民族ならではの、根っからの不謹慎茶々入れ体質とでもいいますか。
しかし、これらの凡俗的な僕らの感性が、世界的規模でも通じるとは思わないほうがよさそうですね。
というのも世界の大部分に生息している民族のうち、「聖書」を信仰のよりどころとしているひとたちの比率は、なんと地球総人口の半数以上を占めているんです。ユダヤ教徒、イスラム教徒、あと、キリスト教徒のすべてがそう---彼等にしてみれば、「ハルマゲドン」はギャグどころじゃない、マジそのものの場所ですよ。下手にギャグなんかやったら、命だって落としかねない。信仰ってコワイですから。その意味で、そういった全世界の諸々の、無数の信徒の信仰が雪崩れこんでいく場所としての、こちら「ハルマゲドン」は、やはり全地球史的な要所なのではないか、とイーダちゃんは考えないではいれません。
ほんというといまでも「ハルマゲドン」をいささかオカルティックな、半ばSF的・残り半ば幻想的みたいなイメージをかぶせて見てみたい気持ちが自分のなかに少々残ってるのを感じるのですけど、たぶん、これって対岸の火事みたいに、あえて離れた場所から高見の見物を決めこんでいたい気持ちがいざなう、一種の自分だましなんでせうね。
ええ、きっとそっち方面に解釈しちゃいけないんです。
いわゆる「ハルマゲドン」を物語的な幻想としてじゃなく、厳然たる歴史的事実として向きあわなくちゃいけない季節が、近未来において巡ってくるような気がします。というより、あえてそっちサイドからの心的準備をしておいたほうが、これからの時代はむしろ現実的で生きやすいように思えてならないんです。
予感? ええ、あえて言葉にすると予感というしかないでせうねえ。
なんとなく---DNAからの警告みたいな漠然とした印象説明しかできなくて恐縮なんですが…。(^.^;>
ただ、このようなおどろおどろしい「ハルマゲドン」なんかを表に出さなくとも、いわゆる「ハルマゲドン危機」めいたものを日常ひしひしと肌で感じてるひとは、いまの世の中にたくさんいらっしゃるだろうと思います。
高度経済成長のころ---あるいはバブリーな80'Sのころ---なら、そのようなことをいうとそれこそKYとして袋叩きにされたもんですが、さすがにいまじゃこの種の「人類文明の通せんぼ」を実感として感じていないひとはいないでせう。
そんなものはまったく感じていない、人類の未来は薔薇色だ、とあくまでいい張るひとがあるとしたら、恐ろしく鈍感な方であるか、もしくはなんらかの利権のために白を黒といいくるめることを生業としていらっしゃるかの、たぶんどちらかでせう。
あえて悲観論をもてあそぶつもりはありませんが、人類に明日がないというのは極めて明晰な判断だと思います。
だって、どっからどうみても、このまま立ちゆく道理がないですもん。
たとえば---
ひとつ。いま現在、ほかの生物種が1年に5万~15万種! の規模で絶滅している。
ふたつ。中国の経済成長に伴う超・公害の発生で、中国国内においての奇形児の出生率が本年度14パーセント! を突破した。
みっつ。アメリカのサブプライム・ローン破綻の総被害額は、すでに6000兆円!---うわ。もうどうしようもないよ、この額じゃ---を超えているが、さらに2011年度には、シティ・バンクの倒産すら確実なものとして見こまれている。
うわあ、どうするのよ、これら…?
どれをとっても、とことん破滅的。ことごとくが国家デフォルトと戦争に行きつくような致命的な事実ばっかりじゃないですか。
いささかうさん臭げなオカルト「予感」コース側からたどっても、反対側の事実列挙の科学的分析サイドのコースからまわっても、所詮はおんなじ「ハルマゲドン」的決着にもつれこんでいっちゃうというこのふしぎ---。
せっかくの機会ですからオカルト・サイドからの「ハルマゲドン的証言」をもう二つ、三つ挙げておきませうか。
----日本の国は雛型であるぞ。 雛型でないところは真の神の国ではないから、よほど気つけて居りて呉れよ。 今の世は地獄の二段目ぞ、まだ一段下あるぞ、一度はそこまで下がるのぞ。 まったく雨の降らない雷鳴が一日中鳴り響き、三日三晩続くとき、その後に三度の火の洗礼(火事と洪水)があり、恐るべきことが起こるぞ。 地震、雷の火を降らして大洗濯するぞ。 江戸がもとのすすき原になる日近づいたぞ…。(岡本天明「日月神示」より)
ああ、怖い…。何度も読んでるけど、いざ、この文章を書き写すとなると、これ、はじめて試みましたが非常に怖いですねえ。
日本には、聖徳太子の「未来記」のころから予言の伝統があり、これは、あの大本教の出口王仁三郎の弟子筋にあたる、岡本天明氏の手によるものです。
これによると、近未来、ニッポンはどうも海外の勢力に上陸され、蹂躙されたあげく、さんざんな目にあうらしい。
まったく雨の降らない雷鳴ってのが特に怖い。これは、ひょっとしてプラズマ兵器のことじゃないでせうか?
さらにもうひとつ、日本の誇る大霊能力者にして大予言者でもあるところの、出口王仁三郎氏の言葉の引用いきませう。
----シベリヤ狐は死にたれど 醜の曲霊は種々に 妖雲を呼んで東天は 北から攻め入る非道さよ オホーツク海や千鳥船 カラフト島をゆさぶりて 暗雲低く仇鳥の 舞い下がり上がる恐ろしさ 北海道から三陸へ なだれのごとく押し寄せる ここを先途と連合の 戦いの場や神の国 華のお江戸は原爆や 水爆の音草もなき 一望千里の大利根の 月の光も哀れかし 残るは三千五百万 ○○○○○○の旗の下 どっと攻め入る○○○○の○○○○沿いや人の無く 非義非道の場所せまく ○○○○○○○○○○ あわれ崩るや○○○ 血汐に赤き続一も ○○○○の殺戮も ここに終りて神の子は、再び原子に還るぞかし (出口王仁三郎「霊界物語」より)
聖書の「ハルマゲドン」とちがって、こちらの日本の2書が述べているのは、祖国・ニッポンの断末魔の未来のようですが、うわあ、マジ怖いですねえ…。
岡本さんも出口さんも只者じゃないお方ですから、筆先にもただならぬ力があり、キーボードでこうして書き写しているだけで、なにか憑依されているような、イタコチックな重みを感じます。
「ハルマゲドン」ならまだ遠い異国での破滅物語として、いくらかの心的逃避も可能なんですが、舞台が日本に限定されてしまえばそうもいかない。想像力の遊びの余地が取り払われてしまうわけで、目のまえで危険な刃物を振りまわされているような禍々しい感触がぐわーんと直接きちゃう。となると、これ読んで、なかには怒りだすひともでてくるんじゃないでせうか。
しかし、イーダちゃんの予測と兼ねあわせてみるなら、この偉大な2書の警告、いよいよあたってきてるって感じがひしひしとしますねえ。
予言というよりは、これ、もう近未来のデッサンかもしれない。
僕は、「戦争」という産業でここ何十年と喰ってきたアメリカの軍産複合体が、だんだんジリ貧になってきたいま現在、ワシントンや各国政府のマスコミごと巻きこんで、起死回生の新たな戦争惹起をもくろんでいるような気がしてならないんです。
新たなベトナム戦争っていうか、そういう類いの、ま、それは彼等なりの生業というか商売なんですが。
で、今度彼等に狙われてるその舞台というのが、日本なんじゃないか、と僕は睨んでるわけなんです。
相手国として想定されているのは、うーむ、中国あたりが臭いんじゃないかなあ…。(^.^;>
根拠のない病的な空想といわれちゃそれまでなんですが、そうやって読むと、いま現在の世界の流れなんかと案外重なってくる気がしてきやしませんか? 2書の予言とも状況だんだんあってきてますしね。ま、ホントいうと、まったく重ならないというのがいちばんの理想なんですが---。
いずれにしても容易ならぬ未来が我々のすぐ足元までやってきている、ということはどうやら否定できない事実のようではないですか。
予言や「ハルマゲドン」をまったく知らなくとも、誰だってそれくらいは分かります。本能と勘と無意識とでね。
アメリカの16都市が破産宣言をした、というニュースがいまさっきネットから入ってきました。
なんというか、すさまじい流れですよ。まるで、人類の過去の業 (カルマ) の清算期にむりやり立ちあわされているような気分です。
目のまえに次々と垂れこめてくるこの重苦しい暗雲の群れ---これらををどう払い、どう前進するのか?
それが、2011年の僕等に課せられた、宿命的な課題なのではないか、と思います。
超・重い話になっちゃってスミマセン---政治ネタは重苦しくなるから嫌いなんですが---いちどはこのネタを展開しとかないと、このブログ全体が嘘くさい綺麗事になってしまうような気がして、この年の瀬の際に、あえて苦いコトバを振りまかさせて頂きました。
乱文多謝---最後まで付きあってくれてありがとう---どうか、良いお年を---。 M(_ _)M