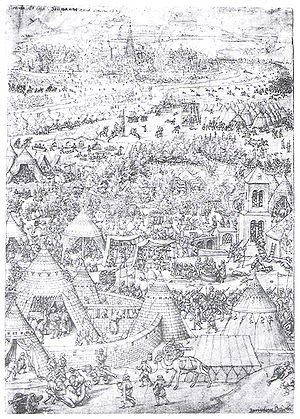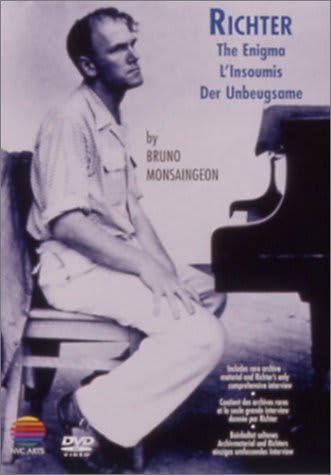2014年の7月27日---超・酷暑の夏日---イーダちゃんは、錦糸町の「すみだトリフォニーホール」で行われた、オーケストラ・ダヴァーイのコンサートにいってきました。
指揮は、あの森口真司センセイ---。
演目は、チャイコの「スラヴ行進曲」とプロコフィエフの「スキタイ組曲;アラとロリー」、それと、メインのショクタコーヴィッチの11番なんか。
オール・ロシアのプログラミングですねえ、いいなあ…。
僕は、個人的にドストエフスキー、ゴーゴリ、ホロヴィッツからプーチンまで、骨がらみのロシアン・ファンですから、このプログラミングにはいささか陶然たるものがありました。
なお、この選曲をされたのは、指揮の森口センセ御自身だとか。
ダヴァーイのひとたちがみんなロシア・マニアなのをあらかじめ察した上で、
----だって、みんな、こういうの好きでしょ?
と、いったとかいわなかったとか…。
そりゃあ、こうまでいわれたら、オケは喜ぶよ。
ちなみに、このオーケストラ・ダヴァーイってのは、アマチュアのオーケストラなんです。
パンフを見ると、結成は2007年となってます---いわば、オケの7年モノ。
でね、なんだか知らないけど、ここ、みんな、ベラボーに巧いのよ。そして、ロシア物をいっつも演奏するの。
前の公演にいったときのプログラムの布陣も、たしかチャイコのバレエ曲がメインだったと記憶してます。
そのときはね---正直いうと、オケの面々の「オレはうまいんだゾ」って我のほうが曲よりも大きく聴こえてきて、感心はしたけど感動はしなかったの。
----ふーん、やっぱ、アマチュアなんだなあ…。
みたいな、そんな印象。
あざといっていうか、仇光っていうか、そっち系の自我主張的要素のほうがどうしても先に耳に入ってきてしまい、「音楽」のなかに僕が参入するのを妨げているような、一種微妙な齟齬感がちょっとあったんですよ。
でも、まあ、とにかくハンパなくうまいから、モノは試しにもういちどいってみるか、とまたきてみたわけなのサ---。
× × ×
で、今回の演奏の感想をさきにいっちゃいますと、それがもうね、お世辞ぬきに素晴らしかった…。
1999年にサントリーホールで聴いた、ええ、生イーヴォ・ポゴレリッチのショパンの2番よりよかった。
僕、どっちかっていったらピアノ・フリークでして、オケの音ってちょっと苦手な口なんですよ。
もってるCDなんかもピアノ音楽が10としたら、オーケストラの配分はせいぜい2くらい。
でもね、今回にかぎっては、そんな嗜好の垣根なんか関係なかった。
今回は、森口センセの指揮が見たかったんで、僕、2Fの天井桟敷席のいちばん端に陣取っていたんです。
そこからなら知りあいの奏者がよく見えるからという理由もあったんですが、実際に演奏がはじまると、そんな瑣末な観察アングルは綺麗サッパリ翔んじゃってましたね。
それくらい、今回のダヴァーイの演奏は「よく生きて呼吸していた」と思います。
森口センセイのタクトの先から眼に見えない光の糸が伸びていて、その糸がビオラ部隊にまず繋がり、次にファゴット、ホルン隊に繋がり、さらには、フルートやオーボエ奏者のもとに次々と紡ぎ足されていくのが、僕、まざまざと見えましたもん---マジ。
桟敷からあんまり身を乗りだして見てるんで、休憩時間には、ホールの係の姉ちゃんに注意されたほどでした。
でもね、僕にそうさせるくらい、その日の演奏は凄かったの。
あえてコトバにしようとすると嘘くさくなるけど、入魂の、真摯極まりない、ええ、熱くて胸に刺さりまくる演奏だったと思います。
オケのパッションも凄かったけど、僕がとりわけ凄いなと思ったのは、この音楽の総元締めである、森口センセイの「確信」でした。
それが、あまりにも濃く、凛凛しく、音楽の中心地にすっくと立っているので、通常は差しこんできがちのさまざまな「迷い」や「不安」が、この音楽の同心円のなかにまったく入りこんでこれないのです。
うん、光ってましたよ、森口センセイ---オケの面子がこれだけひとつになり、脇目もふらず、迷いのかけらもなく、これほど音楽に邁進できたというのは、一重に森口センセイ内のこの「確信」のおかげだろう、と僕は読みたいですね。
オケだけじゃない、当日の観客席もそうでした。
当日の観客席のお客の無数の目線も、すべてこの森口真司というオトコの放つ「確信」のオーラに導かれて、あらゆる日常の迷いから解き放たれて、ステージ上で生起する音楽の歩みようを無心に見つめていました…。
つまり、観客とオケと指揮者がひとつになって、ある意味理想的な生きた音楽を奏でていたわけです。
こんなことってそうないと思うよ---。
生の音楽って、僕等のそれぞれの職場内事情といっしょで、フツーもっと雑多な峡雑物がいっぱい詰まっているもんだもん。
ちっちゃな不満、悪意、倦怠、それに愚痴とか…。
ほかにもオケ内での人間関係の軋轢だとか、指揮者の解釈に乗れなくて、でも、演奏しないわけにもいかないから、あえて義務的にクールな風情を装っている面子がぽつぽつと見分けられたり、ね。
その種のことって、案外ステージの外まで見えてくるもんなんっスよ。
けど、この日のダヴァーイの演奏からは、それが見つけられなかった。
むろん、生身のニンゲンですから、ある程度の峡雑物はあるのがフツー---当日の演奏でも、それはきっとあったのでせう。
あるにはあったんだろうけど、それよりも、この日の森口センセイ内部から凛凛と発する「音楽的確信」のほうがもっと強かったんじゃないのかな?
それくらい、この日の森口センセイはイカシてました。
うん、寛永14年、島原の乱のクリスチャン農民軍の総大将にして象徴だった、あの年少の天草四郎が放っていた光っていうのは、もしかしてこういう種類のものだったんじゃないのかな、と僕は舞台とちゅうで何度も感じてしまったくらい---。
観客も、オケも、この光の圏内にいると、安心して、浮き世のマイナス・オーラを忘れ去ることができたのです。
通常なら足元に絡んでくる「慢心」やら「不安」やらの影を一掃して、森口センセイの掲示する清冽な「音楽」の流れにすべてを委ね、駆けだすことができたのです…。
おっと。ちと論旨が先走りすぎちゃったい---具体的な叙述にそろそろ回帰しませうか。
◆1曲目:「スラヴ行進曲(チャイコフスキー)」
まず、森口センセイの登場からして、気合いがちがってました。
指揮台に立って、音楽がはじまるまえの一瞬の間---いつの場合も、これはオーケストラ音楽の醍醐味ですよね? これ見ると、僕はいつも武道の組手前の一瞬を連想するのです---が、なんというかフツーじゃなかった。
ここ、あざとい視点からいうと、指揮者って職業の最大の「見せ場」だと思うんですよ。
ですから、どの指揮者にしても、それなりの見せ方っていうのは一応心得てるわけ。
僕は、大指揮者といわれるひとの舞台も何度となく見てるんですが、この日の森口センセイの見せたそれは、彼等の身に馴染んだ「芸風」のそれとは、少々べつのもののように感じられました。
演出的にいったら、あれは、むしろ拙かったんじゃないのかな?
ええ、あの音楽前の刹那の沈黙には、指揮者・森口センセイよりむしろニンゲン・森口真司氏の生地のほうが、強く匂いたっておりました。
ああいう瞬間って、大抵のひとは格好つけちゃうもんだと思うんですけど。
でも、森口センセイはそうじゃなかった。
その種の洗練された身ぶりを示そうともせず、むしろダサダサの田舎っぺのごとく、もの凄く無防備に指揮台のうえに、ただ佇んでられました。
あのとき、森口センセイは、自分が観客のまえにいることも、これから自分がオケを振るということも、意識してなかったんじゃないかしら?
ええ、あのときの森口センセイは、指揮者・森口センセイなんかじゃなく、ひとりの野人のようでした。
なにもかも忘れた野人が、武骨に、自らの内面から音楽があふれ、それがいっぱいになって氾濫する瞬間を、ひたすら待ち受けているようでした。
しばしのあいだ眼をとじて、さらに自分の奥深くにぐいと潜入して、で、内部にたまった音楽エネルギーの総量が溢れんばかりになってきたら、はっしと大きく眼をあけて…
その一瞬のまなざしの強さから、内面の、自らが信じる音楽を、これから真正直に、愚直なまでにまっすぐに演っていこうというセンセイの意志が、痛いほどびしばし伝わってきました。
この段階で、僕はもう森口センセイの「音楽」にKOされていたことを、いま、ここに告白しておきませう。
----うわあ、このひと、まっさらの裸になるつもりなんだ…。でも、どこまでやってくれるんだろう…?
で、決壊寸前のこの沈黙から、静かに滑りだすようにタクトがふられて、さあ、音楽会がはじまったんですけど、僕が最初にびっくりしたのは、このときのダヴァーイの音でした---なんというか、ちがうんですよ、前回のときと。
前回は---オケ関係のひとが見てたらごめんなさい---個人個人の達者さのほうが、僕はどうしても眼についちゃったの。
だから、必然的に、僕の聴きかたも、個人個人の奏者の技量やら音楽性やらのほうに必然的にズームしちゃってたわけ。
けど、今回のは---これは---?
オケの音がするんですよ、巨大な室内楽なんかじゃなくて、あくまで純然たるオーケストラ音楽の音が。
この1週前、僕は、やはりアマチュアのオケである、みずほフィルを聴く機会があって、その音はよく覚えていたんですよね。
ほら、女性ヴァイオリニストと男性ヴァイオリニストとじゃ、出す音がどうしてもちがうじゃないですか? 女性ヴァイオリニストの音は、どっちかというとベターッとした感じの音になる。
腕の筋肉量の差がそうさせるのか、骨密度の性差が影響するのか、ボーイングの差がそうさせるのかどうかは分かりませんが、一般的にそういうことっていえると思う。
(具体例としては、女性ヴァイオリニストではチョン・キョン=ファやムター、対する男性ヴァイオリニストとしては、ハイフェッツやシェリングなんかを思い浮かべてください)
みずほオイルの音は、女性奏者が多いせいか、女性ヴァイオリニストに特有の、そっち系のベターッとした響きがしたんですね。
ベターッなんて表現を使うと悪口じみて聴こえるかもしれないけど、これは、そんな意図はまったくないんであって、僕は、深窓の令嬢のような声色で、あくまで清楚に、柔らかく、適度な抑制をつけながら楚々と歌うみずほフィルの音は、個人的には結構好きです。
対してダヴァーイの音は、男性ヴァイオリニストの特色である、硬質な、いかにも筋肉質的な響きでもって鳴るんです。
前者は、情念の表現向きの音であり、後者は、音楽の動き・構造なんかを示すのに得手がある、と僕は思ってます。
いわば、ロマンティストの音 VS リアリストの音とでもいうのかな?
で、前回のダヴァーイの音は、そっちの後系の男性色が強烈にしてたんですよ。
あまりにも体育会系すぎて、音楽の骨組だけが鳴っているように聴こえてくる瞬間もままあった。
だけど、今回のはそうじゃなかった---頑健で丈夫な骨組のうえに、あくまで適切な肉が乗っていた、なんていうと僕独自の語法すぎて分かりにくいかもしれませんが、要するに、どんな瑣末なフレーズのアーティキュレーションにもそれ相応の意味があり、音楽を聴きながら、その「意味の総体」が客席のひとりびとりにまでぐんぐん届いてくるのです。
百年まえに生きていた、チャイコフスキーという見知らぬ男の内面から生まれた、ややエキゾチックな風情なこの音楽の器に、作曲者自身がどんな意味を盛ろうとしていたのか、あいにくのこと僕は知りません。
でも、それ、届いてきたように思ったな---。
チャイコフスキー特有の豊穣な想像力が、散漫で下司っぽい夢想・幻想ショーに堕ちることなく---というのは、そうなるケースもチャイコ演奏の場合は案外多いんですよ---森口センセイのタクトの下、実にきびきびと、そして、生き生きと、客席の隅々まで振り撒かれていくのは、あれは、なんとも素敵な眺めでした。
僕的には、森口センセイのタクトのお蔭で、あの日のチャイコ、実際のチャイコより性格のいい、活発なベター・チャイコとして鳴っていたように思います。
うん、実際の彼は、資料なんかで読んでても、もっと根暗で、じめーっとしてそうな感じですもん。(ホモだったって証言もあるしね)
創作家ってだいたいにおいてヘンなひとであることが多いんですが、それ考えると楽譜という記号を舞台で実現する演奏家って立場には、非常に重要なものがありますね。
演奏家は、腕のいいのはもちろんですが、なにより性格がよくなくっちゃ、ですね。
これがないと、演奏家が曲にこめた毒も中和できないし、曲の伝達という使命も充分に達成できない。
なんか、こういうと神と預言者の関係みたいですが、演奏家と作曲者の関係って、それに似たものがあるように僕は感じます。
いずれにしても、あれは、豪奢で、キュートで、隠し味の苦みもちゃんと隠しもっていて、しかも、胸キュンの瞬間にも満ちている、ファンタジックで遊戯的な、素晴らしいチャイコフスキーでありました…。
◆2曲目:「スキタイ組曲・アラとローリー(プロコフィエフ)」
この曲を聴いたのは、正直、これがはじめてでした。
パンフを見て、3楽章めの「夜」を最初から楽しみにしていたのですが、よかったですねえ、「夜」…。
静か~な弦のはじまりと、その響きの辺境からひっそりと歩んでくるチェレスタのあの音形…。
プロコフィエフのような「異教的な」雰囲気を売りにしてる音楽は、どれだけ神秘的な深みを出せるかどうかで勝負が決まると思うんですが、いけてましたねえ、この3楽章---。
曲の要として屹立できる、実にパワフルなピアニシモが聴けた、と思ってます。
あ。ちなみに、この曲のあとすかさず「ブラボー!」とやったのが僕---。
◆3曲目」「交響曲11番・1905年(ショスタコーヴィッチ)」
現代有数のシンフォニー作家である、旧ソビエトのショスタコーヴィッテを認めることに関しては、むろん僕だって同意しますけど、芸術家・ショスタコーヴィッチに関して認めるかといえば、僕的にはいささか異論があります。
そのあたりの機微を批評家の許光俊氏も書いているので、彼の発言をちょっと引用をば---
----真にすごい作曲家なのかどうか、私は疑問があるが、近年急速に人気が高まりつつあるので挙げておく。社会主義下のソ連で、粛清されそうな危機を何度もかいくぐり、奇跡的に生き延びた音楽家だ。
その音楽は、クラッシック界有数の暗さを誇る。ただし、体勢を喜ばせるために、最期はガンガン盛りあがって大絶叫大会になることが多い。どの作品も似たように聞こえてしまう=ボキャブラリーが少ないように感じるのは私だけだろうか。
(許光俊「ショスタコーヴィッチに関して」より)
残念ながら、僕の見解も許氏の発言と同様です。
ショスタコは、衆知の通り、もの凄く腕のいい作曲家です---その才能には、もちろん瞠目するし、兜だって脱いじゃいる。
しかし---
藝術っていうのは、はたしてそれだけでいいもんなのでせうか?
僕がいいたいのは、要するにこういうことです。
彼、1906年の生まれです。
あのホロヴィッツよりも3つ下、リヒテルよりは9つ上---意外と近世のひとなんですよね、世代的にいうと。
ロシア革命とソビエト連邦の虚偽については、僕は前ブログ
徒然その113☆みずほフィルハーモニーのショスタコーヴィッチ☆ でも少々触れました。
まあ、そっち系の真相の究明うんぬんは、この際音楽とは関係ないのであえて触れないでおきますが、いずれにしても当時のソビエトが地獄のような環境だったというのは、これは、まごうかたなき歴史であり、また、事実でもありませう。
で、その生き地獄を生きのびてきた苦労人ショスタコーヴィッチの音楽を聴いて、僕がいつも感じること---
それは、旺盛な「生活力」と「狡猾さ」の2点です。
彼の肖像とか見ますと、非常に神経質そうな、線の細い印象が強いので、みんな、つい誤解しちゃうと思うんだけど、僕は、彼、その外貌に反比例するように、とっても強くて逞しい男だったんじゃないか、と睨んでる。
だって、あの地獄の密告体制のなかをなんとか生きのびて、社会的にも成功し、しかも、最期までその成功を維持しえたのですから…。
僕は、成功できたのだから芸術家として不純だったとか、そんなケチなことをいいたいわけではありません。
どんな環境であれ、「生きのびたい」というのは人間としての本能だし、そのために可能な限りの策を凝らすというのは、ある意味、ニンゲンの根本のところの願望でせう。
だから、そこの部分を否定しようっていうんじゃない。
でもね、たとえばショスタコとほぼ同時代を生きた、おなじロシア出身の世界的ピアニスト、スヴャトスラフ・リヒテルなんかが「この悪夢時代に対して」どう対応したか---?
リヒテルの伝記とかを読んでも、リヒテルのそのあたりの証言は非常に曖昧です。
あるところまでいくと、リヒテルは、ふっと黙りこむ---かたくなな貝のように。
この異様な沈黙は、リヒテルの多くのピアノ演奏のなかにも、底の部分に澱のようにそっと潜んでいて、リヒテル藝術の全般に独自の翳りを与えています。
たとえば、
1971年ザルツブルグで録音された、Schumann の Bunt Blatter Op.99----
さらには、
1971,2年におなじザルツブルグで録音された Bach の平均律1、2巻----
僕的には、リヒテルというのは、さほど好きなタイプのピアニストではないんです。
その理由は、彼のピアノって、なんだか薄気味わるいところがあるから…。
僕は、彼のピアニズムが自身の内面をすべてさらけだすのをあえて避けているように、ずっと長いこと感じつづけていたんです。
ええ、リヒテルは、意図的に、確実に何かを隠したんだ、と思います。
それは、語ろうとしても語れっこないから、はじめから他人と共有することを諦めきっているような、非常に濃い「絶望」の香りがたちこめた「なにか」です。
ロシア出身の大音楽家---かのホロヴィッツやレオニード・コーガンのヴァイオリン演奏(コーガンの死には、いまでも根強い暗殺説が囁かれているのは周知のことと思います)のなかにも、僕は、この種の独特の翳りをときどき嗅ぎつけますけど、なんといっても、この意図的な沈黙をいちばん強烈に感じさせるのはリヒテルです。
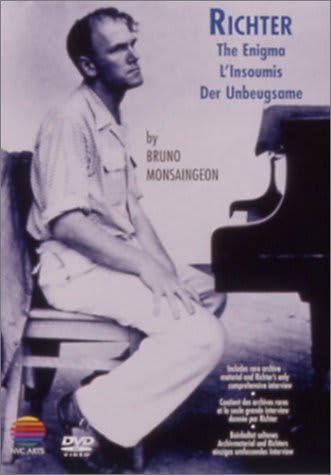
僕は、リヒテルの発信する、この不気味な沈黙に対して、ひたすら黙りこむことしかできません。
彼の発する沈黙の意味も、絶望の深さも、分かるかといえば、むろん分かんない---当然でせう、育った国も環境も、あらゆる面において異なっているんですから。
しかし、リヒテルがピアノにおいてもプライヴェートにおいても、あくまで「それ」を隠しつづけた---ソビエト体制が崩壊して自由に発言できる環境ができてからも、あえてそのことに対して沈黙しつづけたという事実に、僕は、なによりリヒテルの人間としての誠実を感じます---。
ショスタコーヴィッチに関しては、その真逆ね---僕は、ショスタコが、その種の絶望に対して、うまく立ちまわりすぎたと思うんですよ。
恐ろしく器用だった彼は、もちまえの音楽テクでなんだってできた。
ときには「絶望」と添い寝し、ときには「絶望」を帽子ごと殴りつけ、ときには「絶望」に哀願し、ときには「絶望」との妥協ラインを事務的に計算したりして…。
この種のショスタコ特有の饒舌さがね---僕は、大嫌いなんだな、実は---。
もちろん、ショスタコーヴィッチ本人が悪人だったとは思わない---でも、あんまり狡すぎますよ、彼…。
岡本太郎氏の藝術についてのあの名言、
----綺麗であってはならない、美しくあってはならない、心地よくあってはいけない…。
うん、あの3原則にことごとく違反しているのが彼の音楽だ、と僕は思うなあ。
× × ×
というわけでショスタコーヴィッチの音楽を否定したイーダちゃんなんですが、肝心の森口センセイとダヴァーイのショスタコ演奏は素晴らしかった、と思います。
特に第3楽章のアダージョ、ノン・ヴィブラートで影のように開始される曲の冒頭---それから、曲中盤の金管の咆哮から音楽が再びビオラ隊の囁きに引きわたされるあたりは、あの日の演奏会の白眉ともいえる部分だったのではないでせうか。
森口センセイの入魂の指揮も凄かったし、それに答えるオケの面々ももの凄かった。
身体を波打たせて奏すると、音ってあんなに変わるんですね---あれにはマジびっくり。
打王さんのティンパニも黒人のトークドラムみたいに多弁で凄かった。
4楽章の最後のコーダで、森口センセイの指揮にあわせて、鐘を鳴らす3階席の男性の熱血ぶりには思わず目を見張ったな。
そうして、極めつけは、曲の最後の森口センセイの「残心」---すべての音が静止して、会場全体がなんともいえない、ぎょっとするような沈黙に包まれた瞬間---あのいちばんいいところで、野蛮な先走り「ブラヴォー!」を叫んだのは、ありゃあ誰だ? フライングだよ、あれは。KYすぎるじゃないか、君ィ!---と僕はいいたい w 。
森口センセイの掲示されたショスタコーヴィッチは、僕のなかのショスタコ像とはだいぶ姿かたちの異なるものでした---うーん、僕は、彼があんなに「いいひと」だとはどーしても思えんのですよ。彼は、もそっと悪魔寄りの邪悪なモノを隠しもっている男だと僕は感じます---けど、あれだけの音楽力と表現力でもって再現されれば、それは、やっぱり、圧倒されました。
ムラヴィンスキーやコンドラシンのものも含めて、いままで聴いたなかで10本の指のなかに確実にランク入りする、ええ、あれは、見事に「生きて呼吸している」ショスタコーヴィッチの11番でした。
ただ、いささか性善説寄りすぎるショスタコーヴィッチだったんじゃないのかな?---と、僕としてはあくまでもしつこく、性悪説のショスタコ像を主張しつづけたいところです…。
ちょっと長くなりすぎました---しかし、多忙な僕にそうさせるほどの刺激を与えてくれる演奏だったからこそ、こうなったのですよ~---と若干責任逃れみたいなセリフを置いて、そろそろこの記事を閉じることにしませうか?
感じたままのことを正直に書きました。
これを読んで不快に思ったり、怒りを覚えたりしたひとがいたら御免なさい。
けど、ここに嘘はなにひとつ書いていないつもりです---おやすみなさい……。m(_ _)m