
李白、好きです----。
高校のとき習った(中学だったっけ?)教科書のなかのこの一遍を読んだときから、僕ぁ、もう李白のとりこ……。
黄鶴樓にて孟浩然の広陵に之くを送る 李白
故人 西のかた黄鶴樓を辞し
煙花 三月 揚州に下る
孤帆の遠影 碧空に尽き
唯だ見る 長江の天際に流るるを
だってねえ、スケール雄大な、まさにドラマチックな別れの情景じゃないですか、これは?
別れの相手が女じゃなくて、友人の詩人である孟浩然である、という一事もいい。
いまとはちがって、交通機関なんて発達してない古代中国ですからね。
いちど別れたら、今度はいつ会えるかなんてどっちも分かんない。
ひょっとしたら永遠の別れとなってしまうかもしれない。
そのような思いを互いに噛みしめながらの別れを、川べりに咲き誇ったいっぱいの桜が見守ってる。
やるせない思いで遠去かっていく帆船をじっと見送っていたのだけど、やがてその帆影も空と長江のあいまに見えなくなってしまった……。
せせこましい島国根性がすっかり精神の一部に染みついちゃった小人物の僕的視点からすれば、これは、なんたるスケールだべや! と呻るしかない規模のワイドスクリーンです。
でかすぎるよ、何もかも。
大陸的っていうのは、こういうのをいうのかな?
帆影が見えなくなるまで見送るって時間的スケールも、また凄い。
だって、半端じゃないっスよ----長江の彼方に見えなくなるまでって、少なくとも2、3時間は佇んでなくちゃいけない。
この詩のなかには、うん、現代ニッポンを深く毒している、セコくてマメな経済的時間なんてまるきり流れておらんのですよ。
まるで太古人が暮らしていたような、悠久の気配がじんじん滲んでる。
しかも、この語り口ね----企んで編んだ気配が、まったくしていない。
何気に息をするように言葉を吐いたらたまたまこんな詩になった、みたいな天衣無縫の息吹きがある。
さすが「詩仙」と呼ばれてるだけのことはありますね。
ヨーロッパや万葉、あるいはルバイヤートなんかとは、まったくちがう詩世界がここには、ある。
で、この邂逅以来、僕は、この李白って詩人の大ファンになったようなわけなんです----。
詩を好きになると、その詩を書いた詩人のことも当然想像しますよね?
僕も、学はないけど、その語感から自分なりの「李白像」みたいなものを胸中にまあ思い描いてました。
それは、だいたい下記の水墨画の如きものでありまして……

古代中国人のイメージでいうと、大抵のひとの「李白像」は、上記墨絵のようなものに帰着することになるだろう、と思うんですけど。
でもね、それ、ちがってるようなんだわ……。
僕は、民族的偏見なんかかけらもないからどうでもいいんですが、あの李白氏、実は、西域の非漢民族だったんじゃないか、みたいな研究が、最近ぞくぞくとあがってきてるんです。
日本の研究者の松浦友久氏なんかが、李白の父が「李客」と呼ばれ正式の漢人名をもった形跡がないこと、
また、後年の李白が科挙の試験を受験しなかったこと 等を根拠にこの説をだしておられます。
岡田英弘氏と宮脇淳子氏なんかも
----有名な詩人の李白はチュルク系といわれ、杜甫の詩にもアルタイ系の言語的特徴がみられる。
なあんていってられるし、楊海英氏ときたら、
----そもそも詩仙と呼ばれた李白自身はチュルク系であった可能性が高い。また、詩聖の杜甫の項にも「遊牧民の天幕で酒を飲んで、チュルク風の踊りを楽しむのが大好きだ」という詩があるほどだ。
とまでいっちゃってる…。
この件に関して、ネットで面白い記事見つけたんで以下引用します。
「中国に純粋血統の❛漢族❜は存在しない」
13億人の中国人の92%を占めるという漢族が、実際には❛遺伝子学的には現存しない血統❜だという調査結果が出てきた。
「漢族は血統概念ではなく文化的な概念」という通説が学術研究で明らかになったという点で、注目されている。
中国甘粛省蘭州大学の生命科学学院の謝小東教授が「純粋な血統の漢族は現在いない」という研究結果を最近発表したと、中国メディアが15日報じた。
謝教授の研究結果は、中国西北地域の少数民族の血液サンプルDNA研究などから出された。
謝教授は「DNA調査の結果、現代の中国人はさまざまな民族の特質が混ざったもので、いかなる特定民族の特質も顕著には表れてこなかった」と説明した。また「かなり以前から『漢族は中原に暮らしている』と考えられてきたが、これは特定時代の漢族を周辺の他の民族と区別するために作った地域的区分にすぎない」とし、「漢族をこのように地域的に特定して定義することはできない」と指摘した。
例えばBC12世紀の陝西省西安を首都とした西周は漢族政権に属するが、その後の春秋戦国時代に同じ地域に建てられた秦は少数民族の❛西戎❜が主流だったということだ。 (中略)
さらに、中国人は自らを「炎帝と黄帝の子孫(炎黄子孫)」と主張するが、研究の結果、黄帝と炎帝の発源地も❛北狄(ほくてき)❜地域だったことが研究の結果から分かった。
黄帝と炎帝の発源地はともに現在の甘粛省と陝西省にまたがる黄土高原地域で、ともに漢族の本拠地でなく、居住地域でもなかったということだ…。
また、学校の教科書で一度は拝見したでしょう、だれもが知っている紀元前221年に中国最初の統一王朝秦の初代皇帝となった、始皇帝 政、彼もまた胡人(イラン系白人種)であったとの伝説があり、一説には金髪碧眼であったとも、赤い髪・青い目・高い鼻と白人種の特徴が顕著であったとも謂われています…。
(中国大好き 中川隆より抜粋 http://www.asyura2.com/09/reki02/msg/287.html )
メジャーどころでいうと僕の贔屓作家のひとりである、かの加治将一氏が、
「失われたミカドの秘紋~エルサレムからヤマトへ----「漢字」がすべてを語りだす!(祥伝社)」のなかで、やはり同種の主張をされてます。
「もっと立ち入れば」
西山が、歩きながらさらなる苦痛を提供した。
「唐の初代皇帝と言っていい李世民ですが、彼は漢民族ではありません」
「漢族の名門貴族、李家の出身ではないと?」
「誤解されやすいのですが、違います」
きっぱりと言い切った。
「李というのは後付けの名で、出身は鮮卑族。これはもはや学者の間では定説です」
「鮮卑族って、満州族ではないですか?」
……(中略)……
「唐がトルコの国……」
ようやくイメージが湧いてきた。
「トルコ側に史書が今に残っていたら、きっと唐ではなく、あちらの文字で『テング』と書かれていたと思います」
「……」
「唐の広東語の発音はテングです。トルコ語のテング、つまり天可汗の『天』を音写して、『唐』と表記した」
頭がこんがらがった。それを察した西山が繰り返した。
「新しい連合国家の名を『テング』と呼んだ。それを非遊牧民の受けを狙って漢字で『唐』という一字で表したというわけです」
……(中略)……
「しかしそれが本当だとすると、ファーストエンペラー秦に始まり、モンゴル系の蒙古、つまり元、それに今お話しした唐、隋、さらにはラスト・エンペラー清に至るまで、有名どころの王朝のほとんどが漢民族でないことになってしまいます」
望月の頭は、まだイメージの積み残しがあるのか、あしらい切れずに、再び置いてけぼりになっている。
「まだ、だめですか?」
整えきれない望月に言った。
「漢民族優位政策をとる共産党にとって、騎馬民族の王朝などあってはならない歴史なのです。民族だけは超越できない忌々しき問題で、実は、それこそがこの国の最大の弱点と言っても過言ではありません」
「分かります」
「見え透いた嘘でも有形無形に偽りを流し続ければ、民の思いはそれで固まる。漢族の王朝を次々と置き換え、とにかくそれを教え続ける。そうすれば偽りの中に歴史が固まってゆくのです。一党独裁国家なら、教科書を作り話で固めるのは難しい話ではありません…」
(加治将一「失われたミカドの秘紋」より:祥伝社)
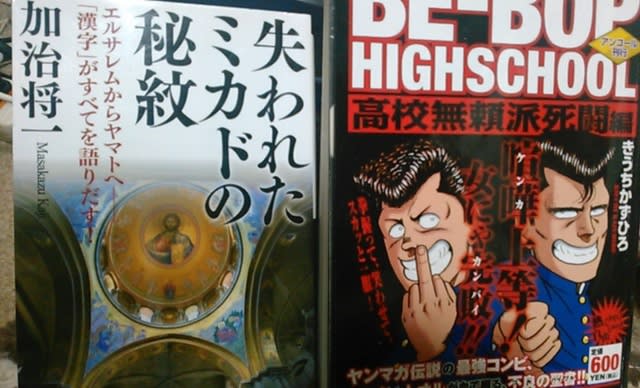
うーむ、恐ろしい話ですが、これは充分にありうる話だ、と僕は思います。
そもそも混血してない純粋な民族なんて観念自体が、いまの学問常識ではリアルティーゼロのお伽噺でしかない上に、
ましてや世界歴史でいちばん戦争が多かった軋轢大陸、地政学でいうところのハートランドの中央に位置するかの大チャイナですもん。
あの悪名高いジェノサイド「易姓革命」が幾度となくくりかえされた、残酷極まりないお国柄。
これで民族の混血がおこらなかった、と思うほうがどうかしてる。
しかも、あらゆる栄誉と富がパンパンに詰まりまくっている、ラピュタみたいな超帝国です。
----あの威張りくさった帝国を落としさえすれば……。
周辺の持たざる国々やあらゆる飢えた異民族がそんな風に思わないわけがない。
嫉妬と憧れと怨みの対象でありつづけていたにちがいありません。
理論的に考えて、混血は当然あったと考えるのが自然でしょう----最新のDNA研究の結果もそれを裏付けているわけだし。
すると、今度は、歴代の中国王朝は、元、清等の少数の場合をのぞいて、漢民族の王朝であった、という現代の「政治的神話」のほうがゆらぎだす理窟です。
で、いま先端の学問が追っているのは、そちら側の事実なんですね、つまるところ……。
そうしたあっち側の「混血」情報としてもっともセンセーショナルなものの第一が、秦の始皇帝の陵墓に置かれた、多数の兵士像として有名なあの「兵馬俑」----
あれの制作に古代ギリシア人が協力していた可能性がある、ということが英BBCが報道し、中国で話題になりました。
----シルクロードが開かれる前に秦始皇帝時代の中国と西洋の間で密接な接触があった証拠が見つかった。
独自に文明を発展させたことに誇りを抱いているクラッシックな中国大衆には、これは面白くない話題だったようですが、この視点は結構学問的裏付けのあるもののようです。
ウィーン大学の教授も最近発見された新たな兵馬俑の像の特徴から、
----ギリシアの彫刻家が中国人に技術指導したかもしれない…。
と述べています。
これなどは、「歴代王朝漢民族支配説」を覆す、有力情報の皮切りでしょう。


さらにはこれね----中国東北部に位置する遼寧省で5500年前の紅山文化の遺跡から発見された 「青い目の女神像」----
この女神さま、方円形の平たい顔で、頬骨がでてて、目は斜めに吊りあがり、鼻筋は低く短く、鼻孔はやや上に反っている。
ま、標準的モンゴロイドの典型的なモデルケースでありましょう。
でもねえ、それには瞳の色が問題なんだな----この女神さま、眼が青いんだわ……。
鳥越憲三郎の著作より以下引用します。(これも上記、中国大好き 中川隆 よりの引用です)
----少なくとも女神像の目が青いのは、中央アジアの人種の血を受けていることを示している。しかし、容貌は明らかにモンゴロイド人種である。そのことは、混血の女性をモデルにしたといえるが、当時の社会に混血が多く、違和感がなかったからであろう。それだけに混血の時期は遠く遡るものとみてよかろう。中国東北部の女神像の分布からみて、その信仰は広域にわたっていたといえる。しかも地母神としての女神像の信仰が新石器時代早期からみられるので、そのことから中央アジアからこの地への渡来は、その時代まで遡らせる可能性もあるであろう。というのは、女神信仰がメソポタミアに起源し、それが中央アジアに広く波及したからで、アナウ文化に女神像を部屋に祀る習俗がみられるのもそのためである。そこで、コーカソイド種族がこの信仰をもたらしたと考えることもできるだろう……。
まあ、文章はまずいと思うけど、このセンセイ、いいこといってます。
ああ、でも、まずは肝心なその女神像のフォトをあげておきましょうかねえ----

漢民族中国王朝支配説を覆すこのような証拠物件は、いまや次々とでてきてるんですよ。
してみると、毛沢東のあの闇雲な文化大革命も、この「漢民族」の政治的優位を世界に示すための、異民族の遺跡・痕跡に対する政治的ジェノサイドだったといううがった見方ができないでもない。
まあ、僕としてはそこまで大局的に話を運ぶつもりはないんだけど。
李白は、701~762年まで生きた8世紀生まれのひとです。
彼がもしかしてチュルク系のひとで、さらには金髪碧眼であった可能性があるってだけでも、僕的にはそれ、とても風流な話題だなあって思えるわけで……。
だって、金髪碧眼、長身の李太白なんて、水墨画風にしみったれた過去の李白イメージよりはるかに「粋」じゃないですか----!
うん、僕は古典的な漢人・李白より、こっち側の新・蛮族風李白のが好きだなあ……。
そのような夢想を編み個人的に楽しむためだけに、このような記事を書いてみ申した。
学問的省察も証拠固めも、したがって大変にいい加減であります。
でも、いいのよ----学問的正しさより、李白の詩で酔うほうが僕にとってははるかに重大事なんだから。
またしても長い、勝手な記事となりました----今夜はこのへんでお開きにしたいと思います----最後までつきあってくれてありがとう----もうちょいで午前0時です----それでは皆さん、お休みなさい……。(-o-yzzz






































