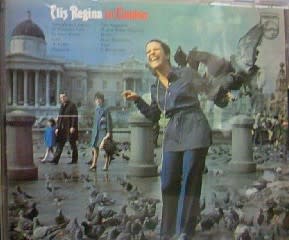というわけで金沢「香林坊」で楽しい一夜をすごしたイーダちゃんが翌日目指したのは、むろんのこと「温泉」!
せっかく石川くんだりまできたんだから、温泉入んないでどーすんのって高揚心地なのでありました。
幸い、翌日の天気は晴れ---金沢駅近郊の○○ホテルの高層の窓に差しこむ朝の光を見て、イーダちゃんは思わずほくそえんだものです。
うわ、ラッキー、と。(^o^)>
ところが、下調べなしのこの思いつき温泉プロジェクトは思わぬ結末を迎えるのです。
最初は僕、金沢駅からJRに乗って、小松にある加賀温泉郷の顔のひとつ、粟津温泉ってとこを目指したんですよ。
粟津温泉って駅で降りて、ここ、またバスを乗り継いでいくのよ。
で、たどり着いた町は、いかにも温泉地って香りがにほいたつ、もー 超・いい風情の温泉どころ…。
もー 好みって感じの、いい意味でのひなびた温泉地。
ここ、あの有名な世界最古の宿「法師」があるとこなんですよ。
そんなわけでイーダちゃんはもうこの粟津温泉街を歩きながら、雰囲気だけですでにはしゃいじゃってね、地元のひとが勧めるこちらの共同湯「総湯」ってとこをまあ訪ねてみたわけなんですよ、これが。
料金は420円。
いつも旅には冬山登山のような大きなリュックをしょっていくイーダちゃんを見て湯番のオバちゃんは、
----あ。お兄さん、そのリュックじゃロッカーに入らないから、そこらへんに置いておくといいよ。あたしがときどき見てるから。
なんて牧歌的なことをおっしゃって…。
そうか、都内なんかとちがって、ここじゃ置き引きなんかもないんだ、と、それ聴いてますますホワ~ンとしたイーダちゃんが夢見心地で服脱いで、湯処のガラス戸いそいそとをあけると----
塩素でした。
ツーンとね、鼻が曲がりそうな塩素の香り。
愕然としました。
けど、それを信じたくなかったんで一応掛け湯だけして、肝心の円形のお風呂に肩まで浸かってみると…
嗚呼、完璧無比の塩素湯ぢゃないっスか。
----ダミだ、こりゃ!
3秒で出ました。
がっかりしたというより、むしろ哀しかった。
というのはね、石川って、水がとてもいい土地なんです。
僕が前日に泊まった金沢のホテルでも、そこ、水道水で温泉じゃないのに、水の質があまりにいいために、僕、ほとんど温泉気分でそのホテル湯を満喫できたほどですモン。
着替え処の温泉の泉質表を見ると、うん、たしかに「条例により衛生のため塩素を投入しています」の文字が確認できます。
身体が乾くのも待たずに服着て、あっというまにこの「総湯」を後にしました---それこそ逃げるように。
宿のオバちゃんが驚いて、
----あら、もう出るの? もっとゆっくりしてけばいいのに。
なんて親しみの声かけてくれるのも逆に哀しかった。
曖昧に笑って、僕、この粟津温泉を去るしかなかったですねえ。
もうね、10分だってこの地にいたくなかったの。
3秒浸かっただけでも、塩素の投入さえなければ、この温泉がいかに極上の温泉だったかくらいはすぐ分かる。
全国でも誇れるくらいのお湯ですよ、ここの単純泉は。
ただ、いいですか、いかにグレートな温泉にしてもね、塩素を入れれば温泉は必ず死ぬのです!
本来の温泉の質がいかにスーパーだったかが感知できるぶんだけ、僕あ、哀しかったなあ。
もー マジ泣きそう(T.T)
最近、不正選挙の訴訟に乗りだして、さまざまなところから脅迫めいたことをいわれても屁のカッパのイーダちゃんなんですけど、この塩素温泉にはひさびさ「太宰のように」しこたま傷ついちゃいました。
----汚れっちまった悲しみに 今日も小雪の降りかかる
汚れっちまった悲しみは たとえば塩素の極上湯……
あーん!<(TyT)>
僕、帰りのバスの待ち時間も待ちきれずに、帰りの7キロの田舎道、歩いて踏破しちゃったほどですもん。
いやー まいりました---こんなにまいったのは、島根の玉造温泉のあの「長楽園」事件以来のことでした…。
(この件に興味ありげの奇特なお方は nifty温泉のイーダちゃんのクチコミページを参照のこと)


その超残念な共同湯・粟津温泉の「総湯」 傷心の帰りの田舎道。路肩の水路をメダカが泳いでいたよ。
でも、まあせっかく北陸まできたんだからと気を取りなおして、今度は、おなじ加賀温泉郷の山中温泉ってとこにいったんです。
JRの加賀温泉って駅で降りて、またまたバスを乗り継いでいくんです。
こちら、あの芭蕉が訪れて、歌まで詠んでいる、いわば加賀温泉郷の老舗的存在なんですね。
いくらか町的な山城温泉をいきすぎて、さらに曲がりくねった道をいき、山の香りがツンと濃くなったころ、よーやくバスは目的の山中温泉に到着しました。
わあ、と思いましたよ。
バスを降りたら、いかにも山の上の田舎町って風貌の温泉町がとーんとひらけてて…。
しかも、この町並、一軒一軒の家々にまでなんともいえない統一感があるんです。
俺たちはこうやって歴史ある山中温泉を代々守ってきたんだゾっていってるみたいな---。
家々の黒々しい瓦屋根の並びが、それから、町並に染みついた温泉町独特の濃い雰囲気が、もうたまんない。
ちょっと恍惚としながら、イーダちゃんは、この山中温泉街をぶらぶら散策してね、それから、ジモティーに道を尋ね尋ねしながら、この山中温泉の顔である共同湯「総湯」を目指したと思いねえ。
山中温泉の「総湯」---それは、全国的に有名な温泉教授が、西の飯坂温泉とまで評したことのある、温泉好きにとって聖地のひとつでもある共同湯なんです。
こちら、町の中心にある、森光子劇場って立派な建物のすぐ隣りにあってね。
それはそれは素晴らしい威容なんですわ---共同湯まえの足湯では大勢の観光客がみんな足湯を楽しんでいるしね---コンクリートと石造りで建てられた、この巨大な共同湯をまえにして、温泉好きなら誰だってじっとしていられるはずがありません。
僕も心からワクワクしてね---この「総湯」の暖簾をくぐったわけなんです、はい。

上図:その山中温泉「総湯」(写真は女湯)。こんな立派な外貌なのに…
この「総湯」、内部の造りもたまらなくレトロでありました。
森光子劇団の芝居のポスターが壁に貼ってあって、むかしの音楽がいい感じに流れてもいて。
浴場の二重戸をあけて、掛け湯の設備があるのも素晴らしい。
でもね、残念ながら、ここも塩素湯でした。
僕は、今度は5秒で、ここ、出ました…。
ほかの旅館をあたってみたら、ひょっとしてそんなことはなかったのかもしれない。
塩素湯じゃない、ちゃんとしたお湯で営業してるお宿もあったのかもしれない。
そういえばいつか、鹿児島の紫美温泉を訪れたとき、噂の紫美温泉共同浴場は残念無念の塩素湯だったのに、そのお隣りの旅館「紫美荘」は噂通りの「神の湯」をちゃんと保持してらして、非常に感動したことがあったことなんかが思い出されもします。
でもね、この日は、これがイーダちゃんの限界でした。
がっかりしすぎてね、もう温泉に入ろうって気力そのものが、なんか萎えちゃったっていうか…。
時間的にもふたつの温泉を訪ねたことで、時間も6時間以上使ってましたからね。
本来ならどっちかの温泉に泊まっていくプロジェクトだったんですけど、それもなし---そんなわけでイーダちゃんの加賀温泉訪問は、非常にショボイ結末を迎えたのでありました---はあ…。
加賀温泉駅についたらもうすっかり夕方になってまして、JRに乗ってとりあえず米原までいきました。
知っての通り、米原駅ってなんにもない処なんですわ。
かろうじて駅前のビジネスホテルで宿とって、それから、一軒だけある駅前スーパーに夕食の仕入れにいって…。
で、買い物籠にカップ麺とか入れてレジにそれをドカンと置いた刹那、ふいにある都市伝説を思い出したんですよ。
それは、滋賀では、スーパーにも鮒寿司を置いてあるっていう内容の伝聞でした。
鮒寿司というのは、クサヤと並ぶ、日本一臭い食品のひとつ。
鮒の腹にお米をつめて、その鮒をドバーッと樽に入れ、そのまま1年も2年も発酵(腐敗)させるわけ。
琵琶湖産のが有名ですよね---でも、僕は、まだそのクッサイ鮒寿司を食したことがなかった。
だもんで、まあダメ元でレジのおばちゃんに聴いてみたわけです。
----あのー 米原ってたしか滋賀、ですよね…?
----はあ、そうですけど(おばちゃんは当然怪訝顔)…。
----あのー じゃあ、こちらで鮒寿司って扱ってらっしゃいます…?
----ええ…、置いてあるはずですけど…。
----マジ? マジっすかあ…!
喜び勇んで小走りで鮒寿司パックを置いてある売り場までいきましたとも。
売り場のおじさんに鮒寿司の食い方を聴いてみる。
なんでも、洗ったりせずにそのまま食えるらしい。
米が腐って麹状になってて、そこが特にクッサイから、好きなひとでも麹だけは取っちゃうとか。
しかし、超好きなひとだと、麹にお茶かけて、お茶漬けにして食っちゃうとか…。
ちょっとハードルが高げなことをいわれるんですよ、はい。
でも、僕、そのときは舞いあがってましたから---で、超ウキウキしながら、あらためてそれをレジにもっていったら、さっきの売り場のおじさんがなぜかまたレジにいらして、
----お客さん、売る側のわたしがいうのもなんですが、わたし、実は、鮒寿司、苦手なんですよ…。
----あらまあ、そうなんですか…。
----ですが、やっぱり地元の名産品ですからね。都会のひとがチャレンジしてくれるのは嬉しいんですよ。
----ええ、チャレンジしてみます。
----ぜひ、チャレンジされてください…。ただ、麹は、ほんと、臭いですから。決してむりせんよぅに…。
----ありがとうございます…。
で、ホテルの部屋帰って、缶チューハイといっしょに、いそいそと鮒寿司のパックをあけたんですね。(記事トップ参照)
そしたら、ツーン!
鼻の曲がりそうな濃ゆい酒カス臭が、もう部屋中にツーン!
一瞬だけ、腰が引けそうになります---しっかし、昼間の温泉の塩素臭にくらべたらこんなのなんてことない! と自らを奮いたたせ、その鮒さんの一切れを口に放ってみると……
----あら。旨いよ、コレ…。旨い!
酒カスの濃ゆい香りとチーズの臭みが入りまじったような独自の腐臭のなか、肝心の鮒さんは意外とシャキッとした歯ごたえがあってね、うん、僕的には非常にコレ、うまかった。
クッサイといわれてた麹も充分イケル。
なにより鮒さんの一切れ一切れに染みついた、酸っぱいような、苦いような、微妙かつキョーレツな、一種コクのある風味がたまんない。
鮒さんのアタマもコリコリ食えたし、クサイといわれていた麹だってお茶漬けにして、ブラボー、あっというまに完食しちゃったよー---。


いやはや、満足---でしたねえ…。
というわけで加賀温泉郷との闘いにはいいところなく敗れ去ったイーダちゃんでしたが、滋賀の鮒寿司食いで温泉の仇を見事討てたのでありました。
滋賀に再訪する楽しみがまたひとつできたということで、ま、終わりよければすべてよし---今夜はこのへんでおいとましたく存じます---お休みなさい---マル…。m(_ _)m