HIV感染症の診療のテーマの中に、お産があります。
日本の女性HIV感染者の約30%が妊婦健診で偶然HIV感染に気づいている状況です。
(妊娠しなければ検査機会のなかった人たち?)
今、日本では母子感染のリスクは1%以下ですが、これは初期の妊婦健診で気づき、抗HIV薬の内服・選択的帝王切開・母乳中止といったいくつかの医療介入をしての数字です。
先にHIV感染がわかっており、途中で妊娠希望のある人は、妊婦でも飲める薬に変更をして準備をします。
母乳をあげることができないことは非常に残念に思う親御さん達も多いですが、感染予防が何よりのケアですし、いまはよいミルク製品もあります。ということで、赤ちゃんを皆で守ろう、とがんばります。
助産師は血液や体液曝露の機会の多い看護職ですので、曝露事故予防の話も重要なのですが、日本でのHIV流行初期に助産師さんにいわれたことは・・・
「母乳と羊水はキレイ」「神聖なもの」
です。
ある流派?では、助産師がお母さんの母乳をしぼり、なめて(飲んで?)何かを診断して食事のアドバイスをするということでした。
(@@;)「げげ。血液と同じですよ。なめちゃうんですか?」→「モチロン」
マッサージも当時は素手でしており、乳頭の亀裂から出血するひともいるなか、母乳・血液を素手でさわる(浴びる)リスクについて、あまり認知していない人も多かったように記憶しています。
研究者に「外国の状況を調べてくれ」といわれて海外に問い合わせても、
「他人が母乳をなめる理由がわからない」「それはいったいなんのため?」
「なぜ他人が乳房をさわるのかわわからない。自分で動けるひとだから、セルフマッサージを教えるだけでしょ」
「体液にさわるなら手袋やゴーグルがあたりまえでしょ。何いってんの」
と、質問の趣旨やチョンマゲニッポンな状況を理解してもらえませんでした。
JICAでアフリカに派遣されていた助産師さんからは、「胸は性器の一部であり、旦那様しかさわってはいけない地域もある。他人がさわったら怒られる」といわれました。
日本の助産師さんは全員が乳房マッサージを売りにしているわけではないようですが、特別なマッサージは「奥技みたいなものです」ということで、認定(免許?)システムもあるのだそうです。
奥義を究めるその勢いで感染症についても学んでいただきたい・・・と思った十数年前の思い出でした。
今はどうなんでしょうね。
(補足)途上国では安全な水の確保が難しいため、お母さん達に抗HIV薬を飲んでもらい、授乳するという手段が選択されることもあります。
日本の女性HIV感染者の約30%が妊婦健診で偶然HIV感染に気づいている状況です。
(妊娠しなければ検査機会のなかった人たち?)
今、日本では母子感染のリスクは1%以下ですが、これは初期の妊婦健診で気づき、抗HIV薬の内服・選択的帝王切開・母乳中止といったいくつかの医療介入をしての数字です。
先にHIV感染がわかっており、途中で妊娠希望のある人は、妊婦でも飲める薬に変更をして準備をします。
母乳をあげることができないことは非常に残念に思う親御さん達も多いですが、感染予防が何よりのケアですし、いまはよいミルク製品もあります。ということで、赤ちゃんを皆で守ろう、とがんばります。
助産師は血液や体液曝露の機会の多い看護職ですので、曝露事故予防の話も重要なのですが、日本でのHIV流行初期に助産師さんにいわれたことは・・・
「母乳と羊水はキレイ」「神聖なもの」
です。
ある流派?では、助産師がお母さんの母乳をしぼり、なめて(飲んで?)何かを診断して食事のアドバイスをするということでした。
(@@;)「げげ。血液と同じですよ。なめちゃうんですか?」→「モチロン」
マッサージも当時は素手でしており、乳頭の亀裂から出血するひともいるなか、母乳・血液を素手でさわる(浴びる)リスクについて、あまり認知していない人も多かったように記憶しています。
研究者に「外国の状況を調べてくれ」といわれて海外に問い合わせても、
「他人が母乳をなめる理由がわからない」「それはいったいなんのため?」
「なぜ他人が乳房をさわるのかわわからない。自分で動けるひとだから、セルフマッサージを教えるだけでしょ」
「体液にさわるなら手袋やゴーグルがあたりまえでしょ。何いってんの」
と、質問の趣旨やチョンマゲニッポンな状況を理解してもらえませんでした。
JICAでアフリカに派遣されていた助産師さんからは、「胸は性器の一部であり、旦那様しかさわってはいけない地域もある。他人がさわったら怒られる」といわれました。
日本の助産師さんは全員が乳房マッサージを売りにしているわけではないようですが、特別なマッサージは「奥技みたいなものです」ということで、認定(免許?)システムもあるのだそうです。
奥義を究めるその勢いで感染症についても学んでいただきたい・・・と思った十数年前の思い出でした。
今はどうなんでしょうね。
(補足)途上国では安全な水の確保が難しいため、お母さん達に抗HIV薬を飲んでもらい、授乳するという手段が選択されることもあります。














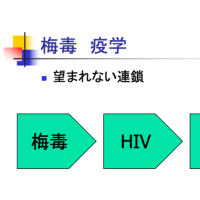
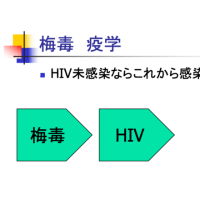
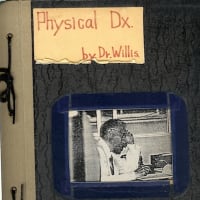

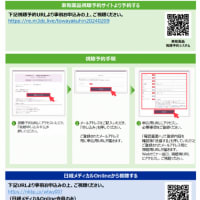
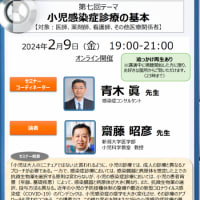
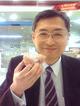





それでも退院後のトラブルや授乳についての悩みをフォローする体制のない病産院もまだ多いので、結局はマッサージにいきついてしまうのだと思います。
味見以外にも「おいしいおっぱい」「母乳の子は良い子になる。顔が違う」とか、厳しい食事療法や舌小帯切除を勧めたり、「母乳は新生児の眼脂に効くから抗生剤の点眼薬でなく母乳をたらす」とかいろいろ根拠のないことが多く見受けられますが、なかなか助産師内部では問題にならないのです。
ただ、「母乳は体液」という視点は私自身も含め甘いかなと、記事を読んでハッとさせられました。
乳腺炎の初期やうつ乳に対してはマッサージが必要なこともありますし、搾乳が必要な人には搾乳介助をしますが、素手で実施しています。
ディスポの手袋を使用している病院はあるのでしょうか?
母乳についての本には、母乳育児と感染症として標準予防策については記述がありますが、実際には「体液」という認識があるかどうか。
なぜ「母乳は体液」という認識が甘いかというと、
妊娠中に感染症の検査がなされているので、母乳を介しての疾患のスクリーニングができている点があると思います。そしてその母乳を介する疾患も、母乳に少し触ったから感染するものではなく、ある期間授乳することで児に感染するものですね。
また血液感染するB・C型肝炎も、母乳は一応感染源とはならないとされています。
もちろん感染症はまだまだ未知の病原体のほうが多いと思うので原則は大事だと思いますが、標準予防策の考え方の「体液」と、新生児が飲んでも感染を起こすことのない母乳について、同一視するのは現実的でないような気もします。
もちろん感染症はまだ未知の病原体のほうが多いので原則は大事だと思いますが、今後はやはりディスポ手袋着用が望ましいのでしょうか?
臨床で改善すべきことがありましたら、どうぞアドバイスをお願いいたします。
ICNを専従でおいている・おこうとする医療機関なのでサンプルが偏っていますが。
10年前くらいは、いろいろな現場の抵抗があったそうです。
「検査してマイナスだからダイジョブ」(感染症の理解不足)
「手袋はクライアントに失礼だから使わない」(精神論・マイポリシー)
最近聞くのは、患者さんの清潔感もかわってきており、自分がキレイにしておきたいゾーンについて「素手でさわらないで」という人もいるそうです。
ま、医療者の仕事中の手指の汚染は、日常生活とはことなりますからね。ごもっともです。
スタンダードプリコーションは、患者→医療者だけでなく、医療者・器具→患者、医療者経由の患者→患者の感染予防です。
でも、感染症の勉強をした上で、コストその他を考えて手袋使用を部分的にしかしていない施設もあります。しかし、使わなくていい、のではなく、前後に手洗いを義務化しています。
医師が(体液に触れないとしても)患者Aから患者Bに行くときに、手洗いあるいはアルコール刷り込み剤で手指消毒をします。
看護職も、1人の患者ケアから次の患者ケアにうつる間に同じようにすることが必要ですが、明らかな汚染などがなければアルコール刷り込み剤でよい、ということになっています。
しかし、体液の付着などがあれば、原則手洗いです。母乳もです。
体液がつくかもしれないし、つかないかもしれない、というときにどう考えるでしょうか。
そばに手洗いのための水道がない場合は「念のため手袋」になるのではないかとおもいます。
・・と、このような判断を個人の資質に依存すると安全管理が危うくなるので標準化が必要になるわけです。
責任ある立場の人達が今どのあたりを指向するか。コストの問題もありますが、予見可能な異を回避しなかった責任が問われる時代ですので、過小よりは過剰にシフトしている印象があります。
手袋系調査もいろいろありますね。
http://www.jstage.jst.go.jp/article/jjam/23/2/23_208/_article/-char/ja
どこまでやるかは施設の特徴や、実際にやっている手技なども関係してくると思っています。
(ちなみに、エイズ診療拠点病院は急性期対応の大きな病院が多いです)