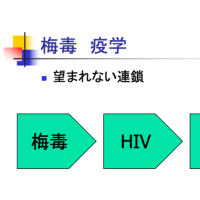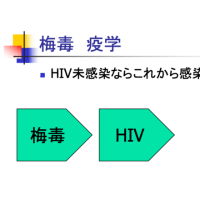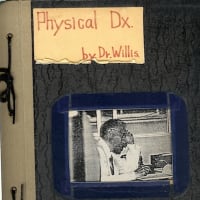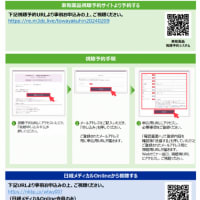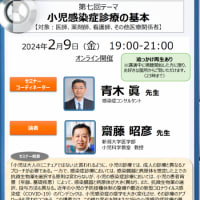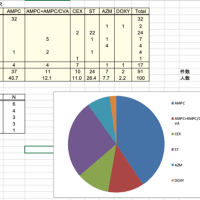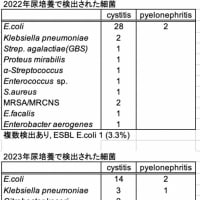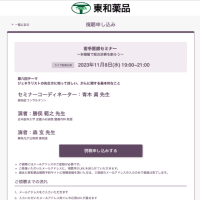年に数えるほどですが、、「当社の○○について講演の中でよろしく」的な依頼があります。適正使用の話をするのですからもちろんお断りします。
多くの場合、そのようなことはいわれないのですし、健全だとおもっています。
利益相反については所属施設に必ずルールがあるとおもいますので、研修医の皆さんはいずれどこかで講義や説明をうけるとおもいます。
所属科や病院の評価につながることもありますので、迷ったら上級医に相談です。
公的な病院に所属している場合、研修医は厳密な意味での公務員ではなくても、外側の人は公務員に準じて扱います。
いろいろな施設の人が参加する催しなどは、そういった厳密対応が必要な人への配慮を考えることが必要。
2010年3月にBritish Medical Journalに掲載された論文は、製薬会社となんらかの経済的な関係をもつかもしれない医師にとっては興味深い内容です。米国のメイヨークリニックの研究者等の報告です。
検証をした202論文のうち、53%(108)はConflict of interestの記載があり、このうち90人の著者(45%)は利益の関連がありました。
Association between industry affiliation and position on cardiovascular risk with rosiglitazone: cross sectional systematic review
糖尿病の薬を服用することによって心筋梗塞のリスクがあがる、下がるという評価について、製薬会社との経済的な関係をもっている医師にバイアスがあるのではないか?ということを検証しています。
心筋梗塞リスクについての評価が含まれる論文等202件の著者180人について調べたところ、
「リスクをあげない」群の8割、「リスクがあがる」群の2割が製薬会社から研究費や講演の謝金等を受け取り有り。薬剤の継続・変更についての意見でも同様の傾向が把握されました。
同様の検討をしている調査も複数あります。
Pharmaceutical industry sponsorship and research outcome and quality: systematic review
すべてダメ、よろしくない、ということではありません。実際に生じている労働に対価があるわけですが、それでもその考え方や許容の仕方は個人によって異なります。
バイアスがかかっていないかという評価を受けるためのまずは情報開示が基本。
海外のカンファレンスやジャーナルではすでにありますが、論文や講演の際にconflict of interestなどをdiscloseするように日本でもなっていくのだろうと想像します。
米国医学研究所(IOM)が医師に製薬企業からの贈り物を受けないよう提言(薬害オンブズパースン会議)
ファイザー社が米国内の医師などへの支払いを開示、情報公開での日本の遅れが鮮明に(薬害オンブズパースン会議)
予防接種でACIPの話題もででていますが、米国での構成要員にはそれはそれは厳しい基準があるのだそうです(家族含めて審査)。
多くの場合、そのようなことはいわれないのですし、健全だとおもっています。
利益相反については所属施設に必ずルールがあるとおもいますので、研修医の皆さんはいずれどこかで講義や説明をうけるとおもいます。
所属科や病院の評価につながることもありますので、迷ったら上級医に相談です。
公的な病院に所属している場合、研修医は厳密な意味での公務員ではなくても、外側の人は公務員に準じて扱います。
いろいろな施設の人が参加する催しなどは、そういった厳密対応が必要な人への配慮を考えることが必要。
2010年3月にBritish Medical Journalに掲載された論文は、製薬会社となんらかの経済的な関係をもつかもしれない医師にとっては興味深い内容です。米国のメイヨークリニックの研究者等の報告です。
検証をした202論文のうち、53%(108)はConflict of interestの記載があり、このうち90人の著者(45%)は利益の関連がありました。
Association between industry affiliation and position on cardiovascular risk with rosiglitazone: cross sectional systematic review
糖尿病の薬を服用することによって心筋梗塞のリスクがあがる、下がるという評価について、製薬会社との経済的な関係をもっている医師にバイアスがあるのではないか?ということを検証しています。
心筋梗塞リスクについての評価が含まれる論文等202件の著者180人について調べたところ、
「リスクをあげない」群の8割、「リスクがあがる」群の2割が製薬会社から研究費や講演の謝金等を受け取り有り。薬剤の継続・変更についての意見でも同様の傾向が把握されました。
同様の検討をしている調査も複数あります。
Pharmaceutical industry sponsorship and research outcome and quality: systematic review
すべてダメ、よろしくない、ということではありません。実際に生じている労働に対価があるわけですが、それでもその考え方や許容の仕方は個人によって異なります。
バイアスがかかっていないかという評価を受けるためのまずは情報開示が基本。
海外のカンファレンスやジャーナルではすでにありますが、論文や講演の際にconflict of interestなどをdiscloseするように日本でもなっていくのだろうと想像します。
米国医学研究所(IOM)が医師に製薬企業からの贈り物を受けないよう提言(薬害オンブズパースン会議)
ファイザー社が米国内の医師などへの支払いを開示、情報公開での日本の遅れが鮮明に(薬害オンブズパースン会議)
予防接種でACIPの話題もででていますが、米国での構成要員にはそれはそれは厳しい基準があるのだそうです(家族含めて審査)。