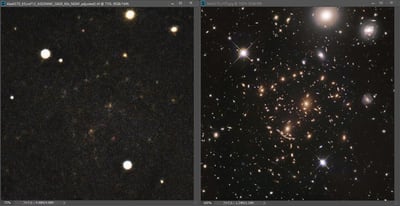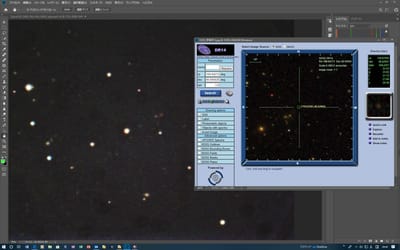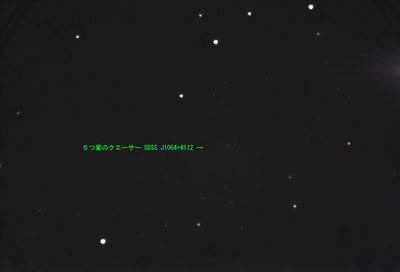昨晩から今朝方に掛けては65cm天文台でお仕事。
主にはFLI-PL09000冷却CCDカメラセットのファーストライト
でしたが、ASI294MCも納品して取扱説明と撮像を行ってきました。
今まで使っていたアポジーCCDが故障し、昨年はまともに観測が
出来ませんでした。今回、田中光化学工業さんからFLI-PL09000を
取り寄せて頂き、無事撮像までこぎつけました。
この件は後日また書きます。
ZWO-ASI294MCも”オマケ”のような形で納品したわけですが、
これが、一発目からこの画像ですよ!
作品撮りでないため、ダークもフラットも撮っていませんし、
薄雲り状態かつ、ウロコ雲多数でした。
ドピーカンで撮ってみたいわ。
M57 , Gain=400 , 12X60s , 12min Total , NoDarkAndFlat

重量級FLIを尻目にこのカメラ、Gain=400でも結構色が出ています。
SharpCapソフトで4X4ビニングし、モニター表示をBoostMoreとすると、
Gain=570maxの場合、M57の動画が見られます。
何がイイって、ライブビュー状態だからピントが分かりやすい。
とにかく、冷却CCDみたいなモッサリ感はまるでなし。
それでピンを詰め、1X1ビニング無しで撮ればOK。
撮像も、3分ならノータッチ・トラッキングで大丈夫です。
もう楽で楽で、帰宅後の画像整理や後処理の手間が膨大になることも
恐れずに撮りまくれます。
今回ASI294MCはサブですが、関係者一同 お~~っ!!
ま、そのような状態ですね。
------------------------------------------
撮影日時:2018/08/02-03
撮影場所:65cm天文台(標高850m)
天候:薄雲り、時々晴れ間、ウロコ雲
気温:27℃
星空指数:30(大きな月あり)
シーイング:3/5~4/5
撮像鏡筒:65cmF12カセグレン鏡筒 , fl=7800mm 直焦点撮影
カメラ:ZWO-ASI294MC (Sony IMX294 Back Side Illuminated CMOS m4/3)
フィルター:無し
コマコレクター:無し
赤道儀:三鷹光器GNF-65フォーク式赤道儀_コズミック・クルーザ改仕様
ガイド:ノータッチ・トラッキングとPHD2ガイドの両方を実施。
ガイドスコープ:60mmF4 + QHY5L-ⅡM
ASCOM Platform 6.3
撮像ソフト:Sharp Cap 3.1(Free版)
画像処理:SI7 , Photoshop_cc
------------------------------------------
・FLI PL09000 + 7 FilterWheelのテスト撮像も行い、36.5mm角の全写野で
ケラレ無く、コマ収差も目立たないレベルであった。
大型CCDのため、写野導入精度は全く問題ないレベル。
・FLI PL09000と合わせ、ASI294MCでも撮像した。(含む取扱説明)
強烈な月明のためバックが下がらず青い画面となる。
TPOINTパラメータ12項目の算入にて導入精度がRMS=13"角となり、
機差補正追尾+大気差補正追尾を行うことで完全にノータッチ・トラッキング。
・PHD2によるAutoGuideも実施。
概ねRMS=0.5~1.0”角で推移していた。
もっとも、まともに晴れないのでノータッチ・トラッキングの方が効率が良かった。
・木星、土星、火星の動画キャプチャーも実施したが、4GB越えのファイルを
USBメモリーにコピーできなかった。これはFAT32の制約である。
exFATまたはNTFSでUSBメモリーをフォーマットし直せば解決する。
・キャッツアイ星雲の視直径がステラナビでは5.8’となっている。
実際に撮影すると1’以下の大きさしかない。これは、最近になって大きな外殻が
発見され、視直径が修正されたことが原因だ。
・ASI294MCの接眼部アダプターを2インチバレルに変更してケラレは無くなったが、
四隅に円形のキズ痕?のようなものが現れている。
・素子温度が28℃程度であった。
気温27度なので思ったよりも低いが、熱ノイズが多い。
夏は冷却機能必須と感じる。
|
+->ダークを引かないと話にならん。