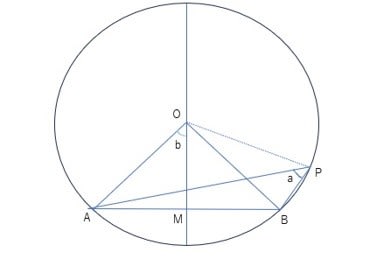2011年7月17日に投稿したブログ「数学の組合せ論に現れる相転移」が、いまだに自身の人気ブログ・ランキングに入るのを見て、数学問題と物理学の相転移とを関連付けることに興味をもつ人が少なくないことを知った。
NHKテレビの数学教室で、解が不定の方程式を扱うというテーマの下に、いくつかの問題が紹介されたが、その中の一つ「フロベニウスの式」を知り、相転移と関連付けて語りたくなった。
4円玉と7円玉の硬貨の組合せのように、x円貨幣とy円貨幣を各々0,1,2…枚組み合わせて任意の金額をつくるとき、組合せできない金額と組合せできる金額とが存在する。フロベニウスの式とは、組合せ不可となる金額の最大数をMとするとき、xy-x-y=Mの式で表現できるというものである。たとえば、x=4,y=7の場合には、M=17となる。
x=2, y=3の場合には、M=1となるので、2以上の金額数の場合には、すべての金額が組合せ可能となる。多くの整数は2または3で割り切れるし、任意の素数はより小さい素数と偶数の和で表せると予想できるので、ありうることである。
x=13, y=17の場合はどうか。M=191となるので、191が組合せ不可となる金額の最大数である。つまり、13円貨幣がm枚、17円貨幣がn枚とするとき、不定方程式13m+17n=191に整数解がないことを表明している。192以上の金額数のいくつかについてこの方程式の整数解が存在することを確認できる。
x,yがより大きな素数の場合にも、Mは大きくなるが、Mを越える数値について、mx+nyが整数解をもつことが予想できる。すなわち、M未満の数値については、x,yの組合せの可否が不揃いであるが、Mを越える数値については、一転してすべて組合せ可能となる。強磁性を示す物質を加熱していくと、臨界温度を越えた温度でその磁性が失われる相転移の現象に類似している。
NHKテレビの数学教室で、解が不定の方程式を扱うというテーマの下に、いくつかの問題が紹介されたが、その中の一つ「フロベニウスの式」を知り、相転移と関連付けて語りたくなった。
4円玉と7円玉の硬貨の組合せのように、x円貨幣とy円貨幣を各々0,1,2…枚組み合わせて任意の金額をつくるとき、組合せできない金額と組合せできる金額とが存在する。フロベニウスの式とは、組合せ不可となる金額の最大数をMとするとき、xy-x-y=Mの式で表現できるというものである。たとえば、x=4,y=7の場合には、M=17となる。
x=2, y=3の場合には、M=1となるので、2以上の金額数の場合には、すべての金額が組合せ可能となる。多くの整数は2または3で割り切れるし、任意の素数はより小さい素数と偶数の和で表せると予想できるので、ありうることである。
x=13, y=17の場合はどうか。M=191となるので、191が組合せ不可となる金額の最大数である。つまり、13円貨幣がm枚、17円貨幣がn枚とするとき、不定方程式13m+17n=191に整数解がないことを表明している。192以上の金額数のいくつかについてこの方程式の整数解が存在することを確認できる。
x,yがより大きな素数の場合にも、Mは大きくなるが、Mを越える数値について、mx+nyが整数解をもつことが予想できる。すなわち、M未満の数値については、x,yの組合せの可否が不揃いであるが、Mを越える数値については、一転してすべて組合せ可能となる。強磁性を示す物質を加熱していくと、臨界温度を越えた温度でその磁性が失われる相転移の現象に類似している。