
久しぶりに文楽へ。
「日本維新の会」立ち上げた橋下さんの発言が議論を呼んでいるけれど、たしかに大阪の国立文楽劇場は、ガラガラ、空席がめだっちゃいます。
ところが一方、こちら東京国立劇場小劇場は連日満員御礼。
二週間前にチケット予約試みたけど、日曜日の昼の部数席しか残っていないという人気ぶり。
どうして、こうも東西で違うのかと、、、、、、。
大阪は国立だから国からも補助金でているのでしょうが、大阪市からも出てるんですね。
大阪は、すごく、すべてのところで、バブル以来、痛みが激しいのかもしれません。
東京は、太夫に対して歌舞伎のように掛け声もかかるし、盛り上がっています。
粂の仙人の物語は、今昔物語が原作。吉野 龍門寺で修行を重ね免許皆伝、空を飛翔するワザを身につけた仙人が、吉野川で洗濯している娘さん足に見とれてツイラクしてしまうという楽しい物語。
ここでは粂仙人は聖徳太子の兄という設定で、ひがみから聖徳太子を陥れようと、龍神を滝壺に閉じ込め干ばつ不作を画策。そこに密命を受けた 花ますという女性を送り込みます。その色香。人形が可愛いし、義太夫節も「ヤア、まくったか」「「もうぐっとまくり上げて川の中へ」「イヤモゾっとした段か」お腹が差し込むと言い出す 花ます。 仙人は手でさすったり介抱「たまらぬ たまらぬ たまらぬ、、、、」と、破戒していく姿が、オカシ面白し!!!!!三種の神器も奪われて、、、、。龍は解き放たれます。
この作品が、歌舞伎の名作「鳴神」になります。
夏祭浪花鑑は、文楽の名作。1745年初演です。作家は翌年から「菅原伝授手習鑑」「義経千本桜」「仮名手本忠臣蔵」を生み出します。
浪花の人情話。
怒りが爆発して、壮絶な義父殺しの場面があります。高津宮神社の祭礼の日、祭り提灯、だんじり囃子、神輿が大祭を盛り上げます。そこで起こる劇中劇の惨劇。
見応え充分。
伝統芸能、頑張ってます。
「日本維新の会」立ち上げた橋下さんの発言が議論を呼んでいるけれど、たしかに大阪の国立文楽劇場は、ガラガラ、空席がめだっちゃいます。
ところが一方、こちら東京国立劇場小劇場は連日満員御礼。
二週間前にチケット予約試みたけど、日曜日の昼の部数席しか残っていないという人気ぶり。
どうして、こうも東西で違うのかと、、、、、、。
大阪は国立だから国からも補助金でているのでしょうが、大阪市からも出てるんですね。
大阪は、すごく、すべてのところで、バブル以来、痛みが激しいのかもしれません。
東京は、太夫に対して歌舞伎のように掛け声もかかるし、盛り上がっています。
粂の仙人の物語は、今昔物語が原作。吉野 龍門寺で修行を重ね免許皆伝、空を飛翔するワザを身につけた仙人が、吉野川で洗濯している娘さん足に見とれてツイラクしてしまうという楽しい物語。
ここでは粂仙人は聖徳太子の兄という設定で、ひがみから聖徳太子を陥れようと、龍神を滝壺に閉じ込め干ばつ不作を画策。そこに密命を受けた 花ますという女性を送り込みます。その色香。人形が可愛いし、義太夫節も「ヤア、まくったか」「「もうぐっとまくり上げて川の中へ」「イヤモゾっとした段か」お腹が差し込むと言い出す 花ます。 仙人は手でさすったり介抱「たまらぬ たまらぬ たまらぬ、、、、」と、破戒していく姿が、オカシ面白し!!!!!三種の神器も奪われて、、、、。龍は解き放たれます。
この作品が、歌舞伎の名作「鳴神」になります。
夏祭浪花鑑は、文楽の名作。1745年初演です。作家は翌年から「菅原伝授手習鑑」「義経千本桜」「仮名手本忠臣蔵」を生み出します。
浪花の人情話。
怒りが爆発して、壮絶な義父殺しの場面があります。高津宮神社の祭礼の日、祭り提灯、だんじり囃子、神輿が大祭を盛り上げます。そこで起こる劇中劇の惨劇。
見応え充分。
伝統芸能、頑張ってます。










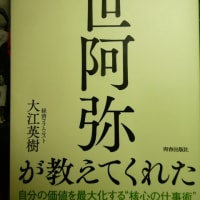
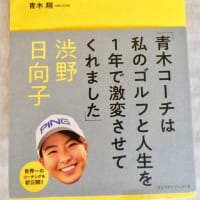
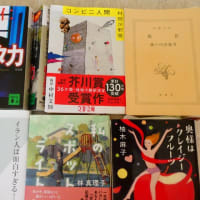
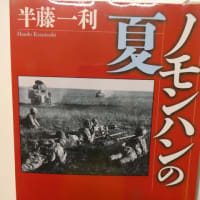
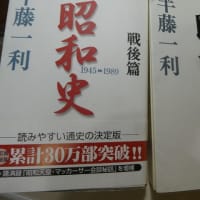
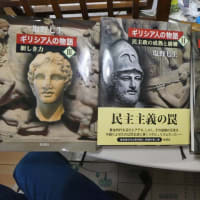

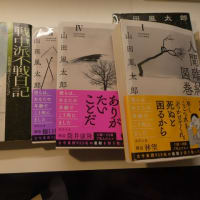

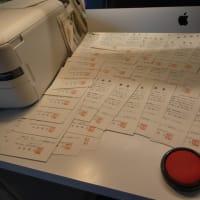






ツイッターの文楽論議で読んだことがあります。
中之島図書館等、今後どうなっていくのでしょうか?
話は違いますが、私が若い頃あった図書館「葵文庫」、
貴重書として名目残っているようですが、なんだか少し残念です。
粂仙人は、ボストン美術展の龐居士(見立久米仙人)で知りましたが、
こちらのお話は更に面白いですね。
>伝統芸能、頑張ってます
大阪は土地柄様々な所に経費が掛かっていると思うので、何とも言えませんが、
伝統芸能、技術は継承していって欲しいです。
でも、そうなると結局は生活面で応援しなくては、
ということになり・・・なんとも難しいですね。
やはり、人気が無いと、衰退へ、、、、。いかに魅力ある舞台にするかでしょうが、お金がかかることです。
オペラも欧米では多大の補助金で成り立っていますから、、、、、難しい問題です。
やはり、政治主導で、経済成長を持続させないと、すべてに、しわ寄せが来てしまいます。
新しい戦略は、誰が、どの政党が実現してくれるか。
ここ半年が重要ですね。
そんなにガラガラだと橋下市長に補助金カットとか言われる事情が分かりました。しかし武士が支えたお能や狂言と違って大阪商人が盛り上げた文楽が関西でさっぱりというのは寂しいですね。
私の母方の祖父は生粋の大阪商人で、仕事もせずに文楽と関西歌舞伎に入れ込んでいた、と祖母から聞かされていたのですが、もうそんな人はいないのでしょう。大衆芸能ですからやはりスターが出ないとダメですね。
もっぱらTVですが、観ていると後ろの人形使いの方々がいつの間にか視界から消え、人形を人として観ている自分がいます。それがまた無理無く自然になんです。
それくらい人形に命が吹き込まれているって事なんでしょうね。
いつか観たいですね。
時に、10大ピアニスト、読み上げました。バリオモ
最高でした! 他の音楽家との絡みが良くわかったし、時代背景、また、知ることの無かった鉄のカーテンの向こう側の事まで知り得たし、まるで年表をみているようで整理がついて頭がスッキリした感じ!
バックハウスが少し端っこにやられていたのが少し残念なり。エピソードが本当に少なかったぬでしょうね。良い本紹介していただきましたっ 感謝!
ついでに 同著者の “カラヤンとフルトウ゛ェングラー”も発注してしもた(笑)
この、差は、どこから来ているのだろうか????
しばし、考えてしまいました。
浪花のこころなのにねーーーーーーーーーーー。
やはり繁盛しなければ、衰退へと向ってしまいます。
東京は、熱気があります。外人も多い。
私の祖母も、義太夫節に凝って、大阪から浜松の家に呼んで、一緒に唸っていました。
近所知り合いを招きましたから、ずいぶん迷惑かけた部分もあったと思います。
22比、楽しんで来てください。
劇場の、人形の表情がわかるようにとても、こじんまりとして、小さいし。
字幕は、しっかりと読めるし、わかりやすいです。
言葉を味わうこともできますし、人形のワザが見事だと感じます。
能はちょっと高尚過ぎますが、文楽は楽しいです。
わーーーーー、よかった!!!!
そんなに喜んでいただけると、私も嬉しい!!
巨匠たちが、意外や意外、すごくお互いに影響し合い、争い、高め合っていったか、いろんな側面から明らかにしてくれます。
戦争、圧政など、それぞれの時代に翻弄されながら、しぶとく勝ち残る彼らの根性が素晴らしいです。
バックハウスは、ひたすら演奏会活動を高めて、沈潜していった方みたいですから、これからの研究が楽しみです。
カラヤンとフルトベングラーも面白そうですね。
とにかく、読ませてくれる本ですからね。。。。。