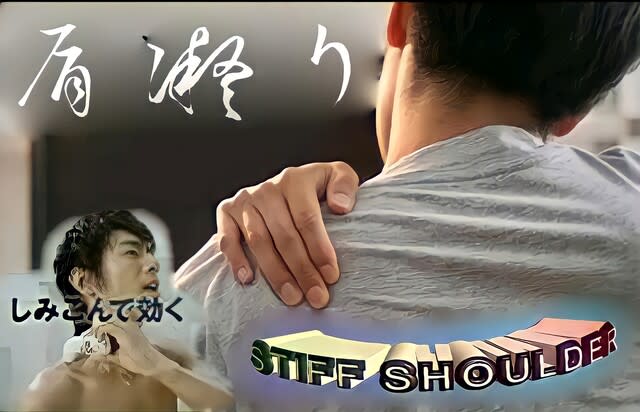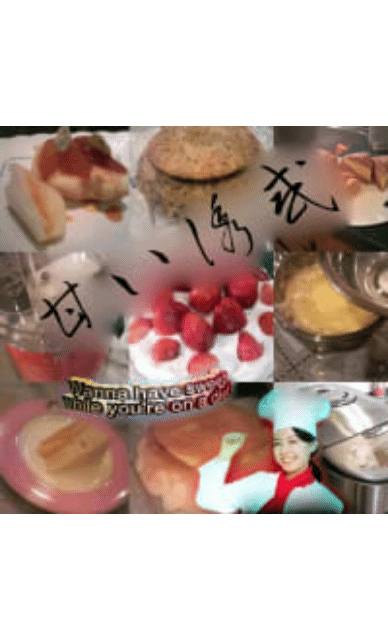oO☆゜.。+o●☆.。+oO☆.○。o∞○。○o'●oO☆゜.。+o●☆.。+oO☆.○。o∞○。○o'●
oO☆゜.。+o●☆.。+oO☆.○。o∞○。○o'●oO☆゜.。+o●☆.。+oO☆.○。o∞○。○o'●
イングレディオンという澱粉を売る会社の広告を頻繁に目にするようになりました。
澱粉を主食とする伝統的な日本型食生活を推奨する当サイトと歩み寄れるところがありそうだと考え、覗いてみました。
👉イングレディオン
澱粉商品
開発している商品については当サイトとしても歓迎できるラインナップなのですが、糖質オフや低糖質に対してアンチの姿勢を主張する当サイトとしては糖質における表現方法に関して多少気になるところはあります。
レジスタントスターチ
レジスタントスターチは難消化性澱粉と訳されますが、多くの日本人が日常的に主食として口にしている白飯はどちらでしょう?
冷やご飯と暖かいご飯でも違いますし、固く炊いた場合と柔らかく炊いた場合でもことなります。
とはいえ、雑穀米や玄米の方がより良いと推奨する人もいますが、必要な糖を得るには胃腸にかかる負担が大きすぎるという説もありますし、ほしいタイミングで糖を得るには時間がかかりすぎるという説もあります。
当サイトでも吸収の良い糖については長く空く食間や運動前に100~150㌔㌍程度ならば摂ることが望ましいとしていますので、その辺りにはどの程度賛同していただけるか興味深いところです。
HI-MAIZE 260
彼らが開発する機能性表示食品の中にはハイメイズ260(ハイアミロースコーン由来)というものがあり、「何これ?」状態でした。
HI-MAIZEのmaizeを翻訳機で訳すと「とうもろこし」であります。
どうやら高分子のとうもろこし澱粉のことで豊富にレジスタントスターチを含むということで世界的に評価されているようです。
NOVELOSE 3490
タピオカ由来のハイダイエタリーファイバーを豊富に含むレジデンススターチ。風味や食感を損なうことなく小麦粉と置き換えが可能といっています。血糖値の乱高下の抑止力になるのは大いに結構なのですが置き換えによって従来品より30㌫の糖質オフになるというから人によっては不足を感じるか、沢山食べたい人にはある意味有り難い食材となるでしょう。
当サイトの理念からすると必要な糖質を確保しなければなりませんので“30㌫の糖質オフになる”は掲げにくい謳い文句ではあります。
とはいえ、以前在籍していた会社ではご飯を食べるダイエットを標榜していたものの、提示されたご飯の少なさに愕然としているのを見たことがありますので、こうした商品が歓迎されることは間違いないでしょう。
NOVELOSE 8490
米由来のダイエタリーファイバー90㌫のレジスタントスターチのようです。
やはり表現方法としては当サイトが勧めるならば多くの粉原料と置き換えることで
「主食やおやつとしてこんなに沢山召し上がれます」という表現となるでしょう。
VERSAFIBE 1490
芋由来のダイエタリーファイバーとして風味や食感を損なうことなく小麦粉と置き換えが可能な商品だそうです。
NOVELOSE W
85㌫のダイエタリーファイバーを有する小麦由来のレジスタントスターチで風味や食感に影響することなく保健食品化が可能です。
このようにイングレディオンという会社は低糖質化を標榜にダイエタリーファイバー豊富な澱粉を開発しているように見えますが、実は間違って洗脳された大衆が安心して澱粉をしっかり摂れるように開発を進めていると解釈できたら素晴らしかろうと勝手に思っております。
素晴らしい澱粉群
この会社ではここで紹介した以外でも、新しいテクスチャをプロデュースした澱粉、食品業界には欠かせない増粘多糖類、独自のコメでん粉製品など素晴らしい製品や理念が窺われます。
とはいえ、私がここでこの会社の説明をするよりも自身でググっていただいた方がより多くの確かな情報が得られるでしょうから、ダイエットに役立ちそうな製品に絞って投稿させていただきました。
世界共通の2大ペットといわれるイヌとネコだが、人間に対する行動は大きく異なる。

①飼い主への態度
イヌ…飼い主が帰ってくるとすぐに出迎えに来る。名前を呼べばすぐに駆けよってくる。なでてもらうと尾をふり全身で喜びを表現。
ネコ…飼い主が帰ってきても、多少視線を送ったりもするが、ほとんど無視を決め込む
。名前を呼んでも近づいて来ない。そのくせ飼い主がくつろいでいるとネコのほうからすり寄ってきたりする。なでてやると気持ちよさそうにゴロゴロと満足気な声を上げる
。ところが飼い主が抱こうとするといやがって逃げたりする。しかも時には爪をたてる事もある。
②エサの食べ方
イヌ…エサを与えると一気に食べる。
ネコ…せっかく与えたエサを拒否したり食べ始めても飽きてどこかへ行ってしまう。
③叱られた時の反応
イヌ…寂しそうに反省の声をあげる。

ネコ…聞く耳を持たないかのように毛づくろいを始めたりする。
このような行動の違いから犬は従順で、猫は気まぐれな動物と考えられている。それは6000万年に渡る壮大な進化の謎に起因するらしい。
犬と猫の祖先は同じ動物だという。進化の過程で枝別れし、全く性質の異なる動物となったという。
30万年前はオオカミ、ヤマネコ。2000年前はトマルクトゥス、サーベルタイガー。2300万年前はキノデスムス、プセイダウルルス、3000年前はヘスペロキオン、ディクティニスとしだいに古くなるほど骨格の違いが少なくなってくる。6000年前に至っては骨格の違いはない。 その動物の名前はミアキス(MIACIS)。分類学上最も古いイヌとネコの祖先らしい。
ミアキスの骨格をみると現在のイタチに似ているという。大きさはネコよりも一回り小さかったという。森林に単独で生活し、ネズミ、小鳥、などの小動物を獲物としていた。
4000年前森林に適応した進化をとげたのがネコへ第一歩。木に登ったり、草木の陰に隠れて獲物を待ち伏せして至近距離から一気に獲物を襲う。そのために瞬発力を持った筋肉が発達した。
さらに音を立てずに接近できるように爪の出し入れが可能となった。暗い草木の陰から明るい場所に飛び出して獲物を襲うことができるように明るさの変化に対応できるように瞳孔を自由に変化させ、目に入る光の量を調整できるように進化…。

加えて夜行性であったため視覚に頼らなくても獲物を襲うことができるように、獲物の動く音を正確に聞き分け、相手の位置や大きさを的確に判断できるように聴覚が発達していった。これがネコの祖先のヤマネコ(WILDCAT)である。
それが人間に飼われるようになり、様々な種類のネコとなった。
森林で獲物を得ることを得意とするミアキスが増えていくなかで、その進化に乗り遅れたミアキスは森林では生活できなくなった。新たに生息地を求めて草原にたどり着いた。草原では見通しがよく獲物をすぐに発見できる反面、相手からも発見されてしまうというデメリットがある。そこで飢えから身を守るために生活形態を変えていくしかなかった。もともと森林で単独で暮らしていたミアキスが草原に出るようになって群れをなすようになった。獲物を得るのに群れによる連携プレーが行われるようになったようだ。自分より大きな動物も襲えるようになり、連携プレーをとりやすくするためにリーダーと順位が誕生。群れは順位にしたがって行動するようになった。
見通しのよい草原では音を立てずに獲物に近づくより早く走れることが必要となった。出し入れ可能だった爪はスパイクのように出たままになり走りやすくなった。一方、視覚や聴覚ではとらえることができない遠くの獲物の存在をキャッチできるように嗅覚が発達。長時間獲物を追いつづけることができるように筋肉は瞬発力よりも持久力に優れたものに変化したそうだ。
上昇した体温を走りながら下げることができるように口を開けて熱を放出できるように進化。これがイヌの祖先であるオオカミ(WOLF)へと進化していったのである。そして人間に飼われるようになって様々なイヌへ進化していったのである。
このように群れと単独という生活形態の違いから形成された性質が現在のイヌとネコに大きな影響を及ぼしている。
イヌは群れの一員として行動をとって来たために飼い主に従順。ネコは単独行動をとって来たために気まぐれという印象を与えているのである。
群れで生活をしてきたイヌは人間の家族を群れにみたてており、飼い主を出迎えたり、名前を呼んで応じるのは自分を群れの一員と心得ているからである。ほめたりすることで自分の存在を認めてもらえたと喜びを大きくするのである。
一方単独で暮らしてきたネコは飼い主が帰ってきてもイヌのように歓迎はせず、そっけない態度をとる。ネコは単独生活者で人間の家は単なる住み家としか思っていない。
ネコが単独生活者でありながら外を出歩いても家に帰って来るのは確実なエサがあり、安全な寝ぐらがあるからである。つまりネコにとっての人間は危害を与えずエサをくれる友好的な動物というふうにしかとらえていない。イヌのように順位があるとは考えていない。
エサの食べ方もイヌの場合、エサを与えると喜びを示し、一気に食べる。いつ獲物を得ることができるかわからず、得た獲物は群れの順位の高いものから食べていた。短時間で少しでもたくさん食べなければ次に食べる機会はいつ回ってくるかわからない。
俗に“イヌ食い”といって空腹でなくても一気にたいらげる習性が残っている。
ネコの方はエサを与えると時々拒否をする。少ししか食べずにどこかへ行ってしまう。ネコは狩りを単独で行うため獲物は自分だけで全部食べられる。自分の縄張りをもっていたために他の動物にエサをとられる心配はない。つまりエサにたいして執着心がなく、食べずにどこかへ行ってしまったりするのである。気まぐれに見えてしまう理由である。
イヌは飼い主に叱られるとしょんぼりする。群れの中では順位の高い者に背くことは許されない。順位の高い者に嫌われることは群れから追い出されることを意味する。最も辛いことなのである。つまりしょんぼりして許しを請うのである。
これに対してネコはだれかに嫌われることなど全く関係ない。人間に叱られることなど意味のない時間なのである。大声を出された不愉快な現実を一刻も早く忘れようという行動に出る。それが件の“毛づくろい”なのである。これをネコの「転移行動」という。全く関係ない行動をとって気分を静めようとしているのである。
侵入者に対する態度も大きく違う。知らない人間が玄関から入って来た場合、吠えて飼い主に知らせる。イヌは自分の群れが最も大切なものと考えているため群れを守ろうとする行動なのである。ネコは侵入者に対して自分だけ物陰に隠れてしまう。ネコにとって自分の身を守ることが最も大切なのである。
このようにイヌもネコも本能に従って生きているのである。人間の目にはイヌは従順、ネコは気まぐれと映るのである。
ところが最近のイヌやネコには問題行動が多い。ネコは飼われていても人間の前では出産したりしなかったが、最近のネコは人間の前で平気で出産をするばかりではなく、子育てをしないのである。ネコの本能を脅かされているからである。
そもそもネコが人間に飼われ始めたのは5000年前の古代エジプトである。穀物の倉庫を荒らすネズミが深刻な問題となっていたが、ネズミをエサとするリビアヤマネコ(LIBYA WILDCAT)を飼いならしていったのである。
これに対してイヌが人間に飼われるようになっていったのは1万数千年以上も前の旧石器時代からだという。当時狩りによって食糧を確保していた人間は効率よく獲物を発見することを必要としていた。また夜の暗闇での侵入者は脅威であった。そこで優れた嗅覚で獲物を探す、侵入者を知らせるオオカミを飼いならしていったのである。このようにイヌは飼いならした人間に忠実に従うことから狩猟犬、牧羊犬、盲導犬など様々なところで役立てるように体格や性格の改良が行われていったわけだ。
しかしネコは人間の命令に従うことはなかったためにネズミ退治以外に利用されることはなかった。そのために愛玩用として外見的な部分だけが改良されていった。
その結果イヌは約300種類。ネコは3分の1の約100種類しかいないという。つまり用途の少ないネコは性質の改良を施されることもなくイヌよりも野性の本能を残してきた。ところが現代の人間との生活環境によって重大な影響を受けている。
まず、単独生活の本能への影響がある。ネコは子供の時から自分を育ててくれた人間を親と考える習性がある。ネコが飼い主について歩いたり、本を開いた時に一緒に覗き込んだりするのは親について学ぼうとする学習行動。人間に遊んでてもらうのは親ネコになめてもうらうのと同じ感覚らしい。
通常ネコは生後3ヵ月過ぎると親との関係を断ち切る。そして外に出て狩りのしかたをおぼえたり、独立した単独生活者として行動を開始する。
ところが最近のネコは室内飼い。食事はもちろん身の回りのことをすべて人間が面倒を見てくる。ネコは3ヵ月をを過ぎても大人になりきれず、子供のままでいつづけてしまうのである。すると単独で生きようという本能が養われず、親である人間に依存して生きようとする。出産の時も一番安心できる人間の前で行う。子育てさえも人間に頼ろうとする。人間の過剰な甘やかし、ネコに独立する機会を失わせてしまったのである。
さらに最近多い問題行動には暴れる、かみつくといった行動がある。ネコは成長すると狩猟本能を発揮してそとで獲物を捕ることを覚える。以前ネコは飼われていても、家と外の出入りを自由に許され、外で狩猟本能を発揮してきた。
ところが室内だけで飼われていると狩猟本能を満たすことができない。安全な家の中では敵から逃げる必要もない。ネコが厳しい自然の中で生きていく能力は人間に守られた平穏な暮らしの中では完全に抑えられてしまう。
それがかえって仇となり、極度のストレスになって問題行動を起こしていたのである。
これらの人間の過剰な甘やかしや室内飼いがイヌの問題行動の原因にもなっている。
それが件の権勢症候群(ALPHA SYNDROME)である。順位のある群れの中で生きてきたイヌは人間を自分より低い立場と見て反抗的な態度を示すようになってきた。
ではイヌが権勢症候群に陥らないようにするにはどうしたらよいか。人間との立場の違いをイヌに理解させる。遊ぶ時には飼い主が必ず勝つこと。散歩の時、スピードや方向を飼い主が決める。このように人間との立場の違いを、イヌに認識させれば権勢症候群に陥ることはない。
ネコの場合は野性の本能を発散させてやること。できればネコには家と外の出入りを自由にさせてやることだが、現代の日本ではネコ白血病ウイルスやエイズウイルス(ノラ猫の10匹に1匹)が蔓延しているためうかつには外に出せない。室内でその本能を満たしてやるためにはおもちゃなどを使って疑似狩猟をさせてやったり、マーキングといって爪跡を残したりにおいを残したりするが、とくにのびた爪を研ぐことができないとネコはストレスを感じる。
爪研ぎを不快に感じるようであればネコを飼うことをあきらめる決断も必要である。ネコの本能を人間の都合で押さえ込むのはネコにとって不幸なことである。森林の中で単独で暮らして来たネコがその本能を満たすために高いところに登ったり、走り回ったとしても叱らないだけの余裕が必要である。
ただ我が家の猛ポメは疑問点が多い。
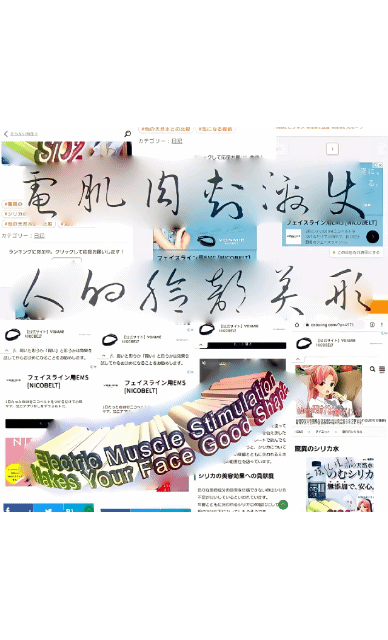
oO☆゜.。+o●☆.。+oO☆.○。o∞○。○o'●oO☆゜.。+o●☆.。+oO☆.○。o∞○。○o'●
小顔になれるボミーのニコベルト?
「小顔になる」で検索をしたこともないのに突然“小顔になるボミーのニコベルト”の広告がスマホ上に現れました。
もともと綺麗で小顔のタレントを起用しての大々的なキャッチコピーの数々は多くの顔デカに悩む女性の心を鷲掴みにしそうです。
中でも気に入ったコピーは“加工アプリなしをデフォルトに”です。昔なら「なにそれ?」と突っ込まれそうな文言ではありますが、スマホや多くのIT機器が日常に台頭してくるとそういったコピーも「だよね~」と自然に受け入れられるようになってきましたので時代を感じます。
エストニア生まれのそれは顔に装着して筋肉への電気刺激を与えるものらしいですが、手で持たなくても良いので何かをしながらでも使用が可能でセールスポイントの一つになっています。手入れも難しくないようですから効果絶対であるならばお勧めしたいところです。
効果があったというユーザーもいるようですが、選べるサイズがないことや刺激への不満や効果が得られなかったというネガティブな口コミもオープンに紹介されていました。
やはり食事も併用しましょう
保証期間が設定されていて返品が可能なようですが、なかなか現れない効果というのは保証期間が過ぎたころに出てくる可能性がありますので微妙な設定といえましょう。
整体でもヨガでもエステでもそうですが、それらに期待はするものの狂いが生じた食欲に任せて正しくないバランスで食事を進めた場合、求めていた結果が得られない可能性が想像に難くありません。
小顔になれそうにない食事を続けながら効果がないと機器のせいにしたりするのは気の毒な気もします。
好意的な口コミの中にもダイエットも並行して行っていたので効果が早く表れたという声もありますが、どんなバランスで食べているのでしょうか。
是非澱粉を主食とする伝統的な日本型食生活を
澱粉を主食とする伝統的な日本型食生活を腹八分目で進めた場合、それだけでも首や顎周りの浮腫みが取れ、余分な脂肪が減り、小顔効果が得られるものですので、そういったハイテク機器に頼らずに小顔を獲得してもらいたいのが本音です。
とはいえ、同等の効果が得られるというライバル会社の機器もあるようですが価格の安さや手入れの簡単さで軍配が上がるようです。といいますか同等の効果が得られる機器も太るような食事をしている人には歯が立たないと思います。
レンタル品で試す手もあるが
何を隠そうレンタル品でお試しもできるそうです。2週間で約3,000円。「一日200円なら試してもよいか」という人にはありかなと。ちょうど効果が出にくい人が効果出てきそうな微妙なお試し期間といえましょう。
機器に頼るのも結構ですがまずは当サイトで食事改善をお試しください。
_/_/犬の嗅覚_/_/
∴‥∵‥∴‥∵‥∴*:・'゜*:・'゜*。.:**:・'゜*:・'゜*。.:*♪:*:・・:*:・♪・:*
犬の能力を確認してみよう…
①視覚能力…視野が広く周囲の状況をよく把握できる。しかし、視力は良くなく0.2~0.3程度。
②聴覚…人間の可聴域が20~2万Hzであるのに対して、犬の可聴域は8~12万Hzと非常に広い。たとえば“犬笛”などは人間には高音の為、まず聞き取ることはできない。犬は可聴域が広いため聞き取ることができる。
③嗅覚…犬の嗅覚は非常に鋭く、その能力を買われ警察犬(police dog)、麻薬操作犬(nircotic investigate dog)、災害救助犬(search and rescue dog)として活躍している。臭いを認識する仕組みを確認すると、臭いの分子が鼻腔の奥にある嗅粘膜に付着すると、その刺激を受けた嗅細胞は神経を通じ大脳の嗅球に伝え、臭いとして感知するのである。臭いの分子を受け取る嗅粘膜の広さは人間が切手2枚分であるのに対して、犬の場合新聞紙1枚分。その刺激を感じ取る嗅細胞の数は人間が500万個であるのに対して、犬の場合2憶個も持っている。
........
体臭の変化
人間は病気になるとその種類によって代謝に変化が生じる。それが臭いの変化となって現れることがある。体臭の主成分は皮膚の下にあるエクリン腺とアポクリン腺から分泌されるタンパク質である。これが皮膚表面に存在する細菌の作用を受けると、さらに独特の臭いとなる。
............
病気によって新陳代謝のバランスが崩れると、分泌物に含まれる物質の種類や量が変化し、普段と異なる体臭を呈することがある。たとえば糖尿病(Diabetes Mellitus)の場合、血糖値を調整するインスリンが病気によって減少や機能低下を起こす。インスリンの働きが悪くなると、血液中に糖分が多く残ってしまう。残った糖分が尿はもちろん汗や息にも含まれ、りんごが腐ったような体臭を呈する。さらに心臓発作の例を見てみると、発作によって心筋梗塞が起こると心臓からの血液排出量が低下する。すると血液中の酸素が不足し、エネルギー源であるグリコーゲンが乳酸に変化する。その量が多くなると血液が酸性に傾く。酸性化が体全体に行きわたると他の臓器の新陳代謝に影響する。当然体臭も著しく変化する。 ....
....
犬の記憶力
12年前に飼い主のもとを離れた犬が飼い主の声を覚えていたという例が報告されている。またいつも飼い主の状態を観察し、記憶している。犬は主人が普段の状態と少しでも異なっている時、本能として気遣いの能力を発揮する。それを群れ本能(Crowd Instinct)という。犬は遠い昔、群れで生活を送っていた。集団の一頭でも病気になれば役割分担が崩れ、狩りは失敗してしまう。仲間の体調や弱点を補おうとする群れ本能が発達した。そして“忠誠”、“服従”、“安心感”の構図を描いている。犬は家族の体調や感情の変化をいち早く気付こうとしているのである。群れ本能は古代から犬に備わる能力なのである。群れ本能を発揮させるためには、飼い主は犬に対し、リーダーとして信頼関係を築くことが大切なのである。犬との信頼関係を築くためには生後2~3ヶ月の間が最も良いとされている。犬は生後3ヶ月までに…
●有効種族に関する社会化
●環境に対する社会化
●自制心
●意思伝達
●階級制度の認識
以上のことを身につけ、生涯忘れることがないという。
ガンを発見した犬
飼い主が気付かなかった皮膚ガンの臭いを嗅ぎつけ、飼い主に報せ、早期発見に導き軽快治療に導いた例が報告されている。この性質を人間のハイテク医療機器に応用されようとしている。
これは皮膚ガンがタンパク質の合成異常により独特の臭いを発するため、その異常を察知した犬が飼い主の病症部分を舐めることで報せることができたのである。
フランスではフォックスシステムという犬の嗅覚を模倣した電気鼻というバイオセンサーによる医療機器を開発していると言う。臭いの成分をセンサーによって、種類や量を測定し、どのような臭いかを分析し、病気を特定することを考えているという。これが成功すると血液検査などの分析方法よりも、早く病気を突き止めることができるという。

∴‥∵‥∴‥∵‥∴*:・'゜*:・'゜*。.:*♪:*:・・:*:・♪・:*★☆。・' ★☆。・' ♪:*:・・:*:・♪・:*
かつて虐待についてTVから学んだことをまとめたことがある。
虐待された人は、そのために極度に性格が歪む場合がある。その歪んだ性格が虐待を引き起こす原因と考えらる。
幼少期に虐待され、我が子を虐待する例は多いと言う。
虐待による性格の歪みの2つの共通点は…
①異常なほどのキレやすさ。
②強烈な自己嫌悪感。
虐待が子供の脳や性格に悪影響を与えることが分かってきた。
虐待する親に多く見られるキレやすいという性格の歪みの原因にはある神経物質の分泌異常が考えられる。その物質とはノルアドレナリンである。ノルアドレナリンの過剰分泌がキレやすく暴力的になる原因だと言う。
ノルアドレナリン(norepinephrine)とは恐怖や不安を感じた時に脳内で分泌される神経伝達物質である。心拍数や血圧を上昇させ、興奮状態を起こす作用を持つ。生命の危機的状況を回避しなければならないような時に大量に分泌される。さらにこれは怒りの感情をも引き起こすという。............

通常時にもノルアドレナリンの分泌が過剰だとちょっとした不安や恐怖にも過剰に分泌され、怒りがすぐに湧き上がり、キレやすい性格が形成されると言う。
幼少期にノルアドレナリンを大量に分泌させるような虐待を何度も受けるとノルアドレナリンを分泌する神経細胞のシナプスが強化される。すると通常の場合でもノルアドレナリンの分泌が過剰なまま定着してしまうのだと言う。するとノルアドレナリンがより過剰に分泌され感情を爆発させ易い。
さて虐待の世代連鎖と強烈な自己嫌悪感とはどのような関係があるのか。
虐待された人は自己嫌悪感が強いという研究結果が数多く報告されている。なぜ虐待されると自己嫌悪感が強くなるのだろうか。虐待は「しつけ」の延長として行われることが多い。虐待を受けながら厳しい指摘と叱責を受けることで、自分を低く評価してしまい、自分自身に確信が持てず、不安を抱えて成長してしまい、何かにつけて自己嫌悪に陥りやすい性格が形成されてしまうのではないかと考えられる。
自己嫌悪感の強い人は相手に原因があるのではなく全て自分に原因があると考える。
そのため普通の人よりもストレスをためやすい。
子育ては自分の思い通りに行かず様々なストレスを受ける。そのような人は子育てがうまくいかなかったりすると自己嫌悪感にさいなまれることが多く、より強いストレスを蓄積してしまう。そのためキレやすい人にキレる機会を与え、虐待に至ってしまうという。
それでは虐待が連鎖する人としない人はどのような違いがあるのであろうか。多くの研究から2つの要因が虐待の連鎖に深く関係すると考えられる。
虐待されキレやすい性格を持つ10代後半の女性19人のノルアドレナリンの分泌量を調べたところ、生後3年以内に虐待を受けた女性のほうが(通常時の)ノルアドレナリンの分泌量がはるかに多いことが明らかになった。つまり生後3年以内の虐待経験は強く脳に影響を与えると言うのである。
それは脳の神経細胞のシナプスの数は生後2~3歳までにピークを迎えるためである。そしてシナプスの数は12から13歳で一定になる。
通常時のノルアドレナリンが過剰に分泌されているとキレやすくなる。当然虐待に至る可能性も高まる。
もう一つの要因は虐待を受けた子供に助けを求められる人がいたかどうかである。
虐待の連鎖が起こっていない人には親戚の人や保母さんなど相談できる相手がいたケースが多いという。虐待により自己嫌悪感が強まっている時に愛情を注いでくれる存在があれば自己嫌悪感にさいなまれることが少ないからである。自己嫌悪感が弱まれば、自分が親になったときにストレスを蓄積させにくくなり、虐待に至る危険性は軽減するのではないかと考えられる。
そこで自己嫌悪感の克服法だが、セラピストが悩みを聞き、ストレスを発散させる。そして虐待の原因が自己嫌悪感にあることを理解させる。自己嫌悪感がストレスを蓄積させることを理解させることで、虐待をする時の感情や行為事態が間違っていることに気付く。こうすることで自己嫌悪感を感じやすい性格が少しずつ改善されていく。
虐待の世代間連鎖を断ち切るには過去を受け止め、乗り越えることが必要…。
イヌとネコ
世界共通の2大ペットといわれるイヌとネコだが、人間に対する行動は大きく異なる
。
①飼い主への態度
イヌ…飼い主が帰ってくるとすぐに出迎えに来る。名前を呼べばすぐに駆けよってくる。なでてもらうと尾をふり全身で喜びを表現。
ネコ…飼い主が帰ってきても、多少視線を送ったりもするが、ほとんど無視を決め込む。名前を呼んでも近づいて来ない。そのくせ飼い主がくつろいでいるとネコのほうからすり寄ってきたりする。なでてやると気持ちよさそうにゴロゴロと満足気な声を上げる。ところが飼い主が抱こうとするといやがって逃げたりする。しかも時には爪をたてる事もある。
........

②エサの食べ方
イヌ…エサを与えると一気に食べる。
ネコ…せっかく与えたエサを拒否したり食べ始めても飽きてどこかへ行ってしまう。
③叱られた時の反応
イヌ…寂しそうに反省の声をあげる。
ネコ…聞く耳を持たないかのように毛づくろいを始めたりする。
このような行動の違いから犬は従順で、猫は気まぐれな動物と考えてしまう。このような性質に見える違いはどういう理由からか…。それは6000万年に渡る壮大な進化の謎に起因する。
犬と猫の祖先は同じ動物だという。進化の過程で枝別れし、全く性質の異なる動物となっていった。
30万年前はオオカミ、ヤマネコ。2000年前はトマルクトゥス、サーベルタイガー。2300万年前はキノデスムス、プセイダウルルス、3000年前はヘスペロキオン、ディクティニスとしだいに古くなるほど骨格の違いが少なくなってくる。6000年前に至っては骨格の違いはなくなる。
その動物の名前はミアキス。分類学上最も古いイヌとネコの祖先なのである。
ミアキスから性質の異なるイヌとネコがうまれた過程を検証すると…
ミアキスの骨格をみると現在のイタチに似ているという。大きさはネコよりも一回り小さかったという。森林に単独で生活し、ネズミ、小鳥、などの小動物を獲物としていた。

4000年前森林に適応した進化をとげたのがネコへ第一歩。木に登ったり、草木の陰に隠れて獲物を待ち伏せして至近距離から一気に獲物を襲う。そのために瞬発力を持った筋肉が発達した。
さらに音を立てずに接近できるように爪の出し入れが可能となった。暗い草木の陰から明るい場所に飛び出して獲物を襲うことができるように明るさの変化に対応できるように瞳孔を自由に変化させ、目に入る光の量を調整できるように進化した。
加えて夜行性であったため視覚に頼らなくても獲物を襲うことができるように、獲物の動く音を正確に聞き分け、相手の位置や大きさを的確に判断できるように聴覚が発達した。これがネコの祖先のWILDCATである。

それが人間に飼われるようになり、様々な種類のネコとなった。
森林で獲物を得ることを得意とするミアキスが増えていくなかで、その進化に乗り遅れたミアキスは森林では生活できなくなった。新たに生息地を求めて草原にたどり着いた。草原では見通しがよく獲物をすぐに発見できる反面、相手からも発見されてしまうというデメリットがある。そこで飢えから身を守るために生活形態を変えていくしかなかった。もともと森林で単独で暮らしていたミアキスが草原に出るようになって群れをなすようになった。獲物を得るのに群れによる連携プレーが行われるようになったのである。自分より大きな動物も襲えるようになった。そして連携プレーをとりやすくする
ためにリーダーと順位が誕生した。群れは順位にしたがって行動するようになった。
見通しのよい草原では音を立てずに獲物に近づくより早く走れることが必要となった。出し入れ可能だった爪はスパイクのように出たままになり走りやすくなった。一方、視覚や聴覚ではとらえることができない遠くの獲物の存在をキャッチできるように嗅覚が発達。長時間獲物を追いつづけることができるように筋肉は瞬発力よりも持久力に優れたものに変化していった。
上昇した体温を走りながら下げることができるように口を開けて熱を放出できるように進化。これがイヌの祖先であるオオカミ(WOLF)へと進化していったのである。そして人間に飼われるようになって様々なイヌへ進化していったのである。
このように群れと単独という生活形態の違いから形成された性質が現在のイヌとネコに大きな影響を及ぼしている。
イヌは群れの一員として行動をとって来たために飼い主に従順。ネコは単独行動をとって来たために気まぐれという印象を与えているのである。
群れで生活をしてきたイヌは人間の家族を群れにみたてており、飼い主を出迎えたり、名前を呼んで応じるのは自分を群れの一員と心得ているからである。ほめたりすることで自分の存在を認めてもらえたと喜びを大きくするのである。
一方単独で暮らしてきたネコは飼い主が帰ってきてもイヌのように歓迎はせず、そっけない態度をとる。ネコは単独生活者で人間の家は単なる住み家としか思っていない。
ネコが単独生活者でありながら外を出歩いても家に帰って来るのは確実なエサがあり、安全な寝ぐらがあるからである。つまりネコにとっての人間は危害を与えずエサをくれる友好的な動物というふうにしかとらえていないイヌのように順位があるとは考えていない。........

エサの食べ方もイヌの場合、エサを与えると喜びを示し、一気に食べる。いつ獲物を得ることができるかわからず、得ることができても、獲物は群れの順位の高いものから食べていた。短時間で少しでもたくさん食べなければ次に食べる機会はいつ回ってくるかわからない。
俗に“イヌ食い”といって空腹でなくても一気にたいらげる習性が残っている。
ネコの方はエサを与えると時々拒否をする。少ししか食べずにどこかへ行ってしまう。ネコは狩りを単独で行うため獲物は自分だけで全部食べられる。自分の縄張りをもっていたために他の動物にエサをとられる心配はない。つまりエサにたいして執着心がなく、食べずにどこかへ行ってしまったりするのである。気まぐれに見えてしまう理由である。
 イヌは飼い主に叱られるとしょんぼりする。群れの中では順位の高い者に背くことは許されない。順位の高い者に嫌われることは群れから追い出されることを意味する。最も辛いことなのである。つまりしょんぼりして許しを請うのである。
イヌは飼い主に叱られるとしょんぼりする。群れの中では順位の高い者に背くことは許されない。順位の高い者に嫌われることは群れから追い出されることを意味する。最も辛いことなのである。つまりしょんぼりして許しを請うのである。これに対してネコはだれかに嫌われることなど全く関係ない。人間に叱られることなど意味のない時間なのである。大声を出された不愉快な現実を一刻も早く忘れようという行動に出る。それが件の“毛づくろい”なのである。これをネコの「転移行動」という。全く関係ない行動をとって気分を静めようとしているのである。
侵入者に対する態度も大きく違う。知らない人間が玄関から入って来た場合、吠えて飼い主に知らせる。イヌは自分の群れが最も大切なものと考えているため群れを守ろうとする行動なのである。ネコは侵入者に対して自分だけ物陰に隠れてしまう。ネコにとって自分の身を守ることが最も大切なのである。
このようにイヌもネコも本能に従って生きているのである。人間の目にはイヌは従順、ネコは気まぐれと映るのである。

ところが最近のイヌやネコには問題行動が多い。ネコは飼われていても人間の前では出産したりしなかったが、最近のネコは人間の前で平気で出産をするばかりではなく、子育てをしないのである。ネコの本能を脅かされているからである。
そもそもネコが人間に飼われ始めたのは5000年前の古代エジプトである。穀物の倉庫を荒らすネズミが深刻な問題となっていたが、ネズミをエサとするリビアヤマネコを飼いならしていったのである。
これに対してイヌが人間に飼われるようになっていったのは1万数千年以上も前の旧石器時代からだという。当時狩りによって食糧を確保していた人間は効率よく獲物を発見することを必要としていた。また夜の暗闇での侵入者は脅威であった。そこで優れた嗅覚で獲物を探す、侵入者を知らせるオオカミを飼いならしていったのである。このようにイヌは飼いならした人間に忠実に従うことから狩猟犬、牧羊犬、盲導犬など様々なところで役立てるように体格や性格の改良が行われていった。
しかしネコは人間の命令に従うことはなかったためにネズミ退治以外に利用されることはなかった。そのために愛玩用(※小さな動物などをかわいがって楽しむこと)として外見的な部分だけが改良されていった。
その結果イヌは約300種類。ネコは3分の1の約100種類しかいない。つまり用途の少ないネコは性質の改良を施されることもなくイヌよりも野性の本能を残してきた。ところが現代の人間との生活環境によって重大な影響を受けている。
まず、単独生活の本能への影響がある。ネコは子供の時から自分を育ててくれた人間を親と考える習性がある。ネコが飼い主について歩いたり、本を開いた時に一緒に覗き込んだり親について学ぼうとする学習行動なのである。人間になでてもらうのは親ネコになめてもうらうのと同じ感覚なのだと言う。
通常ネコは生後3ヵ月過ぎると親との関係を断ち切る。そして外に出て狩りのしかたをおぼえたり、独立した単独生活者として行動を開始する。
ところが最近のネコは室内飼い。食事はもちろん身の回りのことをすべて人間が面倒を見てくる。ネコは3ヵ月をを過ぎても大人になりきれず、子供のままでい続けてしまうのである。すると単独で生きようという本能が養われず、親である人間に依存して生きようとする。出産の時も一番安心できる人間の前で行う。子育てさえも人間に頼ろうとする。人間の過剰な甘やかし、ネコに独立する機会を失わせてしまったのである。
さらに最近多い問題行動には暴れる、かみつくといった行動がある。ネコは成長すると狩猟本能を発揮してそとで獲物を捕ることを覚える。以前ネコは飼われていても、家と外の出入りを自由に許され、外で狩猟本能を発揮してきた。
ところが室内だけで飼われていると狩猟本能を満たすことができない。安全な家の中では敵から逃げる必要もない。ネコが厳しい自然の中で生きていく能力は人間に守られた平穏な暮らしの中では完全に抑えられてしまう。
それがかえって仇となり、極度のストレスになって問題行動を起こしていたのである。
これらの人間の過剰な甘やかしや室内飼いがイヌの問題行動の原因にもなっている。
それが件の権勢症候群である。順位のある群れの中で生きてきたイヌは人間を自分より低い立場と見て反抗的な態度を示すようになってきた。
ではイヌが権勢症候群に陥らないようにするにはどうしたらよいか。人間との立場の違いをイヌに理解させる。遊ぶ時には飼い主が必ず勝つこと。散歩の時、スピードや方向を飼い主が決める。このように人間との立場の違いを、イヌに認識させれば権勢症候群に陥ることはない。
ネコの場合は野性の本能を発散させてやること。できればネコには家と外の出入りを自由にさせてやることだが、現代の日本ではネコ白血病ウイルスやエイズウイルス(ノラ猫の10匹に1匹)が蔓延しているためうかつには外に出せない。室内でその本能を満たしてやるためにはおもちゃなどを使って疑似狩猟をさせてやったり、マーキングといって爪跡を残したりにおいを残したりするが、とくにのびた爪を研ぐことができないとネコはストレスを感じる。
爪研ぎを不快に感じるようであればネコを飼うことをあきらめる決断も必要である。
ネコの本能を人間の都合で押さえ込むのはネコにとって不幸なことである。森林の中で単独で暮らして来たネコがその本能を満たすために高いところに登ったり、走り回ったとしても叱らないだけの余裕が必要である。
肩凝りはなぜ起こるか…
4人に1人は慢性的な肩凝りに悩まされているという。人間は二足歩行することによって肩凝りが起こりやすくなっているという。
それはもともと4本足で生活をしていた人間は下にぶら下がった腕を支えるようにはできていない。片腕で4㌔㌘。ビール瓶4本分である。さらに二足歩行するようになった人間は約5㌔㌘の頭を支えなければならなくなった。
そこで自然と肩周辺の筋肉を無意識に収縮させており、肩が凝りやすくなっているのである。
そもそも筋肉を動かそうとする時、そのエネルギー源としてブドウ糖が用いられる。
そして筋肉を動かした時、ブドウ糖は水、乳酸、炭酸ガスに分解される。乳酸は筋肉疲労物質ともいわれる。そしてこの筋肉疲労物質は静脈によって運ばれ、体内を循環しているうちに分解されたり尿などとして体外に出される。
ところが無理な姿勢や、同じ姿勢を長時間続けていると、縮んだ筋肉が血管を圧迫して血管が細くなり、血液の循環が悪くなる。すると筋肉疲労物質である乳酸が筋肉中に溜まり目詰まりを起こした状態になる。そして普段はあらゆる細胞の活動を手助けしているカリウムなどが筋肉中に留まり感覚神経を刺激するのである。その刺激が痛みの信号となり、脳へ伝達され、痛みと認識すると、肩の筋肉を収縮させるのである。そしてさらに血管を圧迫し血液の循環が悪くなるのである。それが悪循環となり、繰り返され肩凝りと認識されるのである。
このように痛みを伴なった筋肉が部分的な縮んだ状態のことを「懲り」という。
日本人には欧米人に比べ特に肩凝りになりやすい様々な原因があった。
........

【原因その①肩凝り体格説】
日本人は肩幅の狭い撫で肩である。この撫で肩は、腕を支えるために必要な肩や首の筋肉が十分に発達していない状態。肩や首の筋力が弱いと筋肉に負担がかかり、収縮して固くなることにより血液の循環が悪くなる。そのため肩凝りを起こしやすいと言うのである。しかし体格のよい日本人でも肩凝りに悩まされている人が多い。それはなぜか。
【原因その②肩凝り猫背説】
実験によると背筋を伸ばした状態だと、筋肉の収縮はほとんど見られない。次ぎに猫背の状態だと肩の筋肉にかなりの負担がかかっていることが明らかになった。このように猫背になると首から肩にかけての筋肉に負担がかかり肩凝りが起こり易くなる。日本人には立っている時も座っている時も猫背になっている人が多い。日本人は他の国の人々に比べて非常に猫背の人が多い。これが肩凝りの原因になっていると考えられる。
なぜ日本人は猫背になってしまうのか。日本人は、畳の生活を長く続けてきたので猫背になりやすい。リラックスした姿勢をとろうとして自然に胡座をかいたり横座りするようになった日本人は、全体の重心のバランスを上手くとるために猫背になっている。
つまり胡座や横座りの場合、背筋を伸ばして座るよりも猫背のほうがバランスがよく安定している。
畳やカーペットに直接座る習慣が根強く残っている日本人には猫背体型が減らないため、肩凝りも減らないのである。
以上のように日本人は、肩凝りになる要素が非常に多く、潜在的に肩凝りを感じやすい体質である。
では、日本人の中でも肩凝りを感じる人と、感じない人がいるのはなぜか。
【原因その③肩凝り意識説】
肩凝りと言う言葉や概念があることによって肩を意識してしまい、意識することで肩凝りが起こる。
常日頃から肩を強く意識することが更に肩凝りを悪化させる。
人間は驚いたり、何かに体の一部をぶつけたりすると、脳から「身を守れ」という指令が筋肉につわり、筋肉が収縮する。これを多シナプス反射という。
肩の神経に意識が集中して「多シナプス反射」が持続的に起こって肩凝りが起こることも考えられる。
その結果自然と肩の筋肉に力が入り、肩の筋肉が収縮し、血管が圧迫され、血流が悪くなる。すると老廃物などが溜まり、カリウムなどが感覚神経を刺激してその悪循環の繰り返しがやがて肩凝りになっていくというのである。
つまり、肩凝りを強く意識するという心理的作用が更に痛みを増加させてしまうのである。
【肩凝り末梢神経説】
腱と骨の間には骨と筋肉の動きを滑らかにする滑液包というものがある。肩が凝ると筋肉の動きが悪くなるので、動きを滑らかにしようとするため滑液包が大きくなる。するとその上を通っている末梢神経を圧迫し痛みを感じているというのである。よってその滑液包の上、ないしは周辺に末梢神経が通っているか否かによって肩凝りを感じたり感じなかったりするのではないかという説がある。
面白いと思ったのは私だけなのかもしれないが、次のようなことに気がついた。
latitudeとattitudeは全く異なる意味を持つがほぼ共通の
 t
t tj
tj
 dという音を含みます。
dという音を含みます。面白いことにそれぞれの意味(緯度と態度)も異なりこそ、共通のidoという音を含みます。
面白い偶然だと思いません?
_/_/噛む_/_/
最近「噛む」というと「流暢に話せない様」「セリフで躓く様」を連想するほど咀嚼に対する意識が希薄になっているかもしれない。
「噛む」=「咀嚼」の重要性について話してみよう。
食欲は、大脳の視床下部にある満腹中枢と摂食中枢で制御されている。満腹中枢が十分に刺激され、最高値に達するのは食事を始めて15分から30分ぐらいである。
よく噛まないで食事をすると満腹感を感じる前に必要以上の食べ物を摂取してしまうことは想像に易いことである。
余分な食べ物は、それを消化するために労力を強いるので、胃腸には多大な負担をかけてしまうことになる。最初は丈夫で負担に耐えながら消化吸収作用を行うが、少しずつ弱っていき、それが全身の倦怠感や目覚めの悪い朝を迎えることになるのである。これは消化吸収にも運動同様にエネルギーを消費するので、その分だけ体に疲れが出る。
ゆっくりと噛むことにより、適量の食事で消化吸収の流れをスムーズにすることができ、少ない睡眠で疲れが十分にとれるようにもなり、体の調子が整ってくるようだ。
よく噛むことで、唾液腺が刺激を受け、多くの唾液が分泌される。これには体に好作用をもたらす多くの酵素やホルモンを含んでいる。
炭水化物は主に唾液のアミラーゼによって分解されるので、噛むほどに消化器系への負担が軽くなる。
唾液には毒消しの働きがある。発癌性のあるものに唾液を混ぜておくと発癌物質が消えてしまう。ペルオキシダーゼという酵素が、癌の芽である発癌物質(変異原性)を消してしまう作用があるからだという。よく噛むほどにその抗癌作用が働く。この作用は体調によっても年齢によっても大きく差が出る。
【唾液の有用な成分】
・ムチン…粘り成分。口や喉の粘膜が食べ物で傷つかないように保護。
・リゾチーム、ラクトフェリン、ヒスタチン…歯周病やう歯を予防したり、ウイルスや細菌を攻撃する免疫としての働きや血液の凝固を助け止血する働きもある。
・EGF(上皮成長因子)…細胞を修復する作用。
・NGF(神経成長因子)…壊れたシナプスの修復。痴呆防止、記憶力の回復につながる可能性がある。
つまり「噛む」という一見食べ物を細かくする物理的な行為にしか見えない動きも唾液とよく混ぜて体に良い効果をもたらすという大切な役割があるのである。
1996年に東京で日本スペースガード協会設立総会が開かれた。これは地球に接近する危険な物体を調査するネットワークを構築しようというもので、同じく1996年3月イタリアのローマでも各国の世界的に権威のある天文学者が集結し、国際スペースガード財団(International Spaceguard Foundaion)が設立された。さらにNASA内部にも小惑星探査機関「ニート(Near Earth Asteroid Tracking)」と呼ばれる組織も作られていた。
同時期にこのような機関が続々と誕生したのは4年前のシューメーカー・レビー第9彗星の木星への衝突から、地球においての同様の危機を憂慮してのことであった。
ハワイのケック天文台(W.M.KECK OBSERVATORY)では7番目の衝突で起きた高さ1600㎞の火柱をとらえていた。この衝撃によって木星にできた波紋の大きさはほぼ地球と同じ大きさだという。つまりもし地球に衝突していたら、地球は木っ端微塵だという。そのような懸念から研究機関が続々と誕生した。
ニートが設立された1年だけでも危険な小惑星がいくつか発見された。
アメリカアリゾナ州のメテオクレーター(METEOR CRATER)直径1・2㎞深さ170mものこの巨大なクレーターは5万年前、直径50mの隕石衝突によるものと推定されている。つまりクレーターの大きさは衝突した隕石の20~30倍もの穴を作り出すパワーを秘めている。
現在、地球上に確認されているクレーターの数は100個以上。その中でも世界最大のそれはメキシコユカタン半島のもので直径200㎞~300㎞にも及び、6500万年前にできた最大のクレーターである。
もしこの規模の隕石が日本に衝突した場合どうなるか。この規模のクレーターをを作り出すのは直径10㎞ほどの隕石である。東京の中心部に落ちたとすると水戸市(茨城県)、前橋市(群馬県)、富士市(静岡県)がすっぽりと入ってしまうのである。当然この範囲は地殻がふき飛ばされ、巨大な穴があき、地中からマントルがふき出し、すべての都市は跡方もなくふき飛んでしまうのである。
そればかりではない。その衝撃は莫大なエネルギーを放ち大地をふき飛ばす。大量に発生した粉塵は成層圏に達し、地球全体を覆い尽くす。太陽光を遮られ、氷点下の氷の世界となってしまい、地上の生物の65㌫は死滅してしまう。その後大量に発生した二酸化炭素が温室効果をもたらし、衝突時の冬から突如高温にさらされる。これによって残りの生物もほとんど死滅してしまう。
現在地球にとって危険な小惑星は約6000個あるという。最大のものは直径23㎞、433エロス(433EROS)という。地球防衛に関する国際会議報告書ではいくつかの対策案があげられていた。①太陽熱収集器で小惑星を加熱し、蒸気によって軌道を変える。網の目に弾丸をはりめぐらせた巨大ロケットを超高速であて粉々にする。③核爆弾を小惑星の中心部に打ち込み一瞬にして爆破する。とくに③は核兵器保有につながるため疑問視されている。
このように様々な障害があるために防衛策は確立されていない。現在の研究によると人類を滅亡させるような小惑星が地球に衝突するような確立は10万年に1度と言われている。しかし、小惑星の軌道が決定されない限りいつ衝突するか明確にはいえない。近い将来、小惑星の軌道が変わって地球に向かって来ることも十分に考えられる。
地球を脅かすのは何も隕石ばかりではない。人工衛星の破片なども問題化している。地球の回りを飛んでいるほとんどの人工衛星は地球の引力によって次第に引き寄せられ、落ちてくるという。事前に予測し、機体を回転させたり、遠隔推進機の噴射によって軌道を変え、被害を回避できなくはないが、噴射のタイミング1秒早いだけで落下地点が数千㎞のびる。大気圏に突入すると大気との摩擦によって空中で分解する。500個もの破片にもなる。大きさにもよるが、スカイラブのそれは長さ1300㎞、幅160㎞にも及んだ。破片の重さは1㎏~2・5㌧。
安全なはずの人工衛星が再び地球に落ちてくるのはなぜか。地上から36000㎞にある人工衛星は落ちて来ないが、高度数千㎞以下の人工衛星は必ず地球に落ちて来るという。人工衛星は高度500㎞のところで飛んでいるそれは時速36000㎞にも及ぶ。この場合人工衛星には遠心力と地球の引力との2つの力が働き、ロケットエンジンなどの推進力のない人工衛星が宇宙空間に漂っていられるのは遠心力と引力がつり合っているからである。それが落ちて来るのは高度500㎞の上空にも地表の1兆分の1の空気が存在し、普通の大きさの人工衛星には0・5㌘の抵抗が生じる。これは1年間に人工衛星の速度を時速300㎞減
速させる。ということは遠心力が減少し、引力によって地球に引き寄せられる。計算によると地上500kmで打ち上げられた人工衛星はおよそ5年で落下する。ちなみに今打ち上げられている人工衛星の80㌫は落ちて来るという。落下途中にほとんどの人工衛星は大気との摩擦によって焼失する。この時完全に燃えつきないものが人工衛星の落下事故になるのである。
皮肉なことに人類が作り出した最先端の技術が人類の新たなる脅威となってしまったのである。
その人工衛星を監視するために1994年3月にアメリカで大気圏外管制部(SPACE CONTROL CENTER)が設立された。世界各国の13台のレーダーと、4つの巨大望遠鏡からの情報をもとに24時間対制で地球の大気圏外を監視することにあった。さらに人類が作り出した宇宙のゴミをも監視しているのである。この宇宙のゴミのことをスペースデブリ(SPACE DEBRI)という。世界中に配置されたレーダーシステムで地上150㎞から36000㎞までにあるスペースデブリを24時間体制で監視している。大気圏外レーダーシステムによって追跡されたスペースデブリ数は8600個にもなる。最小追跡範囲は10㌢㍍まで可能である。スペースデブリの発生パターンであるが①人工衛星の使い捨て。現在地球の軌道にある人工衛星は約2300機。そのうち95㌫の約2200機が寿命が尽きたか故障で使用不可能となり、放置されている。②ロケットの切り離し。人工衛星はロケットで打ち上げられているが、ロケットは何段にも重ねられた構造になって
いるが、燃料がなくなったロケットを切り離していく。切り離されたロケットはそのままスペースデブリと化す。また捨てられたそれの燃料と酸素が残っていることがある。やがてこの二つ混ざり合い、爆発をおこすとさらに細かい数え切れないほどの金属の破片がスペースデブリとなる。③宇宙飛行士が船外活動をしている時に小さなホコリや機体の塗料がスペースデブリとなる。機体のボルトなども危険なデブリとなる。このような小さなものまでも監視しなくてはならないのは時速数万㎞というスピードで飛行しているスペースシャトルから飛び出したデブリも同様のスピードで飛行し続けるのである。
件のデブリが他の人工衛星や宇宙飛行士らに衝突した際には大変な事故になってしまう。現にスペースデブリからスペースシャトルを救った例がいくつかある。
一方世界各国が共同開発している宇宙計画がある。国際宇宙ステーション(INTERNATIONAL SPACESTATION)である。完成は2003年といわれている。これの宇宙ゴミ対策はどうなっているのか。10㌢㍍以上のデブリについてはレーダーで監視しているので宇宙ステーションの軌道を変えることで回避できる。1㌢㍍以下の宇宙ゴミは外壁を特殊構造(特殊バンパーシールド)にすることで回避できるという。問題となるのは1~10㌢㍍の中規模のデブリである。レーダーでとらえることは不可能。先のバンパーシールドは貫通してしまう。さらに船外活動中の宇宙飛行士とっても最も脅威となるのは1㎜クラスのデブリである。これは
宇宙に無数にあり、宇宙服を直撃したら大変なことになる。宇宙服内の気圧が下がり0になると自分の体温で体内の血液・水分が蒸発し、またたくまに宇宙飛行士は、ミイラ化してしまう。宇宙空間の広さから考えると宇宙ゴミが当たる確率は非常に低いというが危険であることは否めない。だが、現在のところ小さなデブリについてはこれといった対策がなされていない。
というよりも、スペースデブリを回避する安全対策はまだ技術が追いついていないのが現状。
スペースデブリが増えるとデブリ同士が衝突しその数が際限なく増える。これによって地球はデブリの雲に覆われ、人類は宇宙に飛び出せなくなる。
さらにずさんな宇宙計画がひきおこした深刻な問題がある。たとえば1996年11月16日、ロシアの火星探査機「マース96(MARS 96)」が打ち上げられた。打ち上げから1時間37分後、4段目のロケットエンジンの点火に失敗した。
地球からの軌道修正もきかず、地球圏から脱出できなくなった。それは地球の引力によって引き寄せられ、徐々に高度を下げて行った。墜落が避けられないじょうたいになったが、マース96の動力源にはプルトニウム電池が搭載されていた。それは35㎜のフィルムケース大の大きさで中にはプルトニウム238が50㌘入っていた。このプルトニウム238は人体に対して恐るべき毒性を持っている。プルトニウムが落下の衝撃によって大気中に放出されると、人間の肺にプルトニウムが沈着し、集中被爆することになる。
1996年11月17日、マース96をアメリカの大気圏外管制部が捕らえた。コンピュータにより軌道を計算するとオーストラリア中東部に落下する可能性が強いと判明。アメリカのクリントン大統領はオーストラリアのハワード首相にホットラインで連絡を入れ、放射性物質処理チームを含む緊急対応部隊を警戒態勢につかせた。ところが同日8時34分には突如オーストラリア国防省非常事態管理局が会見を開き、マース96はチリ起き1000kmの南太平洋に落下したと公式発表があった。
ところが実際は16日に太平洋上空で爆発しており、その破片が800㎞離れたボリビアとの国境、アンデス山脈まで飛んできたという事実が明らかになった。
1996年11月29日、アメリカ合衆国空域司令部が前回の発表を訂正した。マース96の破片が落下したのは11月17日だけではなくほとんどは16日、その残骸は太平洋、チリ、ボリビアにまたがる320㎞に及ぶ広範囲に落下したと発表した。プルトニウム電池は粉々になり、チリ北部に放射性物質がばらまかれたという。件の合衆国空域司令部によるとマース96の残骸はどこに残っているのか全く見当がつかないという。
それに対してロシア宇宙局によればプルトニウム電池はどのような衝撃を受けても中のプルトニウムが飛び出すことはなく安全と主張している。チリ(CHILE)政府は国際法に基づきプルトニウム電池を回収することを求めているがロシア政府の回答はない。今なお、プルトニウム電池の行方はわかっていない。
現在宇宙空間を飛んでいる人工衛星だが、技術開発衛星910機、科学衛星182機、通信放送衛星472機、気象衛星25機、地球観測衛星52機、早期警戒衛星59機、測地衛星27機、軍事衛星不明…と約2300機にものぼる。しかもそのうち60機以上もの人工衛星がプルトニウム電池を搭載しているという。
さらにNASAでは土星探査機カッシーニ(CASSINI)の打ち上げを計画。惑星探査機としては過去最大級を誇る。計画が成功すれば土星に関する様々な謎が解明されるのは間違いないが、カッシーニにはマース96の170倍の34000㌘ものプルトニウム238を搭載しているという。極秘に進められたこの事実は内部告発によって表面化したが、安全性を主張しながらも万一の失敗に備えて政府は地下シェルターを建設したという。