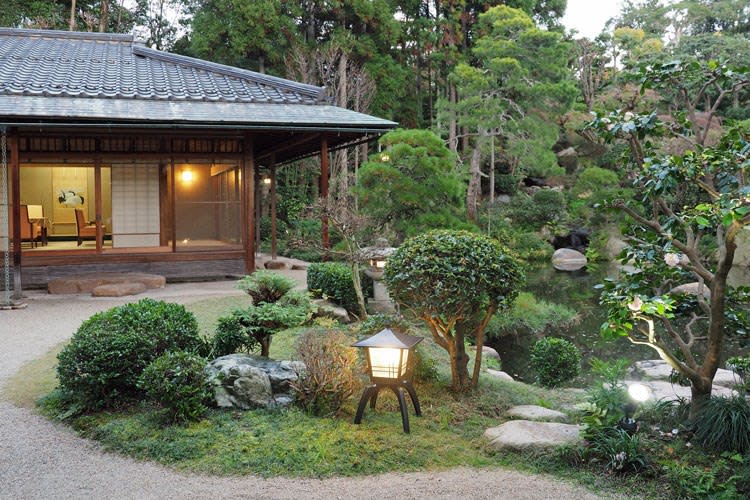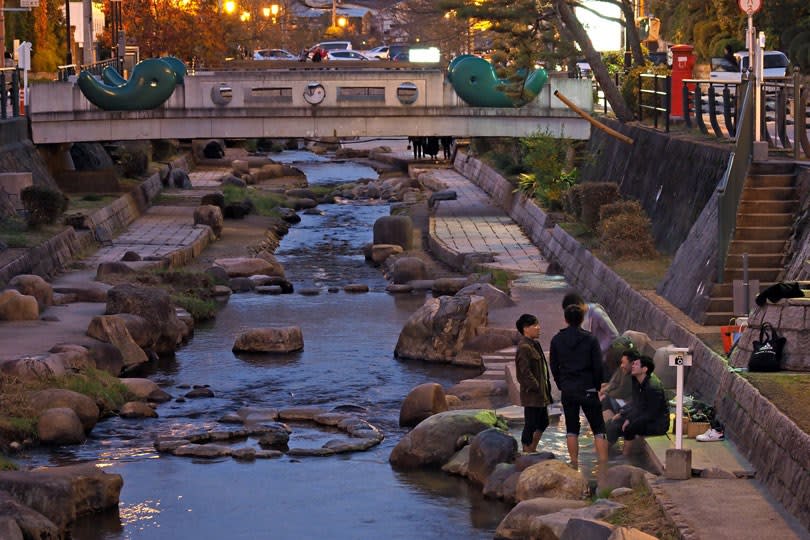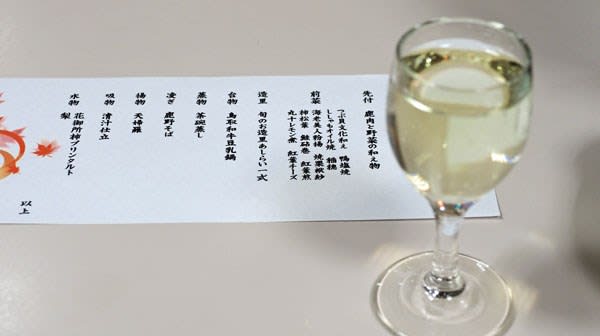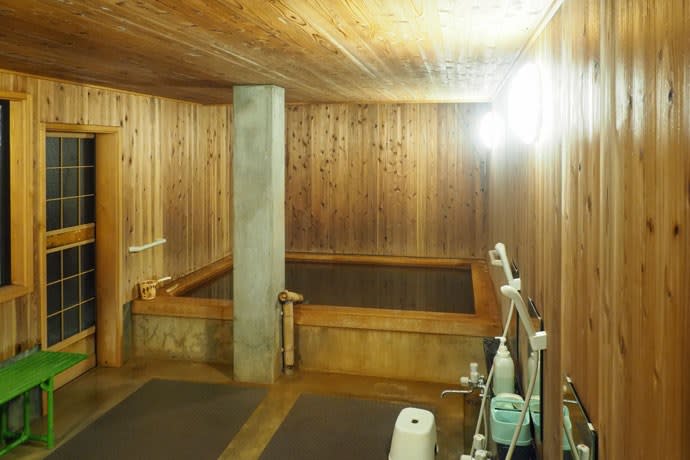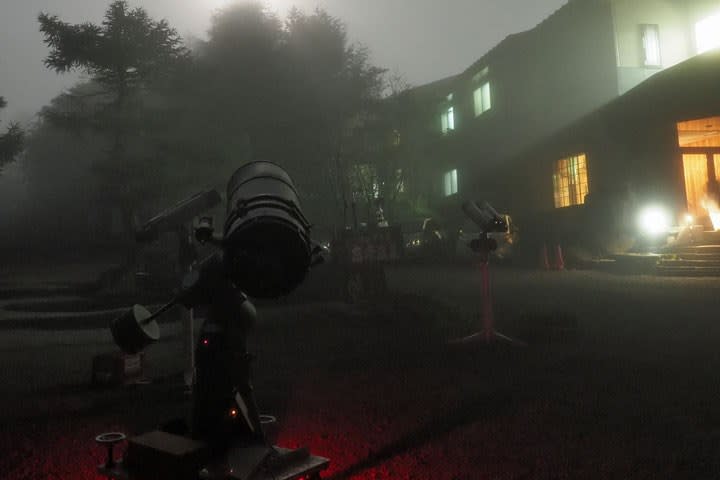れもんです。
玉造温泉長楽園の後編は、お料理と温泉です。
早速、夕食から・・・

山陰の味覚を詰め込んだ、月替わりの懐石料理です。

立派なずわい蟹です。
右側の前菜は、ごま豆腐、鴨西京漬け、海老柴煮、栗甘露煮、なまこの霙和え

どーんと
島根和牛のステーキ

お造りは、雲丹と日本海の鮮魚盛り


豆乳鍋 出雲蕎麦

天麩羅は、地物穴子と
蟹の香り揚げ

えごまの茶碗蒸し


しじみご飯と、デザート三種盛り
とても美味しかったです。 ごちそうさま~ 

続いてお風呂を紹介しましょう。
大浴場は「恵泉」と「華泉」という名の二つがあって、
男女入替え制で、どちらも内湯と露天風呂を備えています。
写真撮影は原則禁止になっていたので、
不本意ですが、HPから写真をお借りしました。
「恵泉」


「華泉」


そして一番のお目当て。
龍宮の湯 と名付けられた大露天風呂がこちらです

※ この写真もHPからお借りしています。

明治42年に完成したという手掘り式の露天風呂で、
混浴ですが、男女とも専用の湯浴み着が用意されています。
このほか、龍宮の湯に続く女性専用の「水晶の湯」があり、
どれもみな、「沸かさず、薄めず」の源泉掛け流しです。
混浴ですが、男女とも専用の湯浴み着が用意されています。
このほか、龍宮の湯に続く女性専用の「水晶の湯」があり、
どれもみな、「沸かさず、薄めず」の源泉掛け流しです。
夜になると、照明が湯気に滲んで幻想的です。



ちなみに、この龍宮の湯も原則撮影禁止ですが、
許可をもらって、入浴客がいない時間に撮っています。
許可をもらって、入浴客がいない時間に撮っています。
さて翌朝は、再び温泉街の散策に・・・。

湯薬師広場 では、湧き出るお湯を自由に汲めて、
持ち帰った温泉水を、化粧水として利用できます。
玉造のお湯は、出雲国風土記にも
一度洗えば肌がすべすべになり、
二度入ればどんな病気やけがも治る
二度入ればどんな病気やけがも治る

と書かれているほどの 美肌の湯
 なんですよ。
なんですよ。朝の散歩を終えて、さあ朝食。
小鉢がたくさん並んだ和定食で、ご飯はもちろん温泉粥をチョイスしました。

出発前に、また龍宮の湯へ。
狙いどおり、広い露天風呂は貸切り状態でした。
日が射してきらきら光る水面に、湯気が立ち上っては流れます。
夕方や夜とはまた違う情景を、たっぷりと楽しませていただきました