都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
「ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン2009」 公演番号132、334、278、315
ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン2009の有料公演が昨日終了しましたが、私が聴いた上記公演番号の4公演の感想を手短かにまとめておきたいと思います。
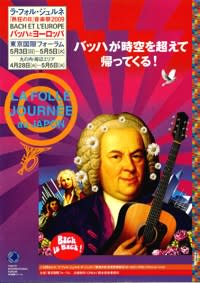
公演番号132 5/3(日)11:15~ ホールB5
J.S.バッハ ゴルトベルク変奏曲ト長調BWV988
ボリス・ベレゾフスキー(ピアノ)
長大なゴルトベルクをロマン派の一大叙情詩の如く弾ききったベレゾフスキー。彼の本調子とは離れている気はしたが、厳格なバッハの音楽を半ば崩すかのようにして、時に憂鬱に、また反面の快活に打ち鳴らす様は、ピアノ曲から広がる世界をゆうに超えたドラマテックなオペラを聴いているかのような錯覚さえ与えられた。雄弁なゴルトベルクも面白い。
公演番号334 5/5(火)15:45~ ホールB5
F.クープラン 4声のソナタ「スルタン妃」/テレマン リコーダー、弦楽、通奏低音のための組曲イ短調
カプリッチョ・ストラヴァガンテ
ジュリアン・マルタン(リコーダー)
スキップ・センペ(チェンバロ・指揮)
注目のセンペとその手兵によるプログラム。丁寧な調律から始まったのは、各々の楽器の音色が溶け合って一つになる甘いハーモニーだった。なかでも秀逸なのは後半のリコーダーのソロを入れたテレマンの組曲。指が的確極まりなく廻るジュリアン・マルタンのリロは表情豊かでかつ瑞々しく、それが小気味よく立ち回るヴァイオリン、そして底部を支えるコントラバスと見事に掛け合っていた。もちろん全体をあうんの呼吸でまとめあげるセンペのチェンバロもそつがない。ソロはチケットが取れずに泣く泣く断念したが、いつかは彼のリサイタルを聴いてみたいもの。
公演番号376 5/5(火)17:45~ ホールG409
J.S.バッハ パルティータ第5番ト長調BWV829、第6番ホ短調BWV830
アンドレイ・コロベイニコフ(ピアノ)
大胆に鳴らすフォルテと、一方でのソフトタッチな弱音部にも神経が行き届いたレンジの広いパルティータ。一気にアクセルを踏んで加速したかと思うと、ふと手の力を抜き、キーへ沈みこませて、音楽に絶妙な表情をつけていた。時に唸りながら情感をこめ、ピアノへ立ち向かうその姿勢は、ピアニストというよりもまるで格闘家のよう。とは言え、トリルなどの技巧の安定感も抜群。終始、バロック音楽の構築美を損なわずに演奏する点に、バッハに対する深い読み込みを思わせるものがあった。
公演番号315 5/5(火)19:45~ ホールA
J.S.バッハ マタイ受難曲BWV244
シャルロット・ミュラー=ペリエ(ソプラノ)
ヴァレリー・ボナール(アルト)
ダニエル・ヨハンセン(テノール)
ファブリス・エヨーズ(バリトン)
クリスティアン・イムラー(バリトン)
ローザンヌ声楽・器楽アンサンブル
ミシェル・コルボ(指揮)
奇を衒うことを全くせず、まるで受難のモノローグを一人で切々と語るかのように進む、コルボらしい内省的なマタイ。透き通るような声を聴かせる合唱はもちろん、清々しい響きで音楽に表情をつける木管群など、定評のあるローゼンヌ声楽・器楽アンサンブルの機動力も見事だった。もちろん歌手も素晴らしい。イエスへの愛を歌うソプラノのペリエ、またアルトのボナールをはじめ、情感のこもった進行で場の雰囲気を盛り上げた福音史家のテノール、ヨハンセンなどはとりわけ印象的。通常休憩を挟む第一部終了後、音楽が進み、二部冒頭のイエスへ死を告げる箇所で休憩となったが、そのまま通して演奏しても気にならないくらいの集中力があった。LFJで聴いたコルボではフォーレのレクイエムが一番感銘を受けたが、それに匹敵するくらいの高いレベルの演奏ではなかっただろうか。

今年は自分のスケジュールもあってか、コンサート以外のLFJならではのイベントにあまり参加出来ませんでした。年々、チケット争奪戦も厳しくなり、ぶらりと有楽町へ立ち寄って音楽を楽しむというイベント色は薄くなくなってきていますが、マスタークラスやキオスク、地下広場、もちろん屋台村などこそお祭りならでの企画でもあるので、なるべく来年はもう少しその辺にも足を突っ込んでみるつもりです。
ところで来年のLFJはショパンやシューマン(?)と聞きました。これまたピアノなどで人気の作曲家だけあってチケットも大変なことになるのではないでしょうか。私としてはどちらかと言うと後者の方に関心があるので、そちらをメインにしてまた行きたいと思います。
*追記:来年のテーマはショパン!(LFJ公式ブログ)
ショパンの他にシューマンではなく、リスト、メンデルスゾーン、パガニーニ、またロッシーニ、ベッリーニ、ドニゼッティらを取り上げるそうです。

*関連エントリ
「ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン 2009」@東京国際フォーラム
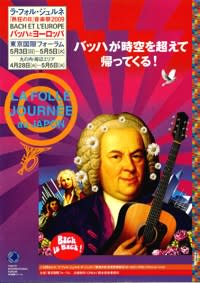
公演番号132 5/3(日)11:15~ ホールB5
J.S.バッハ ゴルトベルク変奏曲ト長調BWV988
ボリス・ベレゾフスキー(ピアノ)
長大なゴルトベルクをロマン派の一大叙情詩の如く弾ききったベレゾフスキー。彼の本調子とは離れている気はしたが、厳格なバッハの音楽を半ば崩すかのようにして、時に憂鬱に、また反面の快活に打ち鳴らす様は、ピアノ曲から広がる世界をゆうに超えたドラマテックなオペラを聴いているかのような錯覚さえ与えられた。雄弁なゴルトベルクも面白い。
公演番号334 5/5(火)15:45~ ホールB5
F.クープラン 4声のソナタ「スルタン妃」/テレマン リコーダー、弦楽、通奏低音のための組曲イ短調
カプリッチョ・ストラヴァガンテ
ジュリアン・マルタン(リコーダー)
スキップ・センペ(チェンバロ・指揮)
注目のセンペとその手兵によるプログラム。丁寧な調律から始まったのは、各々の楽器の音色が溶け合って一つになる甘いハーモニーだった。なかでも秀逸なのは後半のリコーダーのソロを入れたテレマンの組曲。指が的確極まりなく廻るジュリアン・マルタンのリロは表情豊かでかつ瑞々しく、それが小気味よく立ち回るヴァイオリン、そして底部を支えるコントラバスと見事に掛け合っていた。もちろん全体をあうんの呼吸でまとめあげるセンペのチェンバロもそつがない。ソロはチケットが取れずに泣く泣く断念したが、いつかは彼のリサイタルを聴いてみたいもの。
公演番号376 5/5(火)17:45~ ホールG409
J.S.バッハ パルティータ第5番ト長調BWV829、第6番ホ短調BWV830
アンドレイ・コロベイニコフ(ピアノ)
大胆に鳴らすフォルテと、一方でのソフトタッチな弱音部にも神経が行き届いたレンジの広いパルティータ。一気にアクセルを踏んで加速したかと思うと、ふと手の力を抜き、キーへ沈みこませて、音楽に絶妙な表情をつけていた。時に唸りながら情感をこめ、ピアノへ立ち向かうその姿勢は、ピアニストというよりもまるで格闘家のよう。とは言え、トリルなどの技巧の安定感も抜群。終始、バロック音楽の構築美を損なわずに演奏する点に、バッハに対する深い読み込みを思わせるものがあった。
公演番号315 5/5(火)19:45~ ホールA
J.S.バッハ マタイ受難曲BWV244
シャルロット・ミュラー=ペリエ(ソプラノ)
ヴァレリー・ボナール(アルト)
ダニエル・ヨハンセン(テノール)
ファブリス・エヨーズ(バリトン)
クリスティアン・イムラー(バリトン)
ローザンヌ声楽・器楽アンサンブル
ミシェル・コルボ(指揮)
奇を衒うことを全くせず、まるで受難のモノローグを一人で切々と語るかのように進む、コルボらしい内省的なマタイ。透き通るような声を聴かせる合唱はもちろん、清々しい響きで音楽に表情をつける木管群など、定評のあるローゼンヌ声楽・器楽アンサンブルの機動力も見事だった。もちろん歌手も素晴らしい。イエスへの愛を歌うソプラノのペリエ、またアルトのボナールをはじめ、情感のこもった進行で場の雰囲気を盛り上げた福音史家のテノール、ヨハンセンなどはとりわけ印象的。通常休憩を挟む第一部終了後、音楽が進み、二部冒頭のイエスへ死を告げる箇所で休憩となったが、そのまま通して演奏しても気にならないくらいの集中力があった。LFJで聴いたコルボではフォーレのレクイエムが一番感銘を受けたが、それに匹敵するくらいの高いレベルの演奏ではなかっただろうか。

今年は自分のスケジュールもあってか、コンサート以外のLFJならではのイベントにあまり参加出来ませんでした。年々、チケット争奪戦も厳しくなり、ぶらりと有楽町へ立ち寄って音楽を楽しむというイベント色は薄くなくなってきていますが、マスタークラスやキオスク、地下広場、もちろん屋台村などこそお祭りならでの企画でもあるので、なるべく来年はもう少しその辺にも足を突っ込んでみるつもりです。
ところで来年のLFJはショパンやシューマン(?)と聞きました。これまたピアノなどで人気の作曲家だけあってチケットも大変なことになるのではないでしょうか。私としてはどちらかと言うと後者の方に関心があるので、そちらをメインにしてまた行きたいと思います。
*追記:来年のテーマはショパン!(LFJ公式ブログ)
ショパンの他にシューマンではなく、リスト、メンデルスゾーン、パガニーニ、またロッシーニ、ベッリーニ、ドニゼッティらを取り上げるそうです。

*関連エントリ
「ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン 2009」@東京国際フォーラム
コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )









