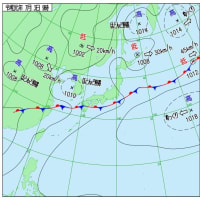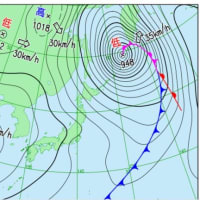何回も書いてきたが筆者は囲碁を趣味にしているが、なかなか上達しないので困っている。勉強でも趣味でも運動競技でも同じかも知れないが、楽をして上達する方法はないようである。などと今更言うことでもないが、囲碁に熱中した若い頃のことを思い出す。それでも囲碁を打っていていろんな人の感情の動きが見られるのが面白い。
一昨日、町の囲碁愛好会の春季大会があった。結果から先に言うと、昇段したばかりの大会で4連敗を喫してしまった。昇段してAクラスい入り全勝して優勝した方もいるのだから立派である。また、五分の星を挙げて昇段が妥当と評価された方もいる。筆者の対戦相手は5,6,6,6段の方々であったなどと理由付けしたい気がするが、それは理由にならないので、とても情けないと反省している。
今大会からルールが変わって、1段差1子(シ;石)、井目(セイモク;9個の石を前もって置いてハンデを付ける)に置く以上の場合に限って上段者がコミ7目を下段者にだす。持ち時間は各40分、賞品は6位(前回までは5位まで)まで、その他にブービー賞、ラッキー賞が新設された。同率者がいた場合は対戦者の勝ち数を合計し(スイス方式というそうである)、それでも決まらない場合は上段者が上位になる。それでも決まらない場合は高齢者が上位になる。
参加者は7~3段のAクラス24名、2段から9級までの24人合計48名であった。
筆者は新しい物好きなので?ブービー賞をいただいた。次回は頑張ろうと思う。
ここで面白いのが、 I 氏のことである。プロの棋士でも対戦が終了すると戦後の検討をするのが通例である。それは次回よい碁を打つために行うのであり素人の筆者らにとっても大事なことである。もちろん対局中に口を挟むのは厳に慎まなければならないことであるが、対局終了後にあそこでこうやるのはどうだろうかと言うようなことは話すことがある。 I 氏は自分の打った手をけなされたと思うのかもしれない。どうも打ち碁の検討で自分の意見と違うことを言われるのが苦手のようである。打った手を検討すことはお互いのためであると思うし見ていた人にとっても勉強になると思うのだが。例えば、筆者が勝負所とも思えるところを、ここでこう打っていたら形勢が逆転していたかも知れないというと、I 氏はそんな配石になっていなかったという。対戦相手の方はよく覚えていてそう打っていたら勝負は分からなかったかも知れないと納得した。しかし I 氏は対局時に自分が打った手が最良?なんだなどと訳の分からないことを言う。石を置くまでどんなに悩むか。あるときは妥協してしまうこともある。いつも最良の手を打っていたら負けることは少なくなるだろう。 I 氏は自分の打った棋譜を覚えていないのかも知れない。それで対局後の検討も苦手なんだろうと思った。そんな I 氏はこの数年昇段できないで現状を維持している。負け惜しみのように昇段したくないから大会でほどほどに打っているなどという。そういう考えかたもあるだろうが、対戦相手に失礼である。
ちなみに4段から5段への昇段規定は、年間6回の大会・対抗戦のうちの3~4大会で10勝をあげればよい。それが果たせない苛立たしさもあるのかも知れないと気の毒にも思う。鼻っ柱だけで無く囲碁ももっと強くなって後進者の指導をお願いしたいと思う。