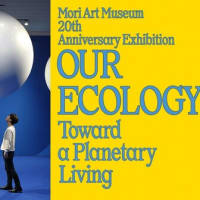2018年はどんな年だったろうと振り返ると、個人的な出来事はさて措き、音楽では2017年のカンブルラン/読響の「アッシジの聖フランチェスコ」(メシアン)のような圧倒的な感銘を受ける演奏会はなかったというのが、まず思うことだ。
だが、もちろん、記憶に残る演奏会はあった。最初に思い浮かぶのは、ピエール=アンドレ・ヴァラド/東響の「プリ・スロン・プリ~マラルメの肖像」(ブーレーズ)。サントリー芸術財団サマーフェスティバル2018での演奏。ソプラノ独唱は浜田理恵。この曲が日本初演されたとき(故若杉弘/都響の演奏だった)、わたしは出張と重なったので、涙をのんだ。それ以来、生で聴くのが念願になっていた。
演奏は驚くほど精密なものだった。無数の均質な音で作られた精巧なガラス細工のような感触、といったらよいか。わたしは2015年の同フェスティバルで聴いた大野和士/都響の「ある若き詩人のためのレクイエム」(B.A.ツィンマーマン)を思い出した。以前ドイツで聴いた同曲の演奏(マティアス・ピンチャー/hr響)とはまったく異なり、理路整然とした演奏だった。
両曲とも20世紀の難曲といわれるが、それを日本人の演奏家がきちんと準備をした上で演奏するとこうなるのか、という思いがした。
それと似ているが、新国立劇場が上演した細川俊夫の「松風」も記憶に残るものだった。わたしはこのオペラをベルリンで観たことがあるが、そのときと今回とではかなり印象が異なった。
それはオーケストラの演奏の違いによる。指揮者は同じであるにもかかわらず(デヴィッド・ロバート・コールマン)、今回演奏した東響は、ベルリン国立歌劇場のオーケストラより、細川俊夫の音楽の静謐さの意味をはるかによく理解し、それが故に(逆説的ではあるが)雄弁な演奏になった。
もう一つ記憶に残る演奏会をあげると、それはラザレフ/日本フィルの「ペルセフォーヌ」。ストラヴィンスキーがアンドレ・ジッドの台本に音楽を付けた作品だが、これがストラヴィンスキーかと我が目を(耳を)疑うような繊細さだった。新古典主義の時期の作品だが、他の作品に比べて、その繊細さは群を抜いていた。
ラザレフはスケールの大きな豪快な演奏をするイメージがあるが(そして事実その豪快さは並外れたものだが)、同時に繊細で、軽やかで、淡い色彩感をもつ演奏もできることを示した。いうまでもないが、ラザレフは大指揮者だ。
だが、もちろん、記憶に残る演奏会はあった。最初に思い浮かぶのは、ピエール=アンドレ・ヴァラド/東響の「プリ・スロン・プリ~マラルメの肖像」(ブーレーズ)。サントリー芸術財団サマーフェスティバル2018での演奏。ソプラノ独唱は浜田理恵。この曲が日本初演されたとき(故若杉弘/都響の演奏だった)、わたしは出張と重なったので、涙をのんだ。それ以来、生で聴くのが念願になっていた。
演奏は驚くほど精密なものだった。無数の均質な音で作られた精巧なガラス細工のような感触、といったらよいか。わたしは2015年の同フェスティバルで聴いた大野和士/都響の「ある若き詩人のためのレクイエム」(B.A.ツィンマーマン)を思い出した。以前ドイツで聴いた同曲の演奏(マティアス・ピンチャー/hr響)とはまったく異なり、理路整然とした演奏だった。
両曲とも20世紀の難曲といわれるが、それを日本人の演奏家がきちんと準備をした上で演奏するとこうなるのか、という思いがした。
それと似ているが、新国立劇場が上演した細川俊夫の「松風」も記憶に残るものだった。わたしはこのオペラをベルリンで観たことがあるが、そのときと今回とではかなり印象が異なった。
それはオーケストラの演奏の違いによる。指揮者は同じであるにもかかわらず(デヴィッド・ロバート・コールマン)、今回演奏した東響は、ベルリン国立歌劇場のオーケストラより、細川俊夫の音楽の静謐さの意味をはるかによく理解し、それが故に(逆説的ではあるが)雄弁な演奏になった。
もう一つ記憶に残る演奏会をあげると、それはラザレフ/日本フィルの「ペルセフォーヌ」。ストラヴィンスキーがアンドレ・ジッドの台本に音楽を付けた作品だが、これがストラヴィンスキーかと我が目を(耳を)疑うような繊細さだった。新古典主義の時期の作品だが、他の作品に比べて、その繊細さは群を抜いていた。
ラザレフはスケールの大きな豪快な演奏をするイメージがあるが(そして事実その豪快さは並外れたものだが)、同時に繊細で、軽やかで、淡い色彩感をもつ演奏もできることを示した。いうまでもないが、ラザレフは大指揮者だ。