今宵はクリスマス・イヴということで、僕の好きなバッハのクリスマス・オラトリオを紹介します。
この曲に出会ったのは芸大2年の今頃です。冬休みの帰省をせずに芸大寮で過ごしていたとき、NHKFMの「バロック音楽のたのしみ」のクリスマス週間の特集で、カール・リヒー盤を聴いたのです。この時に録音したテープが良くなかったので、次の年にもエアチェックを待ち構えていたのですが、使われたレコードは同じなのにひどい雑音で、保存状態が悪かったのだと思い、ガッカリした記憶があります。今回は、「朝のバロック」と改称してからの03年に放送されたエリオット・ガーディナー盤(CD DVD)です。こちらの方が空間は感じられますが軽いですね→weihnachts-oratorium.mp3(右クリックでリンク先を保存 音はビットレートが低いのでそれなりです)。
クリスマス・オラトリオというのは、ドイツでのクリスマス期間、すなわち12月25日から新年1月6日の三王の礼拝の祝日(Dreikoenige)までの13日間に歌われるカンタータ(Kantate器楽伴奏付の声楽作品)の総称の事です。プロテスタントの礼拝に用いられる教会カンタータが主流なので、カンタータと言えば教会カンタータを連想する人が多いようです。バッハのクリスマス・オラトリオは全6部からなっていますが、特に第1部が演奏されます。それは、イエスの誕生の喜びを歌ったものなので、クリスマスに最も相応しいからでもありますが、曲の出来映えも第1部が最高だと思います。
第1部の冒頭はティンパニーとトランペットによる、「幕開け」を強調した主題によって始まります。僕はこの部分を大音量で聴くのが大好きですが、今は音を出せる環境にないのが残念です。合唱部(1,5,7,9曲目)の対訳付きの歌詞はこちらのサイトでご覧下さい。合唱部を含めた全体の構成は次のようになっています。
1. 合唱:歓呼の声を放て、喜び踊れ
2. 福音史家(ルカによる福音書):その頃皇帝アウグストより勅令出で
3. レチタティーヴォ(アルト):いまぞ、こよなく尊い花婿
4. アリア(アルト):備えせよ、シオンよ、心からなる愛もて
5. コラール:いかにしてかわれは汝を向かえまつり
6. 福音史家:しかしてマリヤは男の初子を生み
7. コラール(ソプラノ)とレチタティーヴォ(バス):彼は貧しきさまにて地に来たりましぬ---たれかよく この愛を正しく讃えん?
8. アリア(バス):大いなる主よ、おお、強き王
9. コラール:ああ、わが心より尊びまつる嬰児イエスよ
参考 日々雑録 または 魔法の竪琴
第4曲目(11分頃)のアンネ・ゾフィー・フォン・オッターのアルトで歌われる「備えせよ、シオンよ、心からなる愛もて」が特に美しく、このパートを聴くだけで感動します。2曲目の福音史家(エヴァンゲリスト)の朗読に続き、第3曲目のアルトによるレチタティーヴォと進みます。これにアリアが加わるのが教会音楽の形式「レチタティーヴォとアリア」となっています。エヴァンゲリストを『能』にたとえれば、面(おもて)を付けないでストーリーを語る間狂言(あいきょうげん)のような感じです。
独逸語は聴き取りも難しいのですが、僕はBGM風に聴いています。ドイツ語と書くよりも、独逸語と書いた方が、ドイツ語の性格を端的に表していて面白いですね。モーツァルトの『魔笛』で、パパゲーノの歌にホイサッサと対訳が出るのですが、実際にもホイサッサと発音しているように聞こえます。もしかしたら、日本人と同じイスラエル系の言葉かも知れませんね。
完全対訳はこちら
エフライム工房 平御幸
この曲に出会ったのは芸大2年の今頃です。冬休みの帰省をせずに芸大寮で過ごしていたとき、NHKFMの「バロック音楽のたのしみ」のクリスマス週間の特集で、カール・リヒー盤を聴いたのです。この時に録音したテープが良くなかったので、次の年にもエアチェックを待ち構えていたのですが、使われたレコードは同じなのにひどい雑音で、保存状態が悪かったのだと思い、ガッカリした記憶があります。今回は、「朝のバロック」と改称してからの03年に放送されたエリオット・ガーディナー盤(CD DVD)です。こちらの方が空間は感じられますが軽いですね→weihnachts-oratorium.mp3(右クリックでリンク先を保存 音はビットレートが低いのでそれなりです)。
クリスマス・オラトリオというのは、ドイツでのクリスマス期間、すなわち12月25日から新年1月6日の三王の礼拝の祝日(Dreikoenige)までの13日間に歌われるカンタータ(Kantate器楽伴奏付の声楽作品)の総称の事です。プロテスタントの礼拝に用いられる教会カンタータが主流なので、カンタータと言えば教会カンタータを連想する人が多いようです。バッハのクリスマス・オラトリオは全6部からなっていますが、特に第1部が演奏されます。それは、イエスの誕生の喜びを歌ったものなので、クリスマスに最も相応しいからでもありますが、曲の出来映えも第1部が最高だと思います。
第1部の冒頭はティンパニーとトランペットによる、「幕開け」を強調した主題によって始まります。僕はこの部分を大音量で聴くのが大好きですが、今は音を出せる環境にないのが残念です。合唱部(1,5,7,9曲目)の対訳付きの歌詞はこちらのサイトでご覧下さい。合唱部を含めた全体の構成は次のようになっています。
1. 合唱:歓呼の声を放て、喜び踊れ
2. 福音史家(ルカによる福音書):その頃皇帝アウグストより勅令出で
3. レチタティーヴォ(アルト):いまぞ、こよなく尊い花婿
4. アリア(アルト):備えせよ、シオンよ、心からなる愛もて
5. コラール:いかにしてかわれは汝を向かえまつり
6. 福音史家:しかしてマリヤは男の初子を生み
7. コラール(ソプラノ)とレチタティーヴォ(バス):彼は貧しきさまにて地に来たりましぬ---たれかよく この愛を正しく讃えん?
8. アリア(バス):大いなる主よ、おお、強き王
9. コラール:ああ、わが心より尊びまつる嬰児イエスよ
参考 日々雑録 または 魔法の竪琴
第4曲目(11分頃)のアンネ・ゾフィー・フォン・オッターのアルトで歌われる「備えせよ、シオンよ、心からなる愛もて」が特に美しく、このパートを聴くだけで感動します。2曲目の福音史家(エヴァンゲリスト)の朗読に続き、第3曲目のアルトによるレチタティーヴォと進みます。これにアリアが加わるのが教会音楽の形式「レチタティーヴォとアリア」となっています。エヴァンゲリストを『能』にたとえれば、面(おもて)を付けないでストーリーを語る間狂言(あいきょうげん)のような感じです。
独逸語は聴き取りも難しいのですが、僕はBGM風に聴いています。ドイツ語と書くよりも、独逸語と書いた方が、ドイツ語の性格を端的に表していて面白いですね。モーツァルトの『魔笛』で、パパゲーノの歌にホイサッサと対訳が出るのですが、実際にもホイサッサと発音しているように聞こえます。もしかしたら、日本人と同じイスラエル系の言葉かも知れませんね。
完全対訳はこちら
エフライム工房 平御幸















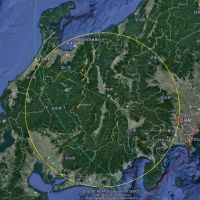
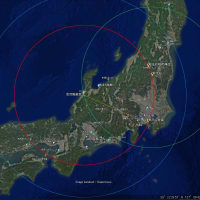

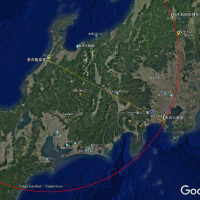






今日、飯島愛さんが亡くなられたという記事が出たので、ネットで検索していてこちらに辿り着きました。
それまで好きでは無かったけれど、日韓共催ワールドカップの時の韓国の不正に対する彼女の発言を支持する、と言った内容のブログ、全く同感でした。私はあれから飯島愛さんに好感を持っていたので、本日の訃報は残念です。
こちらのHPの内容は深くて濃いので、今日からじっくり読ませて頂きます。
年末の折、ご自愛ください。
飯島愛さんが亡くなられたのは4,5日前らしいですが、フジテレビの謝罪に対する風当たりが強くなった時期に一致します。
警察官はやたらに自殺が多いですが、その多くは在日・創価学会の口封じという可能性が高いので、今回も何も出てこないと思います。病死と発表されるのではないでしょうか。
僕は長生きに余り価値を感じない人間なので、若くして亡くなった方をかわいそうだとは思いません。むしろ、この世での役割を全うし、天における自分の価値を高めてこの世を去る栄光を羨ましく思うほどです。
マグダラのマリアのように、罪の女が最も栄光を受けるときが来たのなら、イエスの再臨が近いという事ですね。飯島愛さんは苦痛の表情で亡くなっていたそうですが、天に召されるときは、全ての重荷を下ろして安らかな旅立ちとなるように祈りたいと思います。
彼女の勇気ある発言は語り継がれるでしょうが、勇気ある男の出現が待ち望まれますね。