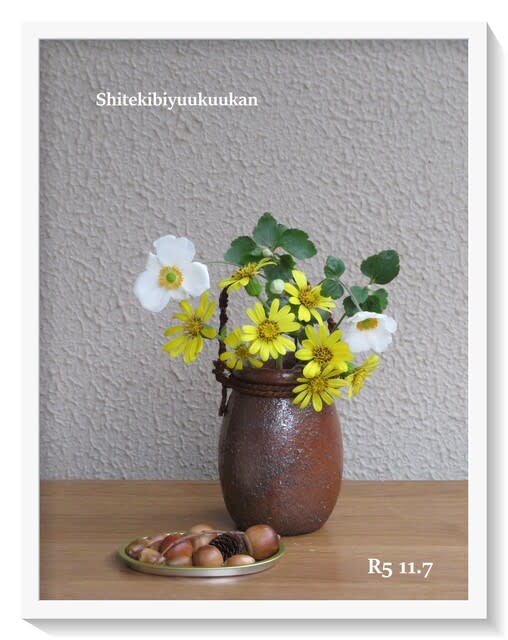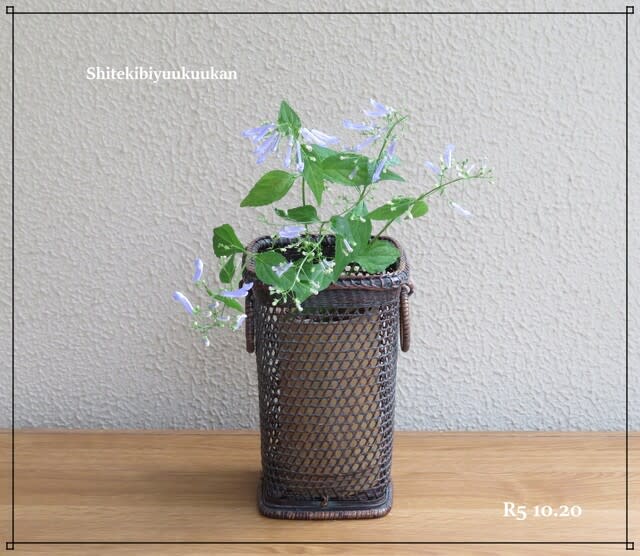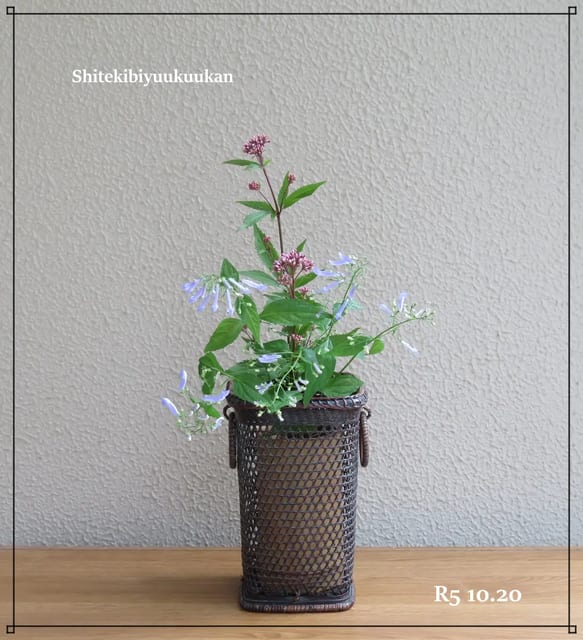玄関前の鉢に
「あけぼの椿」と「月の輪」の二つの名札が付いていて
そこにある挿し木はどちらの椿だろう?と
何年も待っていたのですが
今年、とうとう咲いて
「曙=あけぼの」と判明しました。

~2月20日 大きくてふっくらとした蕾が開いて来ました~
蕾の段階で淡桃色だったので
赤に白の斑入りの「月の輪」でないことは分かりましたが
「曙」を挿し木した覚えが無かったので
この時点では謎の椿でした。

花弁の中には
濃い黄色の蕊がたっぷりと詰まっていそうです。
これは立派な花が咲きそう~♪


~2月22日 開いて来ました~
この姿なら、鉢の名札にある「あけぼの椿」に間違いないな。
挿し木してから、一体何年経ったのだろう~
次に挿し木をする時には
挿し木をした年月日もきちんと書いておかなくてはね。
名前が分かったので
来年からは茶花に使えそうで嬉しい~(^^♪
※曙は加茂本阿弥、数寄屋、太郎冠者などと並ぶ古典椿の一つ。