
( h パラメータとトランジスタ等価回路① と h パラメータとトランジスタ等価回路②を参照してください )
図の特性表より、hパラメータの値を読み取ってみましょう。Yランクの場合、VCE=12V、IC=1mAにおいて各hパラメータは
hie=4kΩ
hre=0.5×10^-4
hfe=180
hoe=2.8μS(357kΩ)
くらいです。
* S=Ω^-1(シーメンス)
hreとhoeは非常に小さいですね。 hre=0 hoe=0 とした場合のエミッタ接地増幅回路の等価回路は右の図のようになります。つまり、エミッタ接地増幅回路は実用上この等価回路に置き換えて何ら問題ないということですね。
【そもそもの話】
小信号の増幅など、トランジスタを特性の狭い範囲で使用する場合は、例えばV=IRのような線形特性とみなすことができるのです。よってhパラメータのような「定数」を用いて等価回路に置き換えたり、計算したりすることができるわけですね。トランジスタを等価回路に置き換えることをトランジスタの線形表現ともいいます。
図の特性表より、hパラメータの値を読み取ってみましょう。Yランクの場合、VCE=12V、IC=1mAにおいて各hパラメータは
hie=4kΩ
hre=0.5×10^-4
hfe=180
hoe=2.8μS(357kΩ)
くらいです。
* S=Ω^-1(シーメンス)
hreとhoeは非常に小さいですね。 hre=0 hoe=0 とした場合のエミッタ接地増幅回路の等価回路は右の図のようになります。つまり、エミッタ接地増幅回路は実用上この等価回路に置き換えて何ら問題ないということですね。
【そもそもの話】
小信号の増幅など、トランジスタを特性の狭い範囲で使用する場合は、例えばV=IRのような線形特性とみなすことができるのです。よってhパラメータのような「定数」を用いて等価回路に置き換えたり、計算したりすることができるわけですね。トランジスタを等価回路に置き換えることをトランジスタの線形表現ともいいます。
















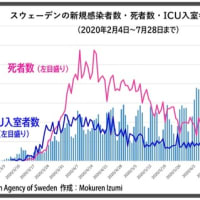











でも、あくまでも「理論上」のものであって、実際に使用するデバイスの目安くらいは測定しておかないと「実際の現場」で「ロットアウト」を喰らいます。
特に2SC1815はHFEやhFEの範囲はものすごく広くて、データシートを鵜呑みにできない現実があるのでした。
こういう「トラの子」を「オーディオミュート」なんかに使用すると大変です。そもそも用途マチガイですが・・・。
デジタル領域で使う場合、トランジスタの「オン抵抗」というものに注目する場合があり、ミュート用途のトランジスタはその値がものすごく低いのです。
バイポーラトランジスタをシミュレーションして実際に組み上げる場合は、実際に使用するデバイスの粗測定が欠かせません。それはホントです!いやぁ~、実際、苦労しましたから・・・。
ある程度、直流でいいですから「HFE」で分別しておくのです・・・「hFE」までは測定してなくていいでしょう。
「HFE」と「hFE」の違い、わかりましたでしょうか?
「HFE」というのはスタティックな直流電流増幅率のことで、市販のテスターで測定できるのはコイツです。
「hFE」というのは、IB-IC特性から求める傾きのことです。信号が変化している状態での電流増幅率です。アンプの実動作の増幅率はこっちのほうになるわけです。
ん、じゃ「HFE」は何に使うのか?っていうと「バイアス設計」に使うことが多いです。アイドリング電流を決めるときとか・・・。
実際の現場は・・・こんな感じです。そんなものです。
(^^)
実践技術は理論のベースに基づきますが、前者は単独でも使えますが、後者は単独ではまったく仕事になりませんね。
トランジスタのミュートとしてのご教示をありがとうございました。また一つ新たな知識が増えました。でもこんなアナログの(ある意味)裏技的な話ができるのも、もうあまり多くの人はいないのでしょうね。
近々、気合を入れてオーディオパワーアンプを設計しようと考えているのですが、初段は2SK30Aを選別に選別を重ねてペアを取る予定です。
たいがいはそれで大丈夫だと思いますが、最後はカットアンドトライになるでしょうかねぇ~?
比較的レベルの高いところ・・・フラットアンプの最終段とか・・・。
ローノイズトランジスタを使ってもコレクタ電流を流しすぎると、やはり「残留ノイズ」に悩まされます。バイポーラトランジスタはもともとノイズ発生源です^^;
初段の場合、VCCを高めにとり、コレクタ電流も0.5mA以下に設定するといいかも?
別に差動入力にこだわることもないでしょうし・・・。
初期の市販プリメインなんかブートストラップでしたし、廉価版はやはりそうでした。
テクニクスのRS-265Uというテープデッキには回路図が付いていたのですが、よく眺めていましたねぇ~、やはりブートストラップでしたけどねぇ~!
録音と再生とマイクアンプに転用していたあたりはものすごくショックでした・・・。「こんな風にやってんのぉ~?」ってな感じでした。
だから、別に現代風に洗練された回路・・・でもなくてもいいと思う私です。
シングルにはシングルのよさがある・・・。
http://homepage2.nifty.com/~mhitaste/audiotop/dcamp_parts/dc_ampparts035.html
これもかなりの贅沢ですねえ。若松通商で3000円近くします。
やはりC1815もオーディオ用に使えますか。たぶんに頷ける話です。実は私のアンプの出力段は2N3055です。この石は大電力用として有名ですが、昔から電源のエミッタフォロワくらいにしか使えないものだろうと思ってたのですが、ためしに出力段に使ってみたら、なんとまあ実によい音を醸し出してくれるではないですか。これには目から鱗でした。
バイポーラはコレクタ電流をあまり流さない方が良いのですね。ありがとうございます、その辺りにも留意して設計します。
2SC2259っていうペアをワンパッケージにしたモノが2個あるのです。
5本足です^^;
もう10数年経ったのかな?オーディオ好きな方からもらったんですよぉ~!
その方とはいっしょに仕事したこともありました・・・。
大事に保管してます^^;
汎用オペアンプのM5218(4558ですね!)にもローノイズタイプがあったように、2SC1815や2SA1015にも完全なコンプリセットとかローノイズ品種はたしかに存在していましたが、ほとんど入手はムリでしょう!
あくまでも、手元に余っている2SA1015を掃く(?)のが目的の1つ!hFEなんて実測100~200程度のモノです。
現実はそんなモノです。
とにかくコレクタ電流を限りなく少なめに・・・結果的に入力インピーダンスも高くなる・・・多少の非直線にかかったとしても目をつむる・・・ってな感じですかね?
だから・・・シングル!ってことです。
やはりC1815,A1015のローノイズ品はあるんですね。店頭のパーツ棚にどさっと入っていたように記憶していますが。たぶんその時限りの限定品だったんでしょうね。
初段はとにかくコレクタ電流を少な目にするのがコツですね。了解しました。
(^^)