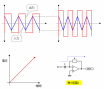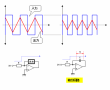今、池上彰がバカ売れである。書店には多くの著書が山積みされており、テレビ番組にも頻繁に登場するようになった。さて、池上彰の何が売れているのかというと、これはいたって単純明瞭であり「ニュースを分かりやすく解説する」ということである。確かに池上氏の解説を聞くと“なるほどそういうことなのか”と分かった気になることが多い。(とはいえ池上彰もニュースの本質は伏せている)
しかしこれは裏返してみれば、一般的に“ニュースは分かりにくい”ということを意味している。特に政治経済についての一般報道は非常に分かりにくいと思えるが、このことは重要な事象である。メディアが意図的に分かりにくく報道しているとも考えられるからだ。何故か?これは“権力がどのようにして権力を維持、拡大しているのか”、この仕組みを一般大衆に理解されると困るからではないだろうか。
少し話題を変える。世界では「単一の言語しか使えない人」を「日本人」と訳すらしい。例えば中国の片田舎の人達も、一般的な日本人を超える英語力を持っているという。確かに、かねてより日本の英語教育に対しては怪訝に思っていた。4年制の大学までを含めると、延べ10年にわたる英語の履修課程があるにも関わらず、大学卒業生の大多数が、ろくに英語が使えない。
何故か?教育の方法論の問題なのか?いや、ここにも作為が感じられる。権力にとっては、大衆としての日本人が英語に堪能になると、何かと不都合があるのではないだろうか。そうでなければ、日本人のこの貧困すぎる英語力はあまりにも不自然である。
多くの日本人は、ニュースがよく分からないし、英語がほとんど使えない。といってもそれで日々の生活に何ら困るわけではない。人々はそれぞれの日常をごくありきたりに繰り返している。しかし、このことがまさに、権力によって誘導され作り上げられた集団的無思考であると捉えることもできる。しかし仮にそうだとしても、人々は無思考ゆえに享受できる娯楽を楽しみ、ほどほどに幸福を与えられて満足している。“ならばそれでいいじゃないか”とも言える。実はこの“ならばそれでいいじゃないか”こそが、権力の狙う核心部なのではないだろうか。
60年~70年代、学生の少なからぬ関心事は政治であった。日米安保。とりわけマルクス主義がブームであった。今や見る影もない。当時の彼らは、仮にそれもまた誘導であったにせよ、ともかく考え何かと闘っていた。いま、権力が誘導する集団的無思考は、すでに完成しているのかも知れない。あたかも教祖に対する信者のように、国家に対する国民という構図を描くことができる。ある一人の青年はこういうだろう。
「国が俺たちに悪いことをするはずないんじゃないの?」「どっちでもいいけど」。
しかしこれは裏返してみれば、一般的に“ニュースは分かりにくい”ということを意味している。特に政治経済についての一般報道は非常に分かりにくいと思えるが、このことは重要な事象である。メディアが意図的に分かりにくく報道しているとも考えられるからだ。何故か?これは“権力がどのようにして権力を維持、拡大しているのか”、この仕組みを一般大衆に理解されると困るからではないだろうか。
少し話題を変える。世界では「単一の言語しか使えない人」を「日本人」と訳すらしい。例えば中国の片田舎の人達も、一般的な日本人を超える英語力を持っているという。確かに、かねてより日本の英語教育に対しては怪訝に思っていた。4年制の大学までを含めると、延べ10年にわたる英語の履修課程があるにも関わらず、大学卒業生の大多数が、ろくに英語が使えない。
何故か?教育の方法論の問題なのか?いや、ここにも作為が感じられる。権力にとっては、大衆としての日本人が英語に堪能になると、何かと不都合があるのではないだろうか。そうでなければ、日本人のこの貧困すぎる英語力はあまりにも不自然である。
多くの日本人は、ニュースがよく分からないし、英語がほとんど使えない。といってもそれで日々の生活に何ら困るわけではない。人々はそれぞれの日常をごくありきたりに繰り返している。しかし、このことがまさに、権力によって誘導され作り上げられた集団的無思考であると捉えることもできる。しかし仮にそうだとしても、人々は無思考ゆえに享受できる娯楽を楽しみ、ほどほどに幸福を与えられて満足している。“ならばそれでいいじゃないか”とも言える。実はこの“ならばそれでいいじゃないか”こそが、権力の狙う核心部なのではないだろうか。
60年~70年代、学生の少なからぬ関心事は政治であった。日米安保。とりわけマルクス主義がブームであった。今や見る影もない。当時の彼らは、仮にそれもまた誘導であったにせよ、ともかく考え何かと闘っていた。いま、権力が誘導する集団的無思考は、すでに完成しているのかも知れない。あたかも教祖に対する信者のように、国家に対する国民という構図を描くことができる。ある一人の青年はこういうだろう。
「国が俺たちに悪いことをするはずないんじゃないの?」「どっちでもいいけど」。