
はてさてまたしても珍妙な回路が出てきましたね。これがカレントミラー回路です。Q1のコレクタとベースを接続してるので等価回路は右の図のようになります。これで何がしたいのかと言うと、自由に値を設定できる定電流源が欲しいのです。具体的にはこの回路によって定電流IC2の値を自由に決めることができるのです。どうですか?そのように動作する様子が見えてきますか?
まずI1を求めます。電源電圧からD1の電圧降下を引いて合成抵抗で割ると、I1=(15-0.7)/(15k+100)=0.95mAとなります。D1のカソード電圧は0.95mA×100Ω=95mV、よってD1のアノード電圧= Q2のVB =0.795V。ということはQ2のVE=95mV。これでI2の電流が求まります。I1と同じ0.95mAですね。R1を10kΩにするとI1、I2はどうなるでしょう?計算ははぶきますが、I1、I2とも1.4mAとなります。ね、巧妙にできてるでしょ?R1でI1を自由に決めることができ、まるで鏡に映したようにI2が同じ電流値になることから、この回路をカレントミラー回路といいます。
実際のカレントミラー回路はダイオードを使わずにQ1のように接続します。これはQ1とQ2の特性を合わせてカレントミラー効果を厳密にするためです。ポイントはQ1、Q2のエミッタ抵抗を同じ値にすることですが、あえてI2をI1の2倍の定電流にしたい場合は、Q2のエミッタ抵抗をQ1のエミッタ抵抗の1/2にします。また下図のようにベースを多段に接続して複数の定電流回路を作ることもできます。このようにカレントミラー回路は非常に設計自由度の高い定電流回路なんですよぉ。
この多段回路の場合は、Q1、Q2、Q3が同じ電流値でQ2、Q3のコレクタ電流は定電流、Q4のコレクタ電流は2倍の定電流です。もうみなさん楽勝ですね。(^^)
関連記事;
定電流負荷 2010-03-04
定電流① 2010-01-08
まずI1を求めます。電源電圧からD1の電圧降下を引いて合成抵抗で割ると、I1=(15-0.7)/(15k+100)=0.95mAとなります。D1のカソード電圧は0.95mA×100Ω=95mV、よってD1のアノード電圧= Q2のVB =0.795V。ということはQ2のVE=95mV。これでI2の電流が求まります。I1と同じ0.95mAですね。R1を10kΩにするとI1、I2はどうなるでしょう?計算ははぶきますが、I1、I2とも1.4mAとなります。ね、巧妙にできてるでしょ?R1でI1を自由に決めることができ、まるで鏡に映したようにI2が同じ電流値になることから、この回路をカレントミラー回路といいます。
実際のカレントミラー回路はダイオードを使わずにQ1のように接続します。これはQ1とQ2の特性を合わせてカレントミラー効果を厳密にするためです。ポイントはQ1、Q2のエミッタ抵抗を同じ値にすることですが、あえてI2をI1の2倍の定電流にしたい場合は、Q2のエミッタ抵抗をQ1のエミッタ抵抗の1/2にします。また下図のようにベースを多段に接続して複数の定電流回路を作ることもできます。このようにカレントミラー回路は非常に設計自由度の高い定電流回路なんですよぉ。
この多段回路の場合は、Q1、Q2、Q3が同じ電流値でQ2、Q3のコレクタ電流は定電流、Q4のコレクタ電流は2倍の定電流です。もうみなさん楽勝ですね。(^^)
関連記事;
定電流負荷 2010-03-04
定電流① 2010-01-08
















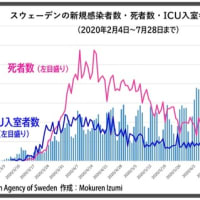








ところで,二倍の電流を得るためには・・・最後の図のQ2とQ3のコレクタを結線すれば二倍の電流になります。ディスクリートでは困難ですが,集積回路では,比精度がとりやすいので,同一抵抗値,同一トランジスタ(エミッタ面積)で設計する方が良いようですね。ディスクリートで作る場合は,熱結合が必要な感じがしますね。
いただいたコメントのレスは「よもやま掲示板」に書いておりますので、ご確認よろしくお願いいたします。
簡単なことですいません。
・エミッタ抵抗をR2:R3=1:2の定数にしたとき、
I1:I2=2:1になるかと思います。
→R2=100Ω、R3=200Ωならば、
I1=0.95mA、I2=0.475mA
・R2=100Ω、R3は短絡(または0Ω)にした場合は、
電流の関係はどうなりますか?
ベース電圧が共通なので、
I1=I2でよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。
コメントありがとうございます。
> I1:I2=2:1になるかと思います。
> R2=100Ω、R3=200Ωならば、
> I1=0.95mA、I2=0.475mA
その通りですね。素晴らしい。
さて、R2=100Ω、R3は短絡(または0Ω)にした場合ですが、
上の関係式にならいますと
R2=100Ω、R3=50Ωならば
I1:I2=1:2になり、
I1=0.95mA、I2=1.9mA となって、I2はI1の2倍になりますね。
ということは、R3が小さくなるほどI2が大きくなり
もしR3=0Ωなら、I2=∞A?になりそうです。
しかし実際には、このような極端な定数を与えた場合は
カレントミラー動作のメカニズムが崩れてしまい、
R1がQ2のベース抵抗として働き、Q2のhFE=100とすると、
I2はおおむね100mA程度になるのではないでしょうか。
また、何でもご遠慮なく質問等してくださいね。(^^)
上記のカレントミラー回路で、
2SK30Aを使用しても、上記の抵抗値で良いのでしょうか。
それと、グランドに近いと所から電気を取り出せばよいのでしょうか?
使用する電源は、
ニッケル水素電池で3V~18V
ICにもよるでしょうが、ヘッドホンやドルビー回路に使う、
電流はどれくらいでしょうか。
1ミリアンペア位で良いのでしょうか?
まず、上記の回路のトランジスタをそのまま2SK30Aに置き換えてもカレントミラー回路にはなりません。差動アンプなどはFETでもできるのですから、なんとなくできそうな気もしますけどね。
(^^)
その前に、”とらん”さんが何をしたいのか?なのですが、例えば定電流回路が欲しいのであれば、トランジスタでもFET(2SK30A)でも作れます。
とにかく何か回路を作ろうとされていて、その回路に使う電源は3V~8Vのニッケル水素電池ということですね。
それからすごいワードが出てきましたが、「ドルビー」ですか。懐かしい。これは有名なノイズリダクションですよね。もしやオーディオ関係の回路を作ろうとされているのでしょうか?
できましたら、どんなものを作ろうとされているのか、具体的にお知らせいただけないでしょうか。
~挨拶~
素人なので、玄人のお口に合う質問が出来るか
心配です。
これからの質問で、とまどいがあったしても、暖かく見守ってい頂けると、幸いです。
~私のアナログ紹介~
実は、アナログデッキの復活を夢見て、ルートの計算も出来ない私が、
半田をもって交流理論に近い改造をしようと夜な夜な作業をしています。
危ない基礎実験の繰り返しで、貴重なカセットデッキを5台ほどつぶしました。
メーカーから無理矢理、回路図と実装図をもらい。バイアスやカセット再生アンプの各回路の電源のプラス・マイナスの場所も突き止めました。
マイナスB電源を知ったのは、ここ1ヶ月の話です・・・・。
今までの、危ない実験の結果分かったこと。
【実験結果1】
各回路は、すべて独立電源で動かすと、ノーマルテープがメタルテープに匹敵するぐらい躍動的でした。(それも、引き回し配線でも)
【実験結果2】
各回路の接続配線は、それぞれの容量に応じた線量で良いこと。すべて太配線が良いとは限らないこと。
【実験結果3】
電源は、基本的に電池駆動であること。
ノイズが出にくく、電圧効果もゆるいので、アンペア調整で回路を焼かないように注意する。
【実験結果4】
電池の電圧は、1.5Vではなく1.2Vであること。
【実験結果5】
各回路の決められた電圧は、供給電源が安定していれば、多少の多くても・少なくても普通にうごく事。
これによって、機材の潜在能力が引き出せます。
しかし、使い勝手がもスゴ~~く悪くなります。
それでも、お釣りがきます。
これが、私の紹介と今の状況です。
ニッケル水素電池から、ICを壊さずに安定した電流を供給したいと考えています。
それでは、返事をお待ちしています。
取り組まれておられることを紹介くださってありがとうございました。
やはりオーディオ関係だったんですね。
なかなかの強者とお見受けしました。(^^)
実は私もオーディオ好きが高じてこの道に入った一人です。
さて、大変申し訳ないのですが、今日は野暮用で帰りが遅くなってしまいました。
お話しくださった内容についてのお返事は追って早々にさせていただきますので、
しばらくお待ちください。
カセットテープに思い入れがあると思い、
私の作業経過を見てもらいました。
ニッケル水素電池の大電流放出を押さえる方法を
よろしくお願いします。
JFETは、ただの制作例で、
ノイズの少ない物であれば大歓迎です。
三極レギュレータで、可変抵抗を使えば、
簡単に変圧・変流が出来ますが、
三極レギュレータをアンプにつなぐと、頭が痛くなります。
よって、三極レギュレータの仕様はやめました。
高校の時、まじめに数学を習っておけばよかったと、
今頃後悔ををしています。
アナログの理論は、納得できるのですが、
実際やるのは別問題で、もう手間がかかって
いやになります。
トロンさん、今までは配線は『より線』がよいと
されてきましが、ある説では『より線』より空間のあいた平行線が良いとのうわさ。
もう、どうやって配線を作って良いやら、
途方にくれる次第です。
それでは、発熱が少なくノイズの少ない方法を
ご紹介ください。
気長に待っていますので、よろしくお願いします。