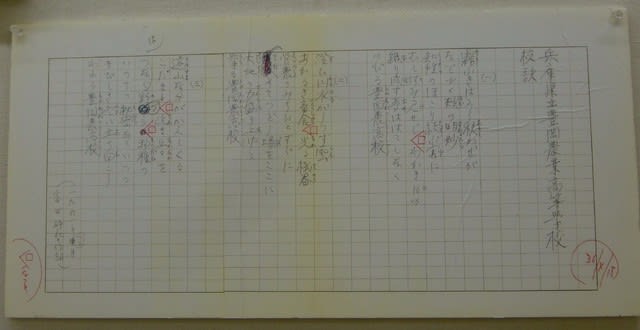「砕花をめぐる文豪と文化人」展を見に芦屋市民センターへ行ってきました。

久しぶりです。


この景色も懐かしい。
もう何年になるかなあ?宮崎翁の言葉に関する教室にしばらく通ったのは。あの頃は翁もまだまだお元気だった。
そして、杉山平一先生の講演もここで聞いたのだった。
その講演が終わって、先生からグリルに誘われてコーヒーをご馳走になりながらお話をお聞きしたのだった。
その内容は忘れたが、思えばぜいたくな時間だった。
今回の企画展示は3階の会場。




そして、わたしが提供している、砕花さん愛用の帽子。

これ、アイルランド製の高級品なのです。アイルランドはイエーツなど有名詩人を輩出しており、砕花翁もご研究だったと。
展示の説明の中に「宮崎修二郎」とありますが、

これは「宮崎修二朗」が正しいです。
この展示物にわたし、見覚えがありました。
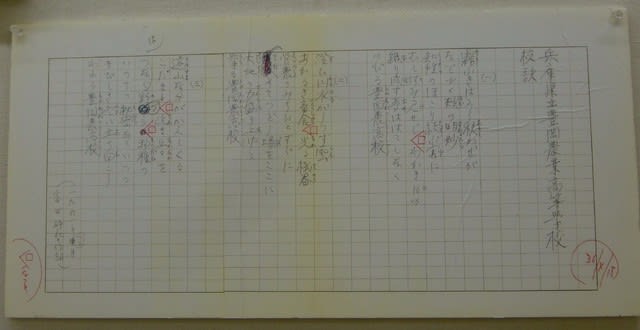
「兵庫県立豊岡農業高等学校校歌」の原稿です。
家に帰ってきて調べてみました。
わたしが宮崎翁から頂いている直筆原稿です。

見比べてみて一瞬、「おんなじや!」と思ったのですが、微妙に違います。
同じのを二枚書かれたということ?
どうやら、わたしが持っているものの方が先に書かれていて、それを清書したのが展示のものということなのでしょう。
清書といっても推敲の痕までが同じ。あ、そうか、2枚同じのを書いてから、訂正があったということなのでしょうね。
だから双方の同じところが同じように訂正されている。それでわたしが、どちらかがコピー?と思ったのでした。
でも、そのころは多分カラーコピーなんて簡単にはできなかったでしょう。しかし見事に同じ字で書かれている。
砕花翁、集中力が並ではないですね。
あ、もしかしたら、この2枚ともが砕花翁の手元に残されていたのかも。きっとそうだ。
そして、ちゃんとしたものを1枚書かれて、それはこの兵庫県立豊岡農業高等学校に渡されたのだろう。
10月1日には、センターの隣のルナホールで「富田砕花と谷崎潤一郎」と題した催しがあります。
谷川俊太郎さんがお見えになって講演なさいます。
同時にたかとう匡子さんもお話をなさいます。
その資料にわたしちょっとご協力させていただいています。

わたし、招待券を戴いていましたが、孫の運動会にも招かれていて、孫の方を優先したいと思います。
ちょっと残念。
この会場のすぐ近くの国道2号線に「業平橋交差点」というのがあるのですが、

ここでkohが幼児のころ迷子になりかけた(いや、なっていた)のでした。
芦屋の桜まつりで大変な人ごみの中でした。
奇跡的といってもいいような形でわたしが見つけたのでした。
今思い出してもぞっとする。
よく事故に遭わなかったものだ。
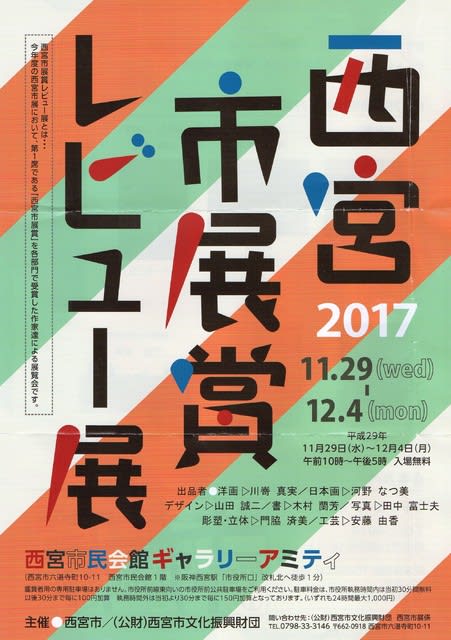

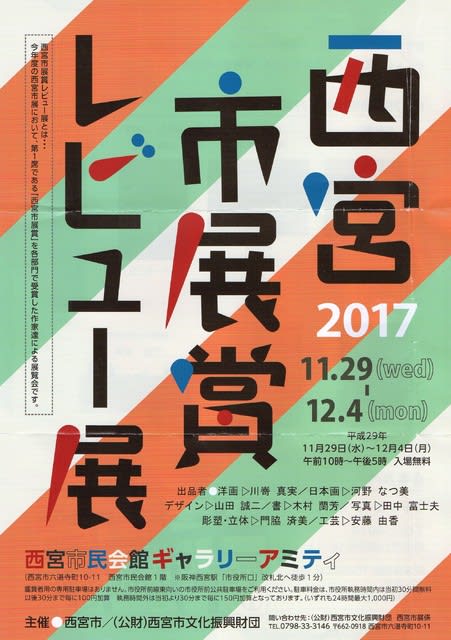













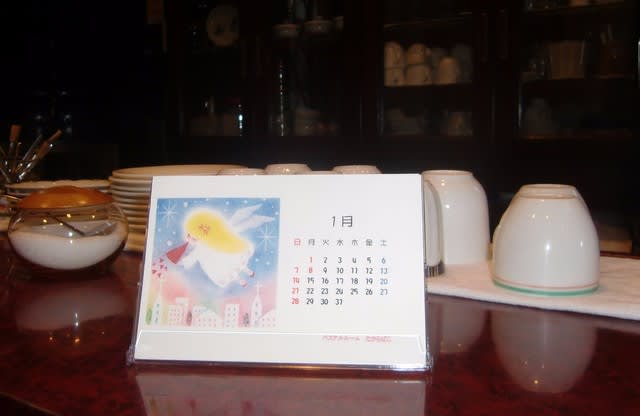





 「KOBECCO」に浮世絵のページを持っておられる、N右瑛さんの「シエリト・リンド」
「KOBECCO」に浮世絵のページを持っておられる、N右瑛さんの「シエリト・リンド」
 K林欣子さん「糸あやつり」
K林欣子さん「糸あやつり」 O倉恒子さん、「神戸の街角」
O倉恒子さん、「神戸の街角」 Y口恵子さんの「路地」です。なぜか気になりました。絵の奥へ行ってみたいような。
Y口恵子さんの「路地」です。なぜか気になりました。絵の奥へ行ってみたいような。




 わたしはこれの右下の写真に興味がわきました。
わたしはこれの右下の写真に興味がわきました。









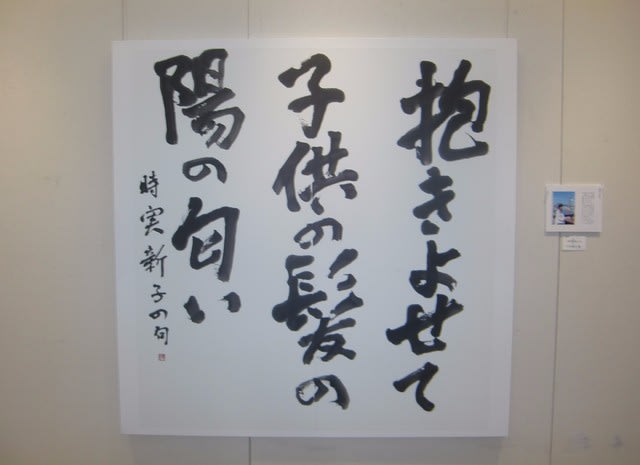







 この景色も懐かしい。
この景色も懐かしい。