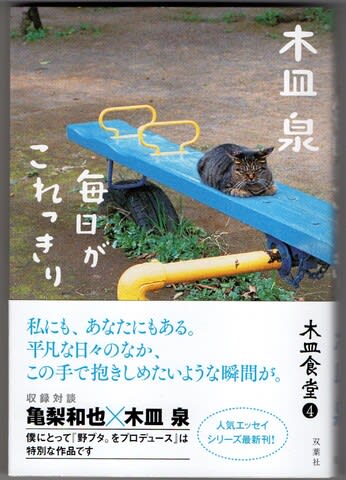中野友廣さんから頂いた「児童話集」、『春風くんと学長先生』。

文庫本版のかわいい本。「児童話集」とあります。
「児童話集」という言葉は、わたし初めて出会います。
中野さんの造語?あるいは私の勉強不足?
読ませていただいたが、これは児童文学ですね。
中野さんは川柳人なので、この本は意外だった。
以下、わたしの感想文です。
まず表紙イラストの学長先生の像が中野さんによく似ておられて、それだけで親近感が湧き、読むのが楽しみになります。
六篇の物語があります。
どれにも親がいないとか、別れが底流にありますが、なぜか暗くないのです。
ほのぼのとして、明るい。これは作者の人柄によるものでしょう。
児童文学ではありますが、人の心の深いところが描かれています。
というのも、作者の中野氏は川柳人でもあって、そのことは無視できないでしょう。
しかも中野氏は、人の心を鋭く描いた時実新子さんのお弟子さん。
人の心の奥底を、軽く表現するのが川柳の一面でありましょうから。
児童文学は、まずは易しい言葉でなければならないでしょう。
まさに中野氏はそれに向いていると言わざるを得ません。
さらに、川柳の人ならばこその、大人の読者にも満足を与える作品となっています。
わたしは大いに楽しませていただきました。
どの作品でも、次はどうなって行くのだろう?と先を読むのを急がされました。
これは子どもが読めばもっとそう思うのかもしれません。
第一話 「春風くんと学長先生」 子どもたちが親しくなった学長先生が急に死んでしまうのですが、なぜか悲壮感がありません。
話の設定によるものか、文体によるものかはわからないのですけれども、ほのぼのとしています。
作者のお人柄としか思えません。
話の先がどうなって行くのかは大体わかるのですが、それを不満に思えず、安心して楽しめるのです。
学長先生は死んでしまったのに、ハッピーエンドのような感じ。
読後感が良かったです。
第二話 「トン君の通知簿」 これはわたしの好きな作品でした。悲しい話ですけど、やっぱり暖かなものが心に残ります。
第三話 「ヤッチンの始球式」 これは面白かったです。お父さんが事故死したりするのだけれど明るいのです。
最後の長嶋(一茂)選手が始球式のボールをホームランしてしまうところ、愉快です。ネタバレ、ごめんなさい。
これ、ほんとにあったことなんでしょうかねえ?そんなことないですよねえ。著者の創作でしょう。
どちらにしても男の子が喜ぶようなワクワクする話でした。
第四話 「市電レストラン」 これは懐かしさを覚えます。
わたしが住む西宮には市電はありませんでしたが、阪神国道と甲子園線を路面電車が走っていました。
特に阪神国道の路面電車は「国道電車」と呼んでいましたが、わたしにもいろんな思い出があります。
第五話 「父ちゃんのお見合い」 父親の再婚を扱ったものですが、わたしも中学生の時に似た経験をしています。
しかし、この話のように明るく楽しいものではありませんでした。うらやましいかぎりです。
親の再婚話をこんな風に書けたらいいですね。
第六話 「ふとっちょ一家と綱引き大会」 これもなんとも楽しい話です。読者が望むような展開になって行くので安心して読めます。
「良かった良かった」と。児童文学はこんなのがいいですねえ。
簡単に書いてしまいましたが、要所要所に川柳人ならではの繊細な目線もあって感心しました。
因みに、この本の発行は1998年です。もう20年以上も前。
中野さん、もうこんなのは書いておられないのでしょうか?
もっともっと書いてほしい気がしますが。
『コーヒーカップの耳』