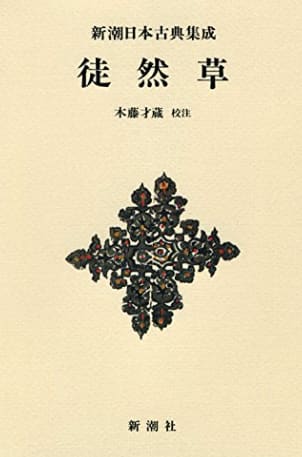
前号で芭蕉がなかなかの源氏読みであったらしいと述べたが、兼好法師も負けてはいないようだ。
たとえば『徒然草』73段に「鼻のほどおごめきて言ふは」とあり、「新潮日本古典集成」の頭注は、これを「鼻のわたりおごめきて語りなす」との「帚木」の一節に送り返している。
「おごめく」を辞書で引くと、用例に『徒然』のこの一節が採られていることがおおいようだ。
この例をみただけではたんなる偶然の類似ではないかともおもえるのだが、たとえば同104節の「荒れたる宿の、一目なきに」という箇所に似た「一目なく荒れたる宿は」なる一節が「花散里」にあると指摘されたりすると、やはり兼好法師の脳裡に『源氏』の記憶がかすめていたのだとかんがえたくなる。
ほかにも「若紫上」の「御垣が原の露分け出て」を踏まえた「御垣が原を分け入りて」というのがあったり、235段の「狐・ふくろふやうの物も、人げに塞かれねば、所得がほに入りすみ……」云々の描写に酷似したくだりが「蓬生」にあるとなると、もはや兼好が源氏を読み込んでいたことに確信をもたずにはいられなくなる。
そもそもタイトルになっている「つれづれ」が源氏オマージュであることをうかがわせるくだりさえある。
17段の「仏に仕うまつることこそ、つれづれもなく」が「賢木」の一節を下敷きにしているらしいふしがあるのだ。
ちなみに『徒然草』でよく参照されている書物に『白氏文集』(やはりよく引かれている『朗詠集』経由かもしれない)があることも『源氏』との親近性を感じさせる。
『徒然草』は鎌倉時代最末期の作品である。
そしてその百年後にこの作品をいわば「発見」したのが正徹である(その歌論『正徹物語』は文庫で読める)。
正徹は最後の勅撰和歌集が編まれた頃の歌壇を先導していた。
応仁の乱前夜のことである。
戦国時代への突入によって宮廷文化は崩壊し、それとともに和歌の伝統は永きにわたって途絶えることになる。
最後の勅撰和歌集『新続古今和歌集』に正徹の歌が一首も掲載されなかったことに丸谷才一は和歌がすでにして死に体であったことを見てとっている。
正徹はいわば“最後の歌詠み”である。
時代はすでに連歌のものになりつつあった。
正徹が二条良基の天敵であったことはぐうぜんではない。
連歌は同時代に生まれた能とともに権力と結びついて花開いた。
ちなみに正徹は世阿弥の女婿であった金春禅竹の歌の師匠である。
定家の衣鉢を継ぐ正徹の幽玄趣味は「芭蕉」(そしてその名も)「定家」といった禅竹の能作品において継承されたとみることもできる。
しかしそもそも『古今和歌集』以後、王朝文化の弱体化によって和歌はすでに勢いを失っていたが、他ジャンルの作品である『源氏物語』をとおして生きながらえていた(フランスで17世紀に死に絶えた[叙情]詩が演劇をとおして命脈を保っていたのに似る?)。『新古今』の編者である定家はそれゆえ『源氏』を特権視したのだ。
正徹と世阿弥の時代にあって和歌はエスプリを旨とする連歌によっていわば世俗化される。その後、権力に取り込まれ高級芸術化した連歌に反旗を翻したのが芭蕉ら俳諧師である……。文学史はそのように教えている。
ところで連歌に「寄合」集なるアンチョコがあることはご存じだろう。
発句に振られたモチーフに呼応するような語彙を集めたいっしゅのシソーラスである。
そのなかに源氏に特化した「源氏寄合」というのもあって、たとえば「桐壺」と引くと「まうけの君」「かゝやく日のみや」「うちゑみて」「おくり物」「おたき」「きぬ一くだり」「こま人」……といった付句に使えそうな語彙が列挙されている。
リストを眺めていると、たとえば「薄雲」に呼応する「春秋のあらそひ」なるタームがあるが、これはすでに『徒然草』にも使われている(「新潮」の頭注は「野分」に送付している)。
寄合はのちの俳諧師や謡曲作家によっても重宝されていたらしい。
「新潮日本古典集成」の「謡曲集」の頭注には代表的な寄合『連珠合璧集』の引用(「橋トアラバ柱」といったような)が大々的になされているが、なるほどと思わせられることがおおい。
ちなみに世阿弥は源氏を読んでいた形跡がなく、「源氏大綱」といったレジュメ本および寄合をもっぱら参照していたらしい。
源氏に昏い者(筆者はその一人)にはピンと来ない語彙がおおいが、その裏に多くの暗示をふくむ凝縮された語彙たちとしてサンプリングのヒントになることはうけあいだろう。












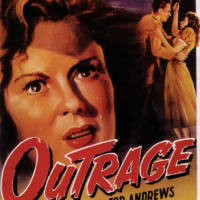




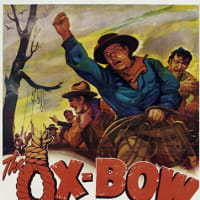

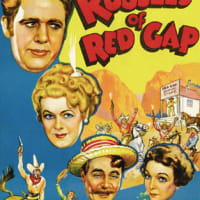
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます