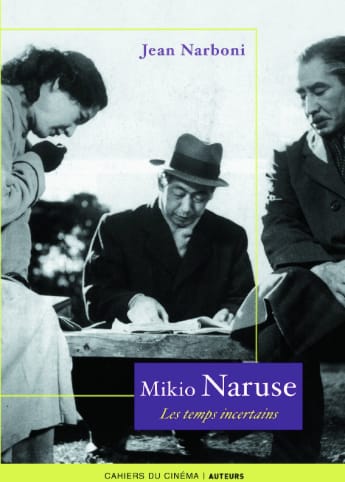デヴィッド・リンチ「ツイン・ピークス The Return」(2016年)
オリジナルシリーズから四半世紀の月日が経ち、功成り名遂げたセレブなアーティストとなったリンチにはやりたい放題が許されるようになった。
難解さはもはや野心の高さというよりは安心できるブランドイメージをしかいみしない。
光量を落としたテレビらしからぬライティングの多用が目を引くが(本作はなによりもまずフィルム・ノワールであることをおもいだそう)、ブラウン管時代ならさておき、解像度がすばらしく上がっているきょうびの受像機をかんがえれば前衛的でもなんでもない。
ぐっとハイブラウでアーティーになったぶん、オリジナルシリーズを彩っていたソープオペラ的な要素は薄まっている。
このスタイルをストイックにワンシーズン貫いたのは天晴れだが、“映像作家”としての文体をつきつめて純化させる見返りとして、『The Return』は連続ドラマとしての豊かさの同義語であるいわば“雑味”をうかつにも洗い落としてしまった。
俺にとってオリジナルシリーズはこれまでにもっとも入れあげた“海外ドラマ”でありつづけている。
ただし俺にとっての「ツイン・ピークス」は、ファーストシーズンの幕切れ、すなわちもっとも感動的なキャラであったリーランド・パーマーの死とともに終わってしまった。
“リーランド・ロス”に陥った俺は、クーパーと狂気の上官との対決にヘザー・グレアムとの安っぽいラブストーリーが絡むかなんかのセカンド・シーズンには最後までノレないままだった。
『The Return』にはオリジナルシリーズ(もはや通して見直す気力はない)の懐かしい面々が顔を揃える。
マイケル・オントキーンとララ・フリン=ボイルの不在は寂しいかぎりだが、クーパーもアンディもルーシーも“ローラ・パーマー”さえも、その面影は意外なほどに昔のままだ。ホークの精悍さには渋みのある貫禄が加わった。
ミゲル・ファラーの頭髪の薄さは従弟のジョージがまだ無名だったあの当時そのままだが、その人格はかなり丸くなり、かつてのむちゃくちゃな毒舌は影を潜めている(御大演じる上官ゴードン・コールのお守役がすっかり板についてしまった)。
ウェンディー・ロビーとエヴェレット・マックギルの変態夫婦ぶりはオリジナルシリーズの最大の見所のひとつであったと記憶するが、出番もすくなくなり、ずいぶんとアクが抜けてしまった。
丸太オバサンはつねに同一のアングル、同一の暗い照明によるショットでしか登場しないが、前作と同じ女優が演じているはずだ。
メッチェン・エイミックは年相応に贅肉がついてキツネ目の度合いが増した(たいして娘役のアマンダ・ゼイフライドは日野日出志の漫画の登場人物みたいな目玉の持ち主だ)。
ペギー・リプトンはオリジナルシリーズにおいてその瞳にたたえていた神秘的な深みさえ消えたようにみえるが、どうみても七十路とはおもえぬほどの若々しさを保ち、てっきり別の似た女優にバトンタッチしたものと思い込んで勝手に落胆してしまっていたほどだ(いまでも一抹の疑いが消えない)。
そのリプトンがすこし気をもたせたあとで長年思い合ってきたエヴェレット・マックギルに求婚し接吻をあたえる場面は新シリーズ中でもっとも幸福感にあふれた一幕であり、涙なくしては見られない(「俺はあまりにも長いあいだお前を愛してきた……」と歌うオーティス・レディングをバックに、薄雲が刷毛を引く爽やかな青空のショットがその余韻をしばし引き継ぐ)。
オリジナルシリーズきってのファム・ファタールにしてディーヴァというべきシェリリン・フェンにいたっては酷いまでにオバサンと化してしまった(かのじょはどこかにすてきなほくろがなかったか知らん)。
てっきりもう聞けないものと思っていたかのじょオードリーのテーマ曲がシリーズ終盤、第16話の幕切れに至ってニューアレンジで突然奏されるところは新シリーズ中でもっとも驚きにみちた瞬間だ。
ローラに捧げたシンプルな曲をステージで再演するジェームズの高音の歌声も心にしみる……。(以上の条りには歳月の経過ゆえのとんだ記憶ちがいがまじっている可能性大いにあり。)
青春時代は去った。『The Return』はもじどおりかれら“帰還者=幽霊”たちのものがたりである。舞台はいまや俗界を離れてスピリチュアルな空間(くだんの Red Room?)へと移動し、世俗のしがらみから解き放たれた物語はフィルム・ノワールにやつした聖杯探求(“Lancelot Court”)の旅路を一直線に突き進む……。
新シリーズのコンセプトをさしずめそんなふうに要約できようか?
宜しい。しかしハリー・ディーン・スタントンがもちまえの存在感にどんなにものをいわせ、ナオミ・ワッツや裕木奈江がどんなに熱演してみせたところで、オリジナルシリーズに匹敵するような魅力的な新キャラをただの一人もクリエイトできなかったという厳然たる事実は否定できない。
俺的には、たとえば周囲の誰からも“寒がられる”検死官の見せ場をもっとつくってほしかった。
それいじょうに、もうちょっと若い世代に花をもたせてやってもいいのではないか?
なんでもありの予定調和的なリンチワールドと死臭ただよう過去への郷愁が『The Return』のいっさいである。
郷愁そのものがいわばシリーズの中心的なテーマであり(ローラ・パーマーが象徴するものにたいしてひとつのコミュニティぜんたいが無意識のレベルで抱くことになるそれだ)、シリーズがリンチにとっての「失われた時」であることはさておいて。
やはりあの「ツイン・ピークス」は帰ってこなかった。全18話をさいごまでみるにはよほどの忍耐力が要る。ただし「スターウォーズ」に飽き足らない子供の視聴者は目を輝かせて食いつくことだろう。リンチもさいしょからそれを見込んでいたのではないか?