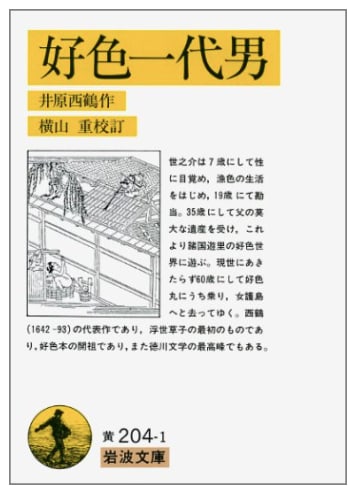
露伴文学は西鶴の発見にはじまり、芭蕉への沈潜によって終わる。
いうまでもなく西鶴と芭蕉とはまったく同じ時代を生きたひとである(かれらはラシーヌやモリエールの同時代人でもある)。
西鶴も芭蕉も俳諧師であり、いずれもいわばその言語の不純性において際立っている。
いずれも雅俗混淆をよしとしたが、西鶴においては俗がまさり、芭蕉においては雅がまさる(その到達点である『炭俵』においてはそのかぎりではないとしても)。
明治文学とはすぐれて言語的な分裂にくるしんだ文学である。
そしてその分裂が強いる奇形性にこそ明治文学の美がある。
明治文学の日本語は純粋でありえなかった。明治の作家たちはあるいみで外国語を話していた(書いていた)。
日本語という言語がもともとそのような分裂の所産であるという事実はとりあえず措くとして。
文学史の教えるところによれば、地方出身の作家らが推進した言文一致にくみしえなかった江戸育ちの露伴、紅葉、一葉は淡島寒月におしえられた西鶴の雅俗混淆体を選んだ。
西鶴にあっては描写と会話が一体化し、同じリズムによって流れて行く。
主語や接続語を大胆に省略する結果として、人称と格とがかぎりなく曖昧化する。
谷崎潤一郎によれば、この曖昧さが普遍性へと反転するのが日本語の特色である。いわく「或る特定な物事に関して云われた言葉がそのまま格言や諺のような廣さと重みと深みを持つ」(『文章讀本』)。ちなみに谷崎によればこの点にかけて里見弴は名手である。
西鶴においてはまた、掛詞などによる奔放なアナロジーによって意味の位相がずれていき、ひとつの文が完結しないままストレッタみたいに別の文へと横ずれしていく。
大古典から俗謡にいたるまで清濁あわせのむ奔放な引用とパロディによってじぶんのことばと他人のことばとが渾然一体となるポリフォニー。
さながら日本のジョイスである。ジョイスほどポリグロットではないにしても。
のちに『運命』などの露伴が日本語に生硬な漢語を強引にぶちこんだのはやはりこうしたポリフォニー性への意志からではないか?
ひょっとしてそれはローマの詩人たちがラテン語のシンタックスを破壊してまでもホメロス的なヘクサメトロンを採用したのにも似た身振りではなかったか?
閑話休題。
谷崎によれば、「西鶴の文章は、僅か五六行を読んでも容易に西鶴の筆であることが鑑定出来るくらい、特色が濃い」。
その「文法の桁を外れている」さまは「一歩を誤れば非常な悪文となりかねない。しかもその一歩の差と云うものが到底口では説明できない」。
西鶴のフレージングはフリージャズ的である。その崩れ方、難解さも含めてこの作品の魅力である。
晦渋なくだりと明解なくだりがかわるがわるでてきて、鵺のごとくに一瞬一瞬その表情を変える。
とぎれなく紡がれるそのフレージングはどこまでもフリーキーだ。
近松のように綺麗に流れていくことがない。書き言葉、読まれるべき言語であることに西鶴の本領は宿る。
うまく言えないが、耳で聞くときの流麗さと目で辿るときの停滞感とのギャップのごときものがあるのだろうか。
口ずさみたくなるフレーズはいくらでも抜き出せる。たとえば、
「桜も散るに嘆き、月はかぎりありて入佐山」
「年はふりても恋しらずの男松」
「『新枕』とよみし伏見の里へ」
「唐紙の竜田川も紅葉ちりぢりにやぶれて」
「口びるそつて中高なる顔にて」
「同じ心の水のみなかみ」
「『これはならずの森の柿の木、口へはひるものこそ』と、薬罐たぎれば」
「谷中の東七面の明神の辺、心もすむべき武蔵野の、月より外に友もなき呉竹の奥ふかく、すひかずら・昼顔の花踏みそめて道を付け」
「ある時ははだか相撲、すずしの腰絹をさせて、しろきはだへ黒き所までも見すかして」
「同じ穴の狐川、身は様々に化かすぞかし」
「浦風のかよひて汐ふくみし脚布も、折節は興あり」
「床近く立ちながら帯とき捨て、着物もかしこへうち捨て、はだかでぐすぐすとはひりさまに、『これもいらぬ物』と脚布ときて、そのまましがみつきて、いな所を捜つて、ひた物身もだえするこそ」
「松嶋や雄嶋の人にもぬれて見むと、身は沖の石、かわく間もなき下の帯」
「三井の古寺、つかひ捨てるかねはあれど隙なくて」
「暮れの松風あげ麩の音」
「『おもしろの春辺やな』。天晴くぜつのもとだて」
「命にはかまひのなきやうに作蔵を切られます御契約」
「いつまで色道の中有に迷ひ、火宅のうちのやけとまる事をしらず」
ここではよみどころのひとつである服装描写を引いていない。
三島由紀夫によれば「明治までの小説には女性の服装美に関する小説家の見識が、いつも示されなければなりませんでした」。
「一時代の趣味のなかで、よい趣味と考えられるもの、悪い趣味と考えられるもの、帯の好み、帯〆の好み一つでも、よい趣味と悪い趣味とが截然と分かれていた時代には、作中人物の良し悪し、服飾に関するその人の性格的特色なども、服飾描写によって容易に表現することができました」。
現代のように趣味が「雑多」になり、良い趣味と悪い趣味が混同されている時代には、小説における服装描写は無意味に近くなっていると三島はつづける。
蓋し至言。このいみで西鶴はプルーストをも先駆けている。
島村抱月いらい、西鶴の「自然主義」が云々されてきた。
志賀直哉はその容赦ない説明の省略に西鶴のリアリズムをみた。
あるいはこれを「俳諧的」な視点に帰すことも可能であろう。
「『一代男』には[ママ]些細なもの、何でもないものに趣を見出して、それらを巧みに使っている」(森銑三)。
森はたのしげにそれを列挙してみせる。
幼い世之介が拵えて侍女たちにあたえた折り鶴。人をたのまずに、みずからするふどし。同じく世之介が踏み割った従姉の糸巻き。行水をみられた女が小箱からとりだして、世之介をたらそうとする芥子人形、起き上がり、雲雀笛。赤頭巾を着せられた梟、時雨に濡れて流れようとする奴の作り髭。浪人源八の柴の網戸に作りなした朝顔。八坂の色茶屋で出した色附けの薑……。
ここにはすでに印象派的なまなざしがある。そこからシネマトグラフの誕生まではあとほんの一歩である。
現に森はつづけて西鶴の色彩感覚の鋭敏さを指摘している。
散り散りに破れたから神の竜田川の模様、出世した世之介の珊瑚珠の数珠、寺泊の女郎たちの赤い鼻緒の雪駄、酒田の売女らのどぎつく塗られた口紅……と、森の列挙はとどまるところをしらない。
同じ世紀、ヨーロッパでやはりフェルメールとライプニッツがはるかのちの映画の誕生を予見していたことを忘れるべきではないだろう。
さて、森によれば「主人公のある長篇俳文」といった趣の「いっしゅ変態の長篇写生文」である『一代男』(森はこれ一作のみを西鶴の真筆ないし単著としている)はジャンルを確定不可能な作品である。
そして漱石の『猫』こそ、その衣鉢を継いだ「特殊文学」である。ひとはその独創性に気づくことなく、小説としての体をなしていないという理由で『一代男』をも『猫』ををもおとしめてきたのである。









