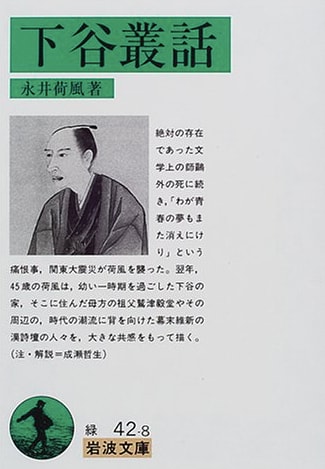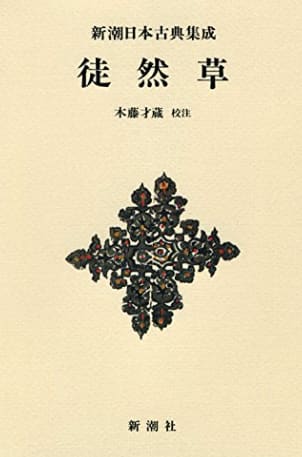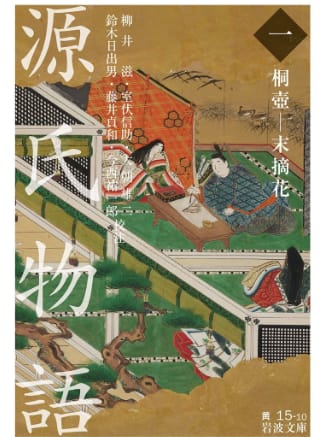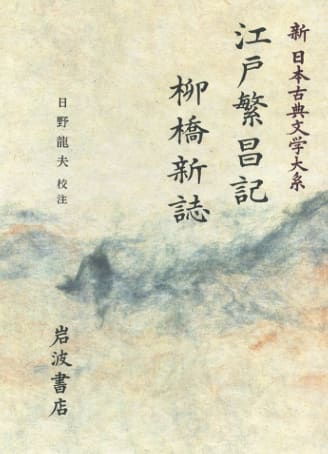
江戸時代、知識階級の子弟は父親などに漢文素読の手ほどきを受けていた。
漢文とは訓読すべきものではなく、原文をそのまままるごと理解すべきものとされた。
もちろん子供は漢文法を知らないが、“眼光おのずから紙背に徹す”で、訓練によって自然に理解できるようになったらしい。
それはなにやら秘教的な術であったようだ。
鷗外や漱石も苦労してその秘術を身につけたのであり、かれらの文学のバックボーンにはこのような秘術の効能がかいまみえる。
高島俊男によれば、読み下し文は、支那文をまるごと暗記するためのツールにすぎない。それゆえ漢文訓読体それじたいはひとつの完結した言語(というか文体)たり得ない。
あくまで原文とセットでしか存在しえない補助的な記号の体系にすぎないのだ。
もちろん訓読じたいは平安時代にはすでにあった。初期の訓読にはいろんな流派があったらしい。
現在でも訓読の仕方は一様ではない。訓読はいっしゅの翻訳だから、訓読のしかたにはその人なりの好みとか癖が反映される。
江戸時代に佐藤一斎が考案した訓読法は、極端に音読を尊重したもので、そのままでは日本語として意味をなさなかったほどであるという。
たとえば「人不知而不慍」をいまふうに「人知らずして慍(イキドオ)らず」とせず、「慍(オン)せず」と読み下すがごとし。(サイト「日本漢文の世界」による)
訓読は原文まる暗記のためのツールとして割り切っていたということなのだろう。
高島俊男はこれを以って訓読を日本語と認めない。
遣唐使の廃止以来、中国語を学ぶ手立てがなくなっていたので、しかたなく訓読にたよっていたのだというわけだ。
高島によれば、いまは中国語を習う手段はいくらでもあるのだから、漢文を読みたければ支那語を習えばいいという。
しかるに日本語はやまとことばで書くのがいちばん効率的であるという。
高島によれば、江戸時代のインテリがこぞって読んだ頼山陽の漢文はたんに下手くそであり、中国人には読めないデタラメな支那文である。
頼山陽はもっぱら日本人の読者を想定して書いていたのだから、はじめから日本語で書けばよかったのだと高島は言う。
当時のむだに漢文をありがたがる風土を高島は愚劣であるとする。
もっとも、頼山陽が『日本外史』を漢文で書いたのにはそれなりの必然性があったという説もあるようだ。
『漢文の素養』という新書本によると、なぜ日本だけに武家支配が生まれたのかというテーマを論ずるには漢文がうってつけであったという。
これだけではよくわからないが、漢文でしか論じられないことがらがたしかにあるのだろう。
本居宣長が言うように、漢文とはすぐれてもののことわりを説くためのことばである。ぎゃくにいえば、漢文を使うと、いやでもものごとを善悪で割り切ってしまうということになる。
未読だが、高橋睦郎の『漢詩百首』は、漢詩本にはめずらしく、原詩を掲げずに読み下し文だけを紹介している。
「日本語を豊かに」という副題から想像されるように、高橋睦郎は漢文読み下し文をひとつの日本語の詩の文体として積極的に位置づけようとしているらしい。
これまた未読だが、この詩人には古代ギリシャ・ラテン文学論もあり、こちらも「和音羅読」というタイトルが告げているように、翻訳文を外国の詩を味わうためのたんなる副次的なツールとみなさず、翻訳文そのものに詩情をよみとろうとしているものと推測される。その逆転の発想はいかにも詩人のものである。
読み下し文のとらえ方においてあるいみで高島俊男の対極にあるかんがえだ。
『漢文スタイル』の斎藤希史は『漢詩百首』を高く評価しつつも、原詩を掲げない本書の方針に根本的な疑問を呈している(「訓読の自由」)。
斎藤によれば、読み下しという行為は、読む主体を漢文(視覚)と日本語(聴覚)に分裂させる。そして漢文の創造性はこの分裂にこそある。この分裂こそが読みの多様性(自由)を許容するのだ。
訓読を退けることも、原文を無視することも、いずれも漢文を読むという行為のこの根本的な契機をスルーしている。
斎藤は言語をすぐれて分裂した、不純なものとしてとらえている。
あるいはあらゆる言語における翻訳という契機を重視しようとしているといってもいいかもしれない。
おもえば中国人が母国語の平仄を発見したのは五世紀に鳩摩羅什らによって仏典が漢訳されたことを契機としていたのだし、あるいは現代ドイツ語はルターによる聖書の独訳によって誕生したとも言われている。
言語的純血主義者の高島俊男を顔色なからしめる明察である。
閑話休題。
江戸の若者らの血を滾らせたのが『日本外史』であるとするなら、明治の文学青年の必読書とされていたのが万延元年に出た『柳橋新誌』である。
『日本外史』どうよう、『柳橋新誌』は漢文で書かれている。岩波文庫版は読み下し文になっているが、もともとは漢文で右側に正訓、左側に戯訓が添えられていた。
たのしいのはこの戯訓だ。「正妓」に「ホンモノ」、「軽浮」に「ウハキ」、「破瓜」に「ヤリクリ」、「軟軟痿痿」に「グニヤグニヤ」、「彼の兒驕れり」に「アノコツラガタカイ」といったように自在。
岩波文庫の解説によると、『柳橋新誌』の文体は(これが範をとる『江戸繁盛記』に倣って)「鬼面人を威す類の固苦しい漢字に配するに、凡そそれとはかけ離れた下俗な口語を以ってした所」にその妙味がある。
それゆえ『柳橋新誌』にはすくなくとも『日本外史』どうよう漢文で書かれねばならなかった必然性があるわけだ。
『柳橋新誌』は著者二十三歳のときに書かれた「初編」とその十数年後、江戸幕府が滅びてから書かれた「第二編」とからなる。(「第三編」も書かれたが、出版を許されなかった。)
江戸幕府消滅を挟んでの花街の変貌ぶり、 before とafter の対比のアイロニーに本書のモダニズム(浪漫主義と言い換えてもよい)があり、文学的な価値があるとされる(それゆえ岩波文庫の解説者は「第二編」のほうに作者の本領をみる。)
大田南畝どうよう、成島柳北は幕臣であった。
柳北フリークの筆頭である荷風は柳北を「戯作者」と貶める白鳥正宗(「下谷叢話」をこきおろした)に痛烈に反論する。
「柳北成嶋弘は戯作者にあらず。旧幕府の時には奥儒者にして徳川氏歴代の実紀を編集補修せし人なり。維新の後には朝野新聞の記者なりき。足下大日本人名辞書奈の部を見ば直に其誤を知る可し。故に予一々之を言はず。足下は予が戯作者の文を読むを見て愚なりとなす。是亦其意を得ざるなり。書は汎く読破すべし。何ぞ其筆者の戯作者たると否とを問はんや」、云々(「白鳥正宗氏に答るの書」)。
なにも幕臣であったから戯作者でないなどとは言えまい。反論する側から荷風が『柳橋新誌』のいわば“思想”に共感したのではないことが暴露される。
すくなくとも、「初編」を浸す郷愁をいっしゅの「思想」とみなさないかぎりにおいて。
荷風の南畝評価がその「徂徠学」(野口武彦)ゆえのものではないのとどうようである。幕臣だったから偉いなんて荷風はゆめにもかんがえないだろう。
柳北の文才は、第一部の掉尾を飾る長大な哀歌にみなぎりわたる。
アイロニー一辺倒のひとではない。
ところで、『柳橋新誌』をよんでいて、西鶴が『遊仙窟』慶安本の戯訓をこのんで借用していることをおもいだした。
先に言及したサイト「日本漢文の世界」によれば、訓読の限界は白話文(口語文)に適用できないことにある。
同サイトは、白話文を強引に訓読した例として露伴訳の『水滸伝』を挙げている。
まさに前述した一斎訓の極致みたいな過激な文体で、とても日本語として読めない文である。
しかし白話体を能く訓読し得た唯一の例外、それも稀代の名訳があるそうで、それは平岡龍城という無名の訳者による『国訳紅楼夢』であるという。
その一節が引かれているが、なるほど「忙忙的衣服を穿了」を「いそいできものをきて」と読ませたりする自在さがなんともたのしいが、中国語を解する読者にはその名人芸ぶりが実感できるという(悲しい哉、わたしはそのかぎりにあらず)。
訓読が詩であり、文学であり得る格好の例だろう。
さて・・・以上は『柳橋新誌』を紹介するための前置きである。同書については項を改めてまたとりあげたい。