
橋にまつわる「大勝負」は何と言っても牛若丸と弁慶の最初の出会いです。
「牛若丸」尋常小学唱歌 作詞、作曲:不明 明治44年(1911年)
京の五条の橋の上 大のおとこの弁慶は 長い薙刀ふりあげて牛若めがけて切りかかる
牛若丸は飛び退いて 持った扇を投げつけて 来い来い来いと欄干の上へ揚って手を叩く
前やうしろや右左 ここと思えばまたあちら 燕のような早業に鬼の弁慶あやまった
童謡「牛若丸」は、巌谷小波(明治を代表するお伽噺作家)の「日本昔噺」(全24編)シリーズ・第23編「牛若丸」(明治29年・1896年発表)を基に作詞・作曲されたとされます。

後世に語り継がれている「義経(牛若丸)」の物語は中世(室町初・中期に成立)した軍記物語「義経記(ぎけいき)」(作者不明)に準拠するとされています。牛若丸や弁慶の活躍した時代から約200年も後に完成したことになります。
「義経記」によると牛若丸と弁慶が最初に出会ったのは「西洞院通松原にある五条天神」となっています。
五条大橋と松原橋
義経や弁慶の活躍した時代は平安時代末期(1100年頃)です。
現在の五条大橋は天正18年(1590)に鴨川の上流にあった橋を豊臣秀吉が今の場所に移築したもので、義経と弁慶が生きた時代には五条大橋はまだ存在していなかったのです。つまり、義経と弁慶の出会いの場所を五条大橋とするのは明らかに間違いだということなのです。


それでは当時の五条大橋は何処かという問題です。
平安時代の五条大路は松原通で清水寺参詣道で大変賑わった都の目抜き通りであったそうです。この地に架かっていた橋が五条橋であり、通りの両側に見事な松並木があったことから五条松原橋とも呼ばれていました。
安土桃山時代,豊臣秀吉が方広寺大仏殿の造営に当たり,この地に架かっていた橋を平安京の六条坊門小路(現在の五条通)に架け替え,五条橋と称した。
そのため,この地の橋の名前からは「五条」が外れ,以後,松原橋と呼ばれるようになったとのことです。


勝負・決斗などの言葉から連想すれば、牛若丸と弁慶が五条大橋での出会いほどぴったりの出来事はありません。しかし、そんなメジャーな逸話がある五条大橋、松原橋は「勝負」を連想させる響きがありません。
古代から源平合戦など幾多の歴史的分岐となった決戦の橋は「瀬田の唐橋」でしょうが、その名称に「勝負・決斗」の響きはありません。
橋の名前に限らず「関ヶ原の合戦」「巌流島の決斗」「一乗寺下り松の決斗」などなど勝負・決斗そのものが地名や事件の名称になることはないようです。
その点からすると「勝負谷橋」の名前の由来も「勝負」という出来事とは考えずらいように思えます。












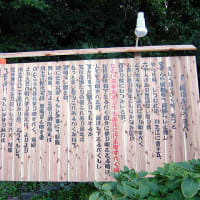
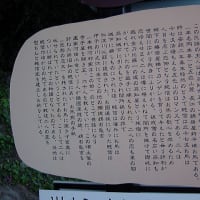


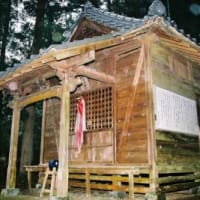


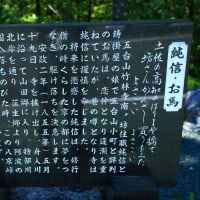







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます