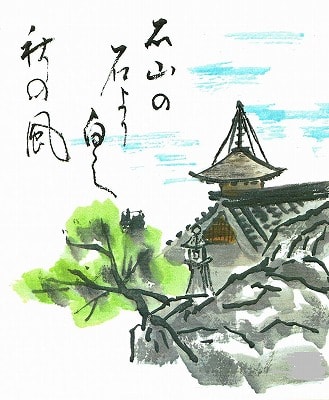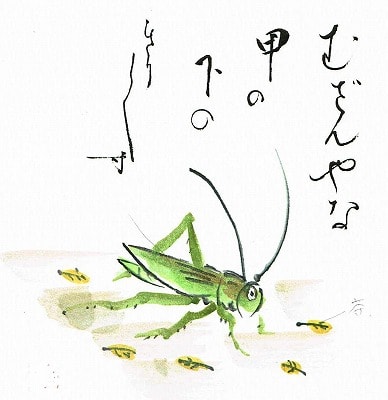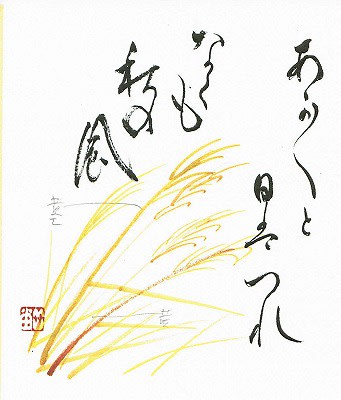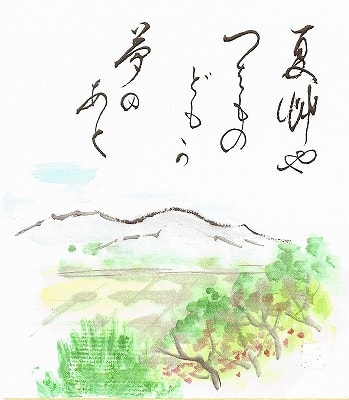奥の細道の芭蕉の句と絵を描き終わりました。1箇所くらいは所縁の地を訪れなければ、と思い大垣市に行ってきました。奥の細道の行程で一番訪問し易いところだからです。また、当ブログにとっては一時期職場があった大変思い出多いところでもあります。
「奥の細道むすびの地記念館」に車を止めて周辺の観光スポットを巡りました。
 「奥の細道むすびの地記念館」の展示は視覚的に理解しやすく、特に館内のAVシアターは3D映像で文字だけでは理解できない情景など、改めて句意を理解できました。例えば「蚤虱馬の尿する枕もと」の情景などは当ブログのイメージしていたものとは程遠い旅の困難を偲ばせるのがよく分かりました。
「奥の細道むすびの地記念館」の展示は視覚的に理解しやすく、特に館内のAVシアターは3D映像で文字だけでは理解できない情景など、改めて句意を理解できました。例えば「蚤虱馬の尿する枕もと」の情景などは当ブログのイメージしていたものとは程遠い旅の困難を偲ばせるのがよく分かりました。








 当ブログが仕事をしていた頃のJR大垣駅舎は木造で駅の周りも個人商店が立ち並んでいました。その中でひときわ目立ったビルが「ヤナゲン」百貨店でした。当時、お中元・お歳暮はこのヤナゲンから贈るのが常でした。駅舎も駅前も近代的なビルに建替えられて面目を一新していますが、往時の賑わいは無く寂しい限りです。当ブログはお酒を嗜みませんので「地元の名酒」などには興味がありませんが、地元の銘菓には大いに関心があります。各地各地にはお気に入りの銘菓があります。名古屋に行けば「万松庵の納屋橋饅頭」金沢に行けば「今屋の柴舟」・・・・・など。ここ大垣は何と言っても「つちや・柿羊羹」です。それ程客の多くない菓子売り場でお土産に柿羊羹を買って帰りました。
当ブログが仕事をしていた頃のJR大垣駅舎は木造で駅の周りも個人商店が立ち並んでいました。その中でひときわ目立ったビルが「ヤナゲン」百貨店でした。当時、お中元・お歳暮はこのヤナゲンから贈るのが常でした。駅舎も駅前も近代的なビルに建替えられて面目を一新していますが、往時の賑わいは無く寂しい限りです。当ブログはお酒を嗜みませんので「地元の名酒」などには興味がありませんが、地元の銘菓には大いに関心があります。各地各地にはお気に入りの銘菓があります。名古屋に行けば「万松庵の納屋橋饅頭」金沢に行けば「今屋の柴舟」・・・・・など。ここ大垣は何と言っても「つちや・柿羊羹」です。それ程客の多くない菓子売り場でお土産に柿羊羹を買って帰りました。

「奥の細道むすびの地記念館」に車を止めて周辺の観光スポットを巡りました。




無何有荘 大垣八幡神社の自噴泉
大垣は湧水が豊富なところで市内のあちらこちらに清冽な涌水が流れ出しています。





各項目の解説はリンク先をご覧ください。