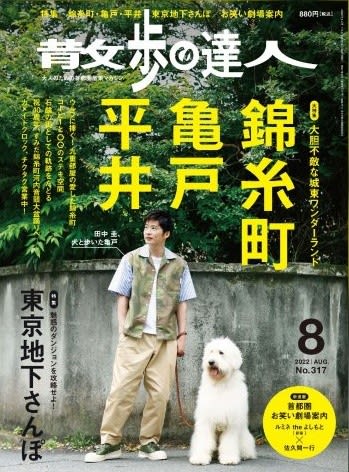いずれも画像をクリックすると本文のサイトに飛びます。
伊勢湾台風から63年。明治以降で最悪の犠牲者数となった災害を振り返る【画像集】 https://t.co/TOFd8LFmzc
— 阿智胡地亭 辛好 (@achikochitei2) September 26, 2022
オスプレイの飛行訓練 これまでよりも低い高度で日米が合意 | NHK https://t.co/V50bjoQq8l
— 阿智胡地亭 辛好 (@achikochitei2) September 26, 2022
60代男性に「若者に金がないのは苦労をしないから」と説教され…“若者の貧困”を自己責任論で片づける日本社会の勘違い #文春オンライン https://t.co/EHveV59smt
— 阿智胡地亭 辛好 (@achikochitei2) September 26, 2022
この国の首相や官房長官が「対話」を得手としなくなって久しい。圧倒的な権力をバックに「御指摘は当たらないもの」「コメントは差し控える」などの決めセリフは「政治の言葉の不毛」を増長した。岸田首相はこの距離感を「聞く力」て埋める役割を自称したのが総裁選だった。
— 保坂展人 (@hosakanobuto) September 26, 2022
業績評価なしの国葬は「私物化」 ノンフィクション作家・保阪正康、岸田内閣を批判 https://t.co/oDoyg3Cy3Q @dot_asahi_pubより
— 阿智胡地亭 辛好 (@achikochitei2) September 26, 2022
この人を国葬するの? 本気で? https://t.co/O0ZS6ZHTAA
— 町山智浩 (@TomoMachi) September 26, 2022
まるで支援装った「半植民地化」、凋落するロシアの天然資源を買い叩く中国 《深川 孝行》 #ネルチンスク条約 #キャフタ条約 #アヘン戦争 #アイグン条約 https://t.co/LCAzV2ofOU
— JBpress(ジェイビープレス) (@JBpress) September 27, 2022
原発回帰で最も心配なのは安全性 恐ろしいのは東電の安全を後回しにする体質 https://t.co/oSMOyQjRSm @dot_asahi_pubより
— 阿智胡地亭 辛好 (@achikochitei2) September 26, 2022
安倍銃撃事件と竹中平蔵。御用学者・元パソナ会長が怯える五輪汚職疑惑と山上容疑者のような法を無視した暴力。日本の雇用は劣化したと認めた彼の未来はど... https://t.co/XB9g6rwrUE @YouTubeより
— 宮台真司 (@miyadai) September 26, 2022
▼旧統一教会から韓国への送金ルートは2つ。
— 有田芳生 (@aritayoshifu) September 26, 2022
①みずほ銀行にウリ銀行の当座預金口座を作り、多くは「ヒョジョングローバル統一財団」の口座に送金している。金孝南がいたときには清心教会の口座にも送金された。
② コロナ以降は日本信者がほとんど清平に行けないので、現金持参はできなくなった。 pic.twitter.com/Fg5aqJ9sUx
花は咲くは作曲者である菅野よう子さんも、作詞者である岩井俊二さんも、宮城県仙台市出身なのですよね。地元を元気付けられないかって考えて作られた曲なのに。
— 綾瀬 (@ayase_cts) September 26, 2022
それを政治利用って。。。 https://t.co/r5NOywNOus