従弟から続いてメールが来ました。
『手長神社、八剣神社の里曳きを初めて見ました。上諏訪の御柱は、下社の影響で「めどでこ」をつけていなかったのですが、氏子の希望もあり数回前の御柱から「めどでこ」をつけるようになったそうです。(トップの画像)
上諏訪の狭い通りをバックもまじえて進みます。
初めて聞く八剣神社の「木遣り」は確かにちょっと変わっていました。
柱の後ろにソリをつけ子供達が乗っています。
宮坂醸造・丸高蔵では味噌汁が振舞われていました。
日が落ちてから手長神社の長い階段を引き上げる御柱は、雨も重なり迫力のあるものでした。
階段を上がり切ると柱の後ろが跳ね上がります。
上諏訪中学の前の坂を進みます。

雨が益々強くなる中、本殿脇の坂を上がります。
あえて外への宣伝を行わないのか、よそからの見物人はほとんど無く、地元の人の手による御柱ですが、
一の柱の長さ、太さは下社の四の柱に遜色無く、上諏訪の市街地の住民が下社の御柱よりこちらの御柱に力がはいるのはもっともだと思いました。』
Kさん、ありがとう。小宮の御柱の雰囲気がよくわかりました。地元の祭がこうして、全員参加で続いているのは素晴らしいですね。
♪八剣神社は諏訪市小和田(こわた)にあります。諏訪が豊臣軍に占領されていたとき、秀吉の命を受けて配下の武将「日根野高吉」が諏訪湖の中にあった「高島」という島に城を築きました。その城が高島城です。八剣神社は高島の島内にあった島民の氏神ですが、島民が高島から現在の小和田の地に移された時、神社もともに移設されました。 この立ち退きのとき、島民は日根野氏と巧みな交渉を行い、諏訪湖全域の漁業権と、新たに広大な農地を獲得しました。我が家の先祖はこの半農半漁の島民の一人だと聞きます。八剣神社はまた、古来より諏訪大社の摂社(筆頭子社)で、諏訪湖の冬の自然現象“御神渡”を検定し、諏訪大社に出来を報告する役割を担ってきました。小和田に移った住民は、移住以来、藩主(日根野氏が他に移ったあと、諏訪氏が戻り、明治のはじめまで諏訪氏が殿様だった)の支配を受けず、行政は住民の自治によって行われました。諏訪湖から湧く温泉を引いた共同浴場で、裸の住人たちが侃々諤々論議を戦わせ、祭の拠出金や揉め事など自分たちで全てを決めていったそうです。
私も小学生のころ、夏休みに諏訪に行ったとき、まだ使われていた大きな共同風呂にイトコたちと入った楽しい思い出があります。
♪手長神社は茶臼山にあり、境内から諏訪湖を見下ろしています。高島城が築城されるまでこの地には諏訪氏代々の城がありました。両神社は宮坂清宮司が宮司を兼任しています。
手長神社 八剣神社
◎ 諏訪湖御神渡り「明けの海」奉告 八剱神社
長野日報社 地域 2010-02-20
諏訪湖の御神渡り神事をつかさどる諏訪市小和田の八剱神社で20日、今季の結果を神前に告げる注進奉告祭があった。神社総代や古役ら約50人が参列。暖冬傾向で御神渡りは出現せず、2季連続で「明けの海」となったことを奉告した。
同神社によると、「明けの海」は戦後29回目。平成元年以降では16回目となり、昭和の15回を超えた。
今冬の諏訪湖は1月中旬に広範囲で結氷したものの、寒さは長続きせず、次第にその面積は縮小した。宮坂清宮司は「諏訪の湖は結氷するもやがて解氷し、小波打ち寄せる明けの海にて御渡りござなくそうろう」と奉告。参列者は神事後、御神渡りができた場合に拝観式で使う予定だったしめ縄をたき上げた。
2004年と1998年に続き、御柱年の出現を願っていた神社総代。宮坂勝太大総代は「残念だが、今年1年が穏やかな年になることを願いたい」。宮坂宮司は「氷点下10度以下の日が1日しかなかった。湖が凍り、御渡りができる自然の偉大さを、明けの海だったことで改めて知らされた」と話した。
奉告祭に続き、諏訪市の諏訪大社上社本宮で注進奉告式があり、結果を記録した注進状を奉納した。注進状の内容は大社を通じて、宮内庁、気象庁にも報告される。
町田市に住む従弟から、もしかしたらと期待していたメールが来ました。
(「小宮の御柱」の説明は下にあります。)
『現役時代に行けなかった小宮の御柱に、9月25日26日と行ってきました。下金子の八幡さま、上諏訪の八剣さま、手長さま、みな同日開催で忙しく見て回りました。
下金子は小さな集落ですから、4本の柱を曳くのに部落総出の様相です。柱にはきちんと「めどでこ」をつけ、子供達が競って乗っていました。
(トップの画像)
私の実家の庭先で子供達の花笠踊りが披露されます。
風船を配り、綿菓子でもてなします。
集落を出るところではお手製のナイヤガラを流します。

小宮の御柱では女の子達も「めどでこ」に乗れます。
鳥居くぐりの難所は大人の出番です。

「めどでこ」の上での逆立ちも上社の御柱と同様です。
25日の里曳きはここまでです。
26日の建て御柱です。
 』
』
“小宮の御柱”とは;webから引用
「諏訪の御柱は諏訪大社だけではありません。今年一年、特に夏の終わりから秋にかけて、諏訪地方全域で「小宮の御柱」と呼ばれる御柱祭が行われます。
小宮とは、諏訪6市町村の各地区に点在する鎮守様、氏神様、産土神など大小様々な神社のことで、そのほとんどに御柱が建てられています。そして、諏訪大社の御柱祭に合わせて、同じ年に各小宮の氏子により御柱祭が行われるのです。
小宮の御柱祭は諏訪大社に比べると規模は小さいものの、氏子の熱い想いは大社以上。子どもからお年寄りまで地区の人々がこぞって参加し、大いに盛り上がります。また、柱を曳いて建てるというところは共通しているものの、各神社それぞれに趣向を凝らした見せ場や変わった催しが行われるのも特徴のひとつ。階段の引き上げ競争や夜間曳行など、小宮ならではの楽しみにあふれています。」
札幌にお住まいのC・Kさんから秋が訪れた札幌の画像を送っていただきました。
「家からこんな雲が見えました!!こんな雲、初めて見たように思います。
北ノ沢公園のナナカマド。実も色づき初めています。
同公園の栗の木です。後1か月もすると、イガグリが木の根元に一杯落ちます。
同公園近くの空き地のススキ。
あるお宅の庭のクルミです。しっかり実をつけています。
♪クルミは小中学生のころ、信州茅野市菊澤の伯母が家で取れたのをよく送ってくれました。
それ以来ずっとクルミは大好きになり、いまも家には買い置きを切らしたことはありません。
実家の庭の白樺にアカゲラ(キツツキの1種)が来ているのに出くわしました。「あんまり穴、開けないでよ~!!」
近所のお庭のコスモス。
ご近所のナナカマド。
ご近所のミズナラのドングリ。
実家の庭の萩です。
ちょっと早い秋を楽しんでいただけましたら嬉しいです」
♪Cさん、ありがとうございます。神戸も朝晩ようやく秋の風が吹き出しましたが、日中はまだまだ真夏です。
札幌は一足先にもう秋なんですね。
「岡本太郎の【明日の神話】懐かしく見ました。設置されている渋谷の通路は時々通るのですが、ほとんど見上げたことがありません。
【明日の神話】が修復されてすぐに汐留の日本テレビの広場に展示されているのを見にいきました。このときの印象が強烈で、さすが岡本太郎と思ったのをよく覚えています。汐留での展示がどのようなものであったか写真を添付しておきます」。

♪Wさん、さすがの構図ですね。確かに今の渋谷の設置条件では、全面を一枚の画像に納めるのは出来ませんでした。ありがとうございました。
隈研吾の設計で、建物は3年半の歳月をかけて新しくなりましたが、美術館の庭園は昔のままです。真夏の庭を家人が歩きました。



地下鉄の駅をあがって、カルチエとプラダの店など有名店が並ぶ道を歩いていくと根津美術館に着きます。


私は昨年10月、雨の日に根津美術館を訪ねました。こちら

犬も歩けば棒にあたる・・
そして美術館の近くにくると

昼飯時になっていて、サラリーマンが列を作っている店がありました。
最近東京や大阪で、よくみかけるようになった「○○食堂チェーン」の店のようでした。
○○には地元のローカルな地名が入ります。こういう風景は元サラリーマンとしては、やはり何となく懐かしい。

阪神福島駅から中之島の国立国際美術館に行く途中、新設なった朝日放送本社ビルの前を堂島川に向かって歩きました。
朝日放送ビルには毎週楽しみに見ている「崖っぷちのエリー」の大きな写真が掲示されていました。
ビルの壁面は鏡のようなガラスが使われています。
玉江橋北詰で左に曲がって、堂島川を右に見て川沿いを歩くとすぐこの石碑があります。

私は、世の中の自伝の中でも白眉の「福翁自伝」をずっと愛読し、大分県中津の福沢諭吉が育った家にも行き、彼が大阪で蘭学を勉強した
緒方洪庵の適塾を何度も訪れ、また彼が設立した大学の入塾許可も貰った諭吉命の人間ですが(結局許可をもらったままになりましたが)、
彼が生まれたこの中津藩蔵屋敷跡だけは今回初めて訪ねました。
それにしても親の心子知らずというか、創立者は「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」と言っておられるのに、
塾生の後継者の中には「〇〇幼稚舎」とかに子を入れて、幼いときから自分は人の上の人だと勘違いするような子供を造っている人もいるやに聞くのも可笑しいです。
石碑を過ぎてすぐ涼しそうな前庭のあるビルがありました。
大阪の中之島にある国立国際美術館で9月12日まで横尾忠則の「全ポスター展」と、平行して「束芋展」が開かれています。束芋も兵庫県出身の創作者です。
横尾忠則は兵庫県の西脇市出身で、西脇高校を卒業して最初に就職した地元の会社から引き抜かれて、神戸新聞社に勤務したことがあります。
そんなことから感覚的に地元の人という親しみがあります。また自分にとっては、昭和40年の最初の頃から、毎月の「話の特集」という雑誌で彼の作品を楽しんできました。
そして今でもなじみのある創作者で、自分が生きてきた時代の記録者という位置付けの人でもあります。
暑い一日でしたが、阪神の福島駅で下車して、大阪市立自然科学館の隣にある国立国際美術館に向かいました。
まず展示されたボリュームに圧倒されました。そしてついポスターの制作された年月もチエックして一枚一枚を丁寧に見ていきました。
長時間、会場にいたせいか、あるいは向こうから来る電波というか、オーラというか、エロティシズムというか、滅びの哀しみというか、
いろんな思いがごちゃまぜになってフラフラになりました。
このポスター展の全作品が掲載されている本がショップにありましたが、12000円はイタイのでネットから作品群の一部を引用します。
ポスターは今回全て展示されています。


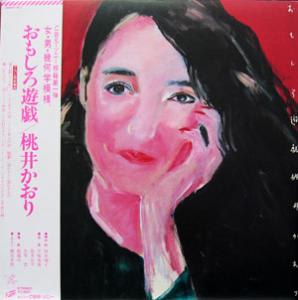

この「浅丘ルリ子裸体姿之図」を初めて見た若いとき、数日間、頭がクラクラしていました。
今回もやはりまたクラクラしました。










































