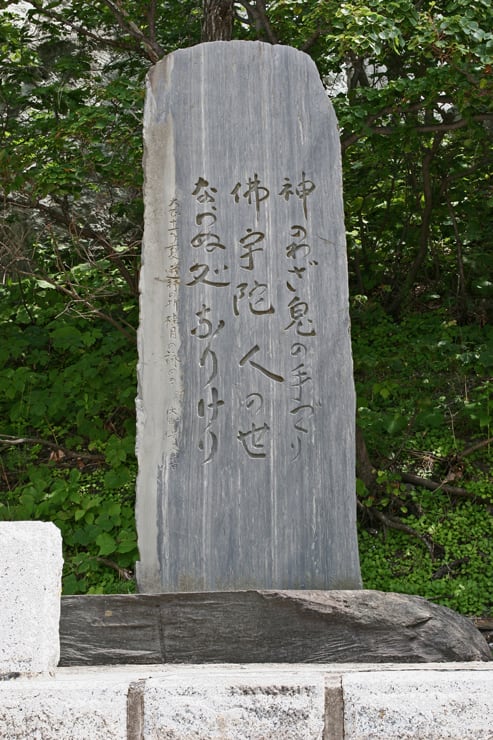この旅の記録は今から8年前のものである。
日本三景 松島
大学2年の時、実家に帰省する途中にこの松島にきたことがある。
港内の海水が汚濁していてがっかりして立ち去ったことを今でも覚えている。

当時は「公害日本」と呼ばれ汚染物質に国民が曝露されていた時代で、隣国、中国の今のような状況であった。

遊覧船に乗り周囲の島々を見ても、とてもきれいで学生時代の嫌な思いが消え去りよかった。

震災の影響が点在している島々に与えたのだろうか。







遊覧船に乗っていた、若いこの二人も今は30代になっているはずだ。
当時はカモメにも注目されていたが、いまはどのような人生を送っているのだろうか。

「あぁあぁ鴎にもわかりはしない(松尾和子「再会」より)」
それから、カモメを間近で撮りたい人はこの観光船を薦める。

東北旅行の3つの目的地。① 恐山、② 土門拳記念館、そして最後になるのがこの喫茶店だ。

日本でも有数のジャズ喫茶である一関の「ベイシー」
その迫力ある音を聴こうと日本はもとより世界中からジャズファンが訪れるという。
店主が気に入った音がでるまで開店しないという店であったが、幸運にも入ることができた。
コーヒーを注文しさっそくその音を聴く。

大音量で、床から体に響いてくる低音は家庭では再生することはできない。
金管や打楽器などは目の前で演奏しているような感じでもあった。
何か評論家みたいな口調になったが、オーディオが好きで機器を購入するためにローン地獄になったほどの歴史がある。
ジャズコンサートもよく聴きにいったし、レコードもかなりある。
事情があってしばらくオーディオを封印していたのだが、解くきっかけになればいいと思って訪れた。

コーヒー2杯、レコード4枚分を聴いて店を出る。
心は満足感、体はリズミカルになっている。
撮影 平成17年7月28日
昨夜は、道の駅「厳美渓」に泊まる。
学生時代にこの地を訪れたときに厳美渓が「きれいな風景」という記憶があったからだ。
天然記念物 厳美渓

店の対岸に吊るされているかごに代金を入れて合図をすると、かごがスルスルと上り、団子が入って戻ってくる。
渓流をかごが行き来する「空飛ぶだんご」は名物だそうだ。

車で移動しながら撮ってみる。

途中で朝のラジオ体操をしていたということは、相当早い時間だ。

撮影 平成17年7月29日
日本三景 松島
大学2年の時、実家に帰省する途中にこの松島にきたことがある。
港内の海水が汚濁していてがっかりして立ち去ったことを今でも覚えている。

当時は「公害日本」と呼ばれ汚染物質に国民が曝露されていた時代で、隣国、中国の今のような状況であった。

遊覧船に乗り周囲の島々を見ても、とてもきれいで学生時代の嫌な思いが消え去りよかった。

震災の影響が点在している島々に与えたのだろうか。







遊覧船に乗っていた、若いこの二人も今は30代になっているはずだ。
当時はカモメにも注目されていたが、いまはどのような人生を送っているのだろうか。

「あぁあぁ鴎にもわかりはしない(松尾和子「再会」より)」
それから、カモメを間近で撮りたい人はこの観光船を薦める。

東北旅行の3つの目的地。① 恐山、② 土門拳記念館、そして最後になるのがこの喫茶店だ。

日本でも有数のジャズ喫茶である一関の「ベイシー」
その迫力ある音を聴こうと日本はもとより世界中からジャズファンが訪れるという。
店主が気に入った音がでるまで開店しないという店であったが、幸運にも入ることができた。
コーヒーを注文しさっそくその音を聴く。

大音量で、床から体に響いてくる低音は家庭では再生することはできない。
金管や打楽器などは目の前で演奏しているような感じでもあった。
何か評論家みたいな口調になったが、オーディオが好きで機器を購入するためにローン地獄になったほどの歴史がある。
ジャズコンサートもよく聴きにいったし、レコードもかなりある。
事情があってしばらくオーディオを封印していたのだが、解くきっかけになればいいと思って訪れた。

コーヒー2杯、レコード4枚分を聴いて店を出る。
心は満足感、体はリズミカルになっている。
撮影 平成17年7月28日
昨夜は、道の駅「厳美渓」に泊まる。
学生時代にこの地を訪れたときに厳美渓が「きれいな風景」という記憶があったからだ。
天然記念物 厳美渓

店の対岸に吊るされているかごに代金を入れて合図をすると、かごがスルスルと上り、団子が入って戻ってくる。
渓流をかごが行き来する「空飛ぶだんご」は名物だそうだ。

車で移動しながら撮ってみる。

途中で朝のラジオ体操をしていたということは、相当早い時間だ。

撮影 平成17年7月29日