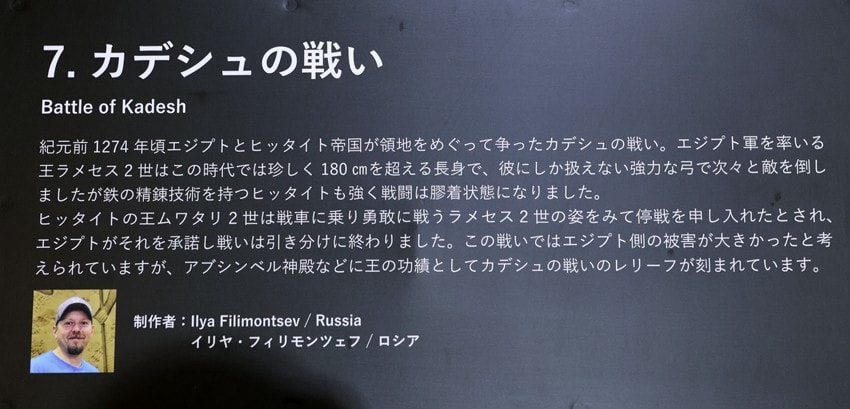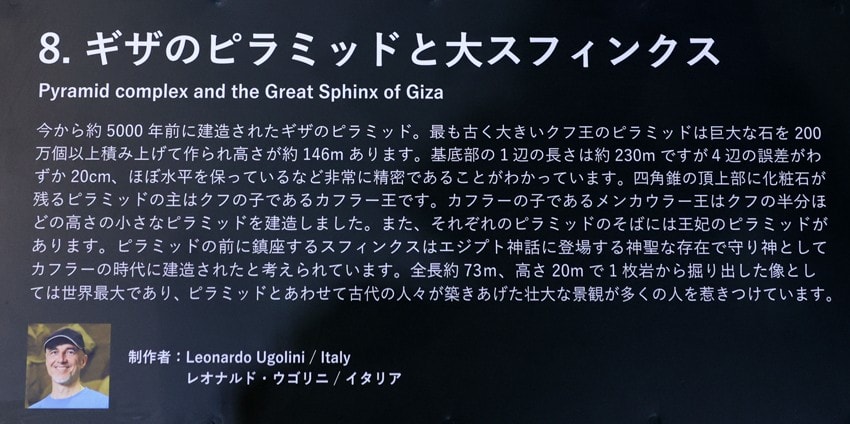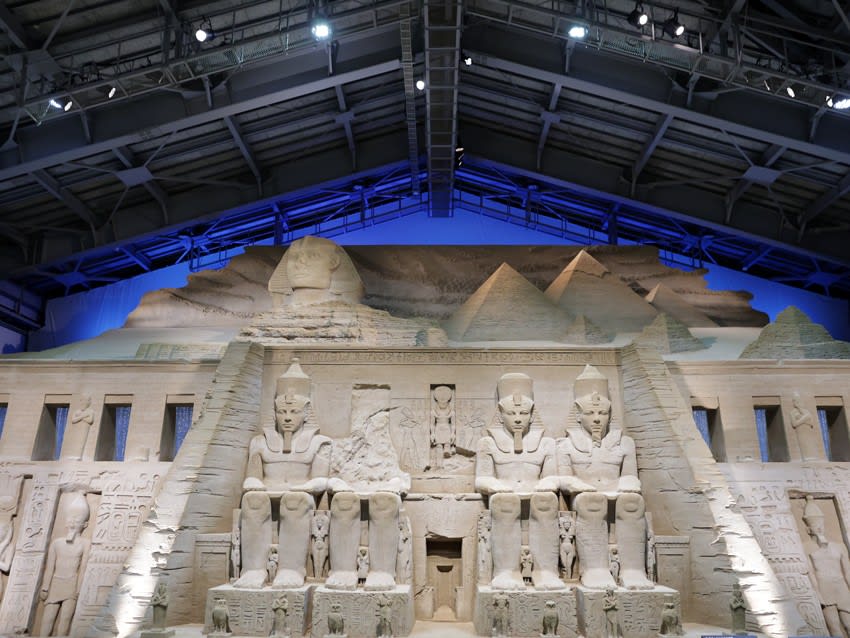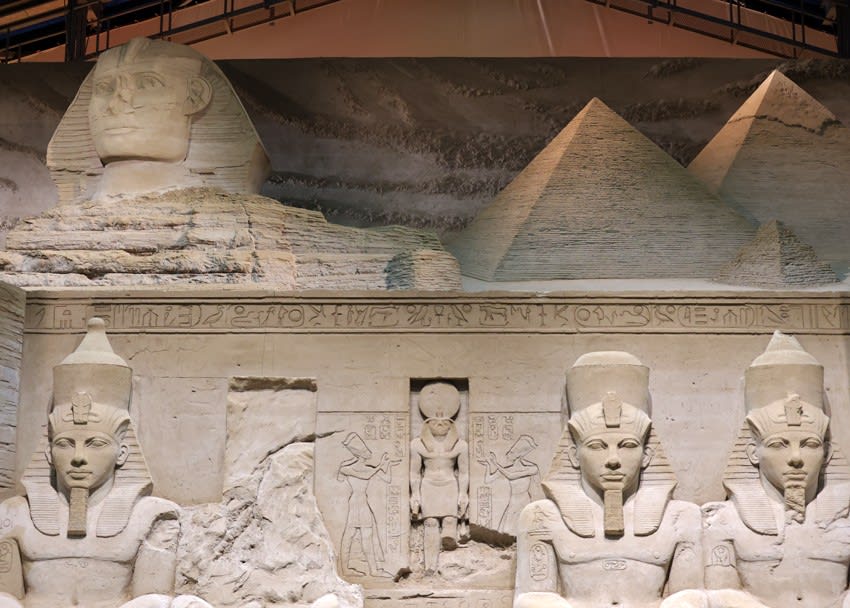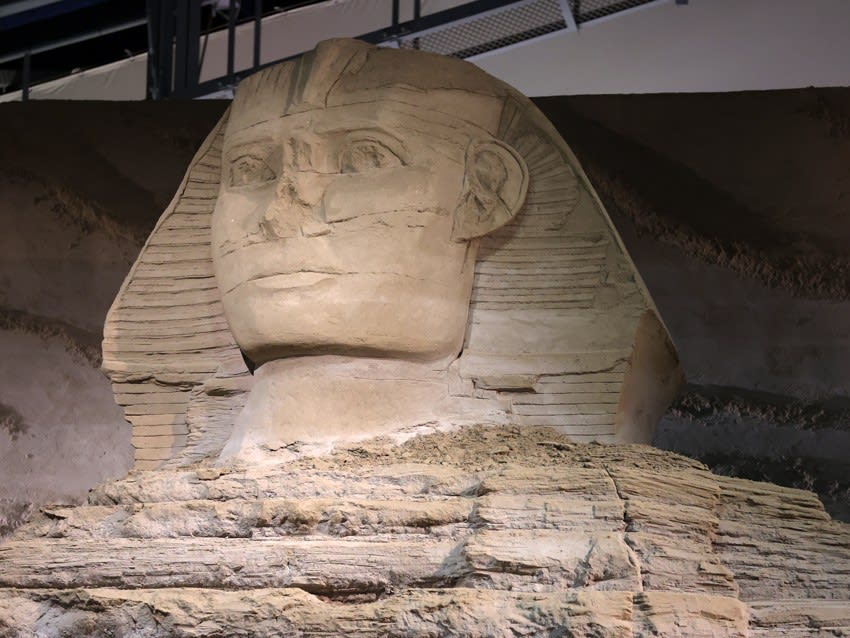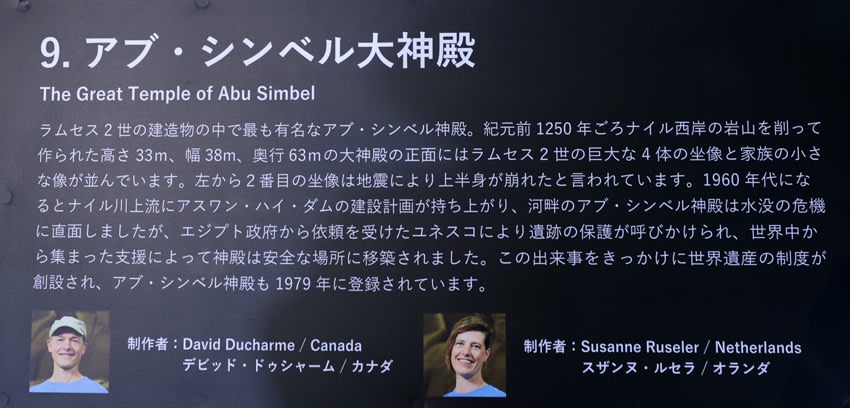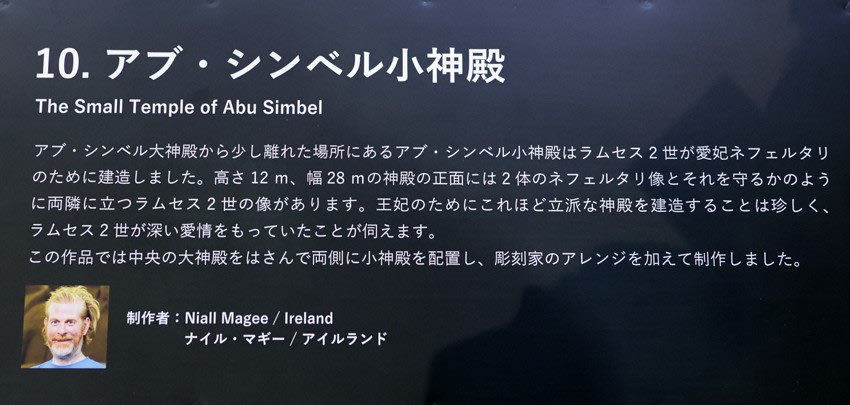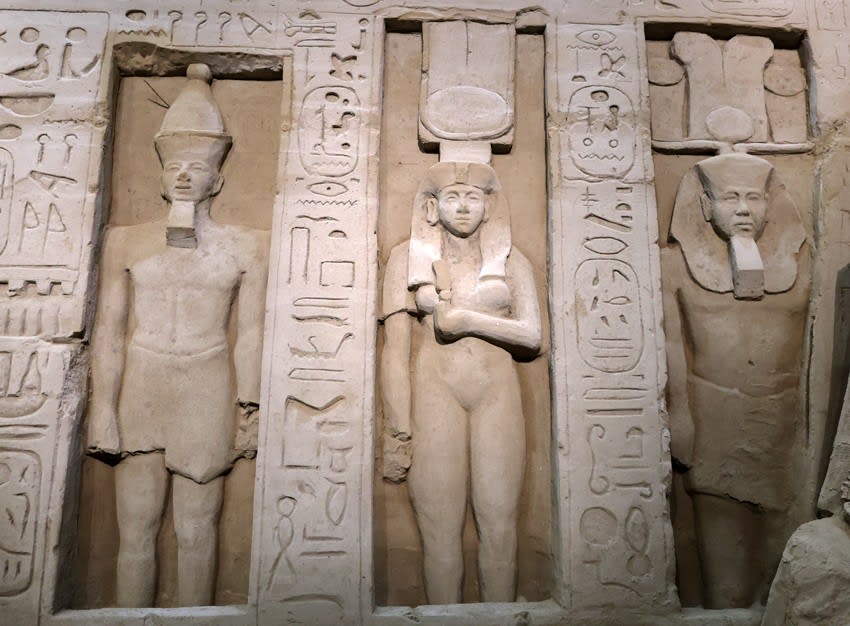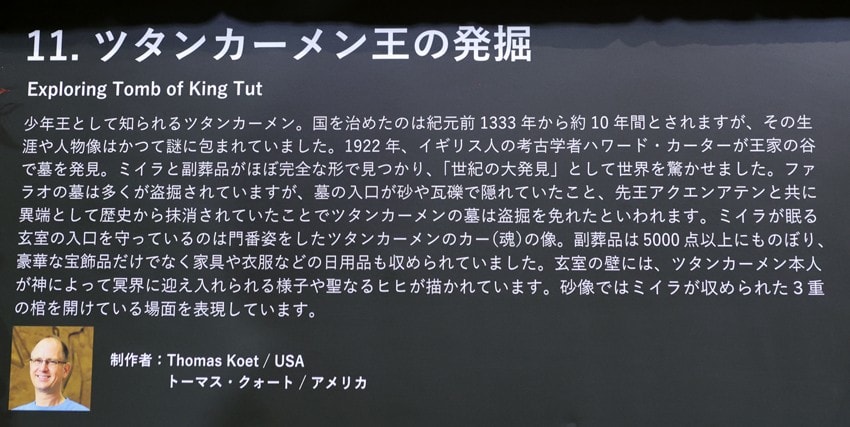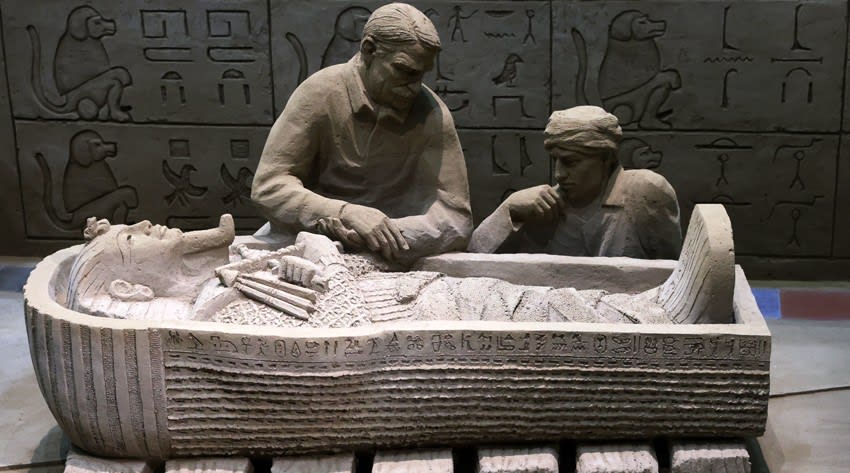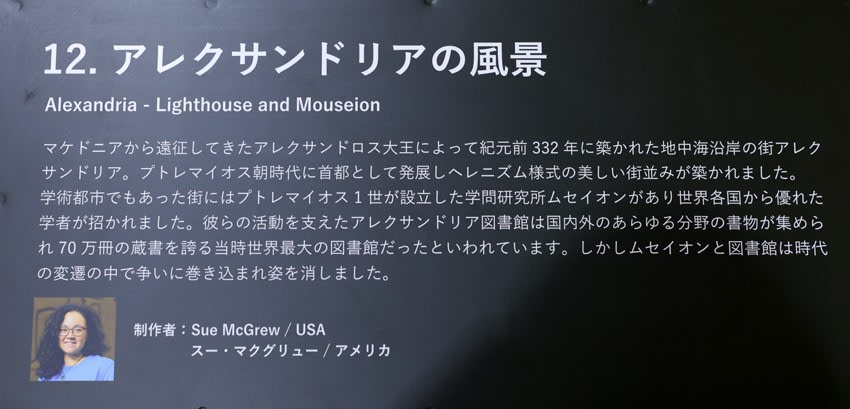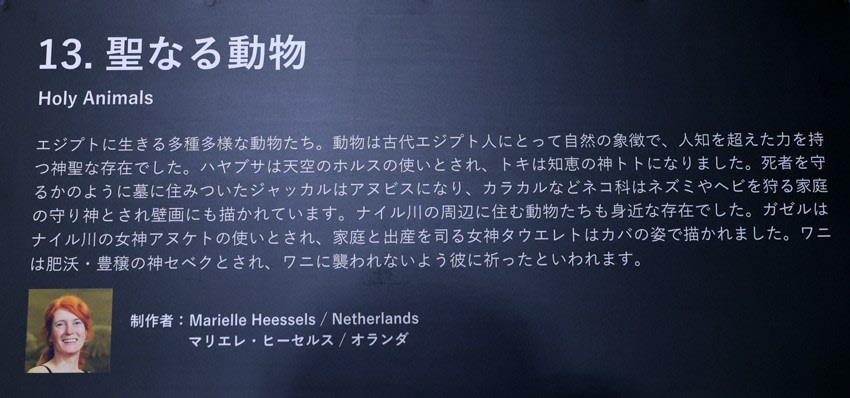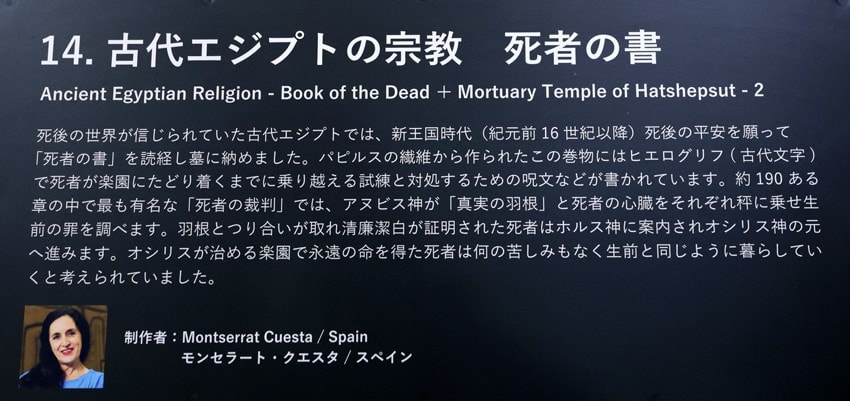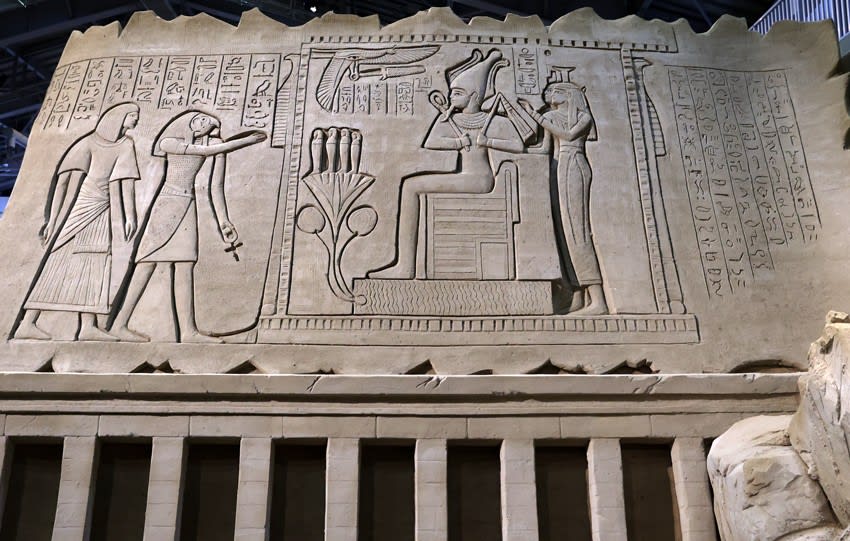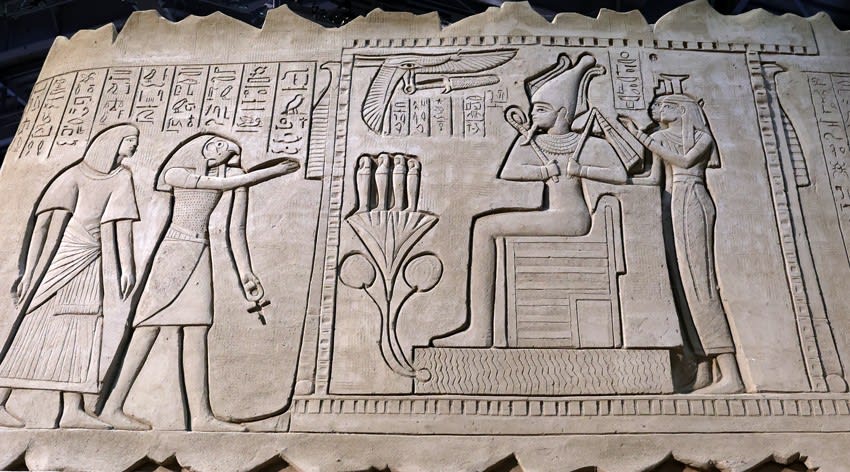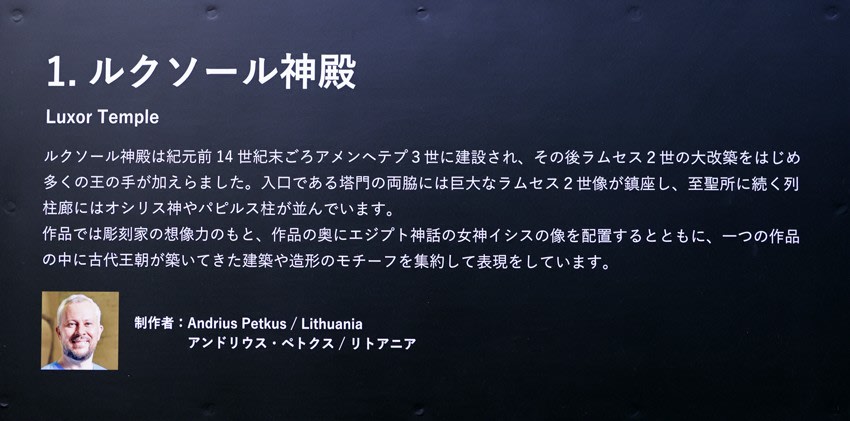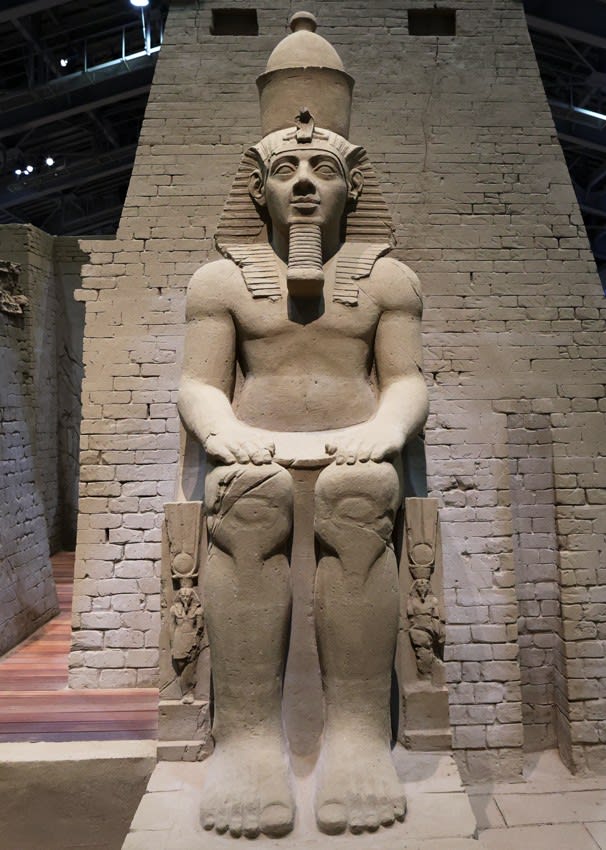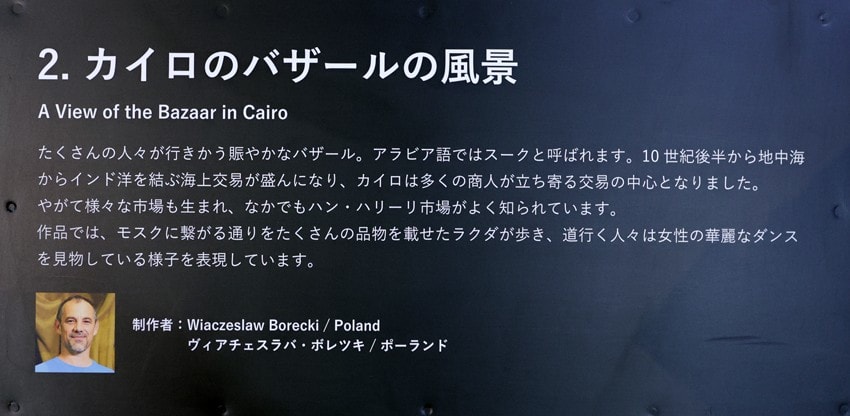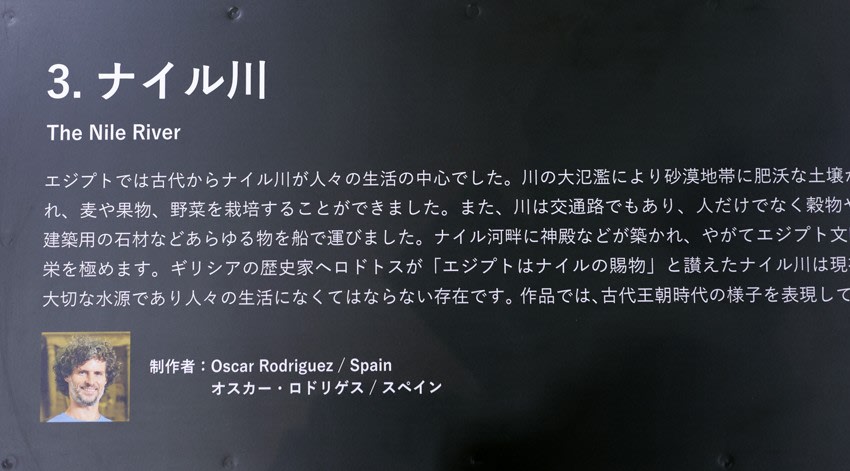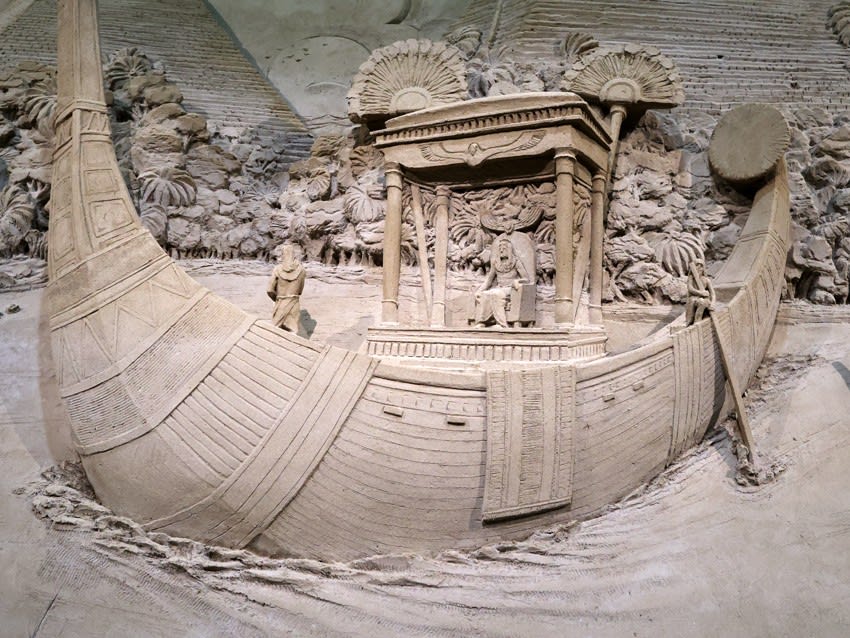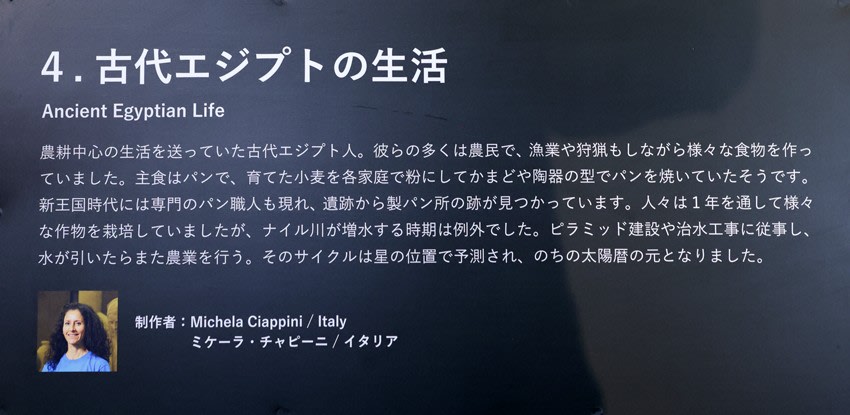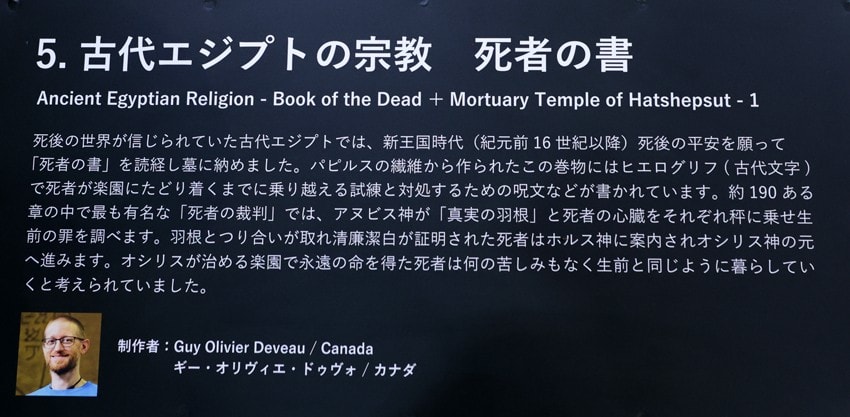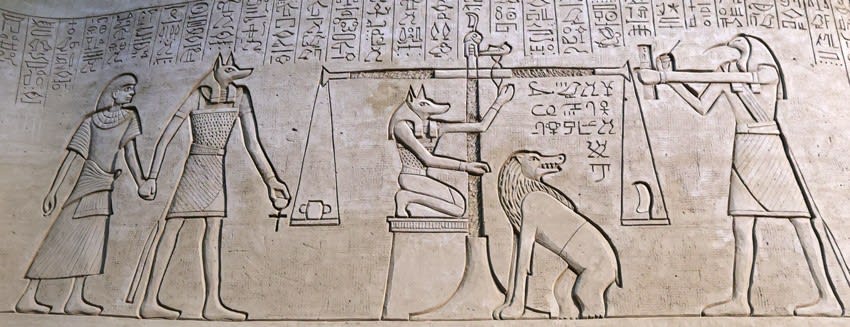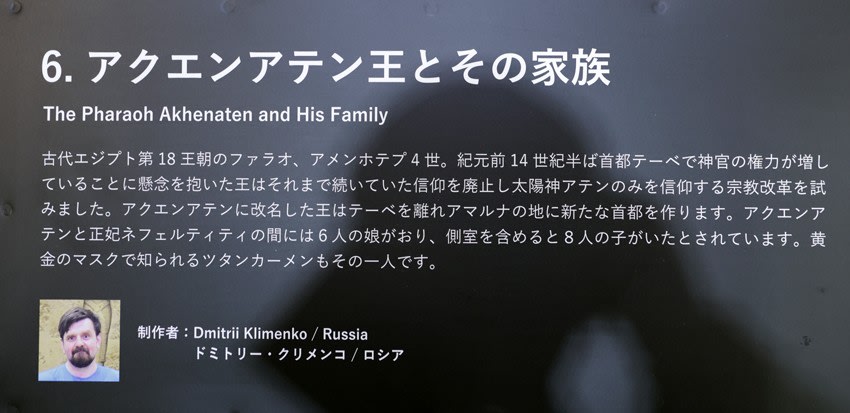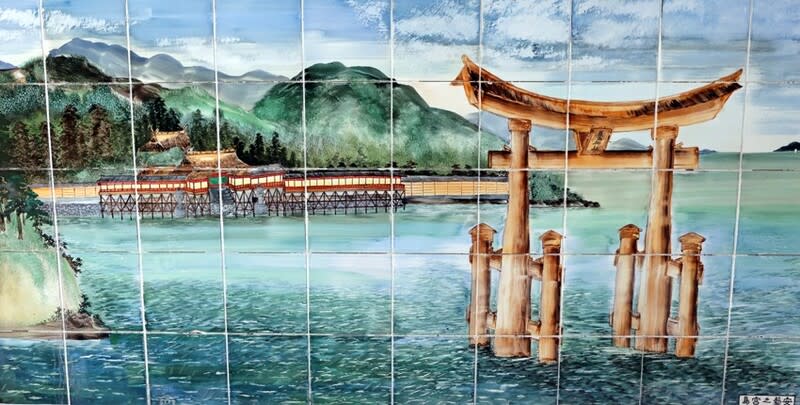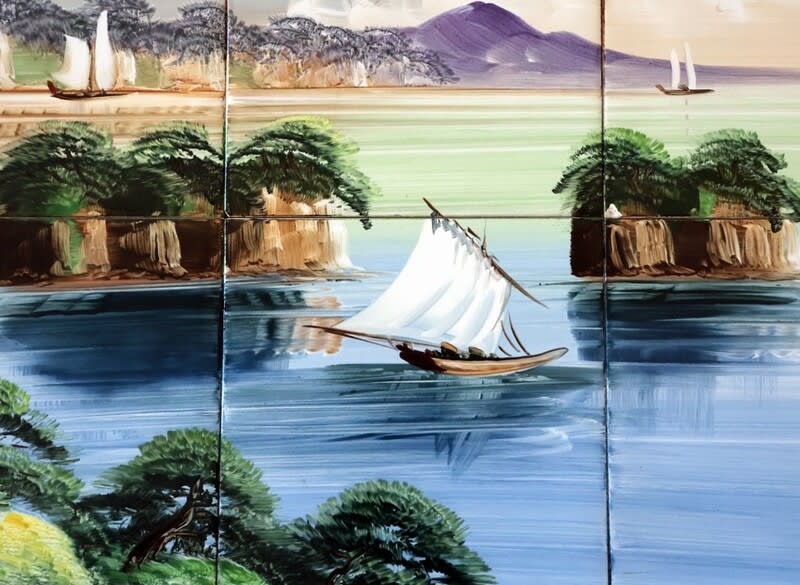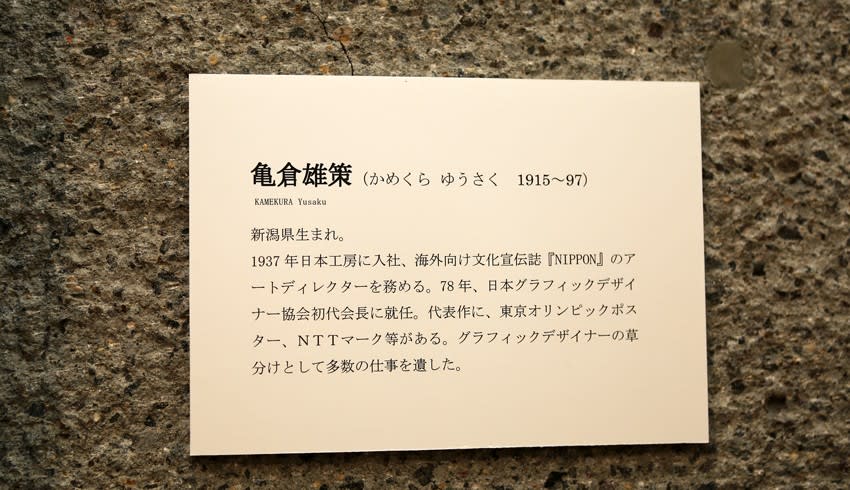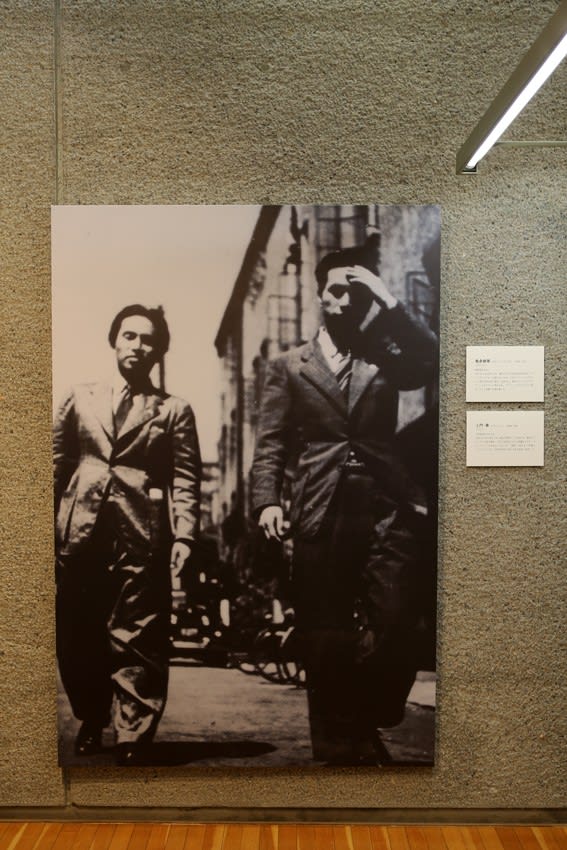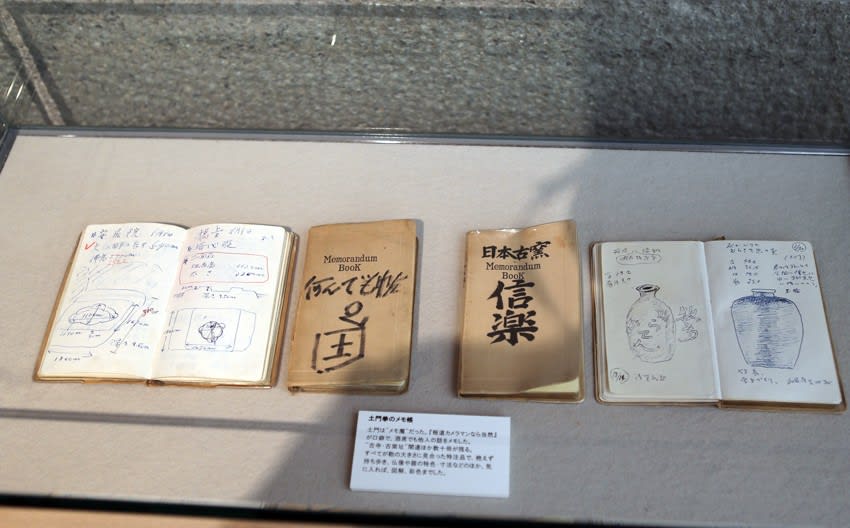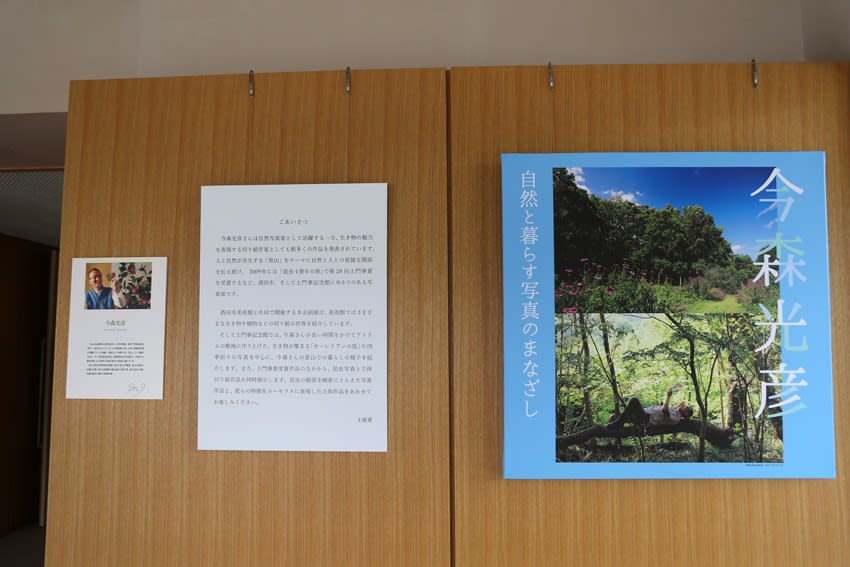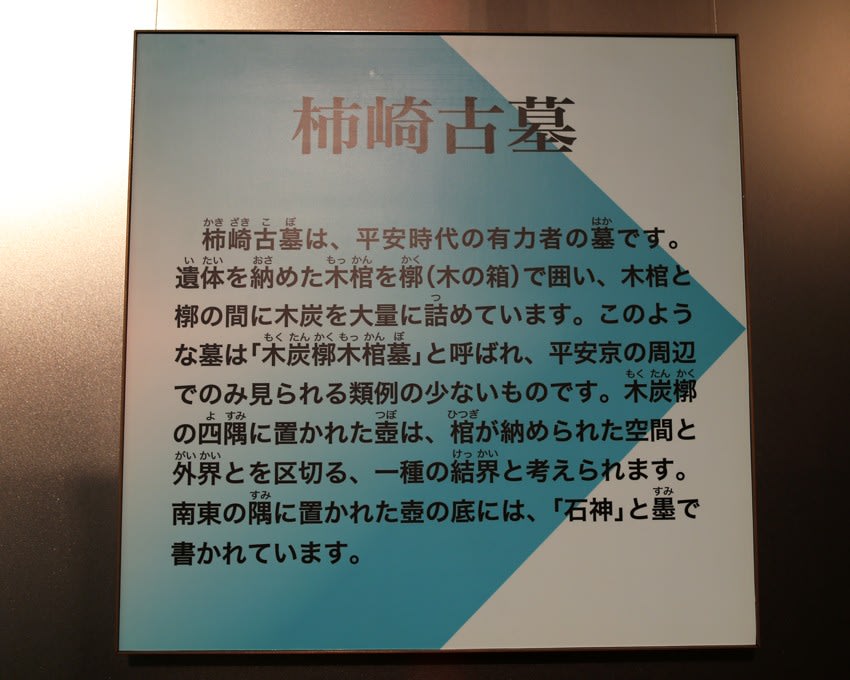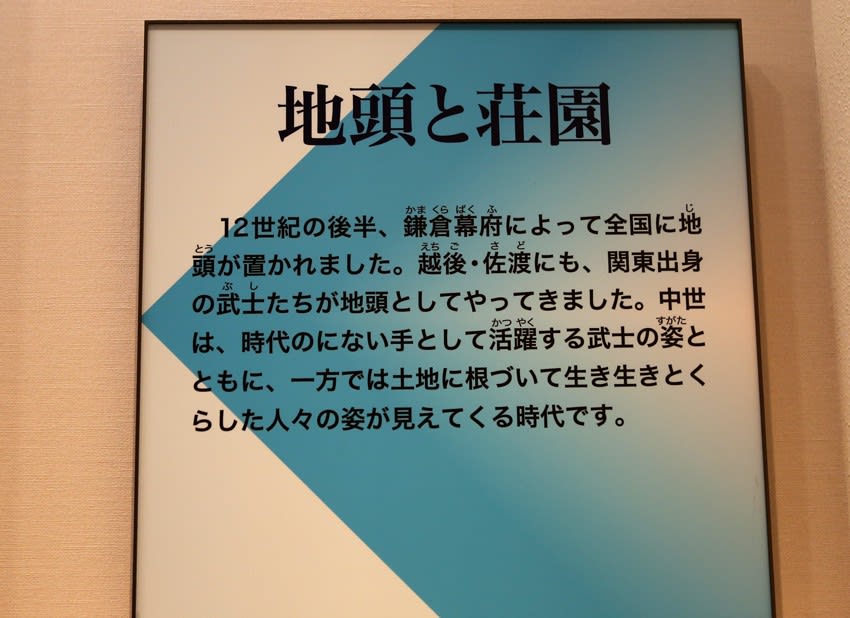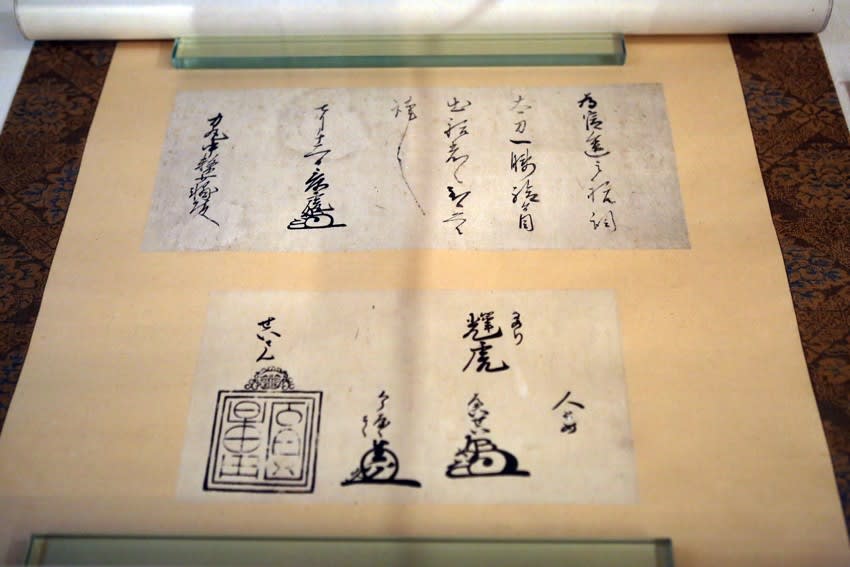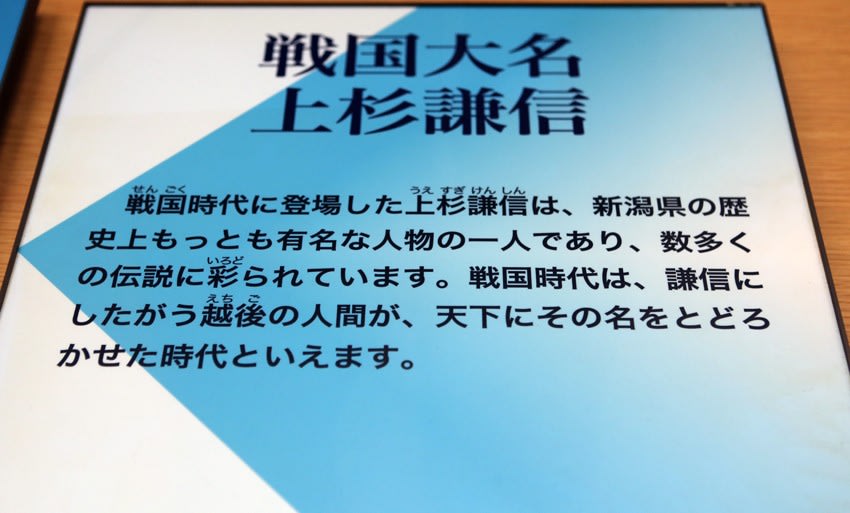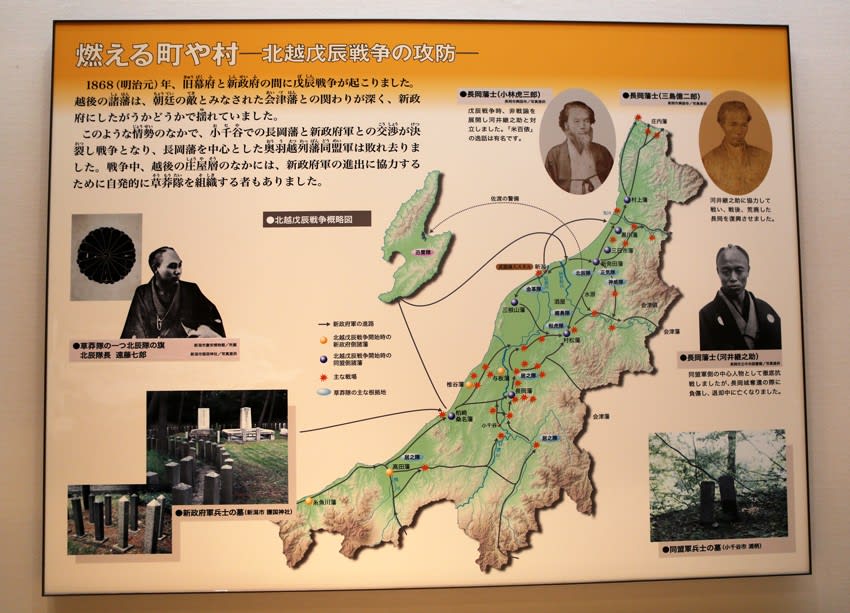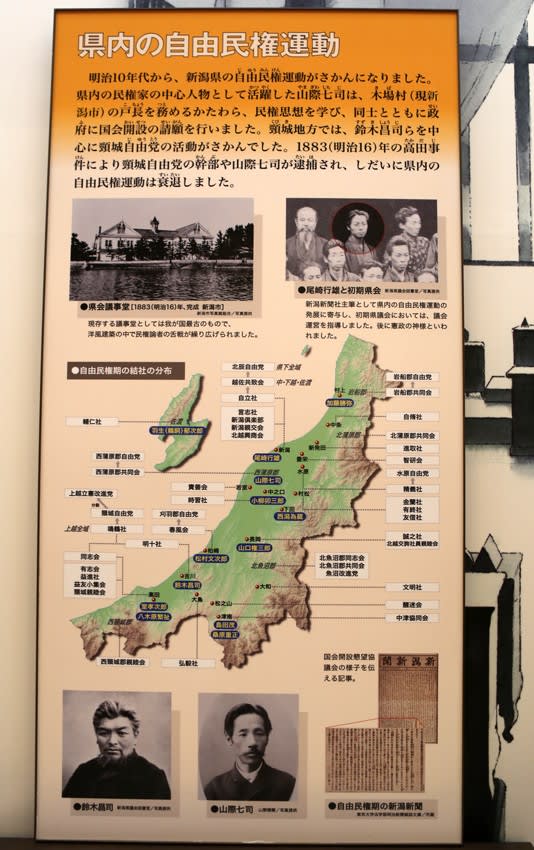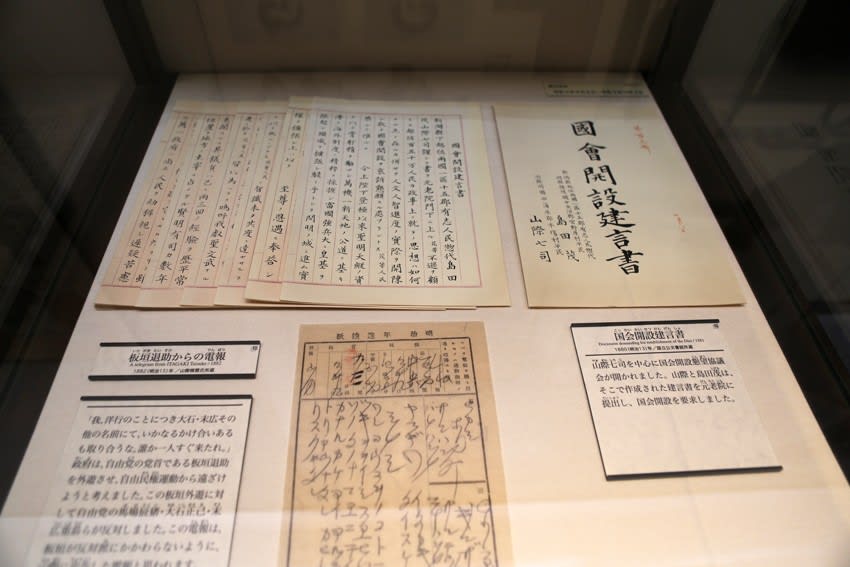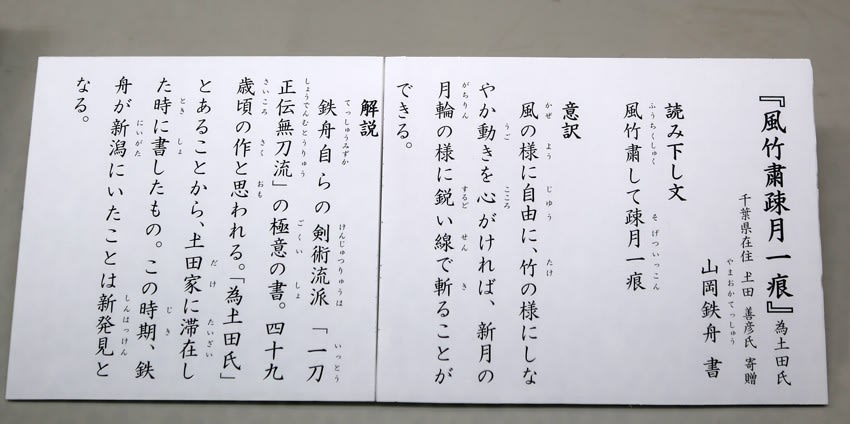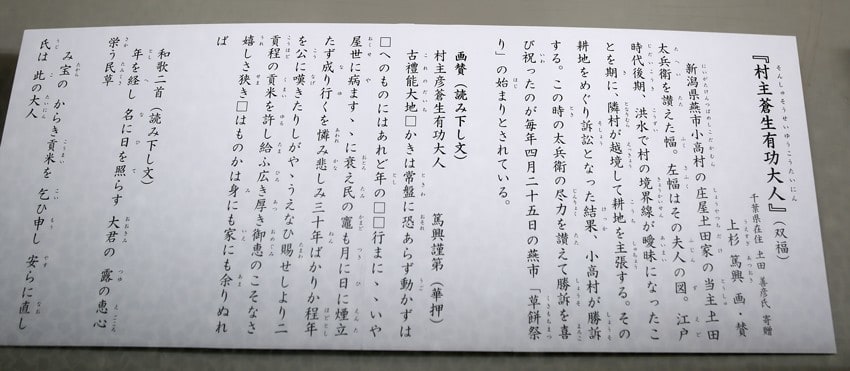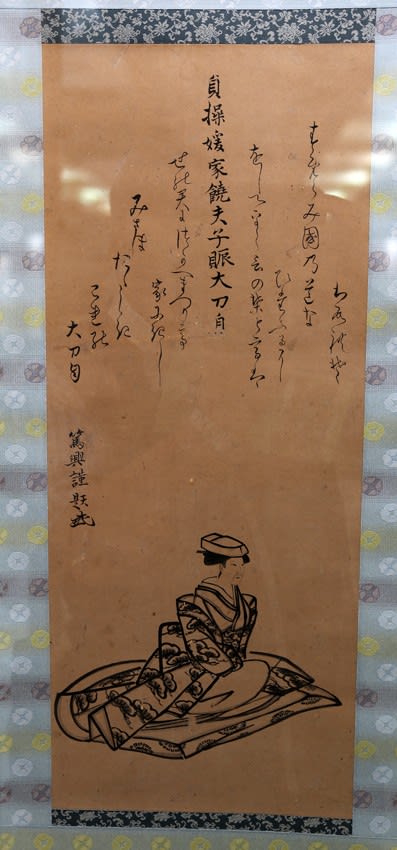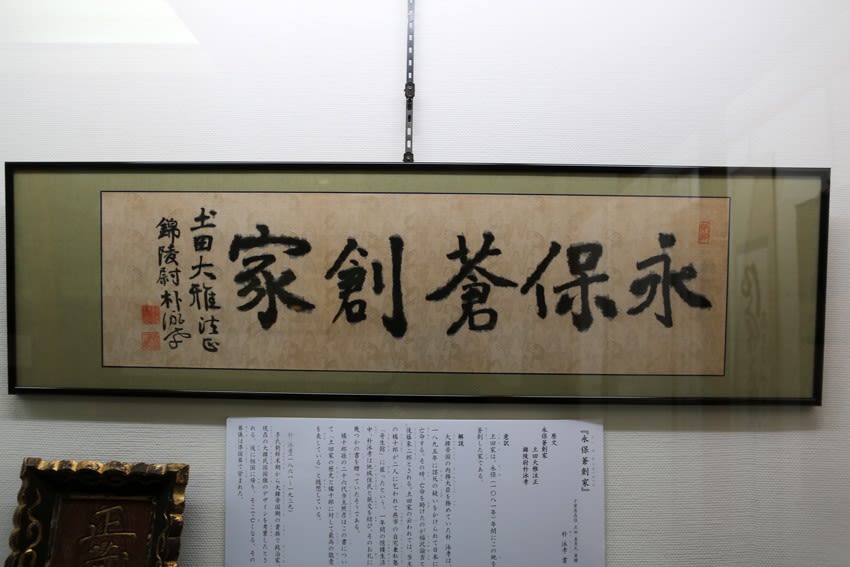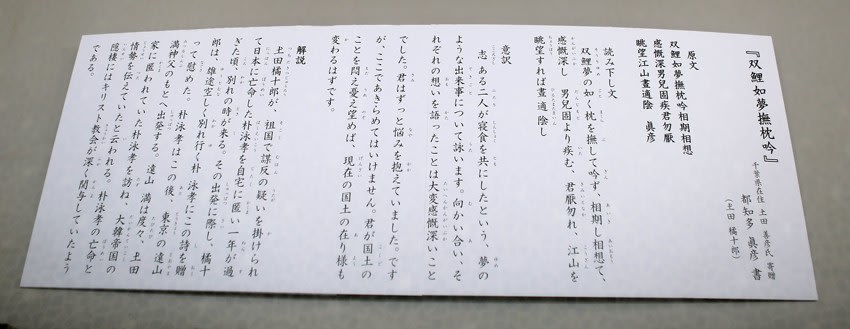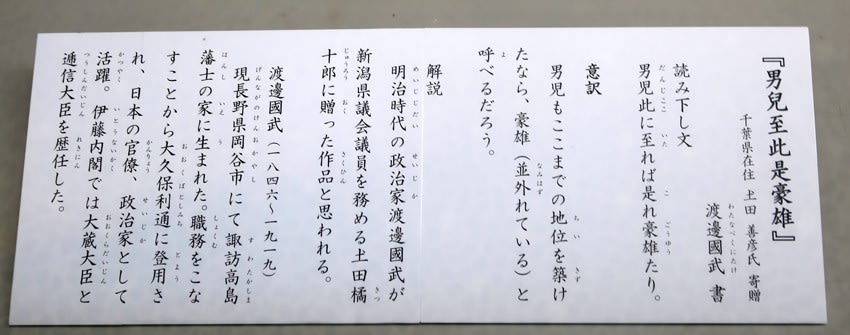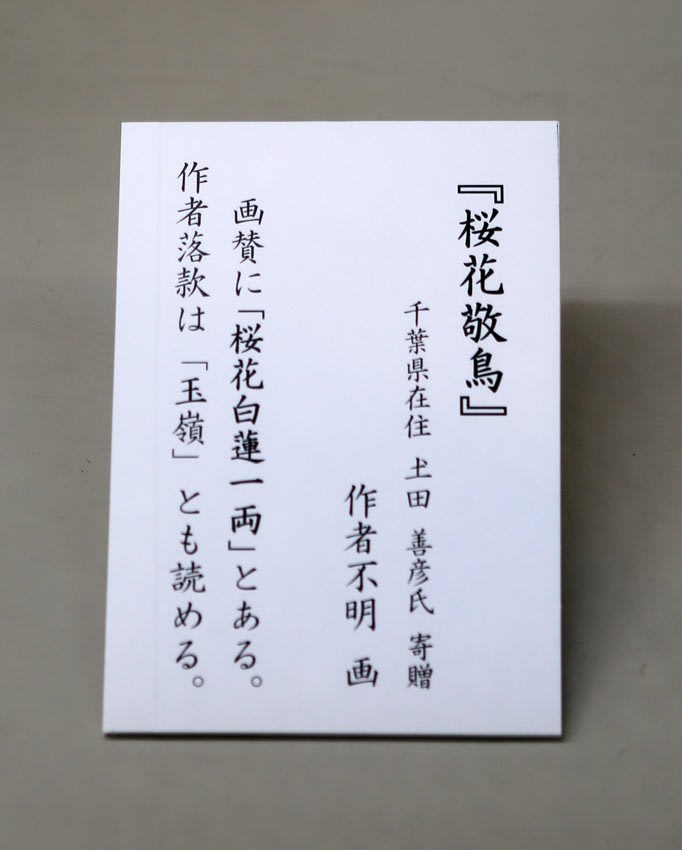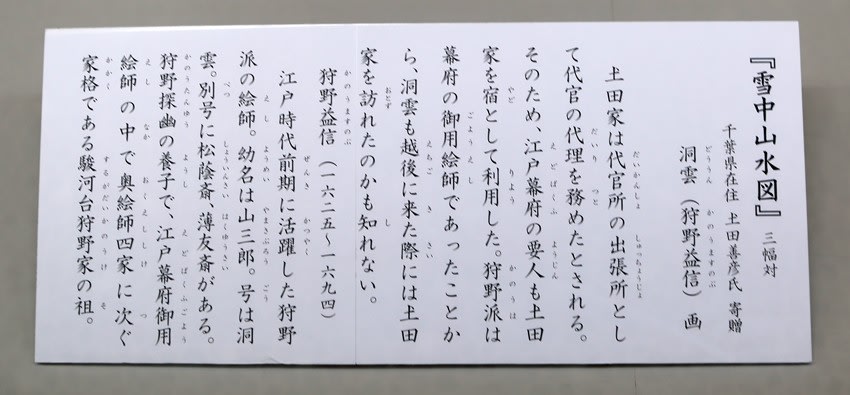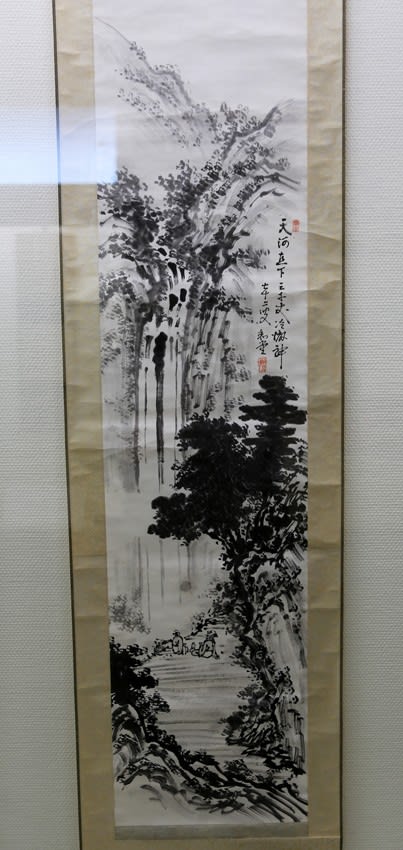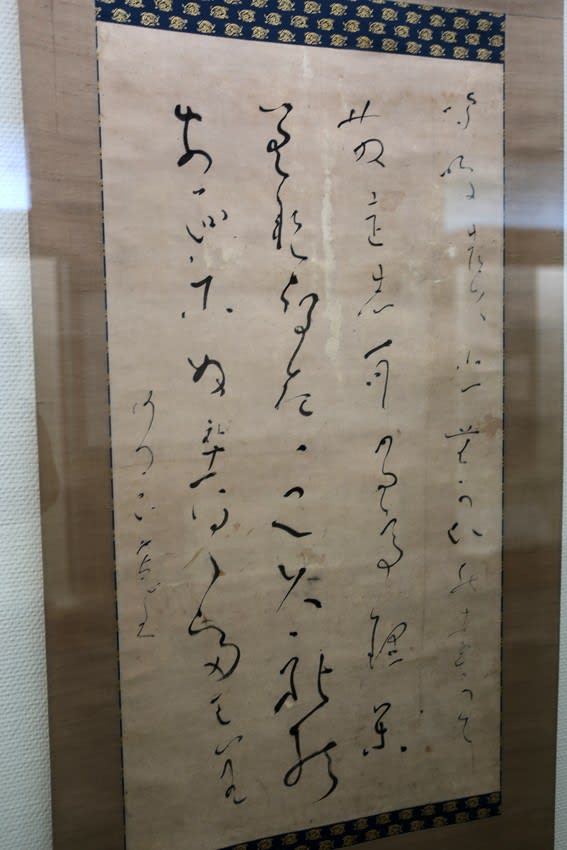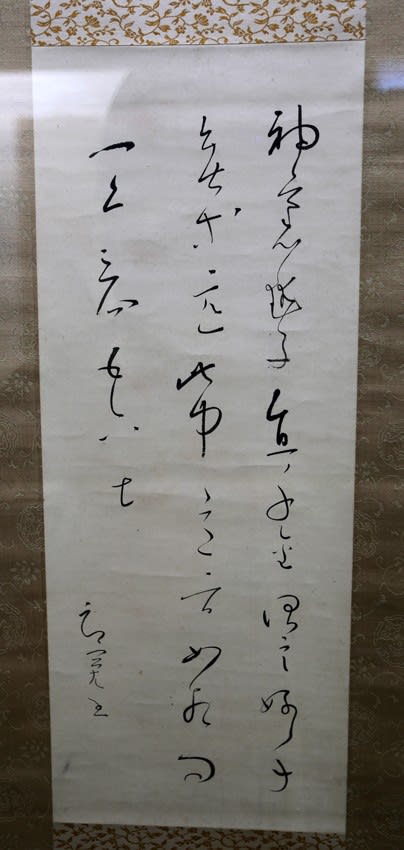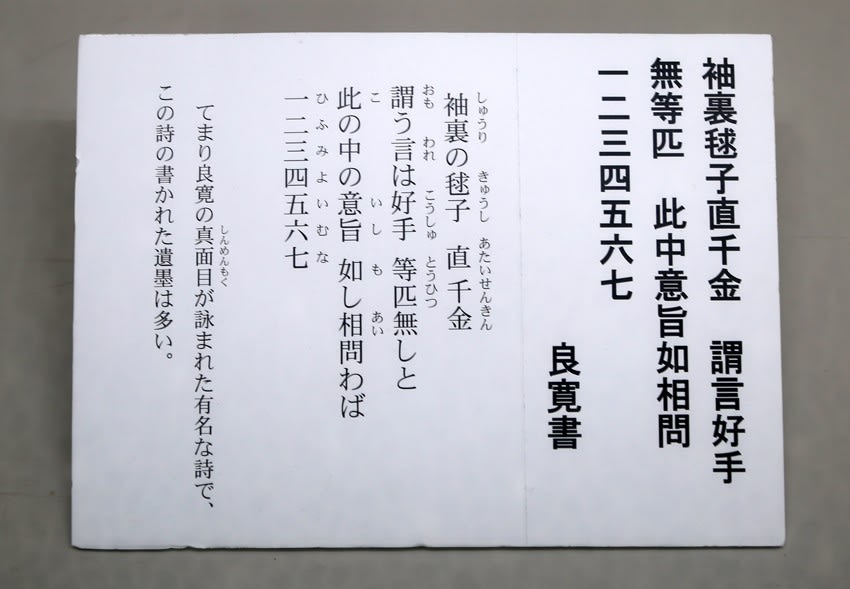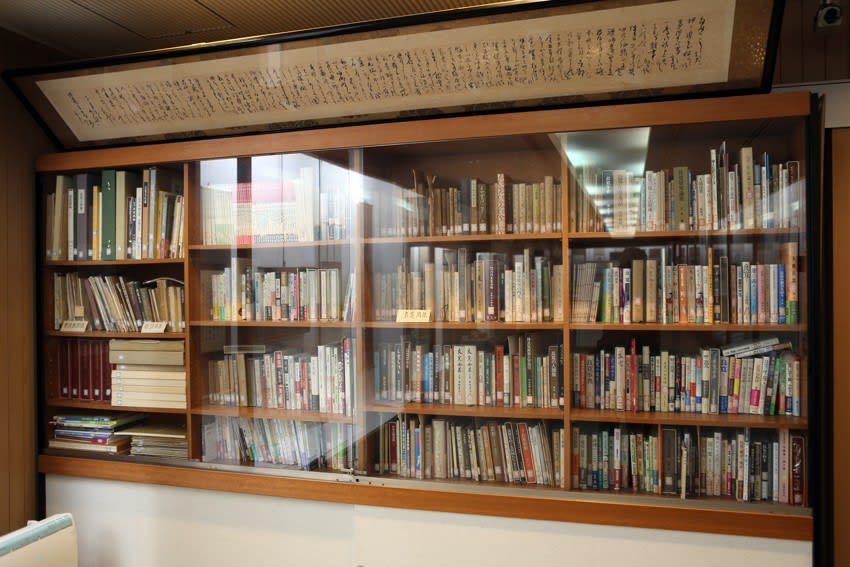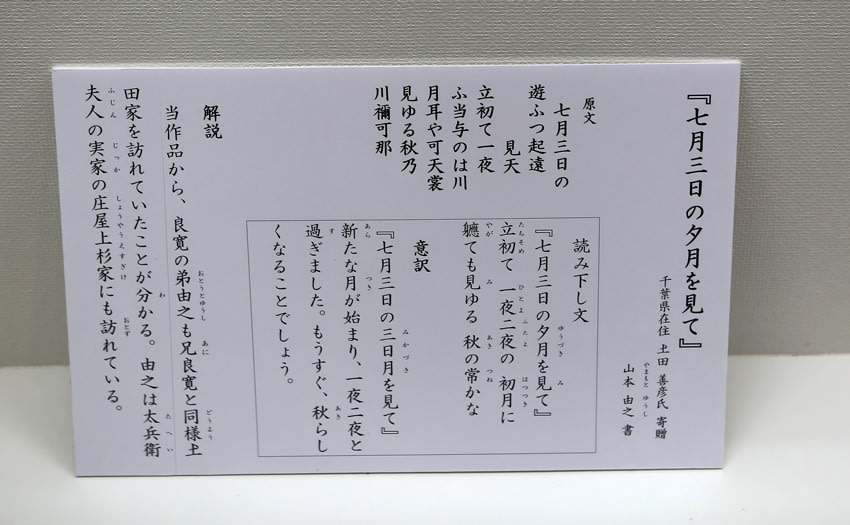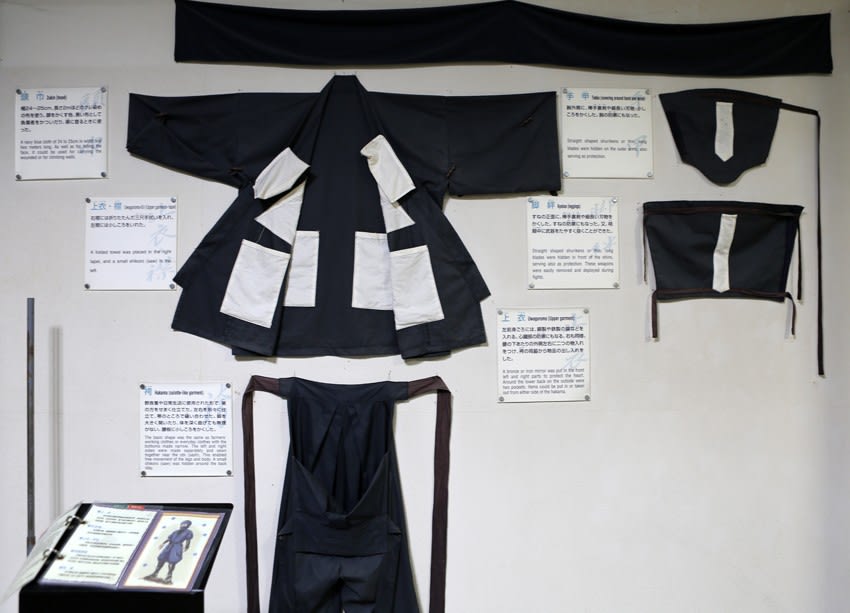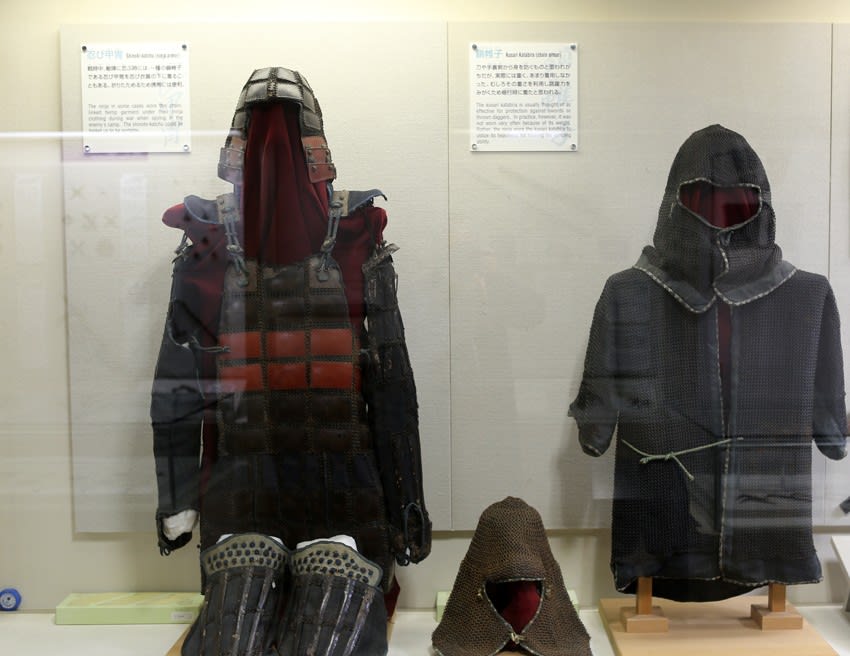砂の美術館・エジプト編 その3
15 ハトシェプスト女王葬祭殿
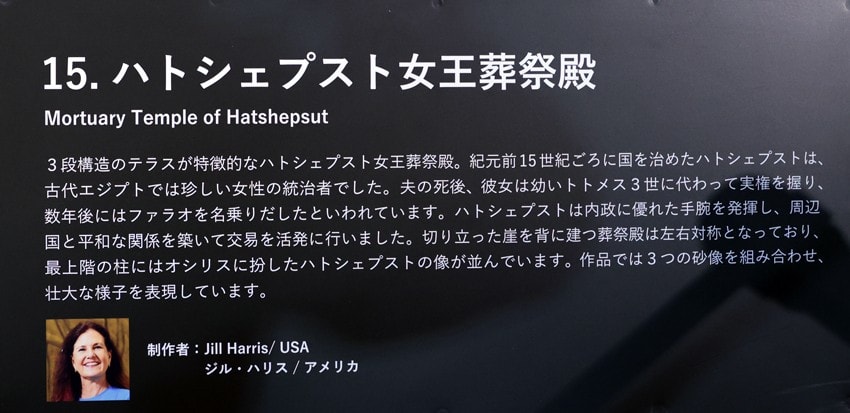

16 古代エジプトの神々
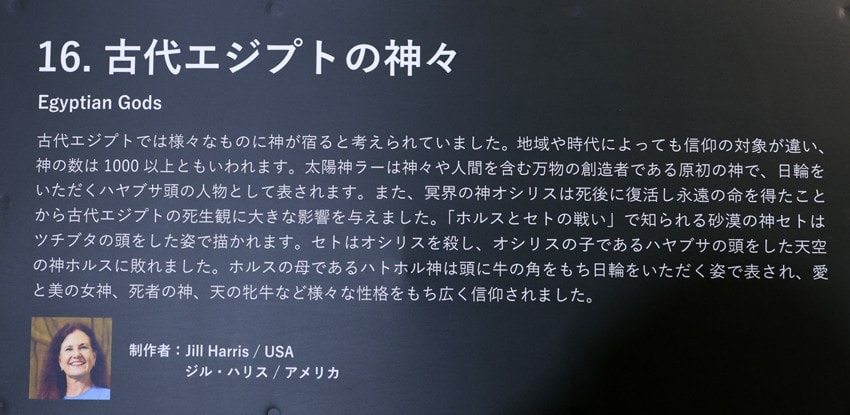

17 クレオパトラ
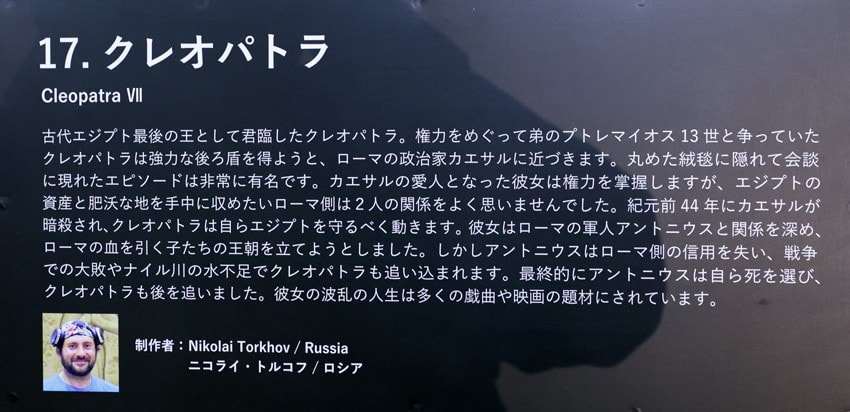



18 イスラムの時代
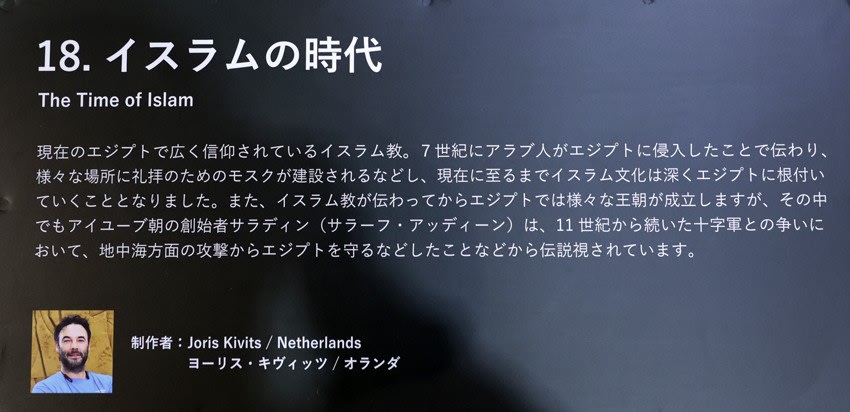



19 ナポレオンのエジプト遠征とロゼッタストーン

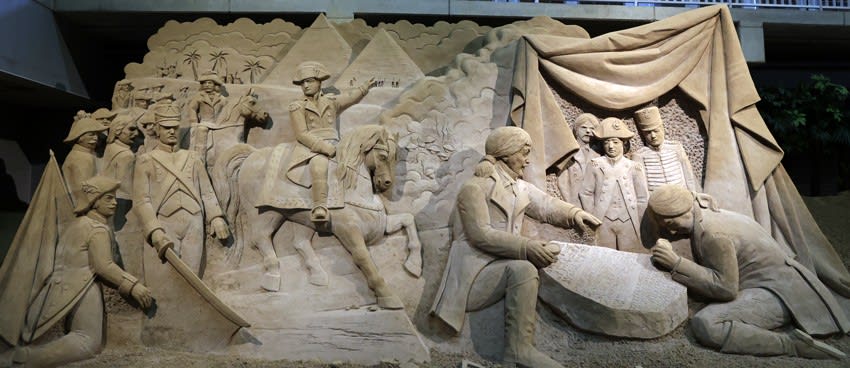
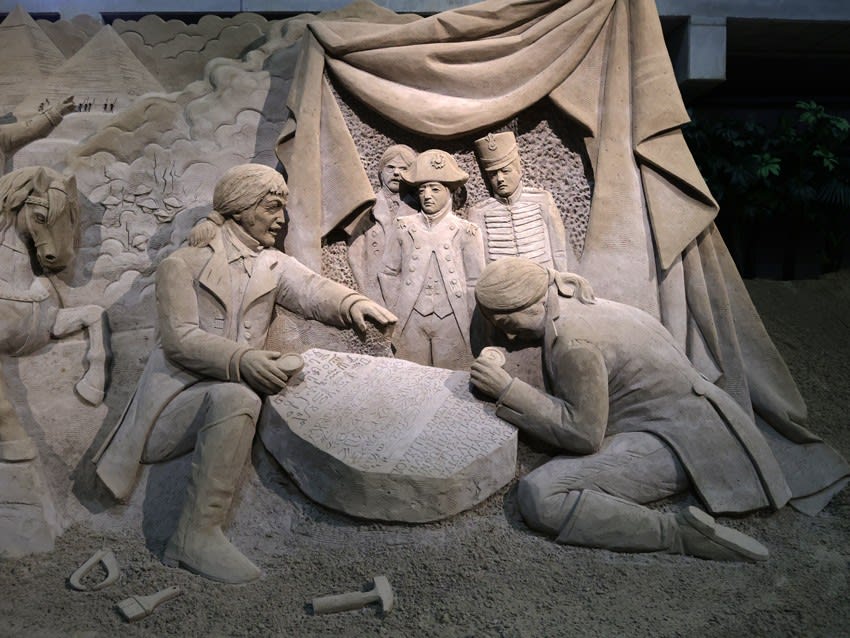
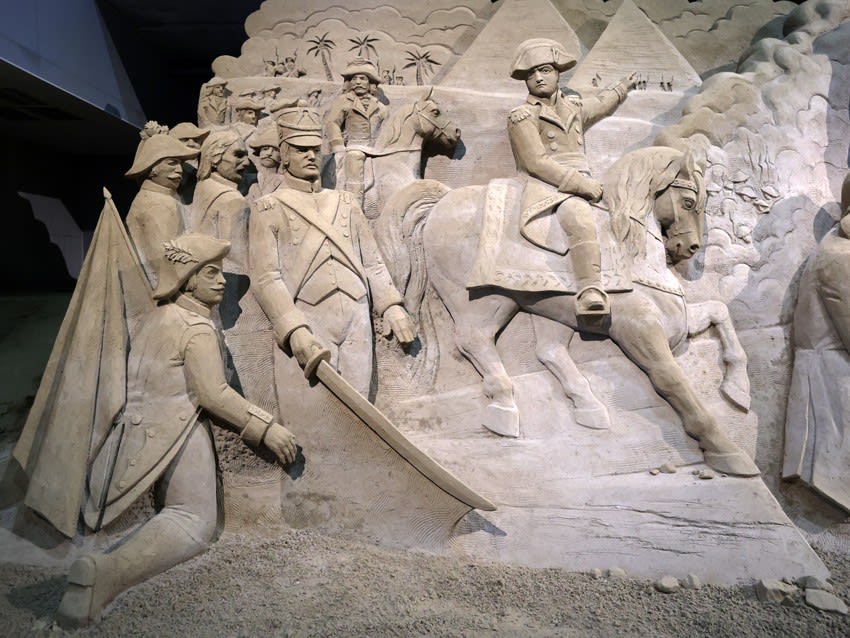
20 バステト




<屋外>
21 ミイラと来世信仰
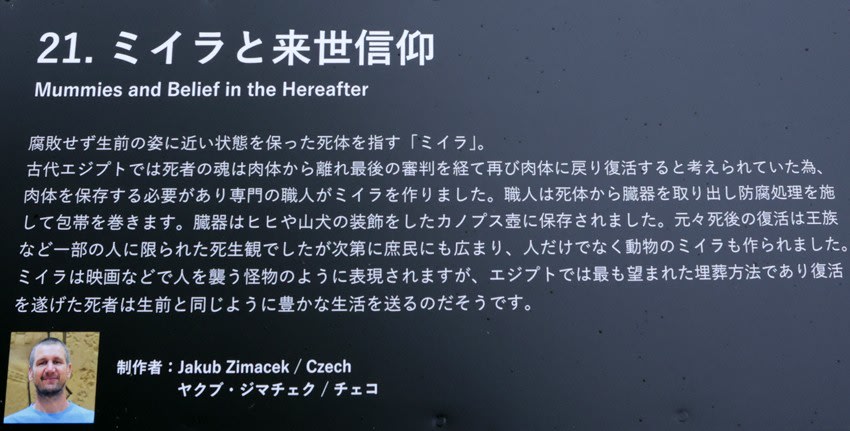



22 ツタンカーメン
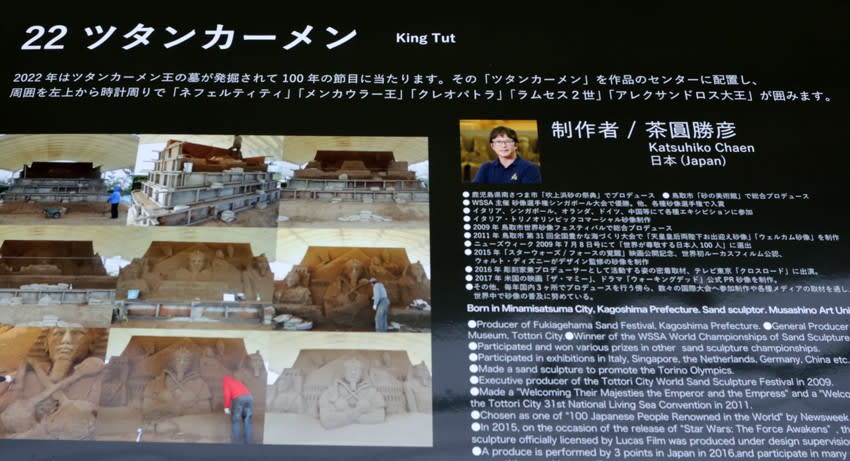


次回に続く
15 ハトシェプスト女王葬祭殿
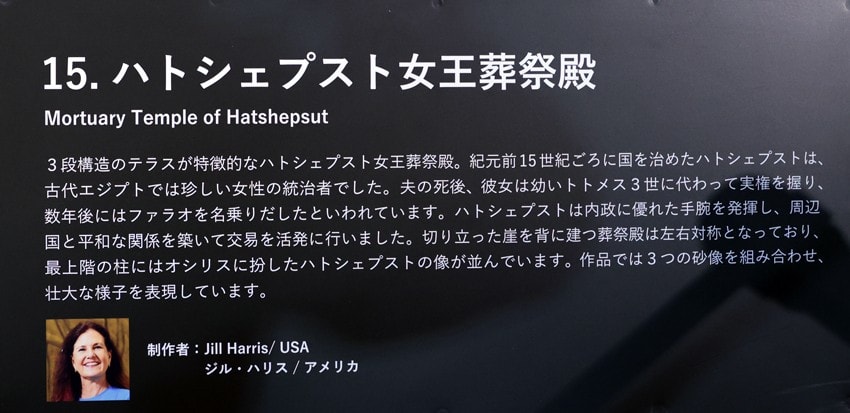

16 古代エジプトの神々
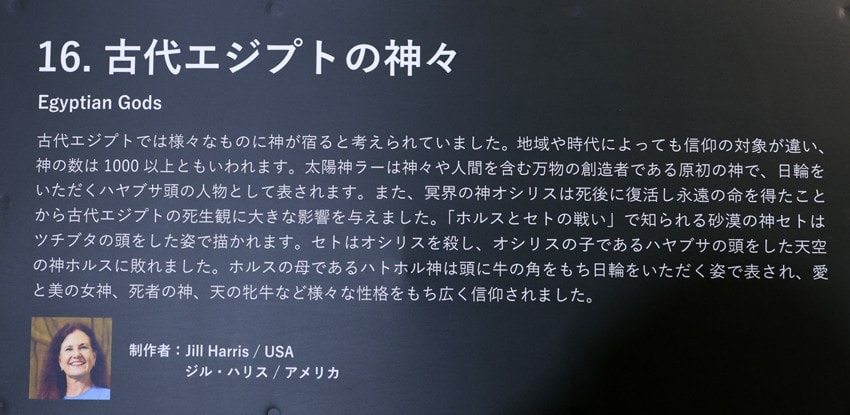

17 クレオパトラ
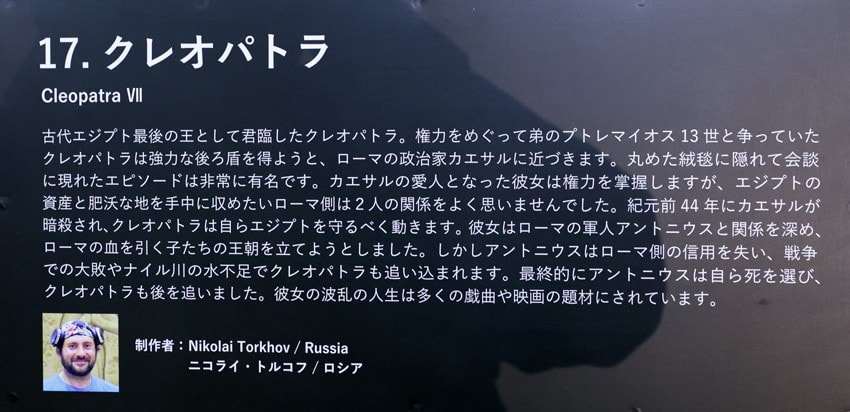



18 イスラムの時代
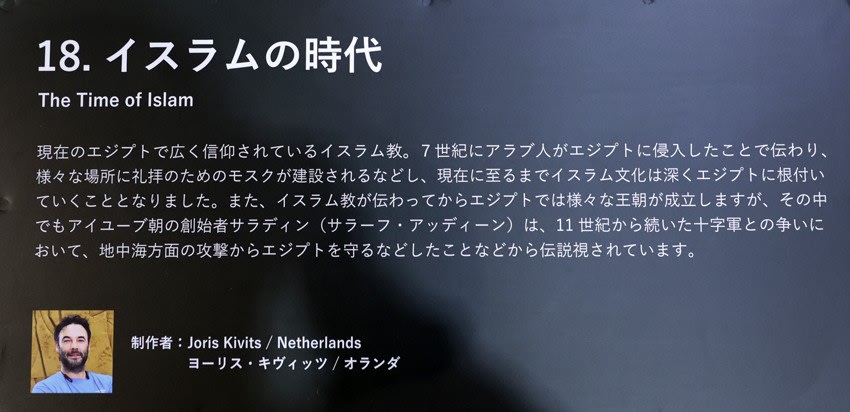



19 ナポレオンのエジプト遠征とロゼッタストーン

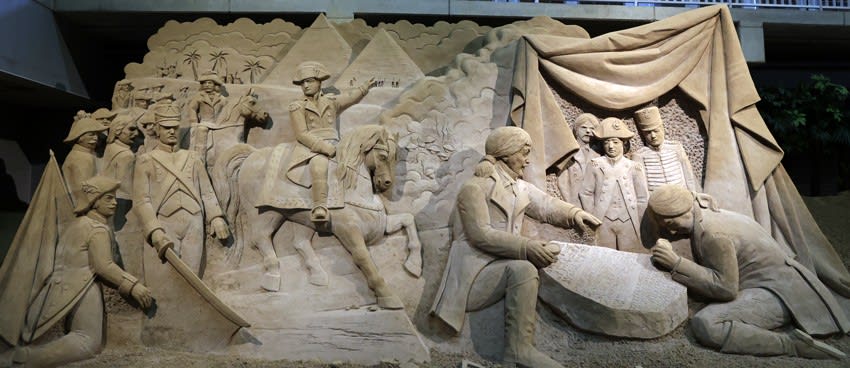
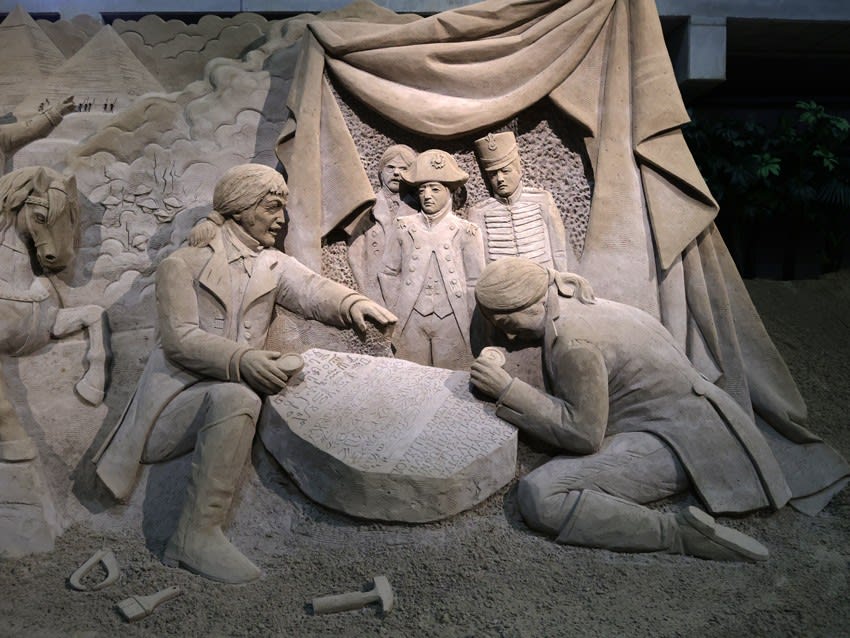
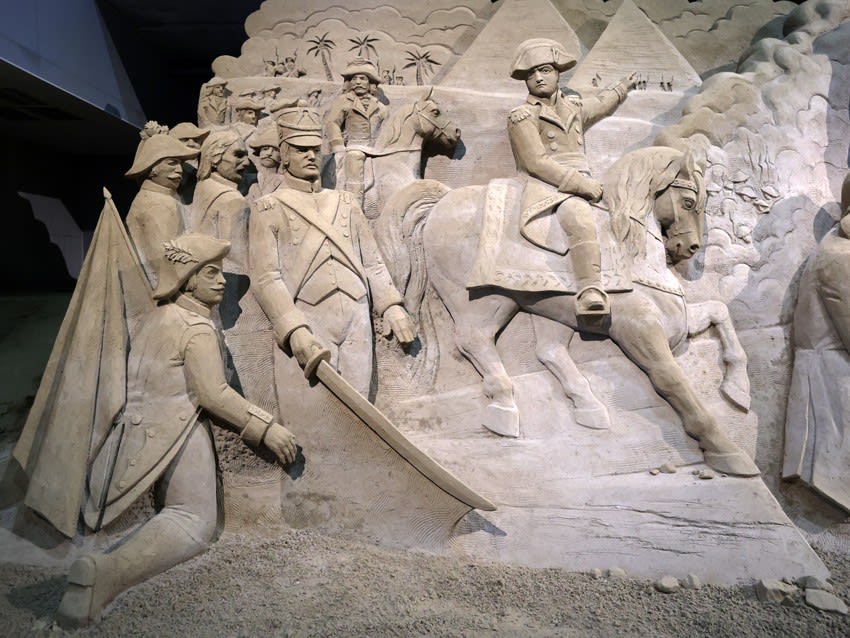
20 バステト




<屋外>
21 ミイラと来世信仰
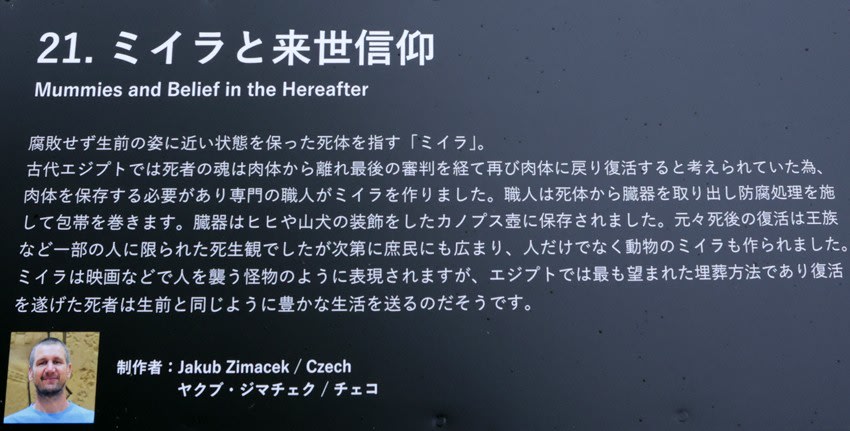



22 ツタンカーメン
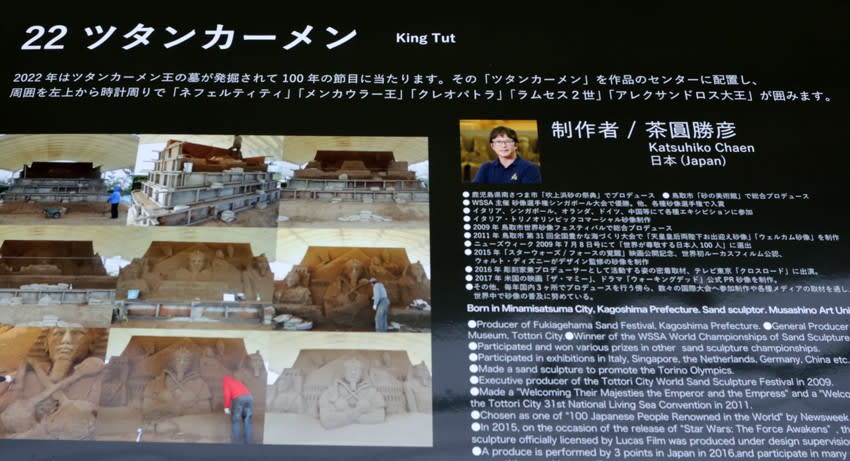


次回に続く