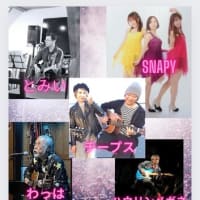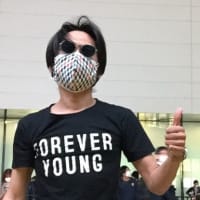お久しぶりです。スターマン★アルチです。
再び、ここで記事を書かせて頂くきっかけが、
チャーリー・ワッツの当然の訃報だったことは、あまりにも悲しい話ですが、
とにかく思いの丈を書かせて頂きますので、お付き合いの程、よろしくお願いいた
します。
ローリング・ストーンズのチャーリー・ワッツが死んだのは8月24日。
早いもので2週間が経とうとしている。
彼が死んで以降、というよりその前後から僕は妙な倦怠感というか、
不思議な感覚に包まれていた。
ロックミュージックを愛する以上、
数々のミュージシャンの死を見届けるのは避けて通れない道で、
特に鮮明に覚えているのは、デヴィッド・ボウイだ。
なにせ僕の名前にも使わせて頂いているぐらい大きな存在ですから。
彼の死を知ったのは、立川へ向かう南北線の電車の中だった。
ネットニュースで彼の死を知った瞬間、僕は思わず座席から立ち上がり、
人目をはばからず泣き出してしまった。
周りからしたら、さぞや迷惑な話だったと思うが、とにかく止まらなかった。
キース・エマーソンが自殺したのは来日公演を控えた暖かい春の日だった。
仕事で静岡へ向かう新幹線の中で僕はそのニュースを知った
(なぜか僕は、そういったニュースを電車の中で知る事が多い)
病気で思うようなプレイが出来ず精神的に病んでいたとはいえ、
「自分から命を絶つことはないのになー」と思いながら、
少し雲が掛かった富士山を見ながら食べた「サブウェイのサンドイッチ」の味を今
も良く覚えている。
他にも、あまりにも多くの愛するミュージシャンの死を見届けてきたが、
いずれにしても一時的な悲しさがあったにしろ、
僕は常に、生きる力を感じていた。少なくとも自分は生きている。
そして、その事実が永遠に続くように思われた。
ただ、今回だけは違った。
チャーリー・ワッツの死を知ったあの日以来、僕はどうも気分が上がらなかった。
このまま、谷底へ転がり落ちていきそうな、なんとも冴えない状態だった。
(Bruce SpringsteenがDownboud trainで歌ったのもこんな気持ちだったのだろう
か)
それぐらい、僕の中でのチャーリー・ワッツ、
そしてローリング・ストーンズは大きな存在だったんだと気づいた。
多くのミュージシャンは年と共に太ったり髪が薄くなったり、声が出なくなった
り、いずれにしても何処か引退した雰囲気が漂っていた。
それは、かつてのイメージを背負い続けることを放棄した無責任な姿にも思えた。
もちろん、それはただの一ロックファンの戯言に過ぎない訳で、
彼らにも家庭があり人生がある。
ただ、チャーリー・ワッツ、そしてローリング・ストーンズは違った。
当然、彼らにも年齢的な衰えはある。
近年のライブ映像を見れば、それは明らかだ。
「老い」が誰もが避けて通れないが、彼らとその他の多くのロックミュージシャン
の違いは、ストーンズのメンバーは皆「現役」であり「現在進行形」であることを
意識し、自分と戦っているということだ。
それが「楽しいこと」なのか「幸せなこと」なのかは本人達にしか分からない。
しかし、体型を維持し、高いパフォーマンスを維持するためにトレーニングをする
のは、非常にアスリート的で、とてもハードなことに決まっている。
特にドラムを1~2時間叩き続けるなんて、若くても厳しいのだから、
どれぐらいチャーリーが努力を続けてきたか、僕なんかはでは想像が出来ない。
富と名声を得たならば、「現役」であることを放棄し、自分に甘えることも出来る
はずなのに、チャーリーはそうしなかった。
それが何故なのかは分からないが、彼が昔と変わらない体型、ルックスで、
シンプルでありながら力強いドラミングを維持し続ける限り、
ロックミュージックのパワーが、今も変わらないことを僕に信じさせてくれてい
た。それがある日、彼の突然の死によって途絶えてしまった。
だからこそ、僕はまるで。10代の頃からの長い魔法から解けたように、
意気消沈していたのだ。
彼のいないストーンズなんて考えられない。
(これに関しては、MASH氏とハウリンメガネ氏が熱く語っているので、ぜひ読んでください) ↓
https://blog.goo.ne.jp/12mash/c/f4bb70881178099efe2e09df9fa43374
僕は何をするでもなく、床に寝転んで天井を見ていた。
音楽を聴くでも、本を読むでもない。外は夏の蒸し暑い日だったが、
カーテンは閉め切っていた。時々、近くを通る電車の音が聞こえる。
今まで信じていたロックミュージックから得たエネルギーは無限に思えたが、
その母体がなくなると、こうも力を失うのか。
僕は所詮、ただの受け身の人間だったのだろうか。
このままではまずいと思った。
とにかく外へ出ようと思った。
つい最近手に入れたばかりの
マウンテンバイク「キャノンデール SUPER V400」に乗り、
何処へ行くでもなく走り始めた。
ふと海を見に行こうと思った。
自分の住んでいる藤沢の海は、
コロナ禍のこのご時世ではどうも行きづらい。
僕は横浜の海を見に行くことにした。詳しい道順などは割愛するが、
真夏の炎天下を自転車で片道20kmを漕ぐのは中々ハードだ。
そして、途中には急な登り坂もある。
最初は、疲れたら途中で引き返そう、ぐらいの気持ちだったが、
気づいたら、身体中の力を込めて、全力でペダルを漕ぐ自分がいた。
頭の中では、常にチャーリーのことを考えていた。
横浜の元町の商店街を抜け、山手へ続く急な坂道を上った。
途中でカトリックの山手教会で聖母マリア像を見た。
どこか心が洗われた気持ちになった。
そのまま山手本通りを抜け、とうとう港の見える丘公園に到着した。
そこからは横浜ベイブリッジや、慌ただしく行きかう車や人々、
停泊しているクルーズ船などが見えた。そういえば近くには外国人墓地もある。
チャーリーも今頃はイギリスの何処かの墓の中なのだろうか。
「ああ、皆生きているんだな」と思った。
そして、気づいたら僕の心に長く居座っていた
どんよりとした倦怠感が消えていることに気づいた。
ロックは、スタイルでもファッションでも無い。
(セックス、ドラッグ&なんとか的な)
自分の信じ、自分の力で生き抜くエネルギーこそ、ロックなんだ。
そして、それは常に自分でなく、相手に向いていなければならない。
そういった意味での「ロックであること」を僕はいつの間にか忘れていた。
それは、チャーリーの死以前から少しずつ感じ始めていた。
チャーリーの死によって、どん底に落ち、そこで僕は気づいた。
「今の自分が全くロックではない」と言う事に。
ロックミュージックの無限の可能性を信じ、
追い続けていた10代の頃の僕が一番嫌っていた、
「絶対にあんな大人になるものか」と思っていた人間になっていた。
それこそが、自分を覆っていた謎の倦怠感の正体だと気づいた。
僕は急に嬉しくなった。山手からみなとみらいへ向かう坂道を、
何とも晴れやかな気持ちで、文字通り「転がる石のように」自転車で滑り降りた。
ロックミュージックは魔法じゃない。
それによって自分の人生が変わるとか、世界が変わるとか・・・
そんな都合の良いものじゃない。
結局は何かを変えるのは自分自身なのだから。
ロックミュージックは、そのきっかけにしか過ぎない。
チャーリー・ワッツは、一発のスネアの音で、
この人生がいかにハードでシリアスなのか、
そして、彼がその人生を生き抜くために
いかに努力し続けていたかを僕らに教えてくれているみたいだ。
「私がやったのだから、君もやりなさい」
チャーリーが死んでから、ストーンズの演奏を聴く度に、
彼のそんな声が聞こえてくるようだ。
さて、そんなわけで、チャーリーが死んでも人生は続く。
これほど素晴らしいことはない。そして、彼の死をきっかけに、
少しでもローリング・ストーンズの音楽を聴く人が増えればと思う。
ストーンズの音楽が必聴なのはもちろんですが、
僕からは敢えて、チャーリーのソロアルバムから一枚ご紹介しましょう。
1991年に発表の「From One Charlie」
こちらはThe Charlie Watts Quintet 名義のアルバムで、
「クインテット」ということから分かるように、ジャズアルバムです。
元々ジャズ志向が強く、1964年には敬愛するサックス奏者、
「チャーリー・パーカー」の生涯を描いた絵本「Ode To A Highflying Bird」を発
表している程です。
このアルバムは、その絵本の復刻にあたり制作されたもので、
チャーリー・パーカーのオリジナルやサックス担当のピーター・キングによるオリ
ジナル曲で構成されています。
チャーリー・ワッツのドラムは決して目立つことはありませんが、
終始リラックスした、気持ちの良いスイング感でバンドを支えています。
「ローリング・ストーンズのチャーリー」でなく、
「ジャズの入門編」としてもおススメの一枚!
ちなみに絵本の方も、簡単な英語と可愛いイラストでおススメです。
とにかく、これからも僕は、転がり続けようと思います。
ありがとうチャーリー!
《 スターマン★アルチ 筆 》