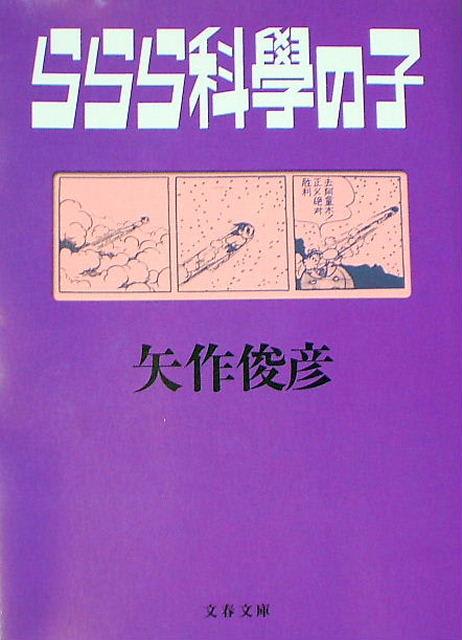 昔、ALTとなぜか文革の話になる。
昔、ALTとなぜか文革の話になる。
「ええっとぉ、文化・大・革命だから……グレイト・カルチュラル・レボリューションかな。まさかね。」
「いいえ、当たってます。The Great Cultural Revolutionです。」
「ほお!?」
まず、このコラムを読んでもらおう。
湯浅学さんのコミック教養講座
少年レボリューション/ダディ・グース著
六〇年代末から七〇年代初めに世に送り出された作品、繰り広げられた言動は、現在も折に触れて、その頃を実体験して知る者からその子どもたちに至るまで、多くの人に影響/衝撃/感動を与えている。
全共闘世代、と一括(くく)りにしようったってそうはいくか、という気骨や意地や強引な説得力を、当時いわゆる“若者”だった人々は持っている。少なくともかつては多くの“全共闘世代”がそう感じさせた。
本書の作者は六八年に十七歳でデビューし、七〇年代中頃、すうっと漫画界から消えた。作品の衝撃は一部で語り継がれて来た。語られるばかりで再読が難しかったが、三十数年ぶりに書店の棚に蘇(よみがえ)っていた。
アメリカン・コミック的描線でドメスティックな“闘争”が描き出される。政治行動がスラップスティック(ドタバタ喜劇)と化す。東大闘争が『マクベス』を模して戯作(げさく)化された大作やゴダール風恋愛ドラマ、日米安保喜劇もある。もじりやサンプリング(引用)が乱舞する快感。月光仮面と佐藤栄作とスヌーピーとその他大勢が縦横無尽に合唱する混沌(こんとん)のオペラが聞こえる。“革命”という言葉に(具体性はなくとも)熱意があった時代に、見る者の心を撫(な)で斬(ぎ)りにして疾駆した。物騒な風が画面から今も吹きつけてくる。
この“革命的漫画力”はむしろ、“気分はいつも戦争”な今だからこそ効く。 (評論家)
……こーんなオシャレな書評があるのか、と思った。朝日新聞の若者向け読書ガイドなのだが、わたしにはとてもマネができない。なぜなら、この書評のなかに一言もふれられていないことがこのコラムのキモだからだ。
その、一度もふれられていない事実とは、ダディ・グースという幻の漫画家こそ、FM東京(今のTOKYO FM)で、深夜直前にオンエアーされていたマンハッタン・オプの脚本を書き(光文社文庫のシリーズはわたしの宝物……現在はソフトバンク文庫で復刊。さっそく買いました)、「神様のピンチヒッター」や「さまよう薔薇のように」などのハードボイルド小説でわたしを熱狂させ、週刊ポストの「新ニッポン百景」で無駄な公共事業を斬りまくり、この「ららら科學の子」で三島由紀夫賞をゲットした矢作俊彦のことであり、彼が大友克洋と組んでかっとばした大ヒット漫画が「気分はもう戦争」(双葉社)なのだ。ついでに言ってしまえば、この頃のダディ=矢作と、「ららら~」は一直線につながっている。だからこれは「ららら科學の子」の書評としても機能しているのである。おそるべき確信犯。うまいなあ。
 大学紛争のさなかに文革まっ盛りの中国へ逃亡した男が、蛇頭の手引きで三十年ぶりに日本へ帰ってくる……作中で何度か明かされるように、これは浦島太郎やリップ・ヴァン・ウィンクルのもじりである。描写がうまいったら。
大学紛争のさなかに文革まっ盛りの中国へ逃亡した男が、蛇頭の手引きで三十年ぶりに日本へ帰ってくる……作中で何度か明かされるように、これは浦島太郎やリップ・ヴァン・ウィンクルのもじりである。描写がうまいったら。
「煙草の自動販売機は、千円札が使えるようだった。書かれてある文字を全部読んだ。ちゃんと釣り銭も出る。」
「大きな白黒写真の埴谷雄高だった。平積みになった本のてっぺんでこちらを凝視していた。あの長い長い小説は完結したのだろうか。作家は当然、老けているはずだが、どの程度、老けたのかまったく判らなかった。ずっと以前からこんな老人だったような気がした。それは銀座の街並みと同じだった。」
「明け方、昔のドキュメンタリーの再放送で、彼は佐藤栄作がノーベル平和賞をとったことを知った。思わずベッドの上に跳ね起きた。たしかにあの首相だった。沖縄返還と引き換えに、アメリカに日本を売り渡そうとしていた男だった。(略)授賞の理由は、沖縄を平和裡に取り戻したことだった。一国のとても地域的なできごとに、なぜ国際的な評価が与えられたか判らなかった」
浦島太郎だからこそ見えてくるものを、これでもかと叩きつけてくる。
そしてそれ以上に、故郷とは何か、竜宮とは何処なのかを問いかける物語でもある。ラストのスマートさは比類がない。ぜひっ!
 第一話はこちら。
第一話はこちら。 ここで活きてくるのが実際の隊士たちと同世代の連中を起用したキャスティングだ。
ここで活きてくるのが実際の隊士たちと同世代の連中を起用したキャスティングだ。 









 2004年9月まで、わたしはこの「新選組!」をリアルタイムでほぼすべて見ていた。これはわれながら(いくら
2004年9月まで、わたしはこの「新選組!」をリアルタイムでほぼすべて見ていた。これはわれながら(いくら 彼が毎週朝日新聞に載せているエッセイによれば、大河を一年間の長期に考えるから大変なのであって、13本のドラマを4クール書けばいいのだと考えることにしているらしい。
彼が毎週朝日新聞に載せているエッセイによれば、大河を一年間の長期に考えるから大変なのであって、13本のドラマを4クール書けばいいのだと考えることにしているらしい。 ここで告白。わたしが生涯を通じて愛する女優がいることを。それはフェイ・ダナウェイ。
ここで告白。わたしが生涯を通じて愛する女優がいることを。それはフェイ・ダナウェイ。 ……08年現在、ポランスキーは巨匠となり、ニコルソンはアカデミー賞授賞式にかかせない“ハリウッドインサイダー”となったようだ。そのことは純粋にめでたいのだけれど(本当に、そう思っています)、製作者のロバート・タウンだけはねぇ。まもなく彼の著作「くたばれ!ハリウッド」も特集します。
……08年現在、ポランスキーは巨匠となり、ニコルソンはアカデミー賞授賞式にかかせない“ハリウッドインサイダー”となったようだ。そのことは純粋にめでたいのだけれど(本当に、そう思っています)、製作者のロバート・タウンだけはねぇ。まもなく彼の著作「くたばれ!ハリウッド」も特集します。 高一のとき、クラスメイトが興奮しながら語った映画は、日テレ「
高一のとき、クラスメイトが興奮しながら語った映画は、日テレ「 ページ13
ページ13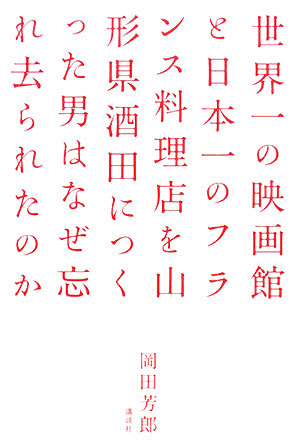 ページ12
ページ12
 山形県人としていろいろと考えさせられる部分も。矢口が標準語で書いた脚本を、フジテレビのわれらが
山形県人としていろいろと考えさせられる部分も。矢口が標準語で書いた脚本を、フジテレビのわれらが 原正人、という名前を、おそらくは映画のエンドクレジットで見たことのある人は多いと思う。洋画配給会社ヘラルドの最強の宣伝部を率い、「エマニエル夫人」「カサンドラ・クロス」「バラキ」など“
原正人、という名前を、おそらくは映画のエンドクレジットで見たことのある人は多いと思う。洋画配給会社ヘラルドの最強の宣伝部を率い、「エマニエル夫人」「カサンドラ・クロス」「バラキ」など“ ・「小さな恋のメロディ」はイギリス本国では劇場公開されず、テレビのみで放映された。
・「小さな恋のメロディ」はイギリス本国では劇場公開されず、テレビのみで放映された。 自己憐憫・自己愛・自己中心的……主人公はこう形容するしかない。とにかくしょーもないヤツなのである。中古レコードショップを経営しながら、女から女へ渡り歩き、ガールフレンドから別れを告げられると逆上し、自分のどこが悪いのかを昔の女たちにききにいく厚顔さ(現代版「舞踏会の手帖」)。自分の浮気は棚に上げ、彼女が他の男と寝たことをいつまでも責め続ける……えーと、開き直るようで申し訳ないが
自己憐憫・自己愛・自己中心的……主人公はこう形容するしかない。とにかくしょーもないヤツなのである。中古レコードショップを経営しながら、女から女へ渡り歩き、ガールフレンドから別れを告げられると逆上し、自分のどこが悪いのかを昔の女たちにききにいく厚顔さ(現代版「舞踏会の手帖」)。自分の浮気は棚に上げ、彼女が他の男と寝たことをいつまでも責め続ける……えーと、開き直るようで申し訳ないが ※もちろんこの映画の最大の魅力は音楽にある。娘へのプレゼントとして「心の愛」を買いに来た客に「娘さんはこんな駄作聴かないにきまってる!」と決めつけたJ.ブラックには笑ったが、それでもスティービー・ワンダーはサントラにちゃんと入っている。大人である。それと、ちょっと
※もちろんこの映画の最大の魅力は音楽にある。娘へのプレゼントとして「心の愛」を買いに来た客に「娘さんはこんな駄作聴かないにきまってる!」と決めつけたJ.ブラックには笑ったが、それでもスティービー・ワンダーはサントラにちゃんと入っている。大人である。それと、ちょっと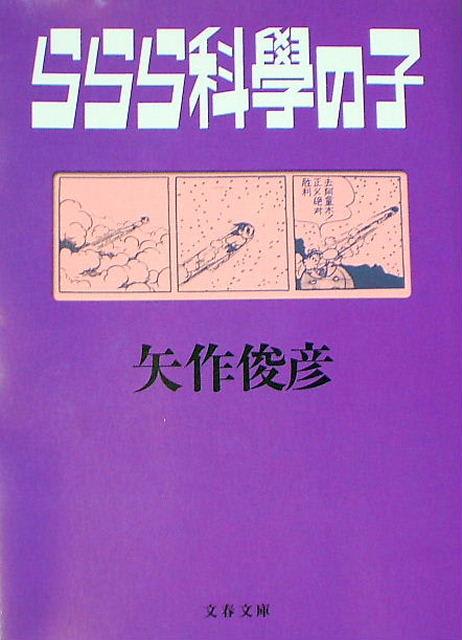 昔、ALTとなぜか文革の話になる。
昔、ALTとなぜか文革の話になる。 大学紛争のさなかに文革まっ盛りの中国へ逃亡した男が、蛇頭の手引きで三十年ぶりに日本へ帰ってくる……作中で何度か明かされるように、これは浦島太郎やリップ・ヴァン・ウィンクルのもじりである。描写がうまいったら。
大学紛争のさなかに文革まっ盛りの中国へ逃亡した男が、蛇頭の手引きで三十年ぶりに日本へ帰ってくる……作中で何度か明かされるように、これは浦島太郎やリップ・ヴァン・ウィンクルのもじりである。描写がうまいったら。




