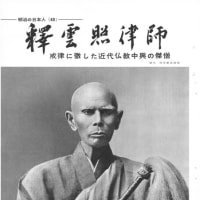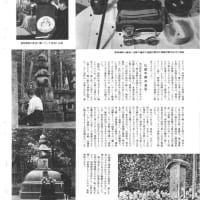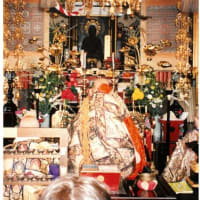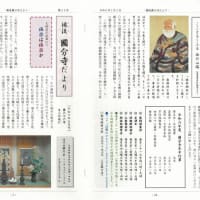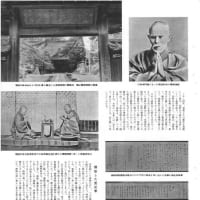(大法輪誌平成十三年八月号掲載)
前回は、紀元前四八〇年頃お釈迦様が中インド北部のクシナーラーで亡くなられた後、ただちに師の遺された教えをその後の依りどころとして確立すべく、五〇〇人の阿羅漢によって仏典の結集(編集)が行われたところまでを述べました。
お釈迦様の誕生されたルンビニー、さとりを開かれたブッダガヤ、初転法輪の地サールナート、そしてクシナーラーは、その後、四大霊場として仏塔が建てられ、お釈迦様を慕い信仰あるものたちの巡礼の地として栄えたということです。
これら四カ所に見られるように、当時の仏教はガンジス河中流域を中心として中インドに広まったに過ぎなかったのですが、次第に西方のマツラーや南方のウッジェーニーなどに伝道がすすめられていきました。
今回は、仏教教団がたくさんの部派に分かれていく部派仏教の時代について述べてみようと思います。
教団の根本分裂
仏典結集によってまとめられた教法と戒律を、お釈迦様在世当時と変わらず大切に護持していた仏教僧団も、仏滅後一〇〇年余りの頃、戒律に関する解釈に対立が生まれていきました。
いかなる食物も蓄えることを許さなかったのに対して塩は蓄えることを認める、正午までと決められた食事の時間を少しのばす、また、お金を布施として受け取ってもよいなどといった、戒律上の十か条の新しい解釈を求める人たちが現れました。今日ごく一部を除いて、どの国のお坊さんもお金を持ち生活している訳ですが、当時はお金に触れることも禁じられていました。
こうした機運に対し、そのころ西方や南方に伝道していた上座に座る長老たちは、これまで通り厳格に教えを守っていくべきだと考え、七〇〇人の長老がヴェーサーリーに会合いたしました。そして、十事と言われる先の解釈を非法として、再度教法と戒律の合誦(再確認)がなされました。これを第二結集と言っています。
これに誘発され、変革を求める主に中インドのお坊さんたちは、なんと一万人ものお坊さんを集め別の結集を行い、それまでの僧団からの離脱を宣言してしまいました。
こうしてお釈迦様没後一〇〇年にして、教団が二つに分裂することになりました。これを根本分裂といい、上座の長老たちを支持する保守派は上座部、変革派は大衆部を名のることになりました。
アショーカ王の偉業
教団の根本分裂があって五〇年ばかりがたった頃、遠くギリシャから兵を興し、インドの地へ侵攻を企てる一大勢力がありました。ペルシャ全土を併合し、パルティアを征服したアレクサンドロス大王は、紀元前三二六年にインダス河を越え、タキシラという商業とバラモンの学問の場として栄えていた都城に入ったとされています。
しかしながら、その後インドの雨期や象軍との戦いに疲弊し、また既にマケドニアを出て一〇年もの歳月が過ぎていたこともあり、それ以上インド国内に攻め入ることはありませんでした。そして、そのアレクサンドロスの勇姿を目撃したインドの人々の中に、のちに西北インドから兵を挙げマガダ地方に進攻し、インドを統一する若き日のチャンドラグプタの姿がありました。
彼はアレクサンドロスの成功をインドで成し遂げるべく、西北インドに侵入していたギリシャ勢を一掃してマウリヤ王朝(前三一七年~前一八〇年頃)を興し、インド南端部を除く全インド最初の統一王となりました。
チャンドラグプタの孫で第三世アショーカ王(在位前二六八年~二三二年)の時、マウリア王朝は最盛期を迎えることになります。そして、彼こそは転輪聖王(世界を統一する理想の法王)と称えられ、武力による政治を改めて仏教を始め宗教を保護し、仏教の教えに基づいた政治を行ったと言われています。
また、仏教が一つの地方宗教から全インドに、さらには世界へ伝播される礎を築く大恩人となりました。日本でいえば仏教伝来間もなくに現れた聖徳太子のような存在でありました。
アショーカ王は元は性格が凶暴で、王位争奪のために多くの兄弟を殺し、凄惨な戦闘を繰り返したと言われています。が、即位してのち仏教に帰依し、インド全土を手中に収める戦場で数十万にのぼる死傷者を出した闘いを恥じて改心すると、熱烈な仏教信奉者となりました。多くの精舎や仏塔を建立し、仏跡や仏弟子の遺跡を巡拝、大規模な仏僧供養を行ったということです。
こうしてインド各地に仏教を知らしめ、さらにはスリランカなどの近隣諸国や、遠くエジプト、シリア、マケドニアなどにも仏教使節を派遣し、キリストも誕生せざるこの時代に、早くも西方世界に仏教の存在を知らしめたということです。また、国内至る所に人と獣のための療院が設けられ、薬草や果樹を植え、井泉を拓くなど、アショーカ王は幾多の福祉事業にも奉仕したと言われています。
アショーカ王のこれら数々の業績は、王がインド各地の石柱や岩に、その地方の言葉で法勅を刻み民衆に公布したものが、近代になって発掘され明らかになったものです。これを「アショーカの刻文」といい、最も多く発見されている石柱碑文は、高さ一〇~一五mの砂岩を直径五〇~七〇㎝の円柱状に建立し、その頭部には獅子頭が飾られていました。
有名なサールナート出土の獅子頭は四つの法輪の上に四頭の獅子が背中合わせに座った美麗なもので、現在インドの国章ともなっています。それら碑文の内容は、仏法の趣旨を伝えたり、王自身の仏教への信仰を語ったもの、お釈迦様の教えに従って殺生を禁ずるなど善業を勧める旨を記されたものなど。またサールナートにある石柱には、仏教教団の分派行動について戒める法勅が刻まれているということです。
上座仏教の伝播
今日スリランカを始めミャンマー、タイなど南アジア、東南アジアの各国で行われている上座仏教は、このアショーカ王が派遣した仏教使節によって伝えられた仏教が、その起源となっています。アショーカ王の王子マヒンダ長老によって仏舎利とともにスリランカにもたらされたと言われる仏教は、根本分裂の際にお釈迦様の教えを厳格に継承した上座部の教えでありました。
マヒンダ長老は当時のスリランカ国王から尊信と保護を得て、首都であったアヌラーダプラにマハービハーラ(大寺)を建て、スリランカ仏教の基礎を築いたと言われています。またマヒンダ長老の妹サンガミッター尼はブッダガヤの成道の地から菩提樹の枝を携え来島し植樹したと伝えられています。
スリランカの仏教は、その後様々な変遷を経つつも、代々の諸王も仏教を厚く保護し、この時伝来された仏教が連綿と伝えられ今日に至っています。そして、十一世紀にはスリランカからビルマへ、また十三世紀にはタイ、カンボジアなどに上座仏教は広まっていきました。
(↓よろしければ、一日一回クリックいただき、教えの伝達にご協力下さい)

日記@BlogRanking
前回は、紀元前四八〇年頃お釈迦様が中インド北部のクシナーラーで亡くなられた後、ただちに師の遺された教えをその後の依りどころとして確立すべく、五〇〇人の阿羅漢によって仏典の結集(編集)が行われたところまでを述べました。
お釈迦様の誕生されたルンビニー、さとりを開かれたブッダガヤ、初転法輪の地サールナート、そしてクシナーラーは、その後、四大霊場として仏塔が建てられ、お釈迦様を慕い信仰あるものたちの巡礼の地として栄えたということです。
これら四カ所に見られるように、当時の仏教はガンジス河中流域を中心として中インドに広まったに過ぎなかったのですが、次第に西方のマツラーや南方のウッジェーニーなどに伝道がすすめられていきました。
今回は、仏教教団がたくさんの部派に分かれていく部派仏教の時代について述べてみようと思います。
教団の根本分裂
仏典結集によってまとめられた教法と戒律を、お釈迦様在世当時と変わらず大切に護持していた仏教僧団も、仏滅後一〇〇年余りの頃、戒律に関する解釈に対立が生まれていきました。
いかなる食物も蓄えることを許さなかったのに対して塩は蓄えることを認める、正午までと決められた食事の時間を少しのばす、また、お金を布施として受け取ってもよいなどといった、戒律上の十か条の新しい解釈を求める人たちが現れました。今日ごく一部を除いて、どの国のお坊さんもお金を持ち生活している訳ですが、当時はお金に触れることも禁じられていました。
こうした機運に対し、そのころ西方や南方に伝道していた上座に座る長老たちは、これまで通り厳格に教えを守っていくべきだと考え、七〇〇人の長老がヴェーサーリーに会合いたしました。そして、十事と言われる先の解釈を非法として、再度教法と戒律の合誦(再確認)がなされました。これを第二結集と言っています。
これに誘発され、変革を求める主に中インドのお坊さんたちは、なんと一万人ものお坊さんを集め別の結集を行い、それまでの僧団からの離脱を宣言してしまいました。
こうしてお釈迦様没後一〇〇年にして、教団が二つに分裂することになりました。これを根本分裂といい、上座の長老たちを支持する保守派は上座部、変革派は大衆部を名のることになりました。
アショーカ王の偉業
教団の根本分裂があって五〇年ばかりがたった頃、遠くギリシャから兵を興し、インドの地へ侵攻を企てる一大勢力がありました。ペルシャ全土を併合し、パルティアを征服したアレクサンドロス大王は、紀元前三二六年にインダス河を越え、タキシラという商業とバラモンの学問の場として栄えていた都城に入ったとされています。
しかしながら、その後インドの雨期や象軍との戦いに疲弊し、また既にマケドニアを出て一〇年もの歳月が過ぎていたこともあり、それ以上インド国内に攻め入ることはありませんでした。そして、そのアレクサンドロスの勇姿を目撃したインドの人々の中に、のちに西北インドから兵を挙げマガダ地方に進攻し、インドを統一する若き日のチャンドラグプタの姿がありました。
彼はアレクサンドロスの成功をインドで成し遂げるべく、西北インドに侵入していたギリシャ勢を一掃してマウリヤ王朝(前三一七年~前一八〇年頃)を興し、インド南端部を除く全インド最初の統一王となりました。
チャンドラグプタの孫で第三世アショーカ王(在位前二六八年~二三二年)の時、マウリア王朝は最盛期を迎えることになります。そして、彼こそは転輪聖王(世界を統一する理想の法王)と称えられ、武力による政治を改めて仏教を始め宗教を保護し、仏教の教えに基づいた政治を行ったと言われています。
また、仏教が一つの地方宗教から全インドに、さらには世界へ伝播される礎を築く大恩人となりました。日本でいえば仏教伝来間もなくに現れた聖徳太子のような存在でありました。
アショーカ王は元は性格が凶暴で、王位争奪のために多くの兄弟を殺し、凄惨な戦闘を繰り返したと言われています。が、即位してのち仏教に帰依し、インド全土を手中に収める戦場で数十万にのぼる死傷者を出した闘いを恥じて改心すると、熱烈な仏教信奉者となりました。多くの精舎や仏塔を建立し、仏跡や仏弟子の遺跡を巡拝、大規模な仏僧供養を行ったということです。
こうしてインド各地に仏教を知らしめ、さらにはスリランカなどの近隣諸国や、遠くエジプト、シリア、マケドニアなどにも仏教使節を派遣し、キリストも誕生せざるこの時代に、早くも西方世界に仏教の存在を知らしめたということです。また、国内至る所に人と獣のための療院が設けられ、薬草や果樹を植え、井泉を拓くなど、アショーカ王は幾多の福祉事業にも奉仕したと言われています。
アショーカ王のこれら数々の業績は、王がインド各地の石柱や岩に、その地方の言葉で法勅を刻み民衆に公布したものが、近代になって発掘され明らかになったものです。これを「アショーカの刻文」といい、最も多く発見されている石柱碑文は、高さ一〇~一五mの砂岩を直径五〇~七〇㎝の円柱状に建立し、その頭部には獅子頭が飾られていました。
有名なサールナート出土の獅子頭は四つの法輪の上に四頭の獅子が背中合わせに座った美麗なもので、現在インドの国章ともなっています。それら碑文の内容は、仏法の趣旨を伝えたり、王自身の仏教への信仰を語ったもの、お釈迦様の教えに従って殺生を禁ずるなど善業を勧める旨を記されたものなど。またサールナートにある石柱には、仏教教団の分派行動について戒める法勅が刻まれているということです。
上座仏教の伝播
今日スリランカを始めミャンマー、タイなど南アジア、東南アジアの各国で行われている上座仏教は、このアショーカ王が派遣した仏教使節によって伝えられた仏教が、その起源となっています。アショーカ王の王子マヒンダ長老によって仏舎利とともにスリランカにもたらされたと言われる仏教は、根本分裂の際にお釈迦様の教えを厳格に継承した上座部の教えでありました。
マヒンダ長老は当時のスリランカ国王から尊信と保護を得て、首都であったアヌラーダプラにマハービハーラ(大寺)を建て、スリランカ仏教の基礎を築いたと言われています。またマヒンダ長老の妹サンガミッター尼はブッダガヤの成道の地から菩提樹の枝を携え来島し植樹したと伝えられています。
スリランカの仏教は、その後様々な変遷を経つつも、代々の諸王も仏教を厚く保護し、この時伝来された仏教が連綿と伝えられ今日に至っています。そして、十一世紀にはスリランカからビルマへ、また十三世紀にはタイ、カンボジアなどに上座仏教は広まっていきました。
(↓よろしければ、一日一回クリックいただき、教えの伝達にご協力下さい)
日記@BlogRanking