昨日の読売新聞朝刊のコラムに
俵万智さんの句が 紹介されていました。
<L と R 聞き分けられぬ耳でよし
日本語をまず おまえに贈る>
日本人にとって
英語の <
L> と <
R> の発音は
特別 難しいという事になっています。
紙面では
ニューヨークのレストランで
「メロン」が通じなかったという話から始まります。
2020年度から
「大学入学共通テスト」に
民間試験が導入されるという動きついての話です。
「読む・書く・聞く・話す」のうち、
「話す」の技能を強化するためなんだそうです。
今後受験する子供や その親にとっては
やはり気がかりな事なのでしょう。
その中で 歌人の俵万智さんの心意気がステキ!
と思いました。
そうです!
日本人なら、日本語をまずキチンと習得しよう!
などと、英語耳や 発音の習得に
人一倍 時間をかけてきて、
しかも 子供達を 当時の「渋沢国際学園」に通わせて
<耳>を養おうと努力した母の この私が
言って良いものかどうか・・・?
でもね。。。
何のために外国語を習得しようとするのか?
と思うと、ね。
言語は、単なる コミュニケーションの道具なわけです。
もちろん、入試などの テストの合否に関わってくるのですが。
それでも、その学力の向上には 習得意欲が必要だと思うのです。
何のために 外国語を習得したいと 人は思うか?
それは やはり コミュニケーションのためだと思うのです。
自分の母国語が通じない人達がいる。
けれど、どうにかして 伝えたい!
そう思う事が、意欲につながります。
という事は、「伝えたい何か」「伝えたい誰か」がないと、
人は 頑張る意欲を持ち続けるられないという訳です。
「伝えたい何か」がいっぱいあって、
たくさんの「伝えたい誰か」がいたら、
何語だろうと、習得できそうな気がしませんか?
人は 人とのつながりが必要です。
人との出会いを喜びとする事ができて、
「これを伝えたい!」と思える事がたくさんあったら、
人は 言語や 言語を越えたもので
なんとか意思の疎通をはかろうとするのではないでしょうか?
言語の習得のために
一番 心がけなければいけないのは、
「ああ! これを、他の誰かに伝えたい!」
と思えるような感動を味わう体験なのだと思います。
あ、これ、面白い!
あれ? これ、こうなってるんだ?
え? それって、そういう事なの?
え? 知らなかったよ!
ねえ、ねえ、聞いて!
そんな事を感じて
人に伝えたくなるなるような体験を
若い人達には いっぱい、してほしい。
いっぱい感じて、いっぱい考えてほしい。
そして、
考える時、人は 母国語がキチンと習得されていなければ
深く思索する事は 難しいのではないでしょうか。
俵万智さんの覚悟は、
外国語習得に向けて、まっとうな考え方かと思います。
ですから、
大学入学共通テストを受けるずっと前から、
「体験する事」と「母国語の習得」を 心がけてほしい。
人に伝えたくなるような体験を、
若くない人達にも、いっぱい してほしい(笑)。
受験勉強から ずっと遠ざかった年代の人達は
きっと 放っておいても 面白い事を求めていれば
できていると思いますが。

「魂が求めているのは、体験そのもの」
と言った方がいます。
その人によると、
<魂>は
良い事も悪い事もひっくるめて、
「体験する事」だけを求めているのだそうです。
だとしたら、何もしない人生なんて、
文字通り、魂の抜けたようなもの、という事になります。
失敗した事や 苦労した事ほど 後になると 良い思い出になったりする、
という事を
私たちは 体験していますよね?
いっぱい体験して いっぱい感動して
「ねえ、聞いて 聞いて!」
をいっぱい言いたいですね。
それを言われた時は、
うっとおしい、なんて言わないでね(笑)。



















 がいいなぁ!)
がいいなぁ!)





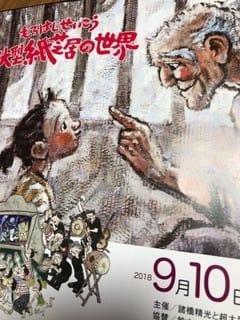









 (2012年10月撮影 だそうです)
(2012年10月撮影 だそうです)