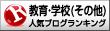「嫌になるぐらい」3月5日
『「決め切る力を」磨くジャンプ』という見出しの記事が掲載されました。フィギュアスケート選手友野一希氏へのインタビュー記事です。その中で友野氏が語る言葉が印象に残りました。
『練習の密度も量も含めて一日中ずっとスケートを考えることを続けていきたいですね。好きを超えるというか。好きな気持ちで練習できることが一番僕は楽しいんですけど。その楽しい過程の中で、スケートが嫌になるぐらいやることが大切なので』という言葉です。
スケートが好き、楽しい、それは友野氏の本音でしょう。楽しみながらハードな練習をこなしている、あるいは常人であればつらいレベルの練習でも友野氏には楽しく感じられるということです。しかし、それでは足りないというのです。根っからのスケート好きの友野氏でさえ、もう滑りたくない、スケート靴を見るのも嫌だというところまで、自分を追い込んでおかないと、伸びることはできないというのです。
学校教育をめぐる議論は、ここ数十年、楽しい授業礼賛ムードの中進められてきました。途中、ゆとり教育の見直しなどもありましたが、基本的には、授業は楽しくなければならない、楽しい授業こそ子供の学ぼうとする意欲を高める、という考え方が主流であり続けてきました。
私も同じ考えです。教員としての実践も、指導主事として教員を指導するときにも、この前提で臨んできました。このブログでも、そうした立場から、授業論、教員の在り方論を述べてきました。これからもその立場に変わりはありません。
ただ、個に応じた教育、個性を伸ばす教育という視点で考えたとき、友野氏がいう「嫌になるぐらい」ハードな訓練的な学びについて研究する必要があるのではないか、と考えるようになってきたのも事実です。
我が国の学校教育は、基本的に落ちこぼれ対策に目を向けてきました。その一方で、浮きこぼしと言われる現象、つまり並みはずれて能力の高い少数の子供への対応については関心をもたないできたという一面があるのです。
しかし、真の意味で個に応じるのであれば、100人に1人、1000人に1人というある分野においては高い能力・資質をもつ子供への対応についても研究されるべきだと考えるのです。その際ヒントになる発想法として、「嫌になるぐらい」が有効なのではないでしょうか。
「嫌になるぐらい」ハードな訓練的学びというと、どうしてもスポーツの場面が浮かんでしまうのですが、科学でも、芸術でも、創作活動でも、その道の一流と言われる人々は、「嫌になるぐらい」ハードな訓練的学びを体験しているはずです。そうした事例を数十、数百と収集し、それぞれ小学生の段階、中学生の段階、高校生の段階でどのように取り入れることができるのか、整理分析し、実践につなげていく、あるいは指導できる教員の育成に生かすということが大切なのではないでしょうか。
ただし、あくまでも子供本人の夢や自己実現のため、つまりは子供の幸せための措置であり、国家の競争力の向上などという目的で行うのではないということは常に意識しなければなりません。