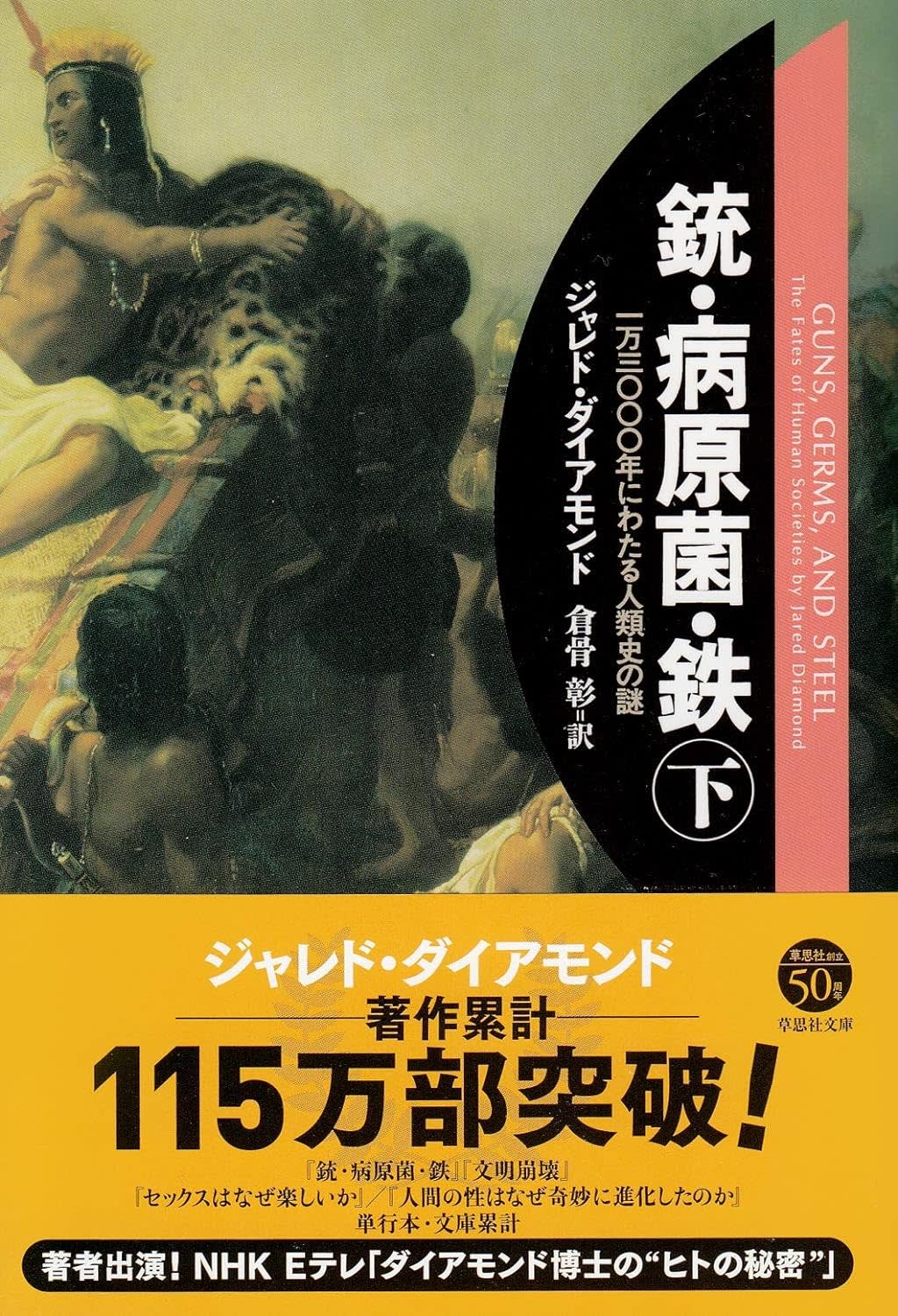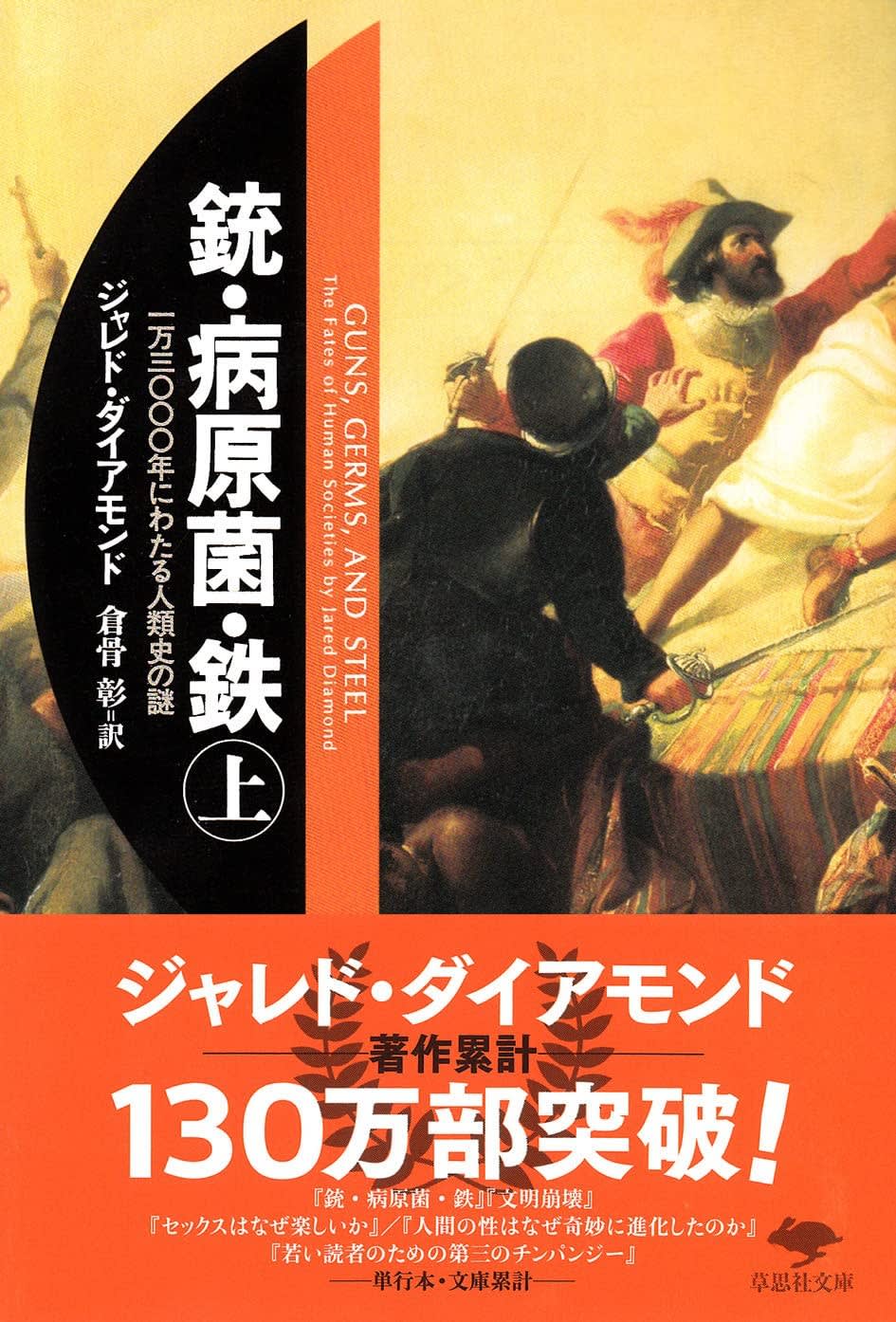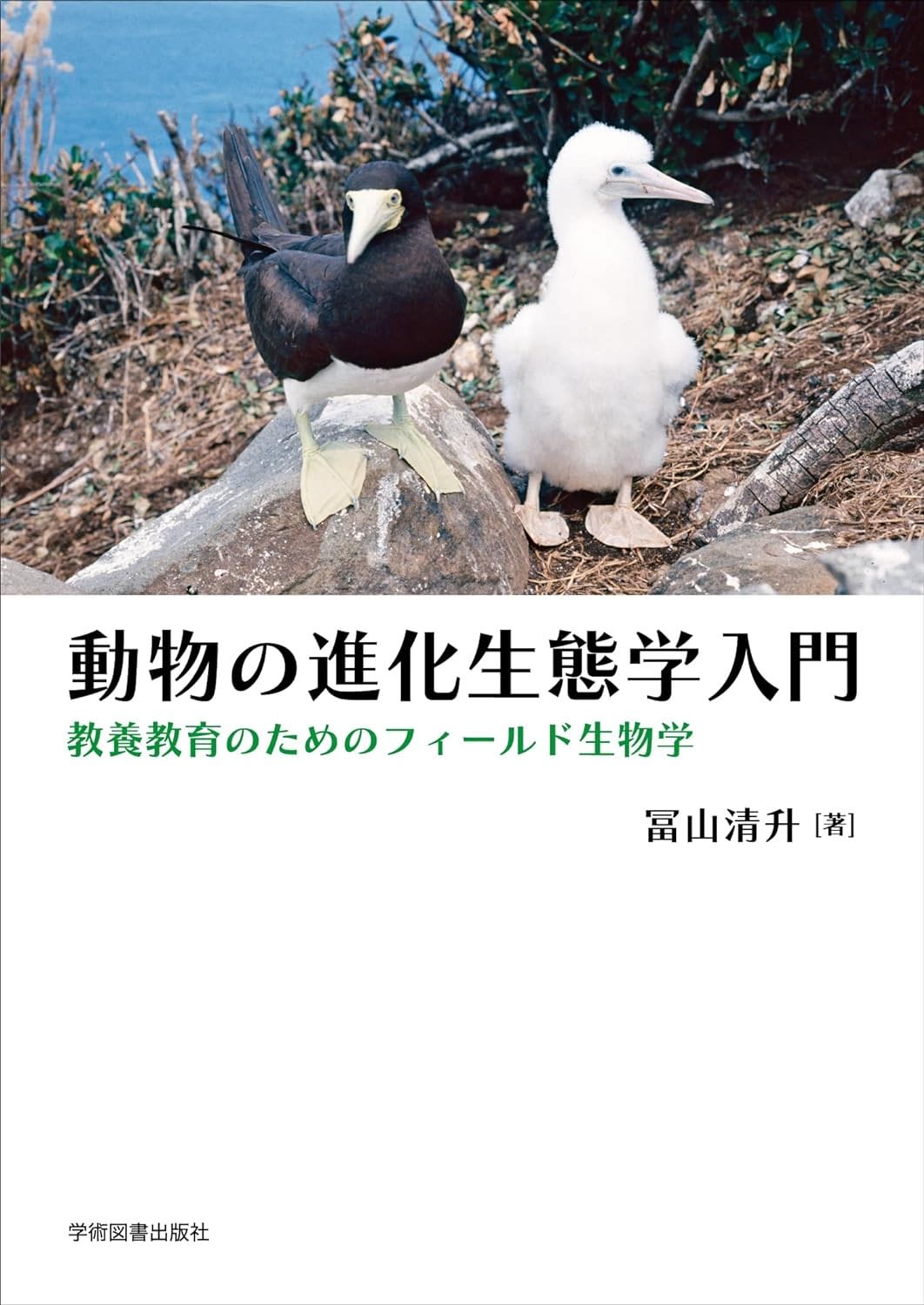
進化生物学は細分化されているが、ゲノム解析中心のバイオインフォマティクスと、フィールド生物学中心の進化生態学と、おおざっぱに2つに分けると、本書は後者の教科書になる。著者の冨山氏は、本書を大学の基礎教育課程において教養教育を学ぶ学生を第一の読者として想定しているが、そこにとどまらない網羅的で十分な内容が含まれている。B5サイズで、索引まで入れると376ページもある大著である。それにも関わらず、たった1名で書かれている。そうなってしまった事情は最後の謝辞において明かされている。最後まで通読するのはけっこうたいへんだったが、とても勉強になったと思う。これで定価2500円はかなりコスパがいい。そして、他に類書がないので貴重な本である。
一方、文字のフォントが細い(老眼にはつらい)、誤字脱字が多い、写真のコントラストが低くてわかりにくいものが多い(写真の著作権の問題があることは「おわりに」で書かれている)といった、進化学用語でいうところのトレードオフの関係にあるような面もある。第2版を出されるときは、そのあたりを考慮して頂けるとありがたい。
本書の構成は、下記のような序章+4部構成+終章となっている。それぞれについて、特記しておきたい点を下記にまとめる。
序章 進化生態学を解説にあたっての前書き
・動物の行動進化を研究するための方法論であり命題である「ティンバーゲンの4つの何故」をあげている。①ある動物のその行動を引き起こしている直接のメカニズムは何なのだろうか(至近要因、機構)。②その行動は、どのような機能的有利性があるから進化してきたのだろうか(究極要因、適応)。③その行動は、ある動物が受精卵から成長し死亡にいたるまでの一生の間にどのような発達過程を経て完成されたのだろうか(個体発生要因、発生)。④その行動は、ある動物が進化してきた過程で、祖先型からどのような道筋をたどって現在の行動に至ったのだろうか(系統発生要因、進化)。「フィールド生物学」では、②の追求が主要テーマとなっている。
第Ⅰ部 生物の進化学
・時代を問わず、民族主義的な知識人(木村資生など)が、「民族浄化のために劣性遺伝子病の遺伝子保持者は子供を作るべきでない。潜性(劣性)遺伝子は取り除かれねばならない」等の主張を繰り返している。これは集団遺伝学の観点からはトンチンカンで誤った発言であるという。現在、潜性(劣性)遺伝子病は、その遺伝子がホモ接合体となって、表現型として発現した場合、日常生活に支障が出る程度に症状が重い遺伝子病(例:先天性聾、フェニルケトン尿症、全色盲、真性小頭症)だけでも数100種類が登録されている。これらの保因者(ホモとヘテロ合わせて)は、100~200人に1人程度いる。これらの遺伝子頻度から逆算すると、誰でも10~20個程度の潜性(劣性)遺伝子病の遺伝子保因者である。確率から言って、潜性(劣性)遺伝子病の遺伝子を持っていないヒトは存在しない。したがって、「潜性(劣性)遺伝子病の遺伝子を社会から取り除く」という主張がいかに的外れであるかがよくわかる。
第Ⅱ部 進化から見た動物生態学
第Ⅲ部 行動生態学
・動物行動学(ethology / behavioral ecology)は、日本においては、動物生態学(animal ecology)の1分野としての扱いが定着しており、動物の個体群生態学(population ecology)や農業分野の応用生態学(applied ecology)の研究者が「行動学研究者」を名乗っている事例も多い。しかし、ヨーロッパにおいては、行動学(ethology)は、心理学分野にその発祥の起源が求められる学問体系と考えられており、生態学(ecology)とは明確に異なった研究分野と見なされている。
・ローレンツ&ティンバーゲン流の動物行動学は一定の功績を残したが、本来の野外観察主義から外れていった。「面白くない」学問分野に変容していき、科学への動機づけが弱体化していった。このため、新たな若手人材の参入が減ってしまった。(部外者である私が外から見ていると、鈴木俊貴さんの鳥の言語研究や高木佐保さんのネコの認知能力研究といった若手のアクティブな研究は今でも目立っているが、昔のような日高敏隆先生が作り出した盛り上がりには欠けているかもしれない)
・結果として、旧心理学からのパラダイム転換(思考の転換)の結果として登場した動物行動学Ethologyは、さらなる新たなパラダイム転換を構築できず、研究分野としては、発展的解消を遂げてしまった。(日本動物行動学会は今でも活動しているが、そこまで低迷しているのか部外者にはわからない。進化心理学はそこそこ注目されていると思うが、興味の対象はまたヒトへと戻っていったということだろうか)
第Ⅳ部 環境と保全の生物学
・外来種の根絶が試みられているが、いったん定着してしまった植物や昆虫類の根絶事業はあまり芳しくない。そのような状況を受け、定着し、その生物群集に組み込まれてしまった外来種は、無理に根絶を目指すのではなく、外来種と固有生態系の共存を目指すべきではないかという世界的な潮流に変わりつつある。特殊病害虫の事例のような外来種ではなく、なおかつ、現状において生態系や産業に著しい影響を与えていない外来種は、正確なモニタリングを行った上で、無理に排除対象とする必要はないと思われる。
終章 日本の進化学や生態学周辺の話
・8ページにわたる終章は、当事者でないと知りえないような興味深いことがたくさん書かれている。「生態学者・伊藤嘉昭伝 もっとも基礎的なことがもっとも役に立つ(辻宜行編)」や「利己的遺伝子の小革命 1970-90年代 日本生態学事情(岸由二)」などに書かれている内容とかぶるかもしれないが、冨山氏にこのあたりのことを書いて新書版くらいで出していただけたら読んでみたい。
いろいろな人が書いているが、日本の進化生態学に遅れがあったとしたら、それはルイセンコ生物学と今西進化論のせいであることは間違いないようだ。