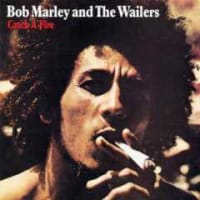バルベ・シュローデル監督がデビュー作「モア」に続いて再びピンク・フロイドを音楽に起用した1972年の作品。映画のタイトルは「ラヴァレ」で日本での公開はずっと後のことであった。フロイドにとっては2枚めの映画音楽である。「モア」を担当したことによりこのバンドは自分たちの音楽を客観的にみれたのだと思う。「モア」とこのアルバムの間にも、ミケランジェロ・アントニオーニの「砂丘」という映画作品の音楽提供もしたが、殆ど使われなかった。
このアルバムはピンクフロイドのディスコグラフィーで考えると、「おせっかい」と「狂気」の間にあるアルバムであり、そういう意味では物凄い位置にある。だが、映画音楽作品だということで、どちらかというと余りファンの間でも重視されなかったが、サウンド的に言うと私は決して突出した作品ではないものの、フロイドの歴史を飾る1枚としては別段見劣りもなく、出来栄えもそこそこであると思う。ただ、 「原子心母」以降、(そして「狂気」を出してしまったために後々のファンにも)フロイドというのは特別な作品を出さないと評価をされないという宿命を辿ってしまったという事実である。酷といえば、酷な身分になったということであろうか。このアルバムを聴いて思ったのは、フロイドは将来的には映画音楽だけでなく、音楽を優先したコンセプトをもって映画を背巣作するのではないだろうかということであった。無論、結果論として、彼らは「ザ・ウォール」というアルバムを出すことになり、それがメガヒット(というかもうテラヒット)になるのだが、このことについては私は勿論その結果の前に予測したことである。なぜそう思ったかというと、「原子心母」はまさに、映画を音楽に置き換えた内容、分かり易く言うとワーグナーの楽劇に等しいからである。ワーグナーの作品は勿論楽劇としても素晴らしいが音楽だけでもその感動は十分に伝わってくるし、そのスケールの大きさも当時としては並はずれていた。フロイドがワーグナーをどう思っていたかは知らないが(どうとも思っていないと思う)、時代を超えても同じような取組を考えるというのが音楽家の常であり、特に、時代をプログレスしているフロイドなら当然の流れであったのだ。そして、このアルバムでは「モア」に比べるとアルバム全体を通して、何か「これだ」という強いインパクトはない。しかし、その変わりに1曲1曲がとても丁寧に作られているし、映画音楽のアルバムといえばそうかもしれないが、(フロイドの作品だと言わなければ)大変良くできているアルバムだと思う。また、4人のメンバーがそれぞれ色々な曲を提供しているのもこのアルバムの特徴で、デビット・ギルモアの作品「大人への躍動」は珍しく、彼もこの曲を最後に暫く書いていなかったり、またロジャー・ウォーターズの「フリーフォア」は、後々の大作「ザ・ウォール」に繋がっているというのがフロイド解説者の大概な見方であるようだ。私などは、寧ろこの曲はビートルズに共通するものを凄く感じるのであり、当時から、解散したビートルズを継ぐミュージシャンというのは沢山名乗りを上げたが、音楽的にも、そしてレコードセールス時にもビートルズを継いだのはピンク・フロイドだと思っているから、そちらの思いの方が強いのである。
映画音楽であるからかもしれないが、全体的に静かな曲が多い。また、アルバムを通しての起伏も激しくない。この映画作品は、さすがの映画好きでも観ていないが、あるブルジョア階級の有閑マダムが、冒険家の青年と出会い、彼の旅に同行する過程で、文明的なものから人間の本質である心と肉体を解き放っていくという内容で、その生の喜びに目覚めていく姿を幻想的に描き出しているらしいが、それがなんで「雲の影」なんだとも思うが、何かフロイド自身はというと、この映画作品コンセプトに関しては寧ろ次作の「狂気」に向けているのではないかと思ってしまうのである。
こちらから試聴できます