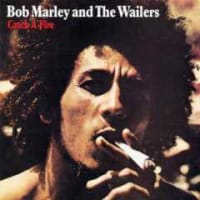世界三大交響曲というのがあるらしいが、一般に、ベートーベンの運命、シューベルトの未完成、ドヴォルザークの新世界らしいが、人に依っては、未完成のかわりにこの悲愴を入れたり、四大と称して悲愴がはいるらしい。交響曲好きな私には何を基準として三大と呼んでいるのか明確な物が不明なので何とも言えないが(多分、ポピュラーなのかと、ただその定義はヨーロッパやアメリカ、日本と随分基準が違う)、例えば四大ヴァイオリン協奏曲のそれは納得できるが、これは全く納得できない。しかもすべて標題がついているのが気に入らない。ようするに有名で分かりやすいという事なのか。私が勝手に選んだら、ベートーベンの英雄、ブラームスの4番、チャイコの悲愴、マーラーの巨人になるだろう、多分。でも、ベートーベンは7番も9番も捨てがたいし、ブラームスは3番、シューベルトの未完成も、そうなって来るとブルックナーも入ってくるし、マーラーだって他にも色々。そうそう、モーツァルトも40番があるし、とどのつまりは3つとか4つには絞れないということかなぁ。でもでも、悲愴はやっぱり入っている。
そんな中でも悲愴は最初に聴いた時の印象が今でも良く覚えているのは、凄く当時の私には難しかった事。それは、当時はまだ理論として自己の中には構築されていなかったが、ソナタ形式がはっきり打ち出されていなかったからだと思う。別の記事に書いたが、チャイコ(余りこの言い方は好きではないのだが、ピョートルというと余計分からないので…)は、美しく、万人に親しみやすいメロディを作ることにはもの凄く長けていて、この部分はモーツァルトに匹敵する唯一の音楽家であるが、如何せん、ソナタ形式はどうも苦手だったようだ。いや、苦手というより好きではなかった、多分形式に拘泥されるのが嫌いだったのだと思う。なので、ベートーベンの方程式に填まっている当時の私としては、葬送曲から始まる第1楽章(しかし第2主題のメロディは実に美しい)、第2楽章は4分の5拍子のワルツで、第3楽章はスケルツォから行進曲へと繋ぎ、第4楽章は「アンダンテ・ラメントーソ」(後世アダージョに書き換えられた)と、4つの楽章の構成は、「急 - 舞 - 舞 - 緩」と、配列が原則とは異なっていて独創的ではあると思う。しかし、その後になって色々チャイコの楽曲を聴いていくうちに、この交響曲第6番が色々な意味で音楽の歴史の一部になっていると気づく。あくまでも交響曲を聴いていると、この楽曲は、ブラームスとマーラーを見事に繋いでいると思うのである。ベートーヴェンからブラームスに継承された抽象的な展開、つまりはソナタ形式に対し、チャイコは想念やドラマを音楽の展開に使おうとしていることから標題音楽的な性格をもち、すなわち、それをソナタ形式で表そうとした部分にチャイコの特徴がある。ブルックナーもワーグナーの影響から標題音楽派であったが、しかし、作品的にマーラーに繋がるものは見当たらなく、そういう意味では、チャイコが書いている7曲(「マンフレッド交響曲」のみ、番号が付けられていない)の交響曲のうち、唯一大きな特徴を持った曲である。
こちらから試聴できます。