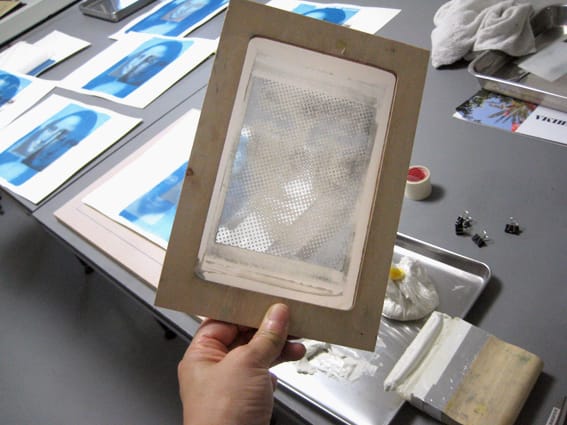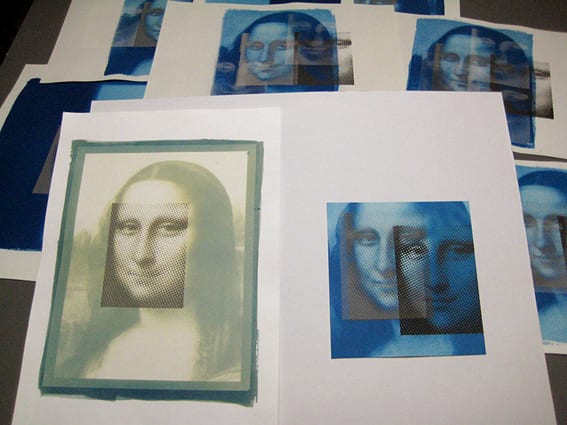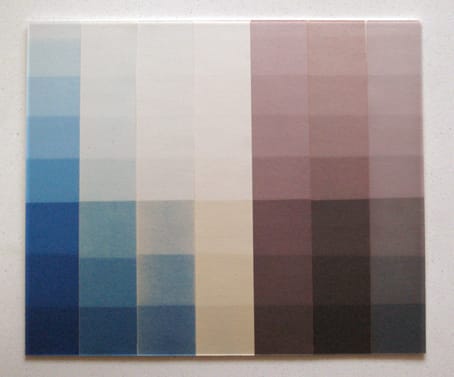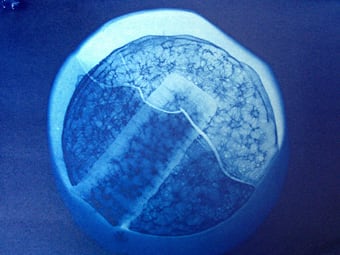雲ひとつ無い快晴。
サイアノタイププリントの講座初日は
通常、参考作品を紹介しながら講義をおこないます。
しかし、この素晴らしい天候を活かして
まずは、その魅力を体験することにしました。
感光液の処方を記したテキストに従い
薬品を溶解して調合
そして
紙に塗布して感光紙を作成しました。
感光紙を乾燥させた後は
休憩をはさまず
屋外にて露光作業をおこないました。
はじめての露光はデータをとることから。
所定の時間で区切り段階露光をおこなうと
このような階調に変色しました。
↓
感光紙を水に浸すと青に発色。
この結果を念頭に入れて
その後は各自のペースで作業を進めました。
この日は夕刻まで陽射しが強く
順調に作業が進みました。
光にあたった部分は青くなり
あたらなかった部分は白くなります。
光と影を操り画面を構築した成果は
コチラ
↓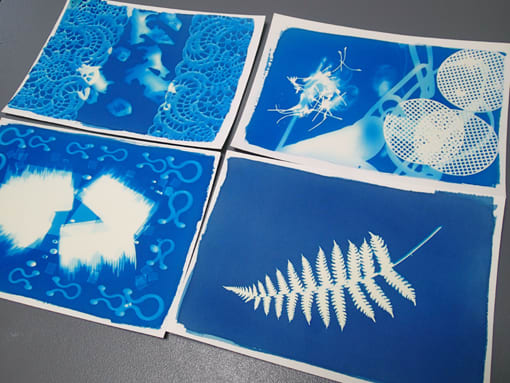
太陽光での露光作業は疲労感をともないますが
その疲れは
スポーツをした感覚と似ているのではないかと思います。
次回からは太陽光と共にプリンターも併用して講座を進めます。
記:徳永好恵
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
大阪・鶴橋にて、写真・写真表現・シルクスクリーンの研究活動をおこなっています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・