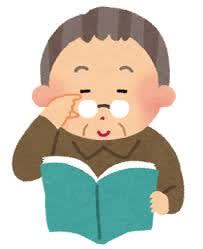普段、新聞を読んだり、小説を読んだり、数多のブログを読んだりしていて、つくづく、日本語の面白さを感じることがある。
子供の頃から比べると、近年、ものすごい勢いで、カタカナ表記が多くなってきているように思っているが、どっこい、漢字、ひらがな、カタカナが、入り混じる日本語の面白さも有り、それは、永久に不滅なのだと思う。
何かを表現したい時、漢字、ひらがな、カタカナ(外来語を含めて)を使い分けて、極く当たり前に暮らしている日本人。中には、同じ言葉、文字でも、微妙にニュアンスが異なる場合も有り、多分、初めて日本語を学ぼうとする外国人には、そのあたりが、なにがなんだか分からないのではないか等と思ってしまうことが有る。
例えば、英語では、動物の「熊」は、「Bear」だが、
日本語では、時と、場所、状況により、「熊」「くま」「クマ」を、使い分けている。
漢字で、「熊」と記せば、単純に、動物をイメージするし、
時代小説等で、よく有る、「熊のやつ・・」、「熊さん・・」、等からは、
なんとなく、破落戸の手下?や、長屋に住む大工?の名前等が、イメージされる。
ひらがな、カタカナで、「お」を付けて、「おくま」、「オクマさん」等となると、
時代小説等で、よく有る、下級武士の奉公人や女中?の名前だったり、長屋に住む職人の女房?の名前をイメージしてしまう。
ひらがな、カタカナで 「くまさん」、「クマサン」とあれば、むしろ、可愛らしさがイメージされる。
ゆるキャラにも、「くまモン」、「メロン熊」、「くま吾郎」等が、有るようだが、それぞれ意図があるのだろう。
言葉や文字だけでなく、日本の文化は、ストレート、単純ではなく、奥が深く、隠された意味を含んでいたりする。それは、逆に、外国人と渡り合う場合等には、誤解を招いたり、理解されなかったりする場合も有るのかも知れないが。
(ネットから拝借イラスト)