
さて、毎日検索ワードの発表ばかりでもなんなので
今日は花風社の次の本から先取り。
英米で行われている療育方法(頻度)のベスト10を発表しましょう。
「どういう療育がドミナントか」っていう調査です。
ASD児によく使われる治療など
(Green et al., Internet survey of treatments used by parents of children with autism. Research in Developmental Disabilities, 27: 70-84, 2006)
1.言語療法 標準的療法 70.0%
2.視覚的スケジュール スキル指導 43.2%
3.感覚統合 生理学的 38.2%
4.応用行動分析 スキル、ABA 36.4%
5.ソーシャルストーリー スキル指導 36.1%
6.ビタミンC サプリメント 30.8%
7.ビタミンB6 サプリメント 30.1%
8.必須脂肪酸 サプリメント 28.7%
9.PECS スキル、ABA 27.6%
10.カゼインダイエット 食餌療法 26.8%
ごらんのとおり、わりと感覚統合はよく行われているようです。
ABAよりちょこっと多いわね。
もっとも感覚統合も、どんどん生まれ変わっていて
今は古典的なエアーズが提唱していたものよりバージョンアップしているらしいですけど。
猿烏賊山の海老踊り軍団の情報の古さにはいつもびっくりするけど
せめて科学的な態度は彼らが誇るように、保持しているんだと思っていた。
でも、ベムこと宮本晋が感覚統合を弾劾するその根拠が一編の雑誌記事で
その雑誌記事を元に感覚統合・十一元三先生の双方を断罪するって、無知っていうのは恐ろしいものだなと思った。
英文記事もよく紹介しているから、大卒(明治大学かな?)みたいだし、英語くらい読めるんだと思ってたら
(別に英語読めるのはいまどきたいしたことじゃないしさ)
自動翻訳で読んでるんだって。
それで他人に紹介できるのか。素人さんは怖いな。
ネットの情報ていうのは、本当にリテラシーが必要ね。
(まあ吉川センセイのように助動詞のニュアンスすっ飛ばして紹介するのもどうかと思うけど。
専門家だけに。)
まあともかく、宮本晋が感覚統合を簡単に弾劾しちゃうのは
大嫌いな花風社が感覚統合にわりとフレンドリーっていう理由だとしたら
科学的な態度とは程遠いけど。
ベムんちの坊ちゃんは、列車の中でトイレに行くのを怖がるらしいけど(揺れが怖い)
そういう不具合は、生活全般に及んでいるはずで、ご本人がいろいろ不便なはず。もちろん、それを訴えるすべを持たない人たちでもあるんだけど。
だからOTさんたちは、そのへんをアセスメントするんだけど、そして前庭覚の不具合というのはかなり治りやすいんだけど
父親が感覚統合に対してかたくななら仕方ないわね。
列車でトイレを使うときにはアシストするらしいけど
息子が40になっても50になっても親が排泄行動をアシストするつもりなら、それはそれで他人の口出すことじゃなし。
私は科学的な人間ではないけれど
こうやって人間観察していて
伸びるうちの親御さんっていうのは、どんな療法も頭から否定せず、その療法がバックボーンにしている知恵をいいとこどりして取り入れている気がしますわ。
そして、ある療育方法に出会ったとき「トンデモかどうか」みたいに
まずそこから学ぼうというより、あらさがしをする系の親の子は伸びない。
それが私が抱いている仮説。
私なりにその仮説を抱きつつ、観察に励みますわ。
えっと、ついでだから、昨日の検索ワードも発表しちゃいましょう。
=====
昨日の当ブログ検索ワードベスト20
1 浅見淳子
2 花風社
3 宮本晋 夫人 ブログ
4 花風社 浅見
5 名大吉川 藤居
6 定型発達者もつらいかな
7 定型発達者もつらい
8 定型発達とは
9 他害児
10 他害のある発達障害
11 先生 先生って慕う子
12 宮本晋
13 ベム 辻井
14 セルフエスティーム
15 労災 利用者 他害
16 薬物体験
17 発達障害専門医
18 発達障害は治らない
19 発達障害 治らない
20 発達障害 専門家
宮本夫人はブログやってるの?
知ってる人がいたら教えてください。私も読みたいわ。
私なりに、問題意識をもっているので。
久々のキティちゃんは横浜中華街バージョンです。
今日は花風社の次の本から先取り。
英米で行われている療育方法(頻度)のベスト10を発表しましょう。
「どういう療育がドミナントか」っていう調査です。
ASD児によく使われる治療など
(Green et al., Internet survey of treatments used by parents of children with autism. Research in Developmental Disabilities, 27: 70-84, 2006)
1.言語療法 標準的療法 70.0%
2.視覚的スケジュール スキル指導 43.2%
3.感覚統合 生理学的 38.2%
4.応用行動分析 スキル、ABA 36.4%
5.ソーシャルストーリー スキル指導 36.1%
6.ビタミンC サプリメント 30.8%
7.ビタミンB6 サプリメント 30.1%
8.必須脂肪酸 サプリメント 28.7%
9.PECS スキル、ABA 27.6%
10.カゼインダイエット 食餌療法 26.8%
ごらんのとおり、わりと感覚統合はよく行われているようです。
ABAよりちょこっと多いわね。
もっとも感覚統合も、どんどん生まれ変わっていて
今は古典的なエアーズが提唱していたものよりバージョンアップしているらしいですけど。
猿烏賊山の海老踊り軍団の情報の古さにはいつもびっくりするけど
せめて科学的な態度は彼らが誇るように、保持しているんだと思っていた。
でも、ベムこと宮本晋が感覚統合を弾劾するその根拠が一編の雑誌記事で
その雑誌記事を元に感覚統合・十一元三先生の双方を断罪するって、無知っていうのは恐ろしいものだなと思った。
英文記事もよく紹介しているから、大卒(明治大学かな?)みたいだし、英語くらい読めるんだと思ってたら
(別に英語読めるのはいまどきたいしたことじゃないしさ)
自動翻訳で読んでるんだって。
それで他人に紹介できるのか。素人さんは怖いな。
ネットの情報ていうのは、本当にリテラシーが必要ね。
(まあ吉川センセイのように助動詞のニュアンスすっ飛ばして紹介するのもどうかと思うけど。
専門家だけに。)
まあともかく、宮本晋が感覚統合を簡単に弾劾しちゃうのは
大嫌いな花風社が感覚統合にわりとフレンドリーっていう理由だとしたら
科学的な態度とは程遠いけど。
ベムんちの坊ちゃんは、列車の中でトイレに行くのを怖がるらしいけど(揺れが怖い)
そういう不具合は、生活全般に及んでいるはずで、ご本人がいろいろ不便なはず。もちろん、それを訴えるすべを持たない人たちでもあるんだけど。
だからOTさんたちは、そのへんをアセスメントするんだけど、そして前庭覚の不具合というのはかなり治りやすいんだけど
父親が感覚統合に対してかたくななら仕方ないわね。
列車でトイレを使うときにはアシストするらしいけど
息子が40になっても50になっても親が排泄行動をアシストするつもりなら、それはそれで他人の口出すことじゃなし。
私は科学的な人間ではないけれど
こうやって人間観察していて
伸びるうちの親御さんっていうのは、どんな療法も頭から否定せず、その療法がバックボーンにしている知恵をいいとこどりして取り入れている気がしますわ。
そして、ある療育方法に出会ったとき「トンデモかどうか」みたいに
まずそこから学ぼうというより、あらさがしをする系の親の子は伸びない。
それが私が抱いている仮説。
私なりにその仮説を抱きつつ、観察に励みますわ。
えっと、ついでだから、昨日の検索ワードも発表しちゃいましょう。
=====
昨日の当ブログ検索ワードベスト20
1 浅見淳子
2 花風社
3 宮本晋 夫人 ブログ
4 花風社 浅見
5 名大吉川 藤居
6 定型発達者もつらいかな
7 定型発達者もつらい
8 定型発達とは
9 他害児
10 他害のある発達障害
11 先生 先生って慕う子
12 宮本晋
13 ベム 辻井
14 セルフエスティーム
15 労災 利用者 他害
16 薬物体験
17 発達障害専門医
18 発達障害は治らない
19 発達障害 治らない
20 発達障害 専門家
宮本夫人はブログやってるの?
知ってる人がいたら教えてください。私も読みたいわ。
私なりに、問題意識をもっているので。
久々のキティちゃんは横浜中華街バージョンです。














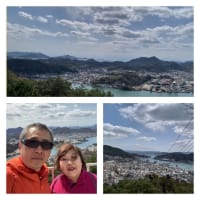





最重度で知的障害のある子達って、情報の取り方や伝わり方や処理の仕方に難があるけれど、方法や術を取得した子達は意外に色んな事がわかっていて年齢相応の部分が沢山あると思います。ちゃんと不便さや困難なことを訴える事ができるようですよ。
自分で回避や解決する子もいるようですし。
色々とできる事が増えた子達を「特別な子」とか「偶然が重なった」と、けなしていた人がいたけれど、私には青年期に入ってもできる事が増えない方が特別な子なんじゃないの。と、いつも思っています。伸びている子達は、体をみんな大事にしています。子供達が発するサインを丁寧にアセスメントしているように思います。他人をけなすことなく、前向きに療育されているように思います。
長沼先生がおっしゃるように、まんべんなくやられていることはない、ので、重度なお子さん達も様々なメッセージを発しているのですよね。
それを読み取ってもらえない子はかわいそうだなあと思いますね。
いろいろとできることが増えた子が特別だとは私も思わないけど、それを特別だとかなんとか文句言う前に自分ちもやってみようとは思わないのがまあ不思議ですが、きっとよくなりたくないんでしょうから。
せめて邪魔しないでほしいですね。
またお越しくださいませ。
うっふっふ。
確かな理論と豊かな実践が
実に「とりつきやすい」テイストで伝えられる本になりますよ。
それこそ、花風社で出していただく意味ですからね。
またお越しくださいませ。