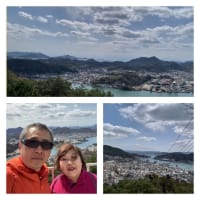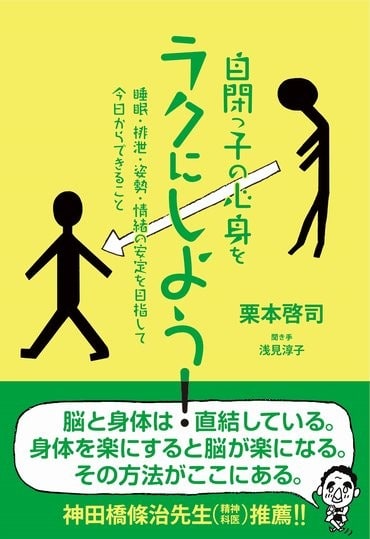
さて、小田原の大先生編です。
その前に、「すぎやませんせ」について補則。
これはとってつけたようなごきげんとりではなく
「すぎやませんせ」は本当に貴重なお仕事をされている。
著書に関して、私は愛読者でもある。
そして今も、虐待の現場で活動していらっしゃるらしい。
つまり、優れた専門家であることはたしかなのである。
ただ私には無礼だった。それだけ。
私に無礼だったというのは、どういうことかというと
おそらく医者の多くが共有している感覚
「医者と患者以外は人間にみえない」をナチュラルになさっただけだろう。
おまけに当時の私はまだできたての会社をやっている30代女子だった。
あの年代の田舎育ちのおっさんとしては、侮るのも理解できる。
感覚がアナクロで、見る目がなかった。それだけの話だ。
医者と患者以外は人間に見えない。
それは社会性のバグのせいであって、医者の多くは、医者になる前は「どこかおかしい」「親のしつけがなっていない」と世間にみられていた子どもだったかもしれない。
物をもらってお礼も言えないのは、自分がコミュ障だということだ。
そうなると、社会の中でつらい思いをし、でもその理由がわからず
「こういう自分を世間が許してくれたら」という思いを味わったかもしれない。
それが発達障害をやるようになり、当事者に出会うと、偏愛に結びつく。
この子たちの社会性は、たしかに至らない。
これを治すなんていう残酷なことを言わず、ありのまま受け入れてくれたら。そういう社会であったらどれだけいいだろう、と願うのだろう。
そして医者として手に入れた影響力で「社会の理解がー」をやる。
彼らの「社会の理解がー」には、理解してほしかった小さい頃の自分がいる。
特性に手を焼いている保護者や当事者はそれにすがる。
でもそんなもん、通じるわけがないのである。
無礼は無礼。いやなやつはいやなやつなのだ。社会はそんなやつらと付き合うことを選ばない。
脳の特性だろうと性格だろうと、つきあいたくないものはつきあいたくない。終わり。
さて、あとがきの問題。
私はたいていの本には、第三者によるあとがきは要らないと思っている。
本とは著者と読者の対峙の機会。
そこに第三者が入り込んで、ああ読めこう読めと指図するのは差し出がましいのだ。
それが社会的地位がある人であればなおのこと。
要らねえ。そういうあとがき。
つけるとしたら著者本人だ。あるいはうちの本なら私。要するに製作側。そうだと著者と読者の対話は続く。第三者が入るとそれがぶったぎられてしまうのである。
多くの文芸の単行本には第三者のあとがきはついていない。あとがきがつくのは、評価がある程度定まった文庫化のときだ。
ところが発達障害関係の当事者本には、かなり多くの場合医者のあとがきがついている。本当に邪魔くさい。うちではつけたくない。
自分の会社の本に、納得のいかないページが一ページでも入り込むのは気に食わないのが私である。
そんなわけで、かつて愛甲さんが自分の著書に「神田橋先生にあとがきを書いてもらったらどうでしょう」と提案したとき「要りません」とはねつけた。
そもそも愛甲さんにはそういう口出しをする権利はないのだと教えてあげたらびっくりしていた。
やはり支援者は、その辺にうといのかもしれない、と思った。
愛甲さんの本を出すのは、愛甲さんのためではない。
愛甲さんのために出すのなら、愛甲さんからお金を出してもらって本を出す。
本を出すのは読者のためなのだ。だから読者がお金を払って内容を自分のものにする。
版元は「ある一定の人数の人々が買ってくれるだろう」という仮説のもとに資金を出す。
愛甲さんにはものすごくお世話になっているが、一円も出資してもらっているわけではない。
だから愛甲さんに、誰をあとがきにするとか、そういうことを決める権利はないのだ。
そして私の判断は、「神田橋先生のあとがきはこの本には要らない」であった。そんなえらい先生が読み方を決めてしまうと、読者が自分なりの咀嚼をする邪魔になる。自分と神田橋先生の読み方が違ったとき、神田橋先生を優先させてしまう。そういうあとがきは邪魔なのだ。誰の? 読者の。
まあその邪魔なあとがきを二度も押し売りしてきたから私は「すぎやませんせ」に怒ってるわけですが。
ところがその私が、身も蓋もなく神田橋先生にお願いしにいったことがあった。
それは黄色本こと『自閉っ子の心身をラクにしよう』出版のとき。
原稿を送って、もし気に入っていただけるようなら帯をくださいとお願いした。
これは決定的に重要だった。
なぜなら、著者が無名だったから。
とってもいいものを持っているのに無名だったから。
そして帯をいただけた。
私は薄謝を振り込んだ。
「すぎやませんせ」と違い、安いだのなんだのはおっしゃらない。
こうやって小田原の大先生は、神田橋先生の後押しでデビューした。
ボディワークの世界では、数少ない権威あるボディワークの理解者として、精神科医神田橋條治先生は有名だったので、「すごい人の推薦をもらったな」と驚かれていたようだ。
小田原の大先生も深く感謝して、盆暮の付け届けとか義理堅く続けていた。
彼には見えていなかったかもしれないが、そもそも原稿を送り、お願いし、薄謝を振り込んで帯を使えるようにしたのは私である。
私のところに盆暮のなにがしかは来なくなったが、神田橋先生のところにはまだ送っているのだろうか。
ふとそんなことを思う朝である。
さて、あとがきの話が長くなったので今回はここまで。
次回、小田原の大先生の神経系についての観察を書く。
続く
その前に、「すぎやませんせ」について補則。
これはとってつけたようなごきげんとりではなく
「すぎやませんせ」は本当に貴重なお仕事をされている。
著書に関して、私は愛読者でもある。
そして今も、虐待の現場で活動していらっしゃるらしい。
つまり、優れた専門家であることはたしかなのである。
ただ私には無礼だった。それだけ。
私に無礼だったというのは、どういうことかというと
おそらく医者の多くが共有している感覚
「医者と患者以外は人間にみえない」をナチュラルになさっただけだろう。
おまけに当時の私はまだできたての会社をやっている30代女子だった。
あの年代の田舎育ちのおっさんとしては、侮るのも理解できる。
感覚がアナクロで、見る目がなかった。それだけの話だ。
医者と患者以外は人間に見えない。
それは社会性のバグのせいであって、医者の多くは、医者になる前は「どこかおかしい」「親のしつけがなっていない」と世間にみられていた子どもだったかもしれない。
物をもらってお礼も言えないのは、自分がコミュ障だということだ。
そうなると、社会の中でつらい思いをし、でもその理由がわからず
「こういう自分を世間が許してくれたら」という思いを味わったかもしれない。
それが発達障害をやるようになり、当事者に出会うと、偏愛に結びつく。
この子たちの社会性は、たしかに至らない。
これを治すなんていう残酷なことを言わず、ありのまま受け入れてくれたら。そういう社会であったらどれだけいいだろう、と願うのだろう。
そして医者として手に入れた影響力で「社会の理解がー」をやる。
彼らの「社会の理解がー」には、理解してほしかった小さい頃の自分がいる。
特性に手を焼いている保護者や当事者はそれにすがる。
でもそんなもん、通じるわけがないのである。
無礼は無礼。いやなやつはいやなやつなのだ。社会はそんなやつらと付き合うことを選ばない。
脳の特性だろうと性格だろうと、つきあいたくないものはつきあいたくない。終わり。
さて、あとがきの問題。
私はたいていの本には、第三者によるあとがきは要らないと思っている。
本とは著者と読者の対峙の機会。
そこに第三者が入り込んで、ああ読めこう読めと指図するのは差し出がましいのだ。
それが社会的地位がある人であればなおのこと。
要らねえ。そういうあとがき。
つけるとしたら著者本人だ。あるいはうちの本なら私。要するに製作側。そうだと著者と読者の対話は続く。第三者が入るとそれがぶったぎられてしまうのである。
多くの文芸の単行本には第三者のあとがきはついていない。あとがきがつくのは、評価がある程度定まった文庫化のときだ。
ところが発達障害関係の当事者本には、かなり多くの場合医者のあとがきがついている。本当に邪魔くさい。うちではつけたくない。
自分の会社の本に、納得のいかないページが一ページでも入り込むのは気に食わないのが私である。
そんなわけで、かつて愛甲さんが自分の著書に「神田橋先生にあとがきを書いてもらったらどうでしょう」と提案したとき「要りません」とはねつけた。
そもそも愛甲さんにはそういう口出しをする権利はないのだと教えてあげたらびっくりしていた。
やはり支援者は、その辺にうといのかもしれない、と思った。
愛甲さんの本を出すのは、愛甲さんのためではない。
愛甲さんのために出すのなら、愛甲さんからお金を出してもらって本を出す。
本を出すのは読者のためなのだ。だから読者がお金を払って内容を自分のものにする。
版元は「ある一定の人数の人々が買ってくれるだろう」という仮説のもとに資金を出す。
愛甲さんにはものすごくお世話になっているが、一円も出資してもらっているわけではない。
だから愛甲さんに、誰をあとがきにするとか、そういうことを決める権利はないのだ。
そして私の判断は、「神田橋先生のあとがきはこの本には要らない」であった。そんなえらい先生が読み方を決めてしまうと、読者が自分なりの咀嚼をする邪魔になる。自分と神田橋先生の読み方が違ったとき、神田橋先生を優先させてしまう。そういうあとがきは邪魔なのだ。誰の? 読者の。
まあその邪魔なあとがきを二度も押し売りしてきたから私は「すぎやませんせ」に怒ってるわけですが。
ところがその私が、身も蓋もなく神田橋先生にお願いしにいったことがあった。
それは黄色本こと『自閉っ子の心身をラクにしよう』出版のとき。
原稿を送って、もし気に入っていただけるようなら帯をくださいとお願いした。
これは決定的に重要だった。
なぜなら、著者が無名だったから。
とってもいいものを持っているのに無名だったから。
そして帯をいただけた。
私は薄謝を振り込んだ。
「すぎやませんせ」と違い、安いだのなんだのはおっしゃらない。
こうやって小田原の大先生は、神田橋先生の後押しでデビューした。
ボディワークの世界では、数少ない権威あるボディワークの理解者として、精神科医神田橋條治先生は有名だったので、「すごい人の推薦をもらったな」と驚かれていたようだ。
小田原の大先生も深く感謝して、盆暮の付け届けとか義理堅く続けていた。
彼には見えていなかったかもしれないが、そもそも原稿を送り、お願いし、薄謝を振り込んで帯を使えるようにしたのは私である。
私のところに盆暮のなにがしかは来なくなったが、神田橋先生のところにはまだ送っているのだろうか。
ふとそんなことを思う朝である。
さて、あとがきの話が長くなったので今回はここまで。
次回、小田原の大先生の神経系についての観察を書く。
続く