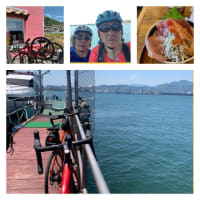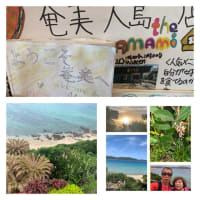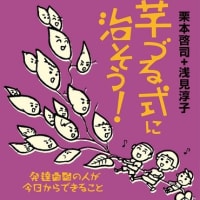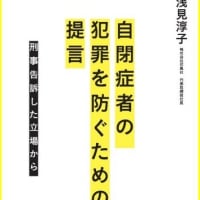岡山で11月15日に行う講演で
主催者様から
藤家さんへの質問が寄せられた。
・告知された辺りから、体調を崩した時期を中心に、そこからどうやって藤家さんは自ら体調管理が出来るようになり就労に結びついていったのか。
・また、就労にあたって何が当事者の立場から一番必要だと思うか?
・就労を考えたら、思春期青年期の学生時代など、何を身につけておくべきか。また支援して欲しいか?
どれも大事な問題だ。藤家さんを招待した理由がよくわかる。
私たちが講演活動を始めたのは04年くらいから。
すでに5年目になる。
二巡目のところも多い。
一巡目では「内面から見た自閉症」を当事者に語ってもらうことが多かった。
(私はツッコミ・引き出し係)
もちろん今でも、初めて行く場所はあるし、初めて自閉症について聞くお客様も多いし
「市民啓蒙講座」みたいなあまりヘビーユーザーではないお客様の講座もあるし
「内面を知りたい」ニーズはある。
でも、以前に比べてずいぶん知識が行き渡ってきた。
たとえば感覚の特異性などというのは
もうかなり知られるようになってきた。ていうか、「ありえな~い」とか否定されなくなった。
そうなると、求められる情報は「ソリューション」。
「困ってきたこと」にどう対応していき、どういう工夫をしているか、実際に自閉と共に暮らしている当事者から聞きたい、という声が多い。
だから、最近の講演では、なるべく事前に希望をうかがうようにしている。
以前その地域でした話と同じ話ではよくないからね。そうすると圧倒的に多いのはやはり、上記のような「どういう工夫を重ねてきたか」なのだ。
ところが、ここで専門家との役割分担の混乱が起きると恐れる人もいる。
私は別に、専門家にするような問いを当事者に投げかけること自体は問題ないと思う。
答えられないことは答えられないと答えればいいだけ。事実そうしている。
その上で、「自分のケースは」と断って
自分がどうやって対処してきたかを語ってもらえることも意味があるし、喜ばれている。
それはそれで、なんらかの役に立つ。たとえ自分や自分の支援している人と特性が違っても。
ところが
「当事者はソリューションを語るな。語っていいのは科学的マインドの持ち主だけ」と主張する人もいてびっくりした。
当事者は生の声を聞かせればそれでいい。それ以上語るな、と。普遍的じゃないから、と。
なんて上から目線なんだろう。何様のつもりなんだろう。
どれだけ一般読者・聴衆のリテラシーを低く見積もってるんだろう。
そして、どうしてそこまで当事者の血のにじむような努力に対して鈍感でいられるんだろう。
身近に見ている私としては、やはり努力のあとを伝えたい。
ちゅん平はどん底に落ちたとき「自分の力で立ち上がるしかない」と決心した。
私はその姿勢から、多くのものを学んだ。勇気をもらった。
当事者が直面する問題は物理的な面にとどまらない。
たとえば「世渡り」。
これは、おそらく「専門家」には究極的なアドバイスができない。できるのはアウトライン。それを習った後は、
それぞれのおかれている立場で、当事者が自力で、工夫を重ねていかなければいけない問題だ。
それから、たとえば、体力づくり。これも、たとえば私なんかにはわからない。
私が自分にけっこう体力があることに気づいたのは、人を雇ってからだ。
一般に人の体力は、私の見積もりよりずっと低かった。ならば鍛えれば? でも
初めから体力のある人とそうじゃない人では適切な運動量も違う。
当事者と支援のプロが話し合って方法を見出すのが効果的ではないのだろうか。
ていうか、はっきり言って専門家の提供するソリューションにも、限界があるのは知っているでしょ? みんな。
私は知ってるよ。
専門家がきっちりソリューションを提供してくれていたら、今回も、トラブルを司法の場に持ち込まずにすんだでしょうね。
患者の「想像力の障害」に対処せず、放っておく「名医」がいる。
一方で自分の想像力にバグがあることを自覚し、気をつけながら社会で生きている当事者もいる。
だから当事者が、というより当事者もまた、ソリューションを提供する側にまわることには意味があると花風社は考えている。障害特性からいって、自分がどの点において進歩していることに気づかないこともあるから、そういうときには「あんたよくやってるじゃん」というツッコミも必要だ。だから編集者としても介入する。
「当事者の提供するソリューションは科学的ではなく、万人に通じない。ただ内面を語ってろ」という理由で当事者の発信を否定するのは、当事者にあまりに失礼だし、そんなことを理由に、本人たちの努力から学ばせてもらわないのは、次世代の人たちのためにあまりにもったいない。
「当事者はただ生の声を聞かせろ。ソリューションを語るな」という人たちは
根源的に差別意識があるのではないのか。当事者に対する。そして無知な(と彼らが意識下で考えている)一般読者に対する。
私はないよ、そういう差別意識。だから当事者のしてきた努力にスポットライトを当てる。これからも。万人に通じなくても、出す意味があると思っている。学ぶものはある。だって私だって、そこから学ぶものは多いからね。
そして私は一般読者のリテラシーをそれほど低く見積もってないから。
というわけで、上記の質問に藤家さんはきっちり原稿を作ってくれるそうです。
楽しみです。
講演の参加お申し込みはこちらへ。
岡山のNPO法人ケセランパセランさんHPです。
写真は前回岡山に行ったときに見つけたきびだんごキティちゃん。リボンが桃なんです。かわいい。きびだんごは昔、父が関西出張のときにお土産に持ち帰ってくれた思い出の味です。