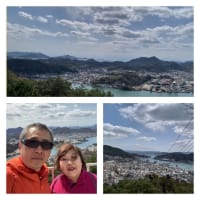さて、「どっとこむ」の方でもお知らせしたとおり、本日2020年2月23日は花風社の創立24周年記念です。
ので、3月1日の福岡講演で配布予定の「Author's Note, Editor's Note」を公開いたします。
特別支援教育、発達障害者支援法の黎明期に発達障害に出会った花風社。
最初はギョーカイと動きを共にしていました。
けれども現実の中で、袂を分かつことになりました。
ギョーカイはつねに、「社会の理解」を訴えていました。
花風社では「それだけでは共存から遠ざかる」という問題意識を持ちました。
そしてソリューションを探りました。
その都度、問題意識に基づいて本を出してきました。
それぞれの本が、どういう企画意図の元に生まれたか、公開します。
=====
Author’s Note どうすれば、社会の中で生きられるのか?
【浅見淳子の考え方は、現実の中でこう変化を遂げてきた。】
『自閉っ子と未来への希望 一緒に働いてわかった本当の可能性』 2011年
「社会が発達障害を理解すれば、みんな生きやすくなる」とは本当か?
最初は支援者たちと志をともにしていた浅見淳子は、やがて支援の世界と社会との溝に気づく。そして「支援者の言いなりでは社会と発達障害者との共存は無理だ」と悟り、支援の世界と訣別し、実りある未来へと方向転換した軌跡を綴った本。
『発達障害、治るが勝ち! 自分の生き方を自分で決めたい人たちへ』 2017年
「本当にこの支援に頼っていていいのだろうか?」そう疑問を感じたら本書を読んでほしい本。
なぜ医療は治さず、療育は伸ばさず、特別支援教育はアリバイに堕しているのか?」
そこには発達を阻む仕組みがある。その仕組みをひもとき、自分の人生を自分でつかむことを発達障害の当事者、保護者及び良心の残されている支援者に呼びかける書。
『自閉症者の犯罪を防ぐための提言 刑事告訴した立場から』 2012年
10年にわたり自閉症者からの加害行為にあった浅見淳子。最初は支援による救済を望んでいたがそれがかなわず司法に訴えることにした。それでもなお、自閉症者と社会は共存できると信じその実現のための提言を行った書。
『NEURO 神経発達障害という突破口』 2019年
2004年以来「自閉症は身体障害ではないか?」と仮説を立てて数々の提言をし、解決策を出版してきた花風社。出版して本を読んで実践した人たちが「治った!」と喜んでくれるようになった。なぜか? 実は治るのは当たり前のことだった。発達障害は神経発達障害だったのだから。「お医者さんに一生治らないと言われても絶望しなくていい」と知らせたくて書いた本。15年間の試行錯誤の一つの到達点。
Editor’s Note 1 【生きづらさは、なくなる。】
『自閉っ子、こういう風にできてます!』
ニキ・リンコ、藤家寛子著 2004年
アスペルガーの二人。いい子たちなのに、努力家なのに、身体感覚と世界観がヘンテコすぎて社会で生きるのがつらい。まずはこのヘンテコさを知ってもらおう! という純粋な赤心から出版してみたら、15年経った今に至るまで売れ続けるベストセラーに。
『10年目の自閉っ子、こういう風にできてます! 幸せになる力発見の日々』
ニキ・リンコ、藤家寛子著 2014年
ベストセラー「自閉っ子、こういう風にできてます!」で多くの人々に衝撃を与えた
・気まぐれな身体感覚 ・へんてこな世界観 はその後どうなったか?
実は前著から出版後10年経ち、二人とも、それぞれのやり方で、「10年前に夢見たような生活」を送っていたことを報告したくて作った本。おめでたいので表紙も水引に。
Editor’s Note 2 【解決策は、見つかった。】
『発達障害は治りますか?』 神田橋條治他著 2010年
「神田橋先生は、治すんです」「まさか!」
社会に無理な要求をするばかりで、一向に治す気も伸ばす気もない発達障害支援の世界に絶望していた2009年夏、「治す先生がいるから本を出そう」と言われたのが本書の始まり。出版から10年。多くの読者が神田橋先生のもとで治っていった。いわば「治そう路線」原点の本。
『愛着障害は治りますか? 自分らしさの発達を促す』 愛甲修子著 2016年
発達障害関係者は「怖がり」ばかり。当事者も、保護者も、そして支援者も。怖がってばかり。社会のあり方を悪意に取ってばかり。だから一般社会と共存できないのではないか?
そういう疑問を持っていた浅見は神田橋先生から「愛着障害がないから彼らが感じている恐怖がわからない」と教えてもらう。そうなの? じゃあ愛着障害って何? 治るの? と自身も愛着障害を治してきた「治せる心理士」である愛甲さんに質問を重ねることで作った本。
『人間脳を育てる 動きの発達と原始反射の成長』灰谷孝著 2016年
身体アプローチを追求してきた花風社は、「身体から働きかけると発達障害は治っていく」ことに気づいていた。でもそれがなぜなのか、理由をはっきり言語化していなかった。そんなときに灰谷さんとの出会いがあり「ああ、これだから発達障害者は身体からの働きかけで発達していくのだ」とその論理と実践を理解できた本。
『脳みそラクラクセラピー 発達凸凹の資質を見つけ開花させる』愛甲修子著 2013年
一言で言うと、本書は不思議な本。どう不思議かというと、これを愛読しているおうちでは治っていく。そもそも「治る」という言葉を使い出したのは愛甲さん。その本人に治るとはどういうことか徹底的にきいてみた。すると、治るとは「普通になる」ことではなく「成長の目詰まりが取れて自分らしさが開花する」ということであることがわかった。
『支援者なくとも、自閉っ子は育つ 親子でラクになる34のヒント』こより著 2015年
発達障害者支援が増えても、一向に「社会に出られる人」は増えない。療育を受けて結局作業所にたどりつくのなら、子ども時代はのびのびと遊んでいた方がいいのではないだろうか。そう疑問を感じさせるほどの支援ギョーカイのていたらく。一方で支援者を頼らないと子どもは伸びる! 凸凹キッズ二人を育てたこよりさんは今、お子さんにお小遣いをもらって悠々自適。支援なくても親子で遊べば大丈夫。それを伝えたくて作った本。
『自傷・他害・パニックは防げますか 二人称のアプローチで解決しよう!』廣木道心、栗本啓司、榎本澄雄著 2017年
自傷・他害・パニックは障害のある人とない人の共存を著しく妨げる。行政もこの問題を解決しようとしている。だいたいが薬物か行動分析であり、前者はご本人たちの健康被害を呼びかねず後者はほぼ役に立たないのに「何かやっている」と言いたいだけのアリバイ支援が行き渡っている。一方で主著者の廣木氏はご子息を含めた多くの人々の自傷・他害・パニックに実効性のある支援をしてきた。そのあり方を伝えるための本。栗本氏によるそもそも自傷・他害・パニックを起こさないための身体作りの提言も必読。
【本当に治るんです! 藤家寛子さんの歩んできた軌跡!】
・診断がつく前の混乱した青春時代を一人称で書いた『他の誰かになりたかった』。
・童話作家になりたいという小さい頃からの夢を叶え自閉の少女の内面を書いた『あの扉のむこうへ』。
・超のつく虚弱体質を克服し、作業所に週五日通えるようになった頃に書いた『自閉っ子的心身安定生活!』。当時は、アスペルガーで虚弱な引きこもり生活を送った人が週五日外に出られるようになるのはまずありえないことでした。
・そして支援を上手に活用し、必要がなくなったら別れを告げ、完全に健常者と同じ就職活動をして成功するまでを書いた『30歳からの社会人デビュー』。
・職場で定着し、能力を発揮し、断薬にも挑戦した『断薬の決意』。
すべて版元として誇りを持って出した本たちです。
ぜひお読みください!
ので、3月1日の福岡講演で配布予定の「Author's Note, Editor's Note」を公開いたします。
特別支援教育、発達障害者支援法の黎明期に発達障害に出会った花風社。
最初はギョーカイと動きを共にしていました。
けれども現実の中で、袂を分かつことになりました。
ギョーカイはつねに、「社会の理解」を訴えていました。
花風社では「それだけでは共存から遠ざかる」という問題意識を持ちました。
そしてソリューションを探りました。
その都度、問題意識に基づいて本を出してきました。
それぞれの本が、どういう企画意図の元に生まれたか、公開します。
=====
Author’s Note どうすれば、社会の中で生きられるのか?
【浅見淳子の考え方は、現実の中でこう変化を遂げてきた。】
『自閉っ子と未来への希望 一緒に働いてわかった本当の可能性』 2011年
「社会が発達障害を理解すれば、みんな生きやすくなる」とは本当か?
最初は支援者たちと志をともにしていた浅見淳子は、やがて支援の世界と社会との溝に気づく。そして「支援者の言いなりでは社会と発達障害者との共存は無理だ」と悟り、支援の世界と訣別し、実りある未来へと方向転換した軌跡を綴った本。
『発達障害、治るが勝ち! 自分の生き方を自分で決めたい人たちへ』 2017年
「本当にこの支援に頼っていていいのだろうか?」そう疑問を感じたら本書を読んでほしい本。
なぜ医療は治さず、療育は伸ばさず、特別支援教育はアリバイに堕しているのか?」
そこには発達を阻む仕組みがある。その仕組みをひもとき、自分の人生を自分でつかむことを発達障害の当事者、保護者及び良心の残されている支援者に呼びかける書。
『自閉症者の犯罪を防ぐための提言 刑事告訴した立場から』 2012年
10年にわたり自閉症者からの加害行為にあった浅見淳子。最初は支援による救済を望んでいたがそれがかなわず司法に訴えることにした。それでもなお、自閉症者と社会は共存できると信じその実現のための提言を行った書。
『NEURO 神経発達障害という突破口』 2019年
2004年以来「自閉症は身体障害ではないか?」と仮説を立てて数々の提言をし、解決策を出版してきた花風社。出版して本を読んで実践した人たちが「治った!」と喜んでくれるようになった。なぜか? 実は治るのは当たり前のことだった。発達障害は神経発達障害だったのだから。「お医者さんに一生治らないと言われても絶望しなくていい」と知らせたくて書いた本。15年間の試行錯誤の一つの到達点。
Editor’s Note 1 【生きづらさは、なくなる。】
『自閉っ子、こういう風にできてます!』
ニキ・リンコ、藤家寛子著 2004年
アスペルガーの二人。いい子たちなのに、努力家なのに、身体感覚と世界観がヘンテコすぎて社会で生きるのがつらい。まずはこのヘンテコさを知ってもらおう! という純粋な赤心から出版してみたら、15年経った今に至るまで売れ続けるベストセラーに。
『10年目の自閉っ子、こういう風にできてます! 幸せになる力発見の日々』
ニキ・リンコ、藤家寛子著 2014年
ベストセラー「自閉っ子、こういう風にできてます!」で多くの人々に衝撃を与えた
・気まぐれな身体感覚 ・へんてこな世界観 はその後どうなったか?
実は前著から出版後10年経ち、二人とも、それぞれのやり方で、「10年前に夢見たような生活」を送っていたことを報告したくて作った本。おめでたいので表紙も水引に。
Editor’s Note 2 【解決策は、見つかった。】
『発達障害は治りますか?』 神田橋條治他著 2010年
「神田橋先生は、治すんです」「まさか!」
社会に無理な要求をするばかりで、一向に治す気も伸ばす気もない発達障害支援の世界に絶望していた2009年夏、「治す先生がいるから本を出そう」と言われたのが本書の始まり。出版から10年。多くの読者が神田橋先生のもとで治っていった。いわば「治そう路線」原点の本。
『愛着障害は治りますか? 自分らしさの発達を促す』 愛甲修子著 2016年
発達障害関係者は「怖がり」ばかり。当事者も、保護者も、そして支援者も。怖がってばかり。社会のあり方を悪意に取ってばかり。だから一般社会と共存できないのではないか?
そういう疑問を持っていた浅見は神田橋先生から「愛着障害がないから彼らが感じている恐怖がわからない」と教えてもらう。そうなの? じゃあ愛着障害って何? 治るの? と自身も愛着障害を治してきた「治せる心理士」である愛甲さんに質問を重ねることで作った本。
『人間脳を育てる 動きの発達と原始反射の成長』灰谷孝著 2016年
身体アプローチを追求してきた花風社は、「身体から働きかけると発達障害は治っていく」ことに気づいていた。でもそれがなぜなのか、理由をはっきり言語化していなかった。そんなときに灰谷さんとの出会いがあり「ああ、これだから発達障害者は身体からの働きかけで発達していくのだ」とその論理と実践を理解できた本。
『脳みそラクラクセラピー 発達凸凹の資質を見つけ開花させる』愛甲修子著 2013年
一言で言うと、本書は不思議な本。どう不思議かというと、これを愛読しているおうちでは治っていく。そもそも「治る」という言葉を使い出したのは愛甲さん。その本人に治るとはどういうことか徹底的にきいてみた。すると、治るとは「普通になる」ことではなく「成長の目詰まりが取れて自分らしさが開花する」ということであることがわかった。
『支援者なくとも、自閉っ子は育つ 親子でラクになる34のヒント』こより著 2015年
発達障害者支援が増えても、一向に「社会に出られる人」は増えない。療育を受けて結局作業所にたどりつくのなら、子ども時代はのびのびと遊んでいた方がいいのではないだろうか。そう疑問を感じさせるほどの支援ギョーカイのていたらく。一方で支援者を頼らないと子どもは伸びる! 凸凹キッズ二人を育てたこよりさんは今、お子さんにお小遣いをもらって悠々自適。支援なくても親子で遊べば大丈夫。それを伝えたくて作った本。
『自傷・他害・パニックは防げますか 二人称のアプローチで解決しよう!』廣木道心、栗本啓司、榎本澄雄著 2017年
自傷・他害・パニックは障害のある人とない人の共存を著しく妨げる。行政もこの問題を解決しようとしている。だいたいが薬物か行動分析であり、前者はご本人たちの健康被害を呼びかねず後者はほぼ役に立たないのに「何かやっている」と言いたいだけのアリバイ支援が行き渡っている。一方で主著者の廣木氏はご子息を含めた多くの人々の自傷・他害・パニックに実効性のある支援をしてきた。そのあり方を伝えるための本。栗本氏によるそもそも自傷・他害・パニックを起こさないための身体作りの提言も必読。
【本当に治るんです! 藤家寛子さんの歩んできた軌跡!】
・診断がつく前の混乱した青春時代を一人称で書いた『他の誰かになりたかった』。
・童話作家になりたいという小さい頃からの夢を叶え自閉の少女の内面を書いた『あの扉のむこうへ』。
・超のつく虚弱体質を克服し、作業所に週五日通えるようになった頃に書いた『自閉っ子的心身安定生活!』。当時は、アスペルガーで虚弱な引きこもり生活を送った人が週五日外に出られるようになるのはまずありえないことでした。
・そして支援を上手に活用し、必要がなくなったら別れを告げ、完全に健常者と同じ就職活動をして成功するまでを書いた『30歳からの社会人デビュー』。
・職場で定着し、能力を発揮し、断薬にも挑戦した『断薬の決意』。
すべて版元として誇りを持って出した本たちです。
ぜひお読みください!