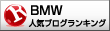ロードバイクに乗る大方は、ビンディングシューズを履きます。
つまりシューズとペダルがくっつくモノです。
スキーのブーツと板をハメるのと非常に似ています。
LOOKブランドが、両方でそれなりに幅を利かせていることが何よりの証拠です。(チャリの方が強いですけど)
そのシューズ側に付けるモノをクリートと呼びますが、これの消耗が激しいです。
素のものですと、ちょっと歩くだけで滑りますので危ないものです。
ちょっとした滑り止め部分が装着されたものがあり、当然そちらの方が高いのです。
1組で2,800円くらいするのです。
以前はこんなに高くなかったと思うのですが、いつからか減るのが怖くなりました。
ですので、歩く際にはクリートカバーなるものを付けてという具合です。
それでもちょっとした移動にまでは使いませんので、やはり減るのです。
そこで新しいものを用意しようとしていると、互換品なるものを見つけました。
お値段は半額近いものです。
しかし、この手のものは正規品に劣るのが常ですから見向きもしないつもりでしたが、ちょっと変わったタイプを見つけました。
クリート本体が2つに分かれていたのです。
それがどういう意味を持つのか分からなかったので調べてみたところ、次に交換する際の位置決めが簡単にできるというもの。
つまりどちらかを外して新しいものに変えるとパズルの様にそこに合うというものです。
どこの製品か見てみると、BMCやFSAの代理店であるフタバでしたから、そう悪くはないだろうと踏んで購入。
マジックでソールに書き込まなくていいけれど、次もこれを買わないと意味がないものです。
とりあえず使ってみると、純正クリートについているパテントという文字の意味が分かりました。
純正のクリートには、真ん中の部分に楕円形の突起物が付いています。
この部分の役割を初めて知ったのです。
これは、ペダリングをしている際にズレる感覚を敏感に感じさせない為にあるものだと。
このポッチ部分がペダルに当たって、摩擦を生む加減が絶妙なのだと知りました。
つまりこれの付いていないクリートは、0度固定以外のものであるとペダリング中に動いている感覚を味わうのです。
ストイックな方以外はグレーの4.5度又は9度のレッドを使っていると思われます。
となると、やはり純正に敵うものはないってことでしょうか、、
つまりシューズとペダルがくっつくモノです。
スキーのブーツと板をハメるのと非常に似ています。
LOOKブランドが、両方でそれなりに幅を利かせていることが何よりの証拠です。(チャリの方が強いですけど)
そのシューズ側に付けるモノをクリートと呼びますが、これの消耗が激しいです。
素のものですと、ちょっと歩くだけで滑りますので危ないものです。
ちょっとした滑り止め部分が装着されたものがあり、当然そちらの方が高いのです。
1組で2,800円くらいするのです。
以前はこんなに高くなかったと思うのですが、いつからか減るのが怖くなりました。
ですので、歩く際にはクリートカバーなるものを付けてという具合です。
それでもちょっとした移動にまでは使いませんので、やはり減るのです。
そこで新しいものを用意しようとしていると、互換品なるものを見つけました。
お値段は半額近いものです。
しかし、この手のものは正規品に劣るのが常ですから見向きもしないつもりでしたが、ちょっと変わったタイプを見つけました。
クリート本体が2つに分かれていたのです。
それがどういう意味を持つのか分からなかったので調べてみたところ、次に交換する際の位置決めが簡単にできるというもの。
つまりどちらかを外して新しいものに変えるとパズルの様にそこに合うというものです。
どこの製品か見てみると、BMCやFSAの代理店であるフタバでしたから、そう悪くはないだろうと踏んで購入。
マジックでソールに書き込まなくていいけれど、次もこれを買わないと意味がないものです。
とりあえず使ってみると、純正クリートについているパテントという文字の意味が分かりました。
純正のクリートには、真ん中の部分に楕円形の突起物が付いています。
この部分の役割を初めて知ったのです。
これは、ペダリングをしている際にズレる感覚を敏感に感じさせない為にあるものだと。
このポッチ部分がペダルに当たって、摩擦を生む加減が絶妙なのだと知りました。
つまりこれの付いていないクリートは、0度固定以外のものであるとペダリング中に動いている感覚を味わうのです。
ストイックな方以外はグレーの4.5度又は9度のレッドを使っていると思われます。
となると、やはり純正に敵うものはないってことでしょうか、、