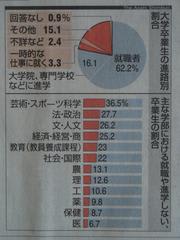科学/宇宙好きの人は見たと思うが、4日(土)の
『サイエンスZERO』で暗黒エネルギー(ダークエネルギー)が取り上げられていた。もともと物理をやりたかったんで僕も興味深く見たのだが、ちょっとした無力感に陥っているところ。
ビッグバンに始まり膨張を続けるこの宇宙、重力によって膨張速度が弱まるどころか、逆に〈暗黒エネルギー〉によって膨張の度合いが強まり、今から1000億年後には重力などに打ち勝って、すべての物質が素粒子の段階にまでバラバラになってしまうという。〈ビッグリップ〉(大いなる引き剥がし)と言うそうだ。
核戦争や隕石衝突、ノストラダムスやインカ暦滅亡説も真っ青の事態である。
この暗黒エネルギー、遠く離れれれば離れるほど大きな作用を及ぼすという、およそ普通の物理学では考えられないもの。だが、重力や電磁気力とはまったく「異次元の」ものであれば、それもアリかなと。
僕もあなたももちろん生きてはいないけれど、輝く星々やおそらくブラックホールさえ、なくなってしまう。どうにも想像できないけれど、まさに「虚無」の世界。
これ聞いて思ったのは、1984年の映画『ネバーエンディング・ストーリー』。子供の想像力の世界が〈虚無〉によって滅ぼされそうになるというもの。
または、冒頭の太極図/陰陽図のようなイメージ。
せっかく生まれた星たち、それと人類含む生命体をなぜ終わらせる必要があるのか。宇宙は永遠だと思っていただけに、残念なこと(いやあるいは、素粒子漂う宇宙空間自体は残るのかも)。
1000億年に、人類の子孫なり異星人なりいるのかどうかわからないが、すべてが引き剥がされることになれば、それは残念なことだろう。「なぜだ!」と言いたくもなるだろう。
誰でもいいから、なぜ宇宙がそんなことするのか、解明してほしいものだ。その仕組み、そしてその理由を。
〈真空エネルギー〉というのがある。真空状態の中では粒子が発生/消滅しているという。これが暗黒エネルギーと関係あるらしいのだが、そもそもなぜ真空で粒子(エネルギー)が発生するのか。
で、素人ながら考えたことは…
おそらく、何かが存在していれば、外の宇宙(別次元と言ってもいいのかもしれない)からは入ってこれないのだが、希薄そして真空になると圧力が弱まった格好となり、そこを臨界点として外からエネルギーが入りやすくなるのだろう。暗黒エネルギーなるものが浸入/にじみ出てくるのだと。
宇宙の暗黒エネルギーはどんどん増えているらしい。自己増殖する性質なのだろうが、エネルギーであるからには、増えるにはどこからか供給されなくてはならないから、それは宇宙の外からしかない。宇宙の真ん中でも暗黒エネルギーは増えているはずだから、宇宙の周りから浸入しているというより、宇宙と重なった、いわゆる異次元の形でしかあり得ない。
まだ明らかな成果は上がっていないようだが、スイスのCERN・大型加速器施設で、異次元の存在確認実験が実験が行なわれている。宇宙の重力が比較的少ないのは、どこかへ抜けているからだろうということ。
つまり宇宙の中と外とで、重力や暗黒エネルギーがやりとりされている…と、こんなイメージ。
自分が死んでも、人類あるいは何かしら生物は生き残り、いつか宇宙に進出していく…そんなイメージをずっと持っていたのだが、それもいつか〈ビッグリップ〉によって終焉を迎える。こうして書いていることも、記憶媒体ごと消えてしまう。
人類の知恵と技術のすべてを何か頑丈なタイムカプセルに納め、異星人/未来人に託したとしても、いずれ跡形もなくなくなってしまう…。これが僕の無力感なのだが、ひょっとしたら1000億年後の知的生命体は、異次元への移動手段を開発しているのかもしれない。。
〈宇宙意思〉というのがあるとすれば、それが宇宙の終わりを決めているのだろうから抗うことは無理なのだが、想念あるいは魂というのもやはり消えてしまうものなのだろうか。そういう形のないものは、この宇宙とは別次元のところの話のような気がする。
死ねば、ビッグリップの謎も理解できるのだろうか。だとすれば、死ぬことも楽しみになってくる
…番組見て以来、ずっとこんなことを考えています。
再放送もおととい11日に終わってしまいましたが、
NHKオンデマンドで今月18日までやってるそうなんで、見逃した方は是非。考えるところ大だと思います。
あそうそう、宇宙創成をテーマにしたショートショート『理科の実験』というのをおととしの7月に書いてますんで、良かったらどうぞ。