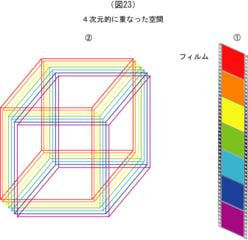真空から素粒子が生まれたり消えたりするのがとても不思議でした。それが「サイエンスカフェ」というセミナーで理解できた、というちょっと小難しい話。
けっこうあちこちにあるようですが、静岡市でもサイエンスカフェが毎月開かれています。静岡大学の理学部が主催で、科学の最先端の話をその道の専門家が講義形式で説明をしてくれるというもの。ゲノムの話から地震の話、素数の話、発光の話まで、好きな人にはたまらない話題ばかり。
そう何回も参加しているわけではありませんが、この1月に「神の粒子ヒッグス」というテーマで開かれたので、出掛けていきました。
さすがに内容は難しかったものの、〈ヒッグスの氷の海〉というものから電子と陽電子とが発生するということが図式で説明され、何となくイメージすることができました。
そこで連想してのが「なぜ真空中で素粒子が生まれたり消えたりするのか」という疑問。質問をしたところ、「真空といえどもヒッグス場というのは存在していて、素粒子が生成/消滅するのは何ら不思議はない」とのこと。
というわけで長年の疑問が何となく分かってきたわけ。どうも真空という容器の方が、素粒子の性質を支配しているらしい。宇宙の真空中を光や電波、重力が伝わるのも、ヒッグスがあるからなのだろう、と思っているところ。
参加者は高校生からおじいさんまで幅広い。隣りに座った男の子が「数学Ⅱ」の教科書で宿題やっていたので懐かしくて見せてもらい、話をしたところ、高一なんだそうだ。
天文学をやりたいという賢そうな子で、そういう高校生が参加しているのであれば、まだまだ日本も大丈夫、と思った次第。
コーヒーも出ますし頭の普段使わない部分が刺激されますんで、皆さんもどうぞ。